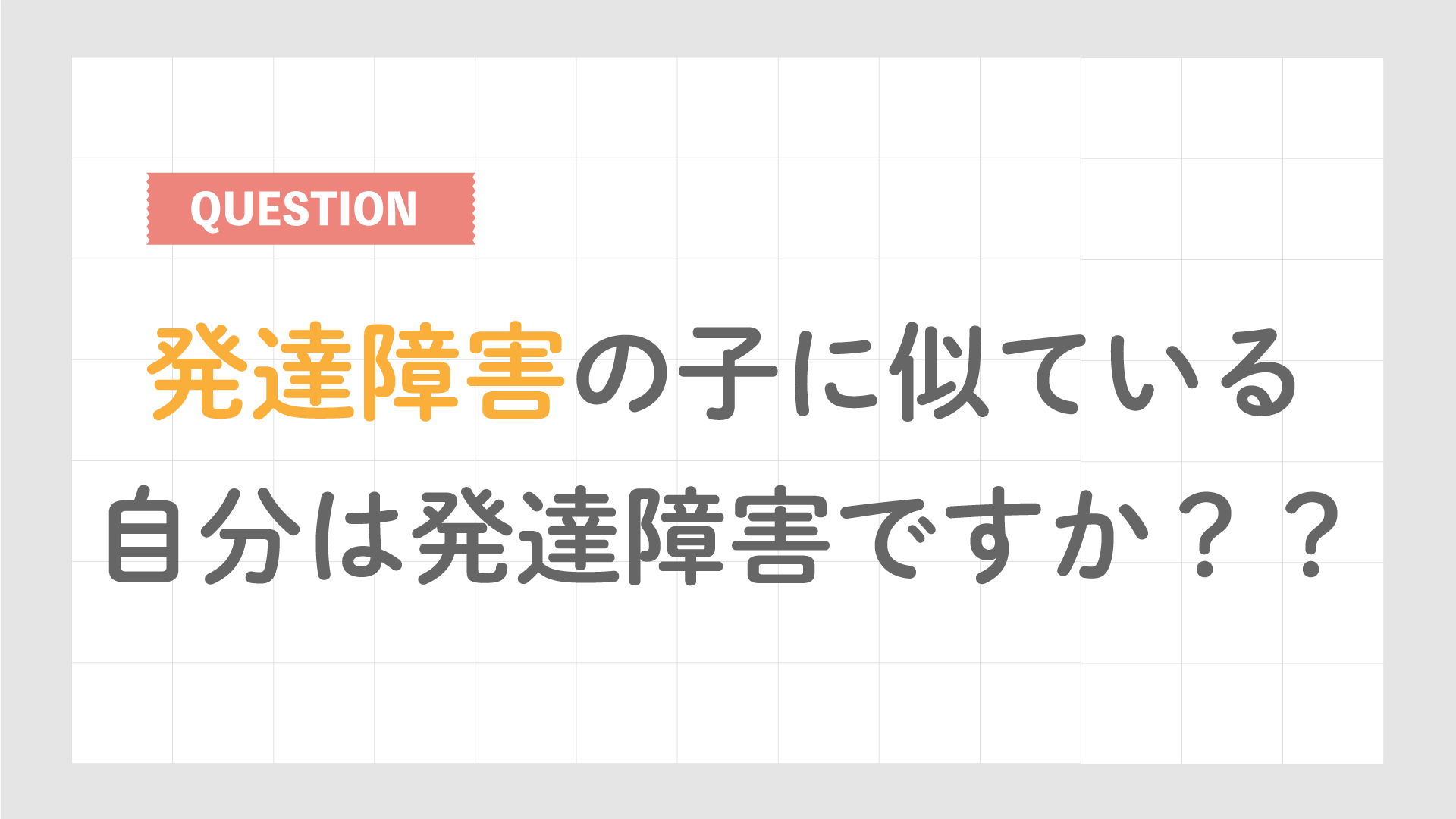子どもの暴力・自傷行為は「助けて」のサイン。発達障害・知的障害の行動をコミュニケーションとして捉え直す支援策
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「障害を持つお子さんの『暴力行動』」についてです。
結論:暴力は「コミュニケーション」である
今日のテーマは「暴力」ですが、まず最初に、僕が一番伝えたい結論からお話しします。
発達障害や知的障害のあるお子さんの「叩く」「蹴る」「噛みつく」「物を壊す」といった行動。
特に、それが一時的なものではなく、中長期的に、いつも同じようなパターンで長続きしている場合、それは単なる暴力ではありません。
それは、本人の「苦しみ」や「混乱」を伝える手段であることが多いんです。
言葉で自分の気持ちをうまく表現できない時、その行動が、本人にとって唯一のコミュニケーション手段になっている可能性があります。
もちろん、暴力はいけないことです。ダメなことはダメだと僕も療育現場ではしっかり教えます。
でも、その行動を捉える「認識」として、特に発達障害や知的障害のあるお子さんの場合、「相手をやっつけてやろう」という攻撃的な暴力として見るのではなく、
「自分の気持ちを伝える術が分からない。分からない結果、暴力でしか訴えられない」
という、助けを求めるヘルプサインとして捉え直すことが、支援の第一歩としてすごく重要なんですよね。
子どもと大人の「安心」を取り戻すために
この動画(記事)を作ろうと思ったのは、コメント欄などで「暴力行動に困っています」「子どもに接するのが怖くなってしまった」という保護者の方の切実な声が多かったからです。
暴力が間にあることで、親子関係がギクシャクしてしまったり、保護者の方がお子さんに対して恐れや不安、恐怖を感じてしまったりするのは、本当につらい状況だと思います。
今日の話は、療育施設で僕たちがどのような視点でその行動を捉え、どう対応しているか、という内容です。
この記事が、皆さんの安心を取り戻すための何かしらのきっかけになれば嬉しいです。
「強度行動障害」という視点
特に、自分や他人を傷つけたり、物を壊したりする行為が、非常に高い頻度で起こる状態を「強度行動障害(きょうどこうどうしょうがい)」と呼ぶことがあります。

ゆう先生の補足解説:強度行動障害とは
強度行動障害は、それ自体が診断名ではありません。主に知的障害や自閉症のある方に見られ、
「自分の体を叩く(自傷)」「他人を叩いたり噛み付いたりする(他害)」「物を壊す(器物破損)」といった、
本人の健康や周囲の暮らしに著しい影響を及ぼす行動が、非常に高い頻度で(または強い強度で)続く状態を指します。
これは本人の「性格」や「わがまま」ではなく、コミュニケーションの困難さや感覚の問題、環境への不適応など、様々な要因が複雑に絡み合って起きる「状態」です。
そのため、行動を無理やり力で抑え込むのではなく、その行動が起きる「原因」を丁寧に取り除き、安心できる環境を整えるという、きめ細やかな専門的支援が必要になります。
今日の内容は、こうした強度行動障害の状態にあるお子さんにも当てはまりますし、そこまでではなくても、日常的な暴力行動に悩んでいる多くの方に共通する話です。
なぜ暴力行動は起きるのか? 5つの背景
暴力というヘルプサインは、本人が抱えているストレスや不快感をうまく表現できず、消化できない結果として噴出しています。では、その背景には何があるのでしょうか。主に5つの原因が考えられます。
原因①:発達的な要因
ASD(自閉スペクトラム症)の特性である「こだわり」が崩れた時に混乱してパニックになったり、ADHD(注意欠如・多動症)の「衝動性」や感情コントロールの難しさから、刺激に対して思わず手が出てしまったりすることがあります。
これは「わざと」やっているというよりは、脳の機能的な特性として、そうなりやすい、爆発しやすい状態にある、ということです。まずはその特性を理解し、本人に合わせた環境を作っていくことが大事になります。
原因②:感覚の過敏・鈍麻
これは非常に多い原因の一つです。他の人には平気な刺激が、本人にとっては耐えがたい苦痛になっていることがあります。
感覚過敏(かびん):特定の感覚を、他の人より非常に強く感じてしまうことです。
例えば、「救急車のサイレンが遠くで鳴っているだけでパニックになる(聴覚過敏)」、「服のタグがチクチクして耐えられない(触覚過敏)」、「強い光が目に入ると混乱する(視覚過敏)」などがあります。
感覚鈍麻(どんま):逆に、感覚を感じにくいことです。
例えば、痛みを感じにくく(痛覚鈍麻)、自分の頭を強く打ち付けても平気だったりします。この「頭打ち」などの自傷行為は、鈍麻さゆえに「より強い刺激」を自分で入れて安心しようとしている(自己刺激)場合や、別の不快感(不安など)を強い痛みで上書きして忘れようとしている防衛行動の場合もあります。
原因③:コミュニケーションの困難
「うまく言えない」ことは、そのまま「体で伝える」ことにつながります。
嫌なことを「やめて」と言葉で伝えられないから、相手を叩いてしまう。欲しいものを「ちょうだい」と言えないから、物を奪ってしまう。
特に、否定的な言葉(「ダメ」「違う」)を言われた時に、どう解決していいか分からず混乱し、パニックから暴力につながるケースは非常に多いです。
原因④:環境の変化とストレス
特に自閉傾向が強いお子さんの場合、「見通しが立たないこと」は非常に強い不安やストレスになります。
- 突然の予定変更
- 初めての場所、初めて会う人
- スケジュールの乱れ
大人にとっては本当に些細な、ケアレスミスのような小さな変化でも、本人にとっては「爆発」の引き金(起爆剤)になることがあります。予測が立ちにくい環境は、それだけで本人を不安にさせ、暴力のきっかけになりやすいんです。
原因⑤:身体的な不調
これは目に見えにくく、見逃されがちですが、とても多い原因です。
頭痛、腹痛、便秘、歯痛、あるいは服のタグがチクチクするといった「かゆみ」。
「お腹が痛い」「かゆい」と言葉で訴えることができれば良いのですが、それが難しいお子さんの場合、その不快感をどうすることもできず、イライラやパニックとして行動に現れます。
暴力行動への具体的な対応(発生時)
では、実際に暴力やパニックが起きてしまった時、どうすればいいのでしょうか。
対応①:安全の確保を最優先する
まず、いの一番にやるべきことは「安全の確保」です。これは年代に関わらず絶対です。
物が飛んできたり、壊そうとしたりしている時は、本人も周りの人も危険です。
- 兄弟がいれば、まず避難させる。
- ハサミや包丁、割れ物など、危険なものを瞬時に判断し、遠ざける。
- 必要に応じて(例えば自傷が激しい場合など)は保護具を使うこともありますが、まずは安全な空間を確保します。
対応②:クールダウンの実践(叱責しない)
安全を確保したら、本人がクールダウン(鎮静)するのを待ちます。
ここで一番やってはいけないのが、「説得」「説明」「叱責」です。
興奮している時に「なんでそんなことするの!」と大声で叱っても、火に油を注ぐだけです。仮にお父さんの迫力ある大声で一瞬止まったとしても、それは根本的な解決にはなりません。
大事なのは「静けさ」と「安心感」です。
- 言葉で説得しようとせず、静かな場所に移動する。
- 照明を落とす、電気を消すなど、目や耳からの刺激を減らす。(僕も現場でよくやります)
- 知的課題が重いお子さんの場合は、ギュッと抱きしめて安心感を与えることもあります。
- 落ち着いてきたら「大丈夫だよ」「怖かったね」と、共感的な言葉を静かにかけます。
療育で大事にしているのは、この「爆発してからクールダウンするまでの時間」をいかに短くしていくか、という訓練です。怒ってしまうことはあっても、気持ちを切り替える練習をしていくことが重要です。
暴力行動を「予防」するためにできること
起きてしまった時の対応も大事ですが、それ以上に大事なのは「起こさないための予防」です。
予防①:構造化(予測できる環境づくり)
原因④(環境の変化)への対策です。「予測できる環境」は、お子さんに絶大な安心感を与えます。

ゆう先生の補足解説:構造化(こうぞうか)とは
「構造化」とは、発達障害のあるお子さんが混乱しないよう、環境を「分かりやすく整理整頓する」という支援の考え方です。
例えば、
- 時間の構造化:絵カードやスケジュール表を使って、「今から何をするか」「次は何をするか」を見通しとして視覚的に示します。
- 空間の構造化:「ここは勉強する場所」「ここは遊ぶ場所」「ここはクールダウンする場所」と、エリアごとに役割を明確に決めます。
こうすることで、「次に何が起こるか分からない」という状況を減らすことができます。
予防②:クールダウンエリアの活用
興奮してしまった時に逃げ込める「安全基地」を、家の中にあらかじめ作っておくことも有効です。
部屋の片隅の一角でも良いので、本人が一人になれるパーソナルスペース(テントの中、布団をかぶれる場所など)を用意し、「イライラしたらここに行こうね」と決めておくことで、本人が自分で気持ちを整理する時間を持てるようになります。
予防③:アンガーマネジメント(深呼吸など)
怒りのコントロールを練習することも大切です。
6秒ルール、クッションを叩く、冷たい水を飲むなど色々ありますが、僕が現場で一番効果を感じているのは「深呼吸」です。
療育のたびに、毎回毎回、半年以上続けて、ようやく怒りそうになった時に「はぁっ」と肩で息をして、自分で気持ちをコントロールしようとする姿が見られるようになります。時間はかかりますが、特に幼少期からこの習慣をつけておくと、自分の感情を客観視する助けになります。
予防④:SSTと代替コミュニケーション (AAC)
原因③(コミュニケーションの困難)への対策です。
暴力以外の「適切な伝え方」を具体的に教えます。これを「SST(ソーシャルスキル・トレーニング)」と言います。
例えば、おもちゃの取り合いで叩いてしまうなら、「貸して」「いいよ」という言葉やジェスチャーを、その場で何度も練習させます。

ゆう先生の補足解説:AAC(代替・拡大コミュニケーション)
言葉で伝えるのが難しいお子さんには、「AAC(Alternative and Augmentative Communication)」=「代替・拡大コミュニケーション」を使います。
要は、言葉の代わりになるツールです。絵カード(PECSなど)や、タブレットのアプリがこれにあたります。
「イライラ」「悲しい」といった気持ちのカードを作っておき、暴力の代わりにそれを見せる、というルールを教えます。
【コツ】:いきなり感情表現に使おうとしても難しいので、最初は「このカード(お菓子の絵)を出したら、お菓子がもらえる」という「引き換え券」として使い、「カードには力がある」と学習してもらうことから始めるとスムーズです。
予防⑤:ABAとPBSの考え方
「なぜ暴力が起きたか」を分析し、「良い行動を増やす」ための科学的なアプローチです。
ABA(応用行動分析):行動を「ABC分析」で捉えます。
A(Antecedent=直前の状況)、B(Behavior=行動)、C(Consequence=直後の結果)の3つです。「(A)お母さんが電話を始めたら、(B)子どもが叩いてきた。(C)お母さんが電話をやめて注目した」。
この場合、子どもは「叩けば注目してもらえる」と学習した可能性が分かります。
PBS(ポジティブ行動支援):ABAの考え方を使い、「罰を与える」のではなく、「良い行動を褒めて増やす」ことを重視する支援です。
上記の例なら、「叩く」原因(注目)が分かったので、叩く前に「注目して」とカードで伝えられたら「(C)盛大に褒めて注目する」ようにします。
叱るのではなく、望ましい行動を育てることを目指します。
親は最大のサポーター(褒める工夫)
暴力行動が続くと、つい叱ってしまいがちですが、本人はヘルプサインを出している状態です。そのサインを受け止め、「じゃあこうしようか」と前向きに導いてあげることが重要です。
そのためにも、親御さんにはぜひ「最大のサポーター」であってほしいと思います。
褒める時にも工夫があります。
「テストで100点を取った(結果)」を褒めるのではなく、「毎日コツコツ勉強していた(プロセス)」を褒めてあげてください。
プロセスを褒めると、その行動(努力)自体が定着しやすくなります。暴力行動が多いお子さんだからこそ、暴力ではない「良い行動のプロセス」をたくさん見つけて褒めてあげてほしいなと思います。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- お子さんの長期的な暴力や自傷は、本人なりの「助けて」というヘルプサインであり、コミュニケーションの手段であると捉え直すことが第一歩です。
- その原因は一つではなく、発達特性、感覚、コミュニケーション、環境、体調など、複数の要因が隠れています。
- 起きてしまった時は「安全確保」と「クールダウン」を徹底し、叱責しません。日常的には「構造化」で不安を減らし、「SST」や「AAC」で適切な伝え方を教え、「ABA/PBS」の考え方で良い行動を褒めて定着させていくことが大切です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
暴力行動への対応は、本当に大変で、心が疲れてしまうことも多いと思います。
でも、ご紹介したような支援(環境構築や教育)を一つ一つ積み上げていくことで、生活しやすくなるのは間違いありません。
今まさにお困りの方は、どうか無理をせず、まずは専門家と相談して計画を立ててほしいと思います。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。