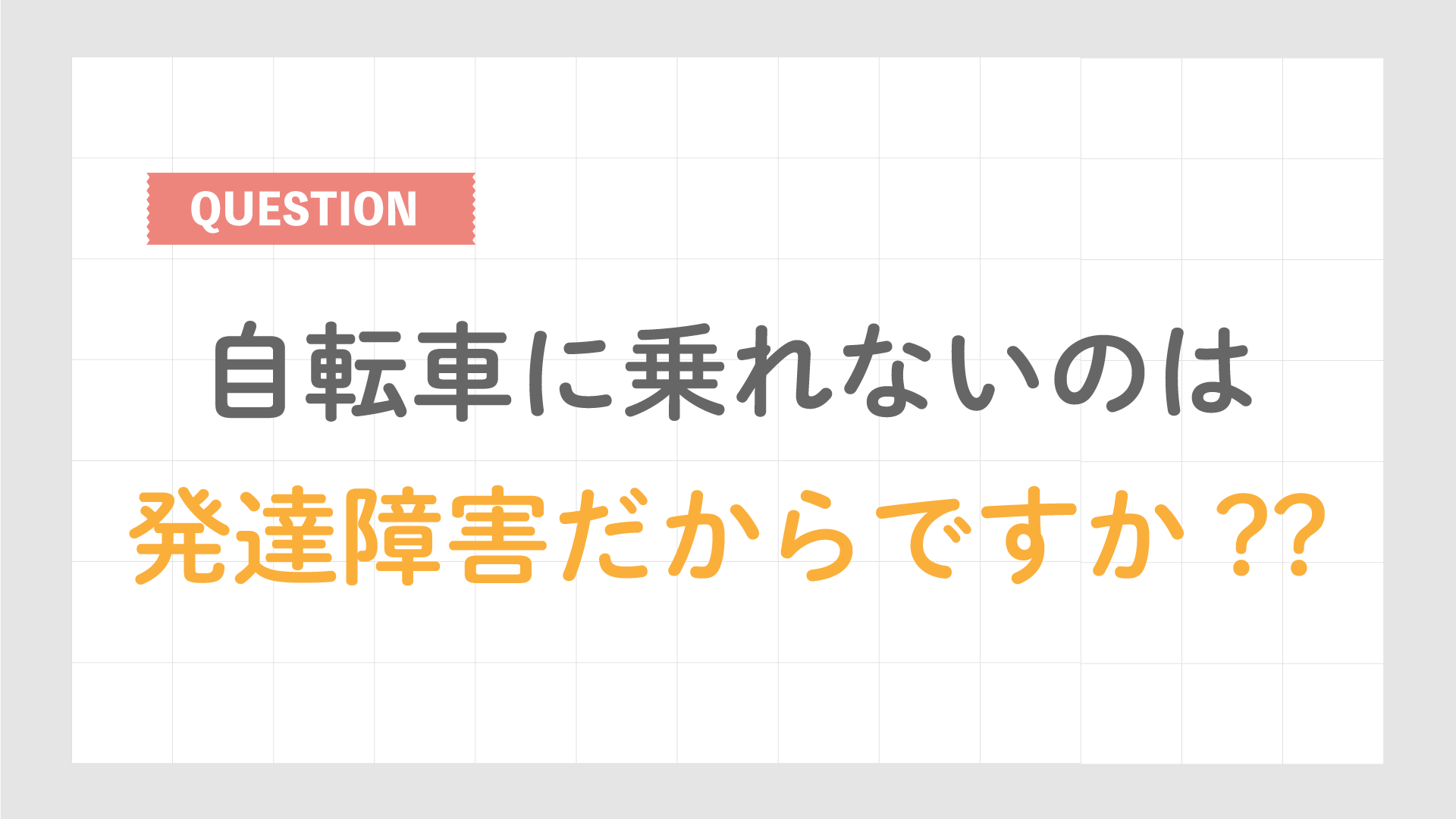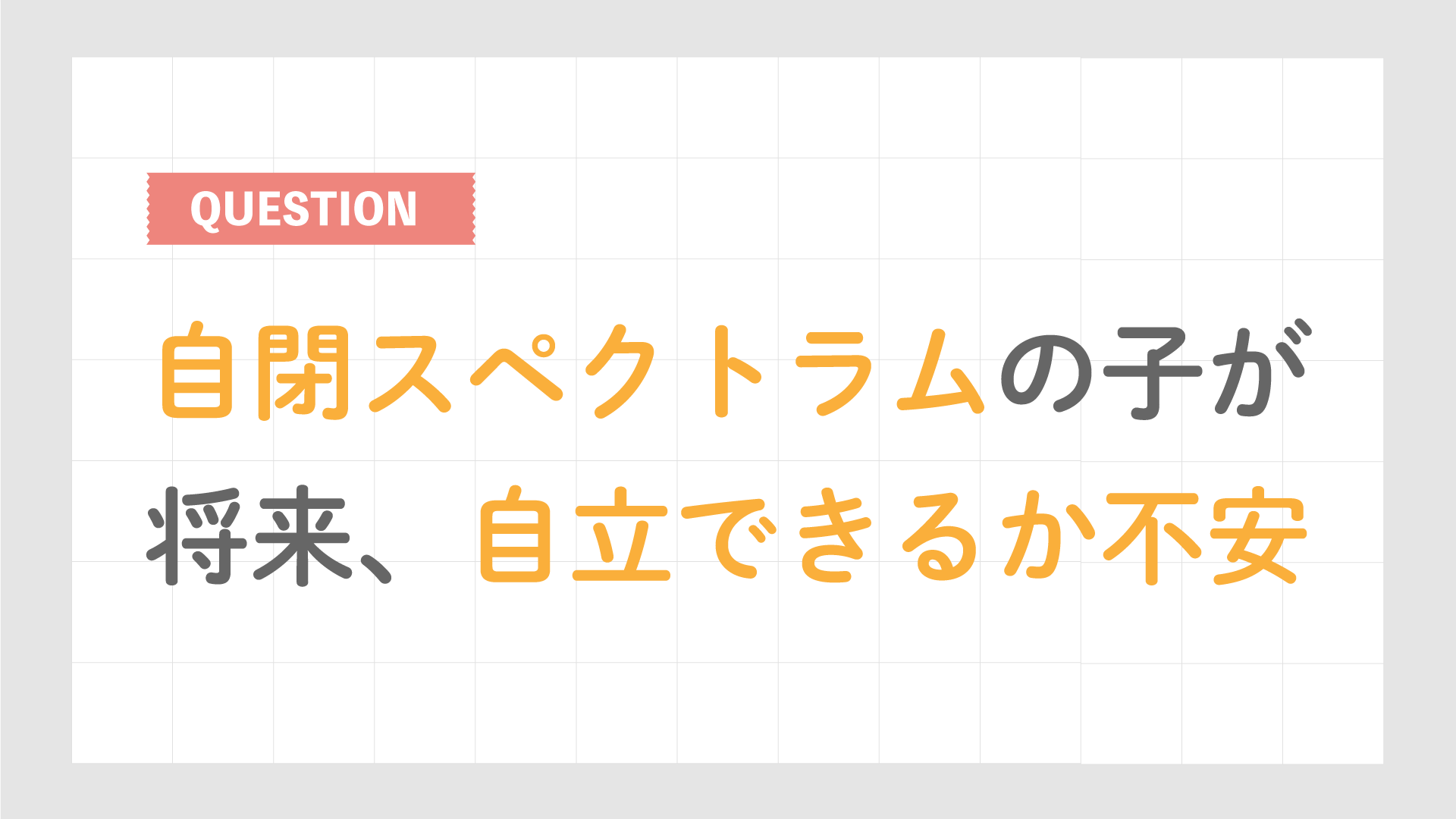ゲーム依存の6割が発達障害?富山の指導員が解説するADHD・ASDとの危険な相性と対処法
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ゲーム依存と発達障害の関係性」についてです。
ゲーム依存は「趣味」ではなく「治療が必要な健康問題」
先日、2025年10月12日に福井県で「神経発達特性のある子供のインターネット利用を考えるシンポジウム」が開催されました。
その中で、依存症医療の第一人者である樋口医師が「ゲーム依存の患者の6割はADHDやASDの傾向を持つ」と発言されました。
「そんなに多いの?」と衝撃を受ける数字ですが、これは樋口医師個人の感覚的なものではなく、日本の臨床現場での実感と、国際的な研究の双方に裏付けられている数字なんだそうです。
つまり、発達障害の特性を持っている場合、ゲーム依存になりやすい傾向がある、ということは一つの事実として言えそうです。

ゆう先生の補足解説:ゲーム障害(WHOの定義)
そもそも「ゲーム依存」とは何でしょうか。
世界保健機関(WHO)は、「ゲーム障害」を正式な医学的疾患(病気)として定義しています。
その定義によると、「ゲームへのコントロールが失われ、生活の中心がゲームになり、学業や家庭生活に重大な支障をきたす状態が、12ヶ月以上続くこと」とされています。
これは単なる「遊びすぎ」や「趣味」のレベルではなく、治療が必要な健康問題である、という認識が非常に重要です。
なぜ発達障害があるとゲームにハマりやすいのか?
「ゲームにハマるのは、本人の意思が弱いからだ」「我慢が足りない」と思われがちですが、そうではありません。
特に発達障害とゲーム依存の関係においては、脳の特性が大きく関わっています。
一言でいうと、ADHDやASDの脳の特性と、ゲームというコンテンツは、ものすごく相性が良いんです。相性が良すぎるからこそ、深くはまっていってしまう、という側面があります。
ADHDの特性とゲーム依存(ドーパミン不足)
ADHD(注意欠如・多動症)の特性がある人は、脳の「報酬系」で働く神経伝達物質「ドーパミン」が慢性的に不足しがち、あるいはうまく活用できない状態にあると言われています。

ゆう先生の補足解説:ドーパミンと報酬系
「ドーパミン」は、一般的に「やる気ホルモン」や「快感ホルモン」と呼ばれます。何かを達成した時に「嬉しい!」「楽しい!」と感じさせ、「またやろう!」という意欲を引き出す役割があります。
ADHDのお子さんが、普段はなかなか動けなくても、宿題の提出期限ギリギリになると火事場の馬鹿力を発揮できることがあるのは、危機的状況でドーパミンが一気に放出されるから、とも言われています。
日常生活ではなかなかドーパミンが出にくく、満足感を得にくい。そこに「ゲーム」が登場します。
ゲー ムは、敵を倒す、レベルが上がる、アイテムをゲットするなど、短時間で次々と「達成感」や「報酬」が得られるように設計されています。
これが、ドーパミン不足の脳にとっては、まさに求めていた強い刺激なんですよね。
ADHDのお子さんにとって、ゲームは不足しているドーパミンを補ってくれる「自己調整装置」のように機能してしまう。
だから、やめたくてもやめられない、強い依存につながりやすいんです。
ASDの特性とゲーム依存(安全基地)
ASD(自閉スペクトラム症)の特性がある人は、変化が激しく、予測不能なことや、感覚的な刺激(大きな音、人の視線など)が多い現実世界に対して、強いストレスや混乱を感じやすい場合があります。
一方で、ゲームの世界はどうでしょうか。
- ルールが明確である。
- 次に何をすればいいか、見通しが立ちやすい。
- 自分のペースで進められる。
- 人との関わりも、テキスト中心など、視覚的で分かりやすい。
- 不快な感覚刺激(音量や明るさ)も自分で調整できる。
このように、ゲームの世界はASDの特性を持つ人にとって、非常に「構造化されていて予測可能」な、安心できる空間なんです。
現実世界でのストレスから逃れるための「安全基地」としてゲームの世界に没頭し、居心地が良すぎるあまり、現実に戻るのが嫌になってしまう…というメカニズムで依存につながっていくケースがあります。
依存が引き起こす問題点
脳の特性とゲームの相性が良すぎた結果、日常生活に支障が出てくると、様々な問題が起こり始めます。
脳の回路と離脱症状(家族との対立)
ADHDの場合、ゲームによる強い刺激(ドーパミン)を受け続けると、脳の回路自体がそれに慣れてしまい、ゲームをやめると強い不快感やイライラを感じるようになります。
ASDの場合、自分を守ってくれていた「安全基地」を強制的に奪われることへのパニックが起こります。
ゲームを取り上げようとした時に、お子さんが暴言を吐いたり、暴れたり、物を壊したりすることがあります。
これは単なる「反抗」や「わがまま」ではなく、薬物依存などと同じような「離脱症状」や、強い不安からくる「パニック」である可能性が高いんです。
神経の苦痛を和らげるためにやっていたゲームを奪われることで、苦痛が増幅してしまう…ここに、この問題の難しさがあります。
日常生活への影響(昼夜逆転・不登校)
依存が進行すると、日常生活のリズムが崩れていきます。
- 昼夜逆転:夜通しゲームをしてしまい、朝起きられない。
- 生活の無頓着:食事を抜く、お風呂に入らなくなる。
- 社会的孤立:家族とのコミュニケーションが減る、不登校になる。
そして、「学校に行っても嫌なことばかりだ(現実のストレス)」→「家に帰ってゲームをすると楽しい(現実からの回避)」→「さらにゲームに依存する」という悪循環が生まれてしまいます。
ゲーム依存への対策と支援
では、どうすればいいのでしょうか。
専門的な支援(二重のアプローチ)
まず大前提として、ゲーム依存、特に発達障害が背景にある場合は、ご家族だけで解決しようとせず、専門家の支援を受けることが非常に重要です。
「依存症」の治療と、「発達障害」への支援、この両方を同時に行う「二重の焦点アプローチ」が必要になります。

ゆう先生の補足解説:認知行動療法(CBT)
ゲーム依存の治療法の一つに「認知行動療法(CBT)」があります。
これは、自分の「考え方のクセ」や「行動のパターン」に気づき、それを現実とすり合わせながら、より良い行動パターンに変えていこうとする心理療法です。
例えば、「イライラしたらゲームをする」という行動パターンに気づき、「イライラしたら、ゲーム以外に何ができるか(例:音楽を聴く、散歩する)」という別の選択肢を一緒に探していく、といった訓練を行います。
ADHDであれば、必要に応じて薬物療法を検討することもありますし、ASDであれば、不安をコントロールする方法や対人スキルを学ぶ訓練(SST)が有効な場合もあります。
家族の役割(監視者ではなく支援者)
ご家族にお願いしたいのは、「ゲーム時間を監視する人」にならないでほしい、ということです。
「30分って言ったでしょ!」と叱る役割ではなく、お子さんと一緒に問題に向き合う「支援者」「伴走者」になってほしいんです。
- 一緒にルールを作る:「今日は30分超えちゃったね。どうしたら守れそうか、一緒に考えようか」
- 現実世界につなぐ:「ゲーム終わったら、一緒におやつ食べようか」「今度、あの場所に行ってみない?」
- 親も学ぶ:ペアレントトレーニングなどを利用し、発達特性への理解を深める。
最も重要なこと:ゲーム以外の「居場所」
そして、僕が一番重要だと感じているのは、ゲーム以外に熱中できること、安心できる「居場所」を見つけることです。
依存先がゲームしかないから、そこに集中してしまうんです。
スポーツでも、創作活動(絵や音楽)でも、仲間との交流(塾や習い事)でも何でもいいんです。
ゲームもするけど、他の楽しみもある。ゲームもするけど、安心できる場所(サードプレイス)が他にある。
このように「依存先を分散させる」ことが、結果としてゲームとの健全な距離感を保つことにつながっていくと、僕は思います。
ゲームは「悪」ではなく「付き合い方」が大事
ここまでゲーム依存の危険性についてお話してきましたが、僕は決して「ゲーム=悪」だと思っているわけではありません。
むしろ、発達障害の特性と相性が良いからこそ、上手に取り入れれば、コミュニケーション能力を学んだり、知識を深めたりする素晴らしいツールにもなり得ると考えています。
問題なのは、ゲームそのものではなく、それ一色になってしまう「依存」の状態です。
用法・用量を守って、上手に付き合っていくことが大切ですよね。
まとめ
今日の記事では、「ゲーム依存と発達障害の密接な関係」について解説しました。
- ゲーム依存の患者さんの約6割がADHDやASDの特性を持つという背景には、脳の特性(ドーパミン不足、構造化された世界への安心感)とゲームの仕組みが強く結びついているという事実があります。
- この問題は「意思の弱さ」ではなく「脳の特性」と「環境」の問題です。ゲームを取り上げるときの激しい抵抗は「離脱症状」や「パニック」である可能性を理解することが大切です。
- 対策としては、ご家族だけで抱え込まず専門機関に相談し、「依存」と「発達特性」の両方にアプローチすること、そしてゲーム以外の安心できる居場所(サードプレイス)を見つけることが解決の鍵となります。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。