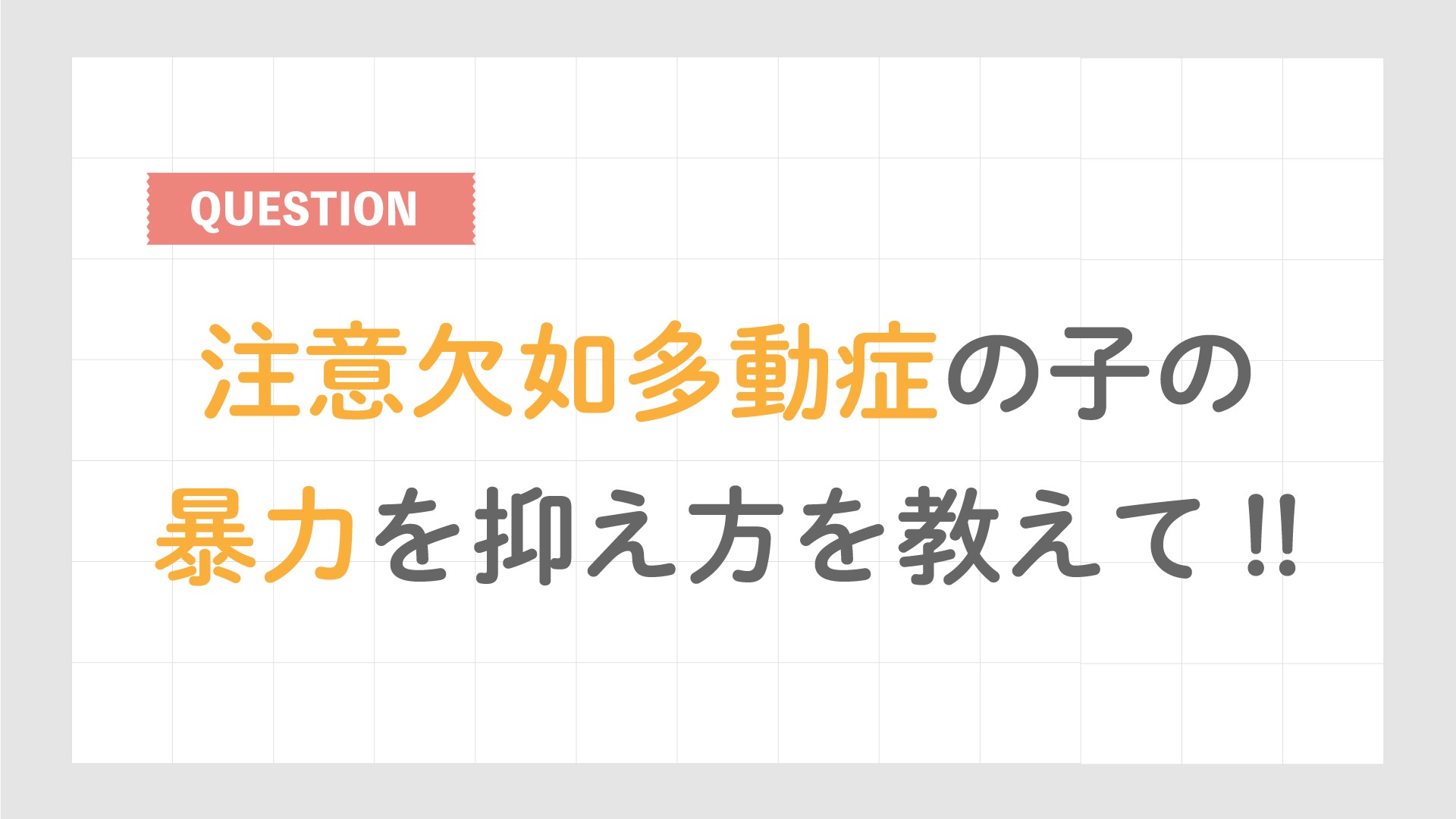HSC(非常に敏感な子ども)とは?「繊細さ」は生まれ持った気質。DOESモデルと発達障害との違い、安心できる支援法
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「HSC(非常に敏感な子ども)」についてです。
HSC(非常に敏感な子ども)とは?
さて、今日はHSCについてです。「HSP」という言葉であれば、皆さん聞いたことがあるかもしれませんね。
HSPの「P」はパーソン(Person = 人)で、大人のことを指しているのに対し、HSCの「C」はチャイルド(Child = 子ども)という意味になります。
なんとなく、日本人に多そうな気質かなと思うんですけれども、今日はこのHSCについて、ただ「敏感なだけじゃないんだよ」ということを深く理解していただけたらと思います。
まず、HSCは人口の約20%に見られると言われていて、だいたい5人に1人くらい。比較的多いですよね。
これは病気や障害というわけではなく、「生まれ持った神経特性」です。脳や神経の反応の仕方に由来する「気質」と捉えるのが一番しっくりくるかなと思います。
HSC (Highly Sensitive Child) や HSP (Highly Sensitive Person) は、心理学者のエレイン・アーロン博士によって提唱された概念です。
正式には「感覚処理感受性(SPS: Sensory Processing Sensitivity)」という神経学的な特徴を持つ人々を指します。これは病気の診断名ではなく、あくまで「生まれ持った気質」を分類する言葉なんですよね。
「敏感さ」は生き残るための戦略だった
この「敏感さ」や「繊細さ」って、聞くとちょっとネガティブな、弱いイメージを持たれることが多いんです。でも、アーロン博士の研究によると、そうじゃないんですよね。
これは、人類が太古の昔に環境に適応するために発達させた、自然な「戦略」の一つだと考えられています。
どういうことかというと、昔、僕らのご先祖様がまだ自然の中で暮らしていた頃、集団の中には危険をいち早く察知する「警戒型」の役割を持つ人が必要でした。小さな物音や匂いの変化に気づいて、「危ない!」と仲間に知らせる役割です。
こういう敏感な人たちがいたからこそ、人類は生き残ってこれたわけです。
現代の日本だと、道を歩いていて熊に会うことは…あ、いや、富山県は市内でも熊の出没情報がめちゃくちゃ多いので、ありそうですね(笑)
でも、1000年前と比べたら、社会は圧倒的に安全になりました。
安全になった現代社会では、この「警戒型」のアンテナの高さが、逆にたくさんの情報を拾いすぎてしまって、本人が疲れやすくなる原因にもなっている。それがHSCの正体の一つなのかなと思います。
HSCの4つの特徴「DOES(ダズ)モデル」
HSCやHSPかどうかを判断する上で、「DOES(ダズ)モデル」という4つの特徴が基準になります。
- D (Depth of processing) – 深く処理する
- O (Overstimulation) – 過剰な刺激を受けやすい
- E (Emotional responsiveness / Empathy) – 強い共感性
- S (Sensing the subtle) – 微細な変化を察知する
この4つすべてに当てはまる場合、HSCの気質があると考えられます。
特に一番大事なのが、最初の「D(深く処理する)」です。
D (Depth of processing) – 深く処理する
これがHSCの特性の中心です。他の3つの特性(OES)は、この「深く処理する」ことから派生していると言われています。
HSCの脳は、入ってきた情報を「はい、終わり」と処理するんじゃなくて、何度も何度も再処理して、意味づけを行う傾向があります。
例えば、近くで「ガサガサッ」と物音がしたら、「なんだろう?」「この音は、もしかしてこうかな? つまり、こういうことか」というところまで、深く考えてしまうんです。
脳科学的には、考える脳みそである「前頭前野」と、記憶を司る「海馬」が強く連携していると言われています。過去の記憶や断片的な情報と、今起こっていることを統合して、複雑な文脈を把握しようとする。
だから、周りから見るとすごく慎重で、「考えすぎている」ように見えることがあります。
O (Overstimulation) – 過剰な刺激を受けやすい
これは、神経の「受信フィルター」がとても細かいイメージです。
僕らの脳は通常、目の前の人の話を聞いている時、周りの車の音とかは無意識にフィルタリング(遮断)してくれています。
でもHSCの子の場合は、そのフィルターが細かすぎて、あらゆる情報を取り込んでしまう。人の声も、遠くの車の音も、光も、匂いも、全部同時に入ってきて、それを全部「深く処理(D)」しようとするんです。
常に五感と神経が全開で、脳がフル稼働している状態。だから交感神経が優位になりやすくて、結果としてすごく疲れやすくなってしまいます。
E (Emotional responsiveness / Empathy) – 強い共感性
HSCの子は、他人の感情を「自分ごと」のように感じ取る能力が非常に高いです。
脳の中には「ミラーニューロン」という、相手の動きや感情を鏡のように反映する神経があるんですが、HSCの人はここが強く活動すると言われています。
他人の痛みや喜びを、まるで自分の経験のように感じやすい。これは優しさの源泉でもあるんですけど、同時に相手の感情に引きずられちゃって、心が疲れやすい特性でもありますよね。
S (Sensing the subtle) – 微細な変化を察知する
光の強さ、音の高さ、人の表情のちょっとした違い…。他の人が気づかないような本当に微細な変化を、素早く察知することができます。
ちょっと余談ですけど、漫画『NARUTO』でいう「仙人モード」みたいな感じで、感知能力がすごく上がってる状態に近いかもしれません(笑)
これは、脳の感覚処理が「背景の刺激」まで同時に分析しているからだと言われています。この能力が、注意深さや、物事の本質を見抜く「洞察力」の源になっているんですよね。
HSCと発達障害(ASD・ADHD)との違い
ここまで聞くと、「あれ? それって発達障害とどう違うの?」と思う方もいるかもしれません。実際、外から見た行動はすごく似ている部分があります。
でも、その行動の背景にある**「脳のOS(メカニズム)」**がちょっと違うんですよね。
HSC と ASD(自閉スペクトラム症)の違い
ASD(自閉スペクトラム症)の子も、HSCの子も、「感覚過敏」があって、特定の音や光、肌触りをすごく嫌がることがあります。ここは似ていますよね。
一番大きな違いは「共感性」です。
- HSC:他人の感情を過剰に感じすぎて疲れてしまう。
- ASD:他人の意図や感情を理解するのが苦手で、コミュニケーションに困難が出やすい。
(※もちろん、これは一般的な傾向で、ASDの人が冷たいという意味では全くありません)
HSC と ADHD(注意欠如・多動症)の違い
ADHDの子も、HSCの子も、授業中に「集中しづらい」という点で似て見えることがあります。
でも、なぜ集中しづらいのか、その理由が違います。
- ADHD:注意があちこちに「飛んでいってしまう」。黒板を見ていたはずが、「あ、今日の晩ごはん何だっけ」とか「あ、グラウンドに犬がいる」とか、全然違うことに意識が移ってしまう感じ。
- HSC:注意が「広がりすぎている」。黒板に集中したいんだけど、目の前に座っている子の動きも、先生の小さなため息も、エアコンの音も、全部の情報を同時に処理しようとして、結果的に一つのことに集中できなくなっている感じ。
ここでお話ししているのは、あくまで一般的な傾向の違いです。
HSCは「気質」、ASDやADHDは「神経発達症(発達障害)」という分類上の違いがあります。HSCの子がASDやADHDを併発しているケースももちろんあります。
大切なのは「あの子は〇〇だ」と決めつけることではなく、「なぜ今、この子は集中しづらいんだろう?」「なぜ疲れやすいんだろう?」と、その子の内側で起きていることを想像してあげることだと僕は思います。
HSCの子どもへの支援と関わり方
HSCの子にとって、たくさんの刺激にさらされる学校という環境は、負担がすごく大きい場所です。
教室の騒音、集団行動、他人の感情…。常に情報処理にエネルギーを使っているので、疲労感を抱えやすかったり、不安感が強かったりして、結果として「登校しぶり」につながることもあります。
これは怠けてるわけじゃなくて、本当に神経がすり減っちゃってる防衛反応なんですよね。
でも家庭で、「学校行きたくない」と言った時に、「気にしすぎだよ」「甘えてるよ」と返されてしまうと、HSCの子は深く処理する特性(D)から、その言葉の裏側まで探ってモンモンと悩んでしまい、自己否定感を強めてしまいます。
HSCは「蘭(らん)の子」
HSCの特性は「蘭の花」に例えられることがあります。

ゆう先生の補足解説:蘭(らん)の子育て
蘭は、すごく良い環境(適切な水、光、温度)に置かれると、他のどの花よりも美しく、見事に開花します。でも、環境が悪かったり、合わなかったりすると、すごく枯れやすいんです。
HSCの子も同じで、環境の感受性が非常に高い。その子の特性に合った安心できる環境があれば、その敏感さが「高い創造力」や「深い共感力」として花開く可能性を秘めているんですよね。
やってはいけないNG対応:「過保護」
ここまで聞くと、「じゃあ、とにかく守ってあげなきゃ」と思うかもしれません。でも、僕が一番お伝えしたいのは、過保護にしすぎないことです。
「お腹痛いのね、じゃあもうやらなくていいよ」と、すべてを先回りして守ってしまうと、せっかく持っている本人の能力(強み)にフタをしてしまうことにもなりかねません。
目指すべきは「本人の力を引き出す」関わり
大事なのは、本人の繊細さを「弱さ」ではなく「才能の裏返し」と捉え、その強みを引き出す関わりです。
- 予測可能で安心できる環境を作るHSCの子は、先の見えないことが不安です。視覚的なスケジュールを使ったり、「次〇〇するよ」と事前に計画を伝えたりして、脳の処理負担を減らしてあげることがすごく大事です。
- 失敗しても責められない空気を作る「失敗してもいいよ」という安心感が土台になります。1回転んでも、立ち上がってもう1回行く。また転んでも、また立ち上がる。この経験の連続性が、HSCの子の心の強さを作っていきます。
HSCの子は、いろんなことを深く理解できる賢い子が多いなと、僕は現場にいて感じます。だからこそ、大人が守りすぎるんじゃなくて、本人の自発性に任せながら、一緒に道を作ってあげる姿勢が大事なのかなと思います。
まとめ
今日の記事をまとめます。
- HSC(非常に敏感な子ども)は、病気や障害ではなく、人口の約20%(5人に1人)に見られる「生まれ持った気質」です。これは、かつて人類が生き残るための「警戒型」の戦略であり、弱さではありません。
- HSCの特性は「DOESモデル」で説明されます。特に「D:深く処理する」という特性が中心にあり、そこから「O:刺激を受けやすい」「E:共感が強い」「S:微細な変化を察知する」という特徴が派生しています。
- 学校などの刺激が多い環境は疲れやすいため、予測可能で安心できる環境を整えることが重要です。ただし、過保護にならず、本人が持つ「創造性」や「洞察力」といった強みを引き出す関わりを目指しましょう。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋Tれば、僕もとても嬉しいです。