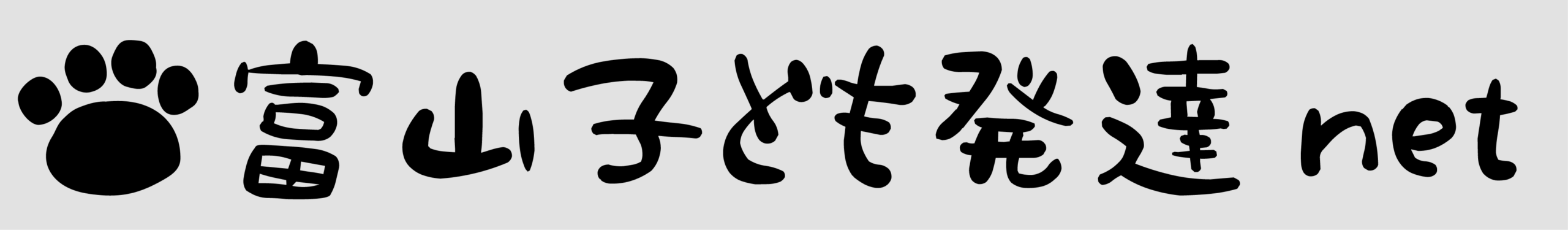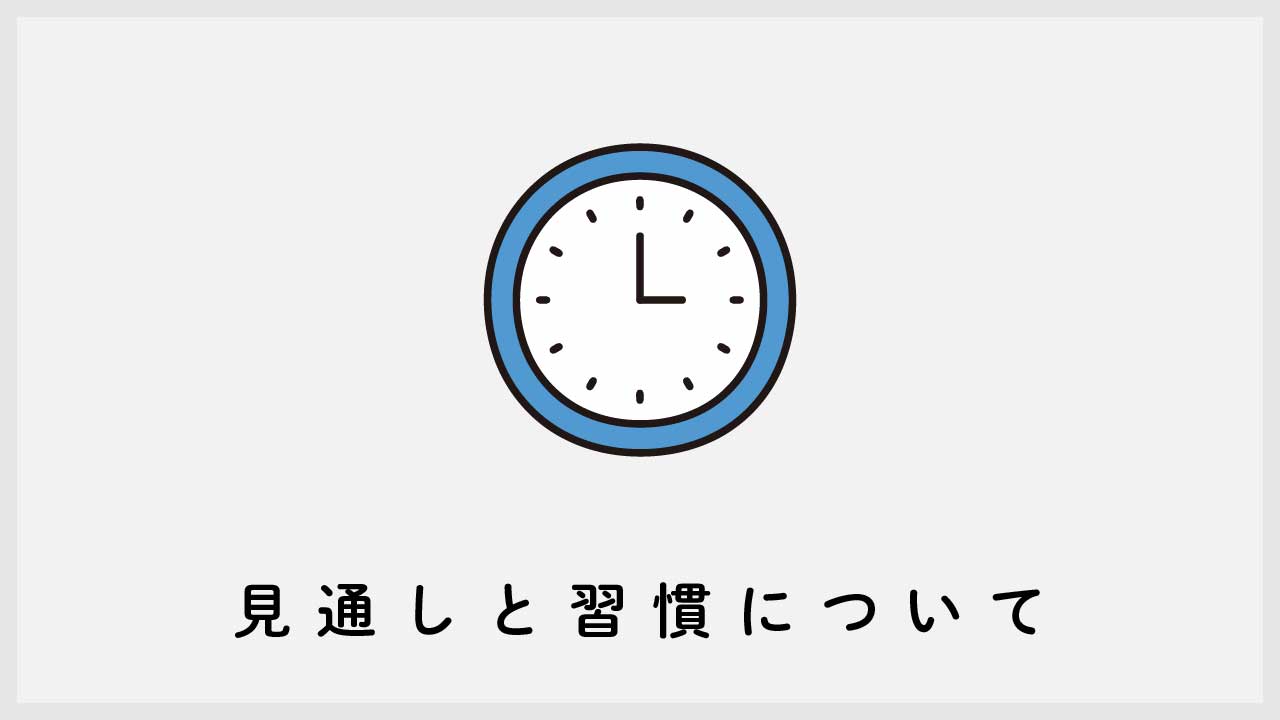支援者の心構えについて|僕の療育の考え方

こんにちは、ゆうです。
今日は「支援者の心構え」について、僕自身がこれまでいろいろな子どもや保護者、先生方と関わる中で「大事だな」と感じていることをお話しします。
支援者というのは、障害を持つ子どもの育児や教育をする周りの大人という意味です。
僕もまだまだ修行中の身で、知らないこともたくさんあれば、うまくいかないことも多いのですが、
その経験を通じて学んできた3つのポイントを、少しでも皆さんのお役に立てたらと思っています。

療育は簡単ではない
話を始める前に、最初に強調しておきたいのは、「療育は簡単ではない」ということです。
発達障害は「脳の機能障害」と言われますが、その原因や有効な支援方法など、まだまだ解明されていないことが多くあります。
だからこそ現場の先生や保護者の方は、日々試行錯誤を繰り返しながら、どうにかこうにか子どもをサポートし続けているのが実情です。
うまくいかないことが当たり前で、結果がすぐに見えないこともしょっちゅうあります。
でも、一歩ずつ着実に成長する子どもたちに寄り添っていくこと自体が療育であり、これが「医療的な側面」と「教育的な側面」を合わせ持つ療育という活動なのだと、僕は感じています。
ただ、簡単ではないし、親の方が疲れてしまうなんてことも多い療育ですが、大事なことは今から話す3つだけです。
僕がこの記事の後に話す、7つの基礎講義の内容はこの下に書いてある3つのことを、より深く、より具体的な形で表したものです。
難しいことではありませんが、とても大事なことなので、ぜひ覚えてみてください。
1. 先入観を持たないこと
世の中には発達障害についての情報がたくさんあり、「この特性にはこの支援がいい」といったマニュアル的な内容も数多く存在します。
それらは参考になることも多いのですが、いざ自分の子どもに合うかどうかは、実際やってみないとわからないんですよね。
「〇〇の特性があるから、これができない」と早々に決めつけてしまうと、本当は将来的にできるかもしれない可能性を潰してしまう危険があります。
特性を見立てることは大事ですが、それを根拠に「この子はこういう支援しか無理」とは思わないようにする。僕はそこをすごく意識しています。
今はできなくても、適切なサポートや学びの要素が積み上がれば、「できるようになる」ことは多いと感じます。
その芽を大人が先入観で摘んでしまわないよう、できるだけ柔軟に見守り、今必要なサポートに徹する姿勢を大切にしたいと僕は思っています。
なので、まずは「決めつけない」。程よく、三歩後ろくらいの距離から、子供を観察する癖をつけていきましょう。
2. 学び続けること
先入観を持たずに支援していくためには、自分自身が常に新しい情報や知識を取り入れることが重要です。
例えば、発達障害と言っても本当に千差万別で、いわば「オーダーメイドの支援」が必要になります。
自分の子に合う支援方法は、他の子に合わないかもしれないし、
他の子に合う支援方法は、自分の子供に合わないかもしれない。
だからこそ、多くの本や資料に目を通し、日々生活の中で実践して、うまくいったり失敗したりを繰り返して、自分の支援の引き出しを増やしていく必要があると感じます。
子どもは着実にちょっとずつ成長します。
それに合わせて支援者もちょっとずつ成長することが大事です。
急な癇癪や予想外の行動など、子どもはときに僕たちの想像を超えることをしてくれます。
そのときに、これまで学んだ知識をフル活用して「なぜ起きているのか」「どんな手立てが考えられるのか」を考えられる人でいたいですね。
僕自身、現場に立ち続け、試行錯誤を重ね、知識をアップデートし続けることで、少しずつ多くの方に信頼してもらえる支援ができるようになってきたと感じています。
なので、大事なことは、子供に合わせて、支援者もちょっとづつ学んだり、成長したりすることが大事ということです。
3. 子どもを本気で大切にすること
子どもが成長していく姿を見ると、僕はときに泣きそうになるほど感動します。
悲しんでいる様子を見ると一緒に悲しい気持ちになるし、子どもが正しくない行動をしているときは厳しく指導するときもあります。
それは、その子が将来自立して「この人生でよかった」と思えるようになるために必要だと思うからです。
昨今は、指導や支援のラインを見極めることが難しいと感じることもよくあります。
ただ今までの経験上、「言ったら嫌われる」「言ったことで二次障害になったらどうしよう」と思って行動しないでいるより、
ちょっと頑張って、子供に熱量を持って「良いことは良い!悪いことは悪い!」と伝えた時のほうが、
その瞬間はお互いぶつかっても、最後は上手くいっていることがほぼ9割かと思っています。
「子どもを大切にする」って、単に甘えさせることではないんですよね。
時には衝突もあるし、やりたくないことをやらせなきゃいけないこともある。
でも、すべては「この子が自分の人生を前向きに生きてほしい」という思いからの行動であり、僕自身「なんとかしてやりたい」「もっとできるようにしてあげたい」という気持ちで、仕事を超えた部分で関わっていると思います。
子どものために本気になれる大人がいると、子どもは一気に伸びることがあります。
支援者の皆さん(特にお父さん・お母さん)が本気で子どもを支えたいと思うならば、大変な道のりでも一歩ずつ乗り越えていこうと考えて行動することは重要です。
時にぶつかり、上手くいかず、支援者の皆さんも辛い気持ちになる時もあると思います。
ただ忘れないで欲しいのは、それでも、本当に大事なことを伝える。
それは、自分の子が大きくなった時に、「この人生でよかった」と思うためなのです。
だから、良いことをしたらいっぱい褒めてあげて、
悪いことをしたら、何がダメなのか、ちゃんとわかるように伝えてあげて、
本人が生きていくために必要な力を育んであげて欲しいと思います。
先生も親も、多くは子供よりも早くこの世をさります。
必ず必要な「時期」に、必要な「バトン」を渡してあげましょう。
僕自身、担当している子どもたちのことが本当に可愛いし、何か力になってあげたいと思うから頑張れるんだと思っています。
なので、大事なこととしては、よく可愛がり、よく教え、良い道に導くことなんだと思います。
まとめ
以上、先入観を持たないこと・学び続けること・子どもを大切にすること、という3つが、僕が療育や支援をする上で大切だと感じているポイントです。
もっと言えば、「現状を受け止め、状況や感情と向き合い、子どもと協力して良い人生を探していく」活動が療育なんだな、と感じます。
言葉で見ると簡単なように思えますが、実際は流動的で予測不能なことも多いし、常に「今」を大事に過ごす必要があります。
遠い先の結果が見えなくても、日々の積み重ねが将来の大きな成長につながると信じて、柔軟に取り組み続けることこそが支援者の本質なのかなと思います。
僕自身もまだまだ道半ばですが、今日お伝えしたことが少しでも皆さんのヒントになれば嬉しいです。
次回からが、支援の初心者が、実際に行う具体的な方法論になります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
では、楽しい療育ライフを始めましょう。