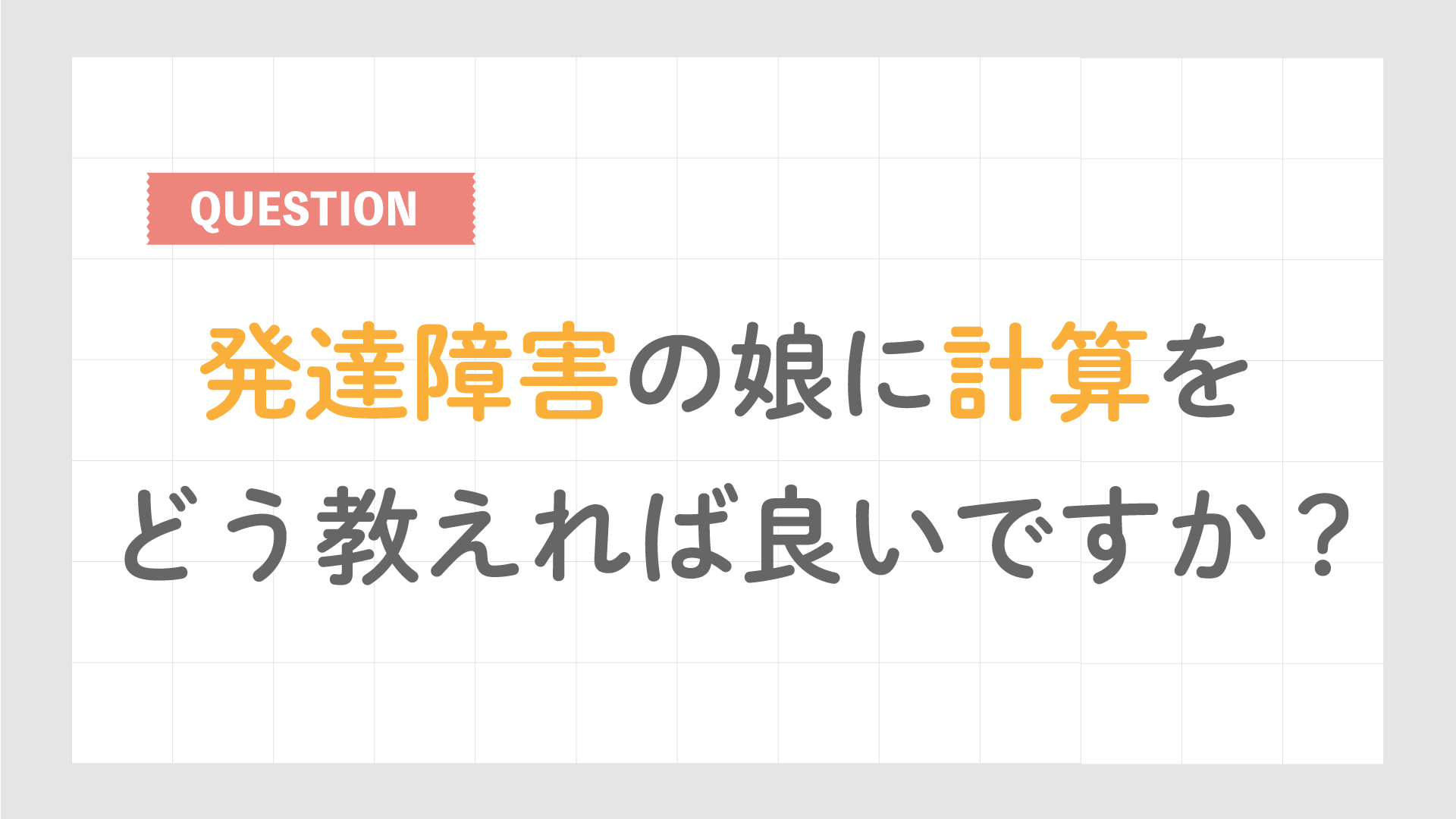「発達グレーゾーン」と「境界知能」の違いとは?富山の指導員が解説する“診断なき生きづらさ”の正体
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「発達グレーゾーンと境界知能の違い」についてです。
最近よく耳にするようになった「発達グレーゾーン」や「境界知能」という言葉。
どちらも似たようなニュアンスで使われることがありますが、「うちの子はどっちなんだろう?」「そもそも何が違うの?」と混乱されている保護者の方も多いのではないでしょうか。
実際、現場で保護者の方のお話を聞いていても、グレーゾーンだと思っていたら境界知能の特徴だったり、その逆だったりするケースもあります。
今日はこの二つの言葉の違いを整理していきたいと思います。
発達グレーゾーンとは?
まず「発達グレーゾーン」ですが、これは発達障害の特性が一部に見られる状態のことを指します。
例えば、自閉スペクトラム症(ASD)のような「社会性の課題」や、注意欠如・多動症(ADHD)のような「不注意」や「多動・衝動性」の特性が部分的に見られる。
でも、医学的な「発達障害」の診断基準を完全には満たさない状態。これが「グレーゾーン」と呼ばれる状態です。
発達障害がある(黒)と、発達障害がない(白)の、ちょうど中間。グラデーションの真ん中あたりにいるイメージですね。
社会性、注意、学習のどこかに課題があるけれど、「障害」とまでは言い切れない。こうした状態を指します。
診断名がないゆえの困難
グレーゾーンの難しいところは、まさに「白黒つかない」がゆえに、本人は生活や人間関係で「なんとなく生きづらい」「頑張っても報われない」と感じやすい点です。
明確な診断名がないので、公的な支援(例えば療育手帳や通級指導教室など)につながりにくい。
周りからも「ちょっと変わってるけど、できる部分もある」と見なされ、「性格の問題」「努力不足」と誤解されて、本人が傷ついてしまうことも多いんです。
だから僕は保護者の方に、「診断名や検査結果よりも、お子さん本人の“困り感”に着目しましょう」とよくお伝えしています。
境界知能とは?
一方で「境界知能」とは何でしょうか。
これは、知能指数(IQ)でいうと「70から85」の範囲にある知的水準のことを指します。

ゆう先生の補足解説:IQ(知能指数)とは?
IQ(Intelligence Quotient)は、同年齢の子どもたちの平均を「100」として、その人の知的発達の水準を数値で表したものです。
・平均的な知能:IQ 85〜115
・境界知能:IQ 70〜85
・知的障害(知的発達症):おおむね IQ 70未満
このように、境界知能は「知的障害」と「平均的な知能」の“境界”に位置することから、そう呼ばれています。
発達グレーゾーンが行動などの「質的」な特徴だったのに対し、境界知能はIQという「量的(数値的)」な特徴で定義されるものなんです。
境界知能の認知的な特徴
境界知能の方は、全体的な認知機能(物事を理解したり、考えたりする力)の発達が緩やかであるため、以下のようなことが苦手な傾向があります。
- 抽象的な物事の理解(例:「適当にやっといて」が分からない、比喩や皮肉が伝わりにくい)
- 複雑な判断や計画(例:頭の中を整理したり、段取りを考えたりするのが苦手)
- 処理速度(例:会話のテンポが早いと理解が追いつかない、新しいことを覚えるのに時間がかかる)
知的障害との大きな違い
境界知能も、発達グレーゾーンと同様に、医学的な診断名ではありません。
「じゃあ、IQ 69(知的障害)と IQ 70(境界知能)で何が違うの?」という疑問が湧きますよね。この1点の差に、どれほどの違いがあるのかと。
昨今では、IQの数値だけでなく、「適用機能」も重視されます。「適用機能」とは、日常生活や社会生活を送る上で必要な能力(例:身の回りのこと、コミュニケーション、読み書き計算など)のことです。
知的障害と診断される場合は、IQだけでなく、この適用機能にも明らかな困難さがあることが基準になります。
境界知能の方は、知的障害と診断されるレベルよりは適用機能が保たれており、「努力すればなんとか自立した生活が送れる」と判断されることが多いんです。
見えにくい困難と二次障害
しかし、「なんとかできる」からこそ、境界知能の方々の困難は見えにくくなります。
大人になってからも、会話は普通にできるし、仕事も一見こなせているように見える。
でも実際は、複雑な指示が理解できず、なんとなく仕事を進めてしまったり、処理が追いつかずにミスを繰り返してしまったりします。
周囲からは「普通にできる人」と思われているため、「なぜこんな簡単なことができないんだ」「努力が足りない」と叱責され、強いストレスを抱え込みます。
その結果、「自分はダメなんだ」と自己否定感が強まり、「うつ」や「適応障害」といった二次障害を引き起こしてしまうケースが非常に多いのが現実です。

ゆう先生の補足解説:二次障害とは?
二次障害とは、発達障害や境界知能などの元々の特性(一次障害)が原因で、周囲の無理解や不適切な対応、失敗体験の積み重ねなどによって引き起こされる、別の心の問題(うつ、不安障害、適応障害、不登校、引きこもりなど)を指します。本人の生きづらさが深刻化しているサインでもあります。
決定的な違いと、重なる場合
ここで、二つの違いをもう一度整理します。
- 発達グレーゾーン = 特性の問題(質的)(例:ASD的、ADHD的な行動の特徴)
- 境界知能 = 知的能力の問題(量的)(例:IQが70〜85の範囲)
このように、見ている側面が全く違います。
2つの状態が重なる場合
さらにややこしいのですが、この2つの状態が重なるケースもあります。
「発達グレーゾーン(ASDやADHDの傾向がある)」であり、かつ「境界知能(IQも70〜85)」という場合です。
こうなると、特性の問題と知的能力の問題が組み合わさり、物事の理解や状況判断、注意のコントロールなどがさらに難しくなり、学校や職場で困りごとが頻発しやすくなる可能性があります。
なぜ今、生きづらさが目立つのか?
発達グレーゾーンも境界知能も、支援が届きにくい「狭間」にいる人々です。
支援学級に行くほどではないけれど、通常学級のスピードについていくのはしんどい。その結果、学校で「努力が足りない」と見なされ、自尊心が低下していく…という負のループに陥りがちです。
そして、この問題が今になって目立ってきた背景には、現代社会が求めるスキルの高度化も関係していると僕は思います。
昔よりも、曖昧な指示の理解、複数のタスクの同時処理、迅速な判断など、高度な認知スキルが求められる場面が増えました。
こうした社会の変化が、境界知能や発達グレーゾーンの人々にとって、過剰なストレスや失敗体験を引き起こしやすくなっている側面があるんですよね。
また、人付き合いの複雑さから、金銭トラブルや詐欺などに巻き込まれやすい傾向も指摘されており、周囲のサポートが非常に重要になります。
【6】まとめ
今日の記事では、「発達グレーゾーン」と「境界知能」の違いについて解説しました。
- 発達グレーゾーンは、「質的」な特性の問題です。発達障害の診断基準は満たさないものの、ASDやADHDなどの傾向が部分的に見られる状態を指します。
- 境界知能は、「量的」な特性の問題です。IQが70〜85の範囲にあり、知的障害と平均の間に位置する知的水準を指します。
- どちらも医学的な診断名ではないため、公的な支援につながりにくいという共通点があります。その結果、「努力不足」と誤解され、本人が疲弊し、二次障害を引き起こしやすいという深刻な課題を抱えています。
結論:読者へのメッセージ
この社会構造の中で、生きづらさを感じるのは本人のせいだけではありません。社会の変化と個人の特性がミスマッチを起こしている、とも言えます。
ただ、社会を恨んだり、攻撃したりしても、現実はなかなか変わりません。僕らはこの世界で生きていかなければならない。
だからこそ、まずは「自分(我が子)の特性を知ること」、そして「無理はしなくていい」と知り、「自分ができること」「自分が楽にできる場所」を誠実に探していくことが大切なんじゃないかなと、僕は思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。