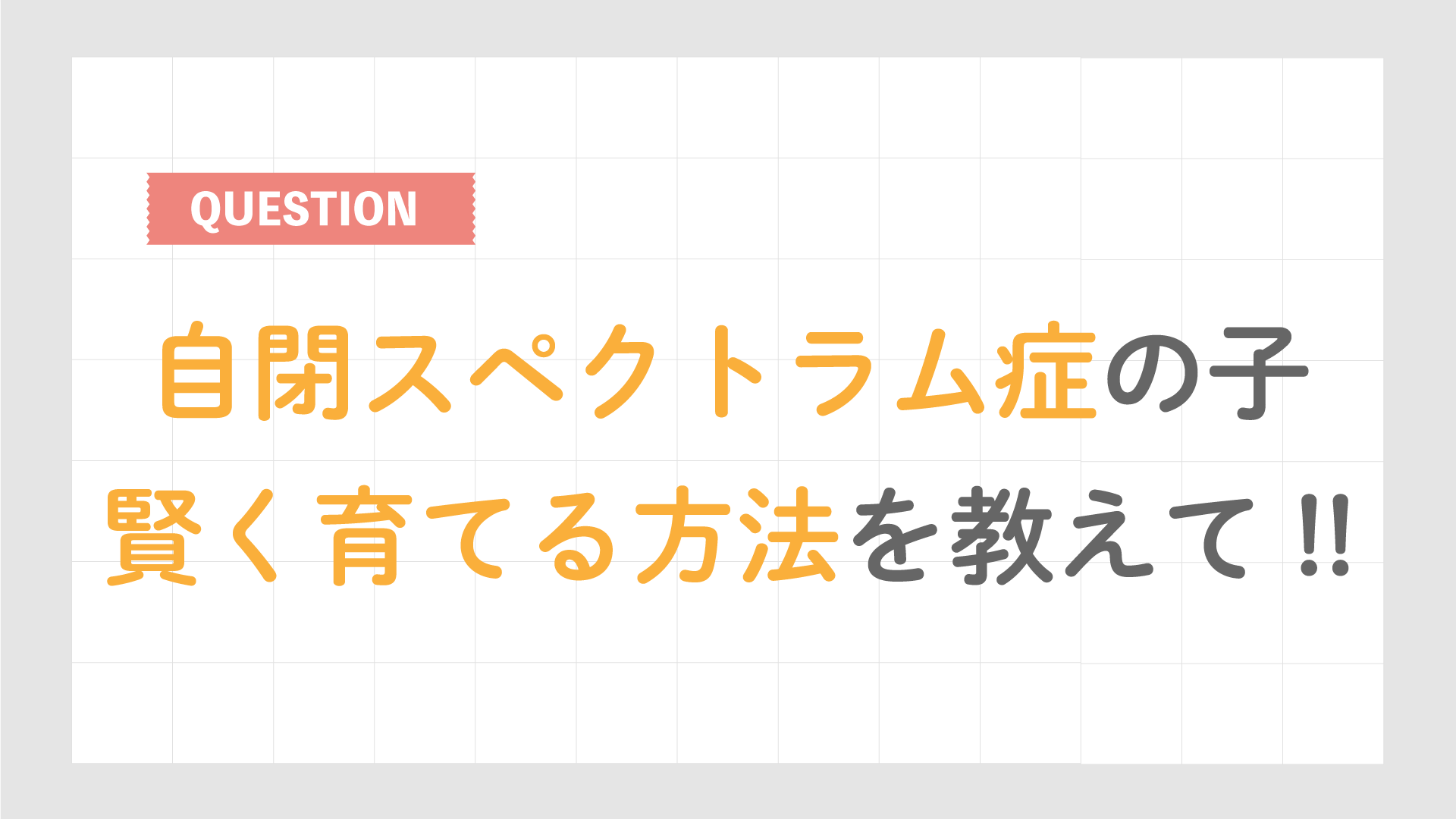ADHD子育て「あるある」10選。保護者の「育て方が悪い?」という悩みに支援員が答えます
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ADHDのお子さんを育てる保護者や支援者が共感する『子育てあるある10選』」についてです。
ADHDの子育て「あるある」10選
さて、ということで今日に関してはADHDの子育てあるある10選ということで、僕が今までADHDのお子さんを持つご家庭から聞いてきた話や、
ネット上の多くの情報をリサーチして、特に「あるある」と感じる10個のエピソードをまとめさせていただきました。
これらのエピソードを通して、保護者の皆様が「1人ではない」ということ、そしてその困難がADHDの特性によるものだという理解を深めていただけると嬉しいなと感じます。
1. 探し物と忘れ物のエンドレスループ
やっぱりADHDの子育てや療育中、よくあるのは「探し物」と「忘れ物」がずっと続く、ということですね。
特に「朝の支度中に、毎日探し物から始まって朝がすごくバタバタしてます」とよく言われます。
宿題だったり、体操服だったり、毎日何かしらがなくなっていて、探し物から1日が始まることが少なくないそうです。
学校に持っていったはずの物がなくなっていたり、どこに置いたか思い出せなかったり。
これは主にADHDの「不注意」の特性に関連が深くて、保護者の方の朝の精神的な負担を増やしてしまうことが多いのかなと感じます。

ゆう先生の補足解説:不注意と「実行機能」
これは本人の「やる気」や「だらしなさ」の問題ではなく、脳の「実行機能(じっこうきのう)」の課題です。
特に「ワーキングメモリ」という、情報を一時的に記憶しておく「脳の作業台」のような機能が関係しています。ADHDの特性があると、この作業台が小さかったり、情報が散らかりやすかったりします。
そのため、「水筒をカバンに入れる」という指示を聞いても、次の瞬間に別の刺激(例:テレビの音)が入ってくると、水筒の情報が作業台からポロッと落ちてしまい、忘れてしまうんです。
2. 常に動き回るエネルギーの塊
食事中だったり、授業中だったり、静かに座っていることが難しい、というのも「あるある」ですよね。
その場面でも手足がモジモジしていたり、席を立ってうろうろしたり。例えば、消しゴムを分解していたり、穴を開けていたり、何かしら活動していることが多いです。
本当に「エンジンが搭載されてるみたい」な感じで、常に何か後ろから押されているように動き回っている。これは主にADHDの「多動性」の特性によるものです。
なぜじっとしていられないのかというと、一説には「脳の覚醒レベル(意識のハッキリ度)」を一定に保つのが苦手だから、と言われています。
じっと座っていると脳の覚醒レベルが下がりすぎて眠くなってしまうため、逆に体を動かしたり、手遊びをしたりすることで脳に刺激を入れ、最適な覚醒レベル(集中できる状態)に自分で調整しようとしている、という側面もあるんです。
3. 話の途中でも遮っちゃう
これもADHDの「あるある」かなと思います。衝動的な発言で、会話が途切れることがよくあります。
例えば僕が話している時でも、話が終わる前から話し始めてしまったり、お友達との会話の中でも急に被せてきたり。
まさに頭に思い浮かんだことを、すぐに口に出してしまうんですね。
その結果、お友達から「むっ」と思われたり、「人の話を聞かない子だな」と誤解されたりしがちかなと感じます。これは主にADHDの「衝動性」の特性に関連が深いとされています。
これは脳の「抑制機能(よくせいきのう)」という、いわば「ブレーキ」をかける力の課題です。
「相手の話が終わるまで待とう」というルールは頭でわかっているんです。でも、頭に浮かんだ「言いたい!」というアクセル(衝動)の方が、ブレーキの力よりも強くなってしまい、行動を止められないんです。
4. 宿題、いつになったら始めるの?
「宿題ができない」というより、「何回言っても宿題をなかなか始められなくて、夜の8時とか9時になってギリギリでやる」というご相談は、僕がやってる学習支援塾でもすごく多いですね。
やるべきことがあるのに、なかなか手をつけられず先延ばしにしてしまう。保護者が声かけをしても、逆に癇癪を起こしたり、別な遊びに夢中になったり。
これ、自分自身も昔そうだったなと思います(笑)。
やろうと思っても、なんかやる気が出なかったんですよね。母親から怒られて、めんどくさい気持ちで適当に終わらす…みたいなことが多かったです。今更ですが、母には大変迷惑をかけたなと反省しています。
これもADHDの「実行機能」の一つ、「課題の開始(Task Initiation)」の困難さです。
やる気がないのではなく、物事を始めるための「最初の一歩」のエンジンをかけることに、ものすごく大きなエネルギーが必要なんです。一度始めてしまえば(過集中で)一気に終わらせることもあるのですが、その「0から1」にするのがとても大変なんですね。
5. 危険行動にヒヤヒヤ「なんでそんなことするの?」
危険をかえりみない行動に、保護者の方がヒヤヒヤする、というのも「あるある」です。高いところから飛び降りたり、車道に急に飛び出したり、危険な行動を平気で繰り返すことがあります。
これ、ちなみに僕のエピソードなんですけど、年長さん(5〜6歳)の頃、車に轢かれたことがあるんです。
車道の反対側に母親がいると勝手に思い込んで、横断歩道でもない車道を突っ切ったら、車に当たりました。幸い、減速してた車だったので軽い怪我で済みましたが、今思うと明らかな「衝動性」だなって思います。

ゆう先生の補足解説:衝動性と「リスク評価」
「危ない」ということが分からないわけではありません。
ですが、「あ、お母さんがいる(かもしれない)!行きたい!」という衝動が湧き上がった瞬間に、ブレーキ(抑制機能)が効かずに行動が先に出てしまうんです。
行動した後に「危なかった」と気づくことはあっても、行動する「前」に立ち止まってリスクを評価するのが難しいんですね。
6. 感情のジェットコースター
些細なことで感情が大爆発して、即座に癇癪が起きたり、涙が止められなくなったりする。これもよく聞く話です。
(特にASDの特性と併発していると、より感情の爆発が起こりやすい傾向もありますが)これは単なる「わがまま」じゃなくて、
ADHDの脳の特性上、心の中に蓄積された不安やストレスを制御しきれなくなって、感情が溢れ出ている状態なのかなと感じます。
これも「実行機能」の一つである「情動調節」の困難さです。
感情をコントロールするのが苦手で、ストレスや不快感を溜めておく「心のコップ」が小さい、あるいは、溜まってもうまく外に「小出し」にできないイメージです。
そのため、些細なことがきっかけでコップの水が一気に溢れ出し、癇癪という形で爆発してしまうことがあります。
7. 何度言っても「効かない」…?
「何度注意しても、まるで聞いていないようなもどかしさがある」というのも、よくありますね。
僕も療育中に、多動も衝動も不注意も持っている子に、真面目に「こうしてね」って伝えると、「はい、分かりました!」って、すごくすごく元気よく返事してくれるんです。でも、次の瞬間には忘れてる(笑)。
この掛け合いが、僕はすごく愛おしいなと思うんですけど、お父さんお母さんからしたら「何回言っても伝わらない…」と、もどかしさや無力感を感じる場面かなと思います。
これは「聞いていない」のではなく、「(ワーキングメモリから)消えてしまう」んです。
耳から「〇〇やっといてね」という指示は入るんですが、それを脳の作業台(ワーキングメモリ)に保持して、行動に移す前に、
別の刺激が入ってきたりして、その情報が消えてしまうんです。だから本人に悪気は全くないんですよね。
8. 片付けられない魔法
部屋がいつも散らかり放題で、終わらない整理整頓に悩まされる…。これもADHDあるあるですね。
学校から持ち帰ったプリントや教材をどこに置いたか分からなくなる。ランドセルを開けたら、底の方にプリントが「化石」みたいになってる(笑)。
僕もこれ、めちゃくちゃありました。プリントをもらってないとか言って、親に怒られるっていうのがよくありましたね。
「片付け」は、「①いる・いらないを判断する」「②どこに何をしまうか計画する」「③順番通りに実行する」という、非常に高度な「実行機能」を使います。
ADHDの特性があると、この「計画立案」や「整理整頓(情報を分類する力)」が苦手なため、どこから手をつけていいか分からず、結果的に散らかったままになってしまうんです。
ちなみに僕は、大人になってから「部屋に物を置かなければ散らからない」という結論に至り、解決しました 。笑
9. 悪気はないんだけど、やってしまう
順番を待てずに横入りしたり、お友達の邪魔をしたり、衝動的に手を出してしまったり。
本人に「悪気」は意外とないんだけど、結果的に友達を傷つけてしまう。療育施設に来られるきっかけとして、この「お友達トラブル」はすごく多いです。
本人に話を聞いてみると、「そういうつもりじゃなかった」「そん時、よくわかんなくなっちゃった」って言うんですよ。
「止めたいんだけど、止められない」というのが、ADHDの子どもたちの辛いところなのかなと感じますね。

ゆう先生の補足解説:「わかっちゃいるけど、止められない」脳の仕組み
これも「衝動性」と「抑制機能」の課題です。
脳の「行け!(Go!)」という信号が、「待て!(Stop!)」という信号よりも圧倒的に早く、強く出てしまうんです。
特に小学生くらいになってくると、本人も「本当はダメだ」とわかっているのに体が動いてしまうので、本人自身が一番悩んでいるケースも多いですね。
10. 「親の育て方が悪い」と自分を責めてしまう
最後のあるあるエピソードは、保護者の方自身の悩みです。
お子さんの落ち着きのなさや衝動的な行動が目立つと、周りから「しつけが足りない」「親が甘いからだ」といった視線を感じたり、言葉を投げかけられたりすることがある、というお話です。
特におじいちゃんやおばあちゃん(親御さんのご両親)から、昔の育て方と比べられて「あなたの教育が悪い」と言われ、自信をなくしてしまう、という話は本当によく聞きます。
これに対して僕がいつも言えることは、まず「本当にお疲れ様です」ということです。
「大丈夫ですよ」という簡単な言葉は言えません。お子さんが癇癪を起こしたり、うまくいかない姿を見るのは辛いでしょうし、変えられない自分も辛い。本当に難しい問題だと思います。
でも、一つだけ言えることは、あなたは1人じゃないということです。
今、辛い気持ちや、自分を責める気持ちを抱えている保護者の皆さんに僕が言いたいのは、「1人で頑張らないで」ということです。
障害という課題は、1人で解決できる問題じゃないと僕は思っています。僕ら支援者、病院の先生、学校の先生、みんな「チーム」です。誰かを頼って、一緒に頑張っていきましょう。
何度も言いますが、ADHDの行動は「しつけ」や「育て方」の問題ではなく、「脳の機能特性」によるものです。
この違いを理解してもらえず、親や子ども自身が「自分が悪いんだ」と責め続けると、自己肯定感が下がり、うつや不安障害などの「二次障害」を引き起こすリスクが高まります。だからこそ、正しい理解と外部のサポートが不可欠なんです。
まとめ
さて、10個のあるあるエピソード、皆さん、いくつ当てはまったでしょうか。
最後に、僕が伝えたいことをまとめさせてください。
1. 子どもの行動は「脳の特性」によるもの
まず、ADHDの行動の多くは、本人のわがままや、お父さんお母さんのしつけ不足ではありません。「止めたいんだけど、止められない」脳の特性によるものです。お子さんを責めたり、自分を責めたりするのをやめて、「今、この環境で何ができるか」と前向きに目を向けることが一番大事かなと感じます。
2. 1人で抱え込まず、外部のサポートを
保護者の方が1人で抱え込まず、外部のサポートを積極的に活用してほしいです。発達障害は、本人を無理やり変えようとするのではなく、環境(人や場所)を整えることで、本人が自然に変わっていくのが理想です。そのためのチームとして、僕らのような療育施設や専門家を頼ってください。
3. 「強み」を活かす長期的な視点を
早期からの療育(発達支援)は、不登校やうつなどの「二次障害」を予防するためにも非常に重要です。
そして、僕がお父さんお母さんに一番伝えたいこと。
ADHDの特性は、裏を返せば「高い好奇心」「溢れるエネルギー」「特定分野への深い集中力」といった「強み」でもあります。
僕自身、小さい頃は虫取りに夢中な「虫博士」で、学校の勉強はダメダメでした(笑)。でも、あの時に本気で集中して取り組んだ経験が、大人になった今の集中力や専門性につながっていると思うんです。
弱み(できないこと)は環境でサポートしてあげて、強み(好きなこと、得意なこと)はどんどんやらせて伸ばしていく。
5年、10年先を見据えて、お子さんの「好き」という小さな炎を育てていく、長期的な目線を持ってほしいなと思います。
結論:読者へのメッセージ(お決まりの締め)
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。