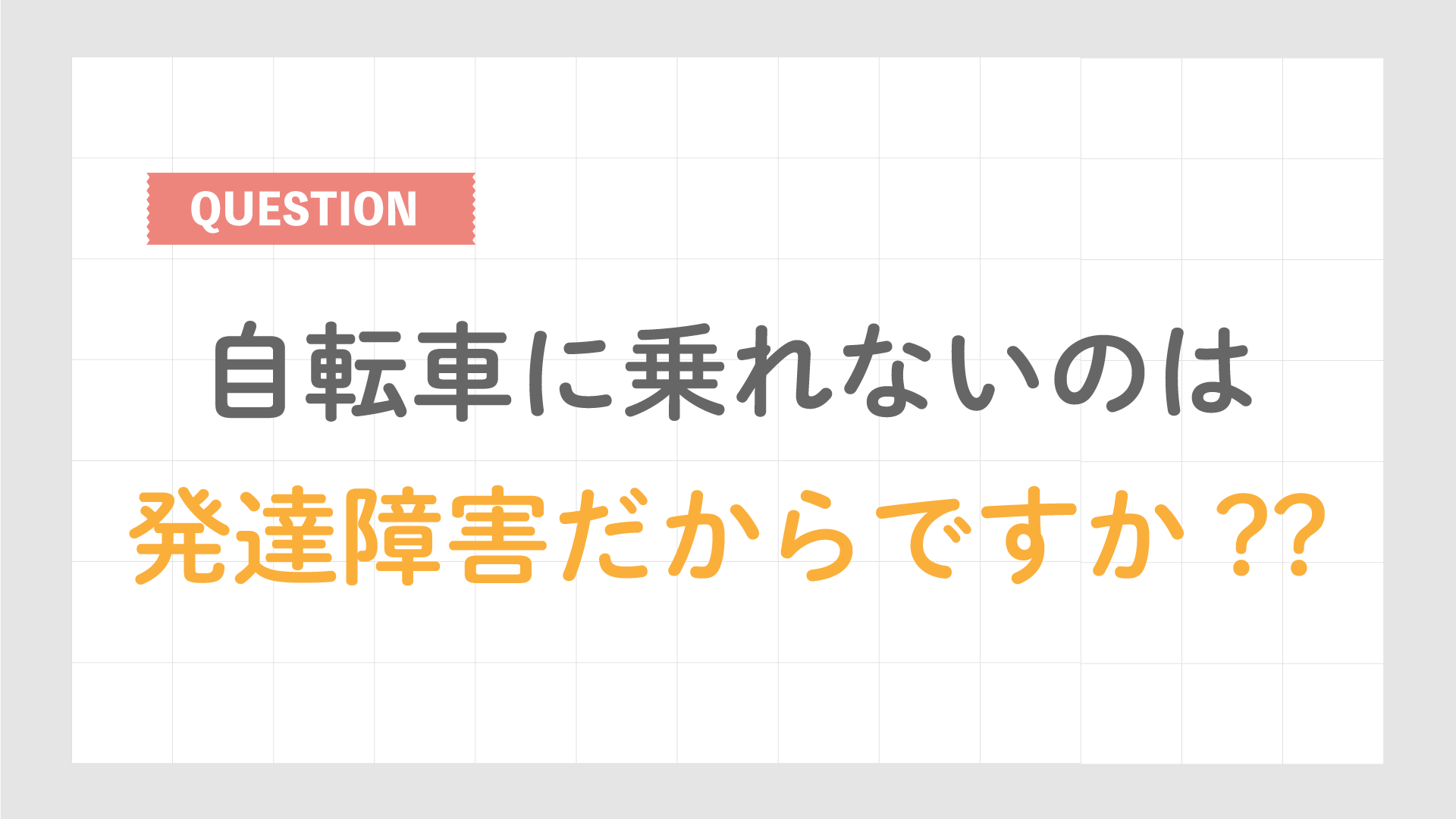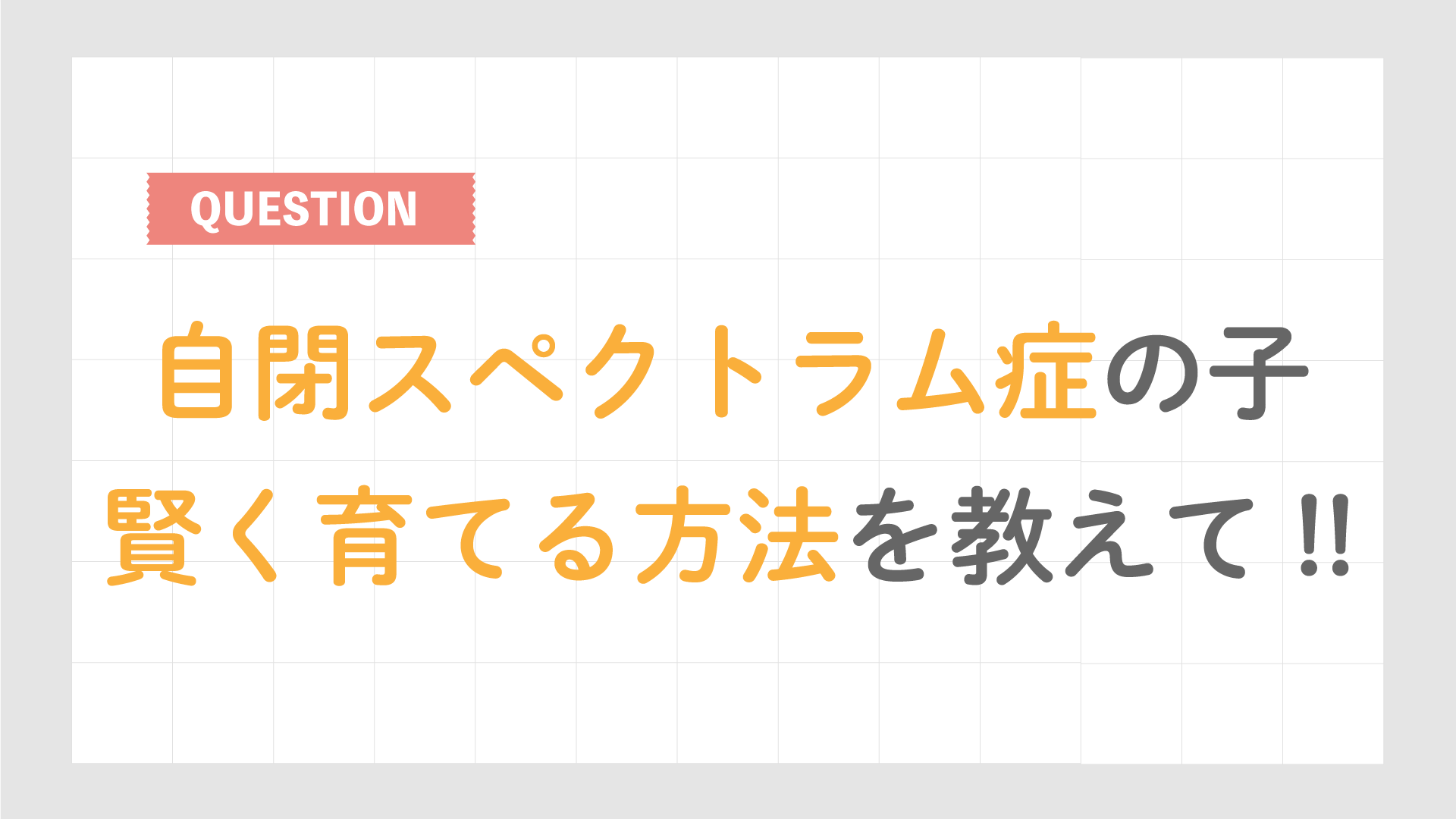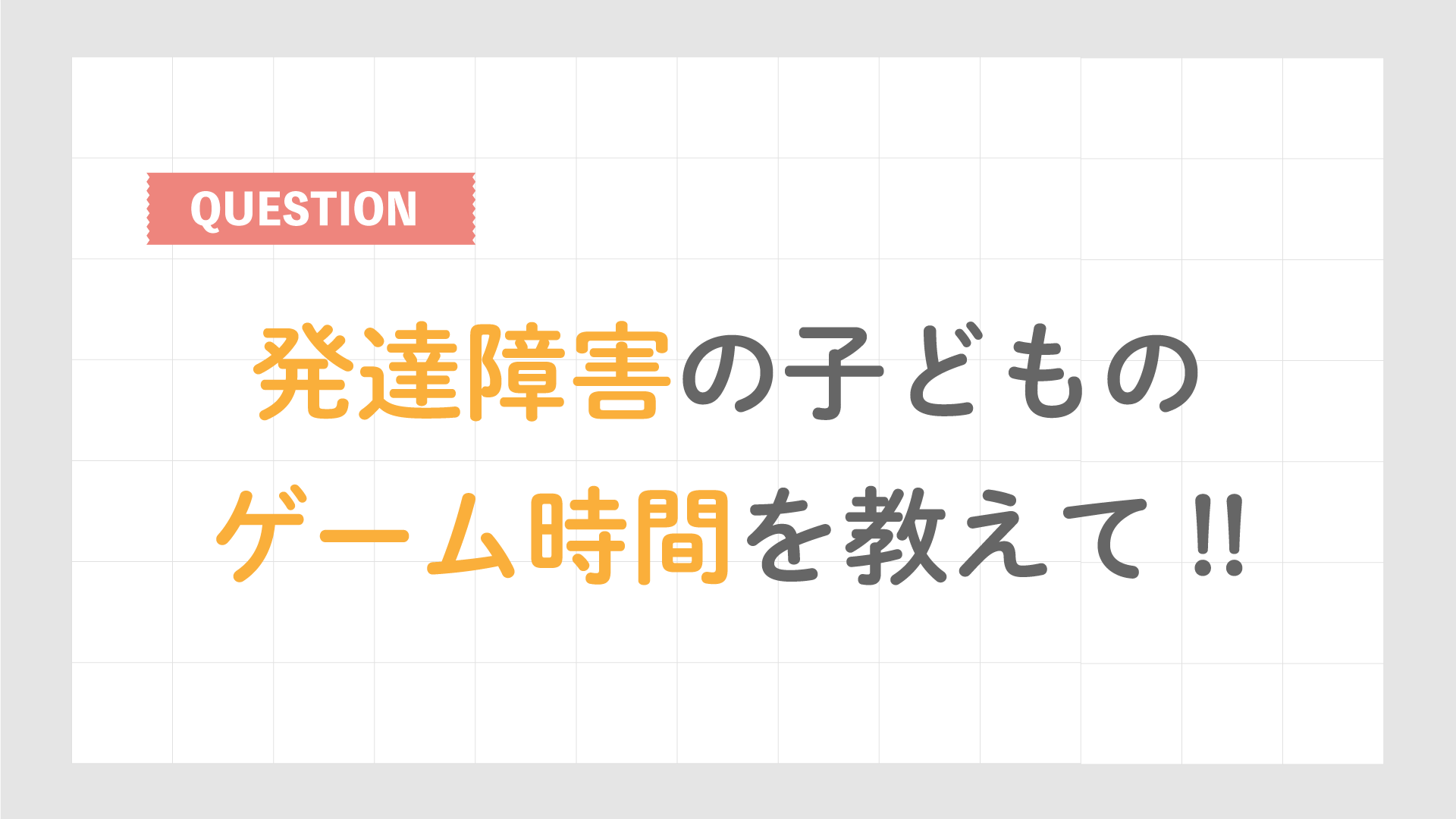ADHDの子に「じっとして!」が通じない本当の理由。努力不足ではなく脳の特性で
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ADHD(注意欠如多動症)のお子さんになぜ『じっとしなさい』という指示が通りにくいのか」についてです。
ADHDの3つの主な特徴
さて、ということで今日は「じっとしていてはなぜ通じないのか」というテーマでお話ししていくんですけれど、まずADHDについて少し解説させていただきますね。
ADHD(注意欠如多動症)というのは発達障害の一種で、主に「不注意」「多動性」「衝動性」という3つの特徴があります。
これらの行動は、本人の努力不足だったり、性格の問題だったり、あるいは保護者の方のしつけの仕方でなるわけではなく、元々の脳の神経回路に原因がある(特性がある)という感じなんです。
ここを間違えてしまうと、「頑張って(しつけを)やったんだけど、なかなか結果が出ない」と親御さんも疲弊してしまいますし、お子さん自身も疲弊してしまう。
まずは「脳の機能的な問題があってできていないんだよ」というところを覚えておいてほしいかなと感じます。
具体的には、集中力が続かない、じっとしていられない、順番が待てない、忘れ物やなくし物が多い、といった特徴があります。
一般的には「こんくらい頑張ればできるんじゃない?」と思われてしまうかもしれないんですけど、現実、本人たちは脳の機能的な課題によってうまくできず、苦しい思いをしていることも多いので、「頑張ってもできない時もあるんだよ」と理解していただけると嬉しく思います。

ゆう先生の補足解説:ADHD(注意欠如多動症)とは?
ADHDは「Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder」の略です。生まれつきの脳機能の発達の偏りによるもので、主な特徴が以下の3つです。
- 不注意:集中力が続かない、気が散りやすい、忘れ物が多い。
- 多動性:じっとしていられない、手足をソワソワ動かす。
- 衝動性:考えるより先に行動してしまう、順番が待てない、話に割り込む。
これらの特性が「しつけ」や「育て方」が原因ではない、という点が支援の出発点として非常に重要ですね。
1. 多動性
手足を動かし続けたり、座っていられなかったりする特徴で、まさに今回のテーマである「じっとしていられない」という部分ですね。
大人から「静かに」「止まって」と言われることが多いのが、この特性が強い子どもたちかなと感じます。
この多動性って、本人の内側からの「衝動」なんです。脳機能でいうと「抑制機能」がうまく働かないことによって、動き出してしまう、喋ってしまう。本人の意思だけで止めるのは難しいのが、この多動性という部分にあたります。
2. 衝動性
考える前に行動してしまう傾向のことです。順番を待てない、相手の話を遮って喋り始めてしまう、衝動的に物を取ったり壊してしまったり。
これも旗から見ると「なんでこんなことするんだろう」と思われがちですが、これも抑制する脳の機能が未発達なことが多く、本人も「やってしまった」と後で苦しんでいることも多いんですよね。この衝動性と多動性はリンクしている時もあります。
3. 不注意
集中力の持続時間が短かったり、気持ち(興味)がすぐにコロコロ変わってしまったりする特性です。結果として、授業中に外を見ていて集中できない、忘れ物が多い、順序立てて物事を進めるのが苦手、といった行動が見られます。
これも「だらしない」と思われがちですが、集中力を保つ神経の働きに特徴があるので、なかなか努力しても難しいところがありますね。
なぜ「じっとしていて」が通じないのか?脳の仕組み
では、なぜ「じっとしなさい」という指示が通じないのでしょうか。
結論を言いますと、ADHDの「じっとしていられない」行動の背景には、「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という脳の働きと、「神経伝達物質(しんけいでんたつぶっしつ)」の働きが関係していて、ここがうまくコントロールできていない結果なんです。
1. 前頭前野(実行機能)の偏り
前頭前野っていうのは、思考(考える力)や行動のコントロールを担う脳の領域です。ADHDのある人は、この部分の調整機能に偏りが見られると言われています。
物事に対して全然我慢ができなかったり、逆に、ある物事に対しては過集中気味に集中しすぎちゃったり。こういう「ちょうどいい」コントロールが効きづらいところがあります。

ゆう先生の補足解説:前頭前野と実行機能
前頭前野は、おでこのすぐ後ろにある脳の「司令塔」のような場所です。物事を計画したり、我慢(抑制)したり、行動を調整したりする「実行機能」という大切な役割を担っています。
ADHDの場合、この司令塔の働きの偏りによって、感情や行動の「ちょうどいい」コントロールが難しくなり、極端な行動(我慢できない、または逆に集中しすぎる)に出やすいと考えられています。
2. 神経伝達物質のアンバランス
ドーパミンとかセロトニンとか、色々あるんですけど、こういう神経伝達物質がバランスよく出ていない、ということも関係しています。
脳の中でのスムーズな情報伝達が起こりにくく、行動や注意のコントロールが難しくなると言われています。
すごく簡単にイメージすると、ドーパミンやノルアドレナリンは「アクセル(意欲・興奮)」、セロトニンは「ブレーキ(安心・抑制)」の役割を持つ脳内物質です。
ADHDの場合、このアクセルとブレーキのバランスがガタガタな状態なんです。
だから、アクセルが効きすぎて衝動的に動いてしまったり(多動・衝動)、逆に意欲のアクセルがうまく踏めなかったり(不注意)すると考えられています。
この攻めと守りのバランスが極端になりがちなんですよね。
見えない「脳内多動」と「報酬系」の課題
さらに、ADHDの子どもたちには、外見からは分かりにくい困難もあります。
1. 頭の中が常にフル回転(脳内多動)
「脳内多動(のうないたどう)」って言うんですけど、外見としては落ち着いて見える時でも、頭の中では次々に思考が浮かんでもうフル回転状態、ということがまあまああります。
いろんなことを常に考えているんですよね。だから、一つのテーマで話していても、頭の中ではどんどん話がズレていってしまったりする。この状態は、脳がすごく疲れやすい状態でもあります。
静かな環境にいればいいかというと、脳内多動は環境に関係なく、自分の中から湧き起こってくるものなんです。
だから、環境設定だけを整えても、本人の内側で起こっているこの衝動性に目を向けないと、支援は難しいのかなと感じます。
2. 「待つこと」が苦手な報酬系
脳の「報酬系(ほうしゅうけい)」という部分にも偏りがあると言われています。
これは、短期的な快楽(すぐに得られるご褒美)にはものすごく強く反応するんですけど、長期的な報酬(地道な努力の末のご褒美)にはモチベーションが続かない、という特徴です。
学校で「お話を聞く」という行動は、地道な作業ですよね。これをやり続けた先にある「良いこと」よりも、今すぐ得られる刺激(立ち歩く、違うことをする)の方に脳が反応してしまう。
だから、話を聞くのが耐えられなくなって走り始めちゃったりする、ということも起こるわけです。
支援の出発点:「止められない」ことへの理解
ここまで話してきた通り、「じっとしていて」がなぜ通じないのかというと、本人の意思だけではコントロールできないことが脳の中で起こっているからです。
脳内多動が起きていたり、前頭前野の働きが弱かったり、神経伝達物質がアンバランスだったり…。
「じっとしていたい」と思っていても、「じっとしていられない」何かが体の中で起こっている。じっとしていること自体が「苦痛」になっている状態とも言えます。
これ、例えるなら、視力の弱い子に「よく見て!」って言うのは結構厳しいじゃないですか。目が見えない人に「見ろ」っていうのは無理な話ですよね。
それに近くて、脳の機能上じっとしていることが難しいのに「じっとしていて」と指示するのは、本人にとって無理難題な可能性が高いんです。
繰り返される注意が自己肯定感を下げる
僕がお父さんお母さんに一番伝えたいのはここなんですけど、この「止められない」ということを理解せずに、「なんでできないの!」と繰り返し注意されてしまうと、どうなるか。
本人はコントロールが難しい行動を注意され続けることで、「あぁ、自分はダメなんだな」という誤解が生じて、自己肯定感がどんどん下がってしまいます。
これが「二次障害」に繋がることも多いのがADHDなんです。
すごく眠い時に「寝るな」って言われてもウトウトしちゃいますよね。それで寝ちゃった時に「なんで寝たんだ!」って怒られても、止められないじゃないですか。
もっと言うと、僕ら「息」って無意識で吸ってますよね。それを「息を吸うんじゃない!」って言われて我慢しても、無理だから吸っちゃいます。
その瞬間に「なんで息した!」って言われても、「そんなの無理じゃん!」って思いませんか?
ADHDの子の「じっとできない」という行動は、それに近い状態なんです。
本人にとってコントロールできない、衝動的・自動的にやってしまう行動を繰り返し注意されると、親子関係や友人関係にヒビが入ったり、孤立感を深めたりします。そして「また怒られる」と思うから、ごまかしたり、嘘をついたりすることも増えてきてしまう。
だから、まずはこの状況、「頑張っても頑張っても、どうやっても止められない気持ちがあるんだよ」ということを、支援する側が心に刻んでおくことが本当に大事です。
もちろん、ADHDだからといって社会のルールを守らなくていいわけではありません。やるべきことはやらなきゃいけないと僕は思っています。
でも、その大前提として、「本人には止められない脳の特性がある」ということを分かっていないと、子どもたちに無理をさせすぎて、心を辛い思いにさせてしまうことが多くなります。
まずは本人の困り事に寄り添うこと。脳の働きを理解することが、支援の出発点なんですよね。
まとめ
今日のポイントを振り返ります。
- ADHDの子が「じっとできない」のは、本人のやる気やしつけの問題ではなく、脳の「前頭前野」の働きの偏りや、「ドーパミン」などの神経伝達物質のアンバランスといった脳機能の特性が原因です。
- 外見からは分かりにくい「脳内多動(頭の中が常にフル回転)」や、「報酬系(長期的な我慢が苦手)」の偏りも、落ち着きのなさに関係しています。
- これらの行動は本人の意思で「止められない」ことが多く、「じっとして!」と繰り返し注意することは、「自分はダメな子だ」という自己肯定感の低下を招く危険があります。まずはその特性を理解し、寄り添うことが支援の第一歩です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。