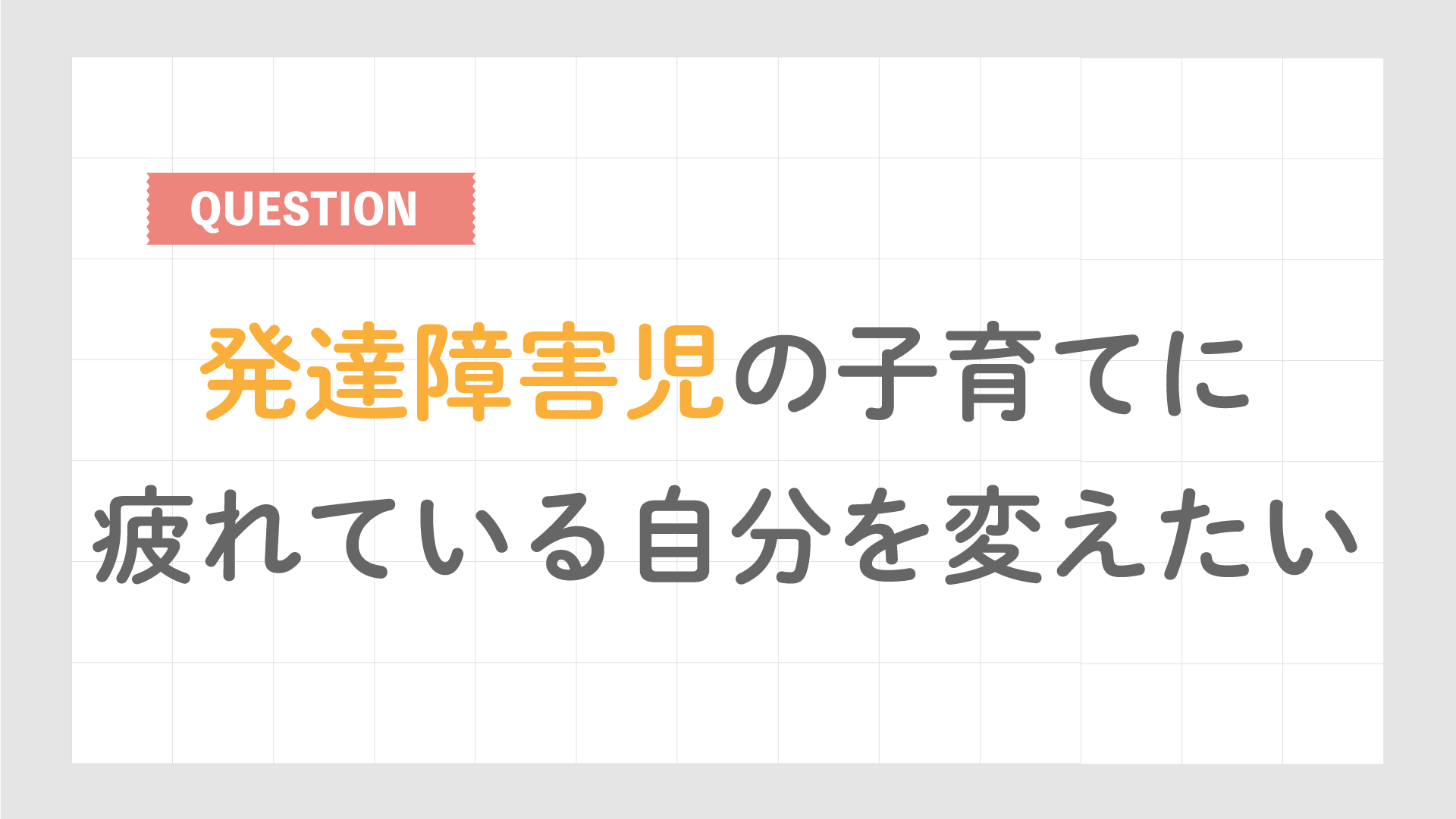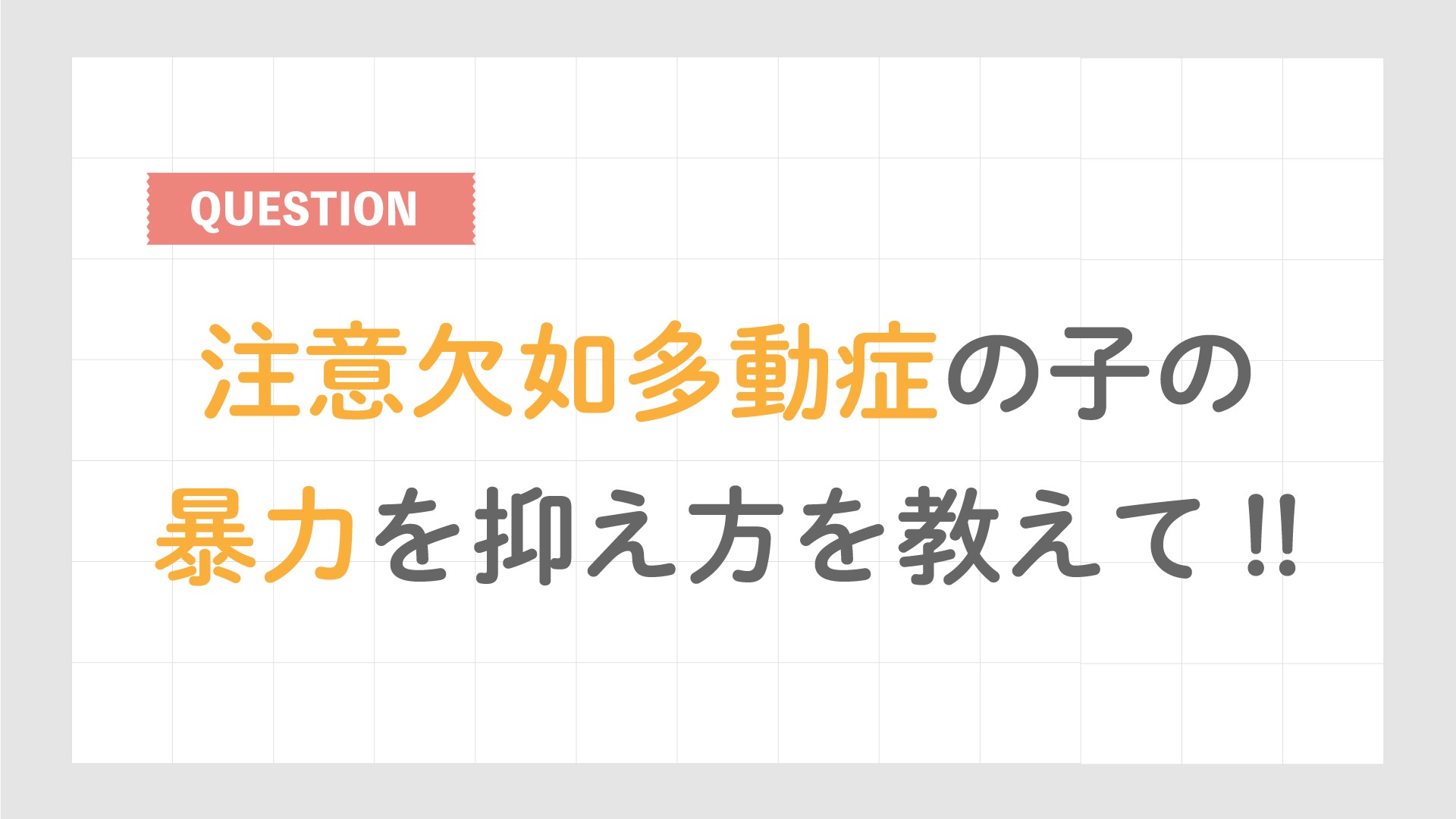なぜASDの子は集団生活が苦手?「疲れ」の正体と、安心できるサポートガイドを現役指導員が解説
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんがなぜ集団生活を苦手とするのか、その理由と具体的なサポート方法」についてです。
「うちの子、園や学校に行くとすごく疲れて帰ってくる…」
「集団の中で一人だけポツンといることが多い気がする」
「どうしてあんなに集団行動を嫌がるんだろう?」
そんな風に感じたことはありませんか?ASDの特性を理解する上で、この「集団生活の困難さ」は非常に重要なテーマです。
今日は、その背景にある「疲れの正体」と、ご家庭や園・学校でできる「安心のためのサポート」について、詳しくお話ししていきます。
ASDの特性を「コミュニケーションの障害」として捉える
さて、今日お話しするASD(自閉スペクトラム症)ですが、これを一言でどんな障害なのかと表すのであれば、僕は「コミュニケーションの障害」だと感じています。
相手に対して自分の気持ちを上手に話したり、逆に相手の気持ちを上手に受信したり、そういったやり取りがスムーズにできないのが、ASDの特性なんですよね。
そして、保育園や学校といった「集団生活」の場では、このコミュニケーション能力がとても大事になってきます。
だからこそ、ASDの特性を持つお子さんにとって、集団生活はとても辛いものになってしまったり、なかなか適用できなかったりするパターンがあるんです。
ただ、最初にお伝えしたいのは、「集団の中で無理をしてほしい」というわけでは決してない、ということです。
その子の個性(個別性)が活かされた状態で、集団の中に溶け込めるのが一番良い。そのために、私たち大人が何ができるのかが大事なんだと思っています。
なぜ集団生活は「疲れる」のか?
では、なぜASDのお子さんにとって、集団生活はそんなに大変なのでしょうか。
一言でいうと、「疲れる」からです。
例えば、
- 周りの人の表情を読み取るのが難しい
- 急な予定変更が起こる
- 騒音や光、人の多さといった感覚的な負荷が強い
こういった、本人たちが苦手とすることが集団生活にはたくさん詰まっています。その環境の中で気持ちよく過ごすためには、常に「耐えなきゃいけない」部分が多すぎる。だから、集団の中で疲れ切ってしまうんですよね。
その「疲れ」の理由を、もう少し具体的に見ていきましょう。
理由①:目に見えない「非言語情報」を読む負担
集団生活というのは、言葉だけのやり取りではありません。「表情」「態度」「その場の雰囲気」といった、目に見えない非言語的な情報から、多くのことを読み取る必要があります。
ASDのお子さんは、こうした目に見えない情報や「暗黙のルール」を理解するのが苦手なことが多いです。
つまり、周りの定型発達の子どもたちが「当たり前」に、無意識でやっている空気読みを、ASDのお子さんは「ものすごく頑張って、頭をフル回転させて」初めて成立させている状態なんです。
そんなの、疲れますよね。だから会話が苦手になったり、その場に合わせるのがしんどくなったりするんです。
「メラビアンの法則」という有名な説があります。人がコミュニケーションで受け取る情報のうち、
- 視覚情報(表情、見た目)… 55%
- 聴覚情報(声のトーン、話し方)… 38%
- 言語情報(言葉そのものの意味)… 7%
だと言われています。つまり、定型発達の人は、会話の実に9割以上を「雰囲気(非言語情報)」で判断しているんです。
でも、ASDのお子さんは、この「雰囲気」の部分の受信が難しく、逆に「言葉そのもの(7%)」の方に重きを置いてしまう傾向があります。
だから、相手は軽い冗談のつもり(雰囲気)で言ったのに、言葉通りに受け取って本気で怒ったり、傷ついたりしてしまう。
この「受信の仕方のズレ」が、集団生活でのすれ違いを生む大きな原因なんですよね。
理由②:「曖昧な言葉」が不安を招く
ASDのお子さんは、言葉を文字通りに解釈する傾向が強いです。そのため、冗談や比喩、そして「曖昧な表現」は、彼らにとって大きな不安を呼びます。
例えば、「ちょっと待ってて」「適当にやっておいて」と言われても、
「『ちょっと』って、具体的に何分?」
「『適当』って、どういう状態?」
と、全く見当がつかないんです。その結果、自分勝手に行動したように見えてしまったり、混乱して固まってしまったりします。
こういう時は、「あと1回で交代ね」「(時計の針が)5になったら終わりだよ」というように、数値や行動で具体的に示すことが、お互いのすれ違いをなくすために非常に重要です。
理由③:お互いの「当たり前」が違う(二重共感問題)
「ASDの子は人の気持ちがわからない」と誤解されがちですが、そうではありません。最近では「二重共感問題」という考え方が注目されています。
ASDのお子さんが定型発達の子の「暗黙のルール」を読めないのと同じように、定型発達の子もASDのお子さんの「独特な表現」や「こだわりの意味」を理解できません。
お互いに相手のことが理解できず、結果として「相手が悪い」と思ってしまう。この双方のギャップが、喧嘩や溝の原因になります。
これは、「ASDの人だけが共感性に欠けている」という古い考え方(誤解)を覆す、とても大切な概念です。
簡単に言えば、「ASDの人はASDの人同士では、とてもよく共感し合える」「定型発達の人は定型発達の人同士で、とてもよく共感し合える」という研究が元になっています。
問題なのは、「ASDの人」と「定型発達の人」という、異なる神経タイプ(ニューロタイプ)の間で、お互いの「当たり前」が違いすぎること。
それによって、お互いに共感し合うのが難しくなっている、という「双方向の問題」なんです。どちらか一方の「欠陥」ではない、という視点が、支援の第一歩になります。
理由④:「いつもと同じ」へのこだわり(予測可能性の追求)
集団生活では周りがどんどん変化していく中で、「いつもと同じ」にこだわってしまうお子さんがいます。
この「こだわり」は、単なるワガママや頑固さではありません。
ASDのお子さんにとって、この世界は情報が多すぎて、次に何が起こるかわからない「カオス(混沌)」のように見えていることがあります。一寸先は闇、みたいな感覚です。
そのカオスな世界で、なんとか自分が行きやすくなるために、「手順」や「配置」といった秩序(ルール)を自分で作って、世界を安定させようとしている。
それが「こだわり」の正体であり、彼らにとっての「自衛策」なんです。
予定や環境を安定させること、つまり「構造化」は、彼らの不安やパニックを減らすことにつながります。
理由⑤:急な「予定変更」への戸惑い
理由④とつながりますが、だからこそ「急な予定変更」はASDのお子さんにとって大混乱の元です。行動が爆発してしまう「メルトダウン」を招くこともあります。
僕らが何気なく受け入れている「予定の変更」は、ASDのお子さんの脳に、ものすごく高い負荷をかけます。
なぜ予定変更がそんなに大変なのか。これは「実行機能」と「中枢性統合」という脳の働きが関係しています。
- 実行機能:計画を立てたり、注意を切り替えたり、行動をコントロールする力です。予定が急に変わると、この「切り替え」の機能に強い負荷がかかり、対応できなくなってしまいます。
- 中枢性統合:バラバラの情報を、ひとつの「全体」としてまとめる力です。この力が弱いと、予定が変わった時に「全体がどう変わるのか」を把握できず、パニックになりやすいです。
理由⑥:感覚の過敏さ(気合や根性では無理)
集団生活の「ざわざわ音」がどうしてもダメ、蛍光灯の光が眩しすぎる、といった「感覚過敏」も、集団生活を困難にする大きな理由です。
これは「気合」や「根性」でどうにかなる問題ではありません。神経学的な特性です。
すごく寒がりの子が、寒い中で「勉強に集中しろ」と言われても無理ですよね。それと同じで、本人にしか分からない「不快」や「痛み」に常に耐えながら集団にいるわけですから、疲労困憊してしまうのは当然なんです。
集団生活を支えるサポート方法:鍵は「予防的支援」
では、どうすればいいのか。
一番大事なのは、問題が起きてから対処する(叱る、我慢させる)のではなく、「予防的支援」をすることです。
僕は動画で「プロアクティブ支援」という言葉を使いました。これは「先を見越して、能動的に行動する」という意味です。
つまり、本人が困る前に、大人が先回りして環境を整えておくことが、何よりも大切なんです。
具体策①:スケジュールと予告(事前準備は8割)
ASDのお子さんにとって、最大の不安は「次に何が起こるか分からない」ことです。
だからこそ、「何が」「いつ」「どこで」起こるのかを「視覚」で提示して、不安を徹底的に減らします。
- 写真や絵カードを使った1日のスケジュール
- カレンダーでの行事の予告
- 初めての場所に行く前の「下見」(写真でもOK)
- 「ソーシャルストーリー」を使って、新しい体験の流れを予習する
使える視覚支援はすべて使って、「事前準備は8割」の気持ちで万全にしておくことが、集団生活での安心につながります。

ゆう先生の補足解説:ソーシャルストーリーとは?
これは、特定の社会的な状況(例:「運動会の練習」「友達との遊び方」)について、何が起こるのか、周りの人はどう感じるか、そして自分はどう行動すればよいかを、本人の視点で具体的に書いた短いお話のことです。
これを事前に読んでおくことで、本人は「心の準備」ができ、新しい場面での不安を大きく減らすことができます。ご家庭でも簡単に作れますよ。
具体策②:スモールステップでの参加(見る→一緒にやる→交わる)
集団が苦手な子に、いきなり「みんなと一緒に入りなさい!」というのはハードルが高すぎます。不安と恐怖でいっぱいだからです。
ここには明確な「順番」があります。
- 「見る」:まずは集団の端っこで、みんなが何をしているかを見るだけ。参加しなくてOK。
- 「一緒にやる」:次に、先生や親など、安心できる大人と「一緒に」やってみる。
- 「交わる」:そして初めて、自分一人で(あるいは子どもたち同士で)交わってみる。
この「小さな成功体験」を、一歩一歩踏んでいくことが大事です。1回見てみたら「やれそうだな」と思い、1回一緒にやったら「次もできそうだな」と思う。この積み重ねが自信になります。
具体策③:興味・得意を「役割」にする
集団活動が苦手でも、その子に「得意なこと」や「大好きなこと」が必ずあるはずです。
それを「役割」にしてしまうのも、すごく有効な方法です。
例えば、みんなで何かを作る活動が苦手でも、恐竜が大好きなら「恐竜博士として、みんなにヒントをあげる係」になってもらう。
それだけで、本人は「好きな部分だけ」で集団に参加でき、ハードルがぐっと下がります。
この「できた!」という感覚を増やしていくことが、何よりも大事です。「できた」という体験が積み重なると、「レジリエンス」、つまり心の強さが育っていきます。

ゆう先生の補足解説:レジリエンスとは?
レジリエンスとは、「心の回復力」や「しなやかな強さ」のことです。
誰でも失敗することはあります。集団生活でうまくいかないことがあっても、「僕はこれが得意だから大丈夫」「前もできたから、もう一回やってみよう」と、失敗から立ち直る力がレジリエンスです。
この力を育てるのは「強み」や「好き」の分野での成功体験です。
集団生活での苦手さを補って余りあるほどの「自信」を、得意な分野で育ててあげることが、将来的な生きやすさにつながっていきます。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- ASDのお子さんは「コミュニケーションの障害」という特性上、集団生活で求められる「非言語情報(雰囲気)」の読み取りや「曖昧な言葉」の解釈が非常に苦手です。
- 周りが無意識でやっていることを、常に頭をフル回転させて処理しているため、集団生活は「非常に疲れる」場所です。
- この「疲れ」や「予測不能な不安」が、一見「頑固」に見えるこだわりや、予定変更でのパニック(メルトダウン)の引き金になっています。
- 支援の鍵は、問題が起きてから対処するのではなく、「予防的支援(プロアクティブ支援)」です。スケジュールやルールを「視覚化・構造化」し、本人にとって「予測可能で安全な場所」を作ることが何より大切です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。