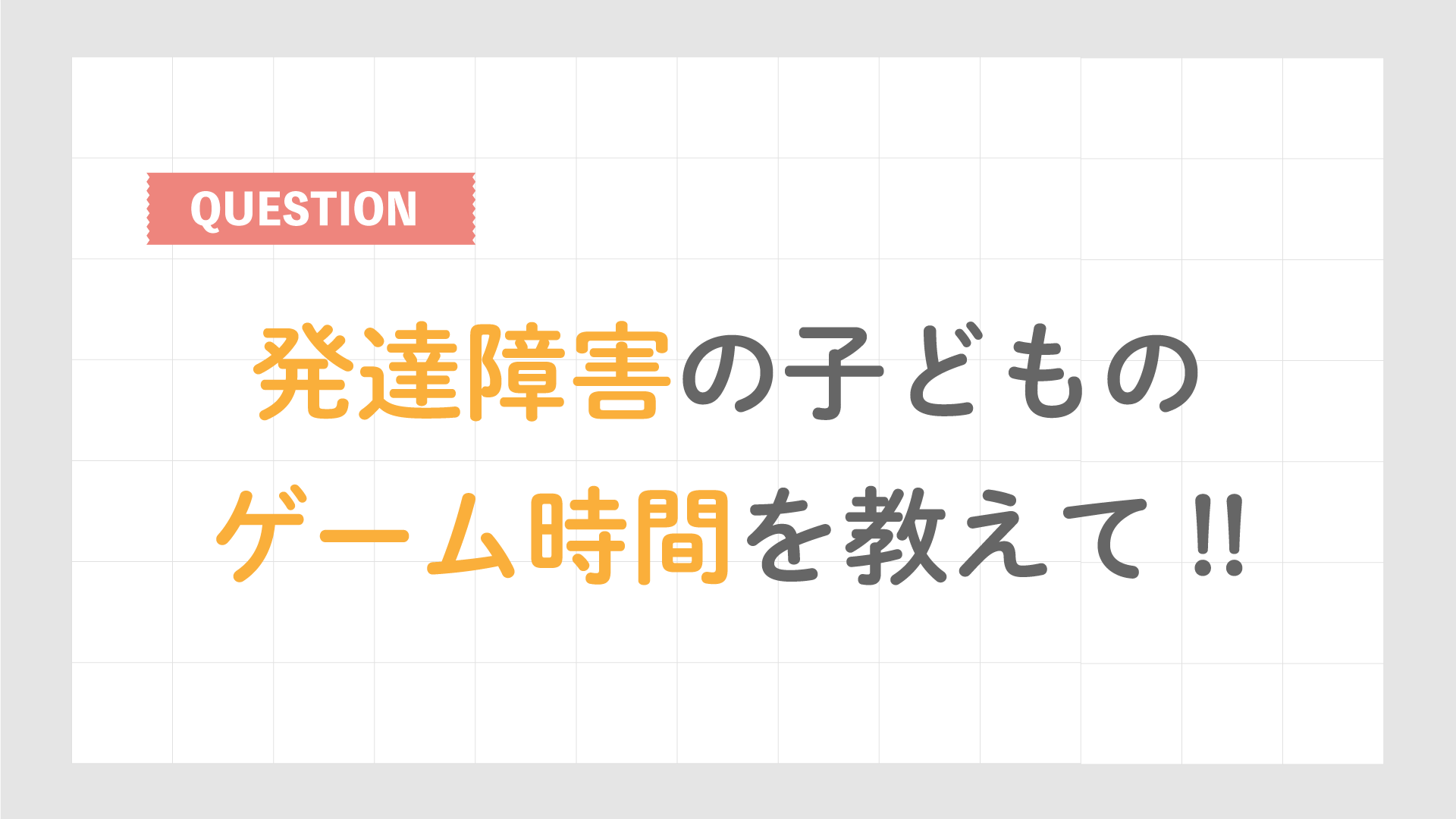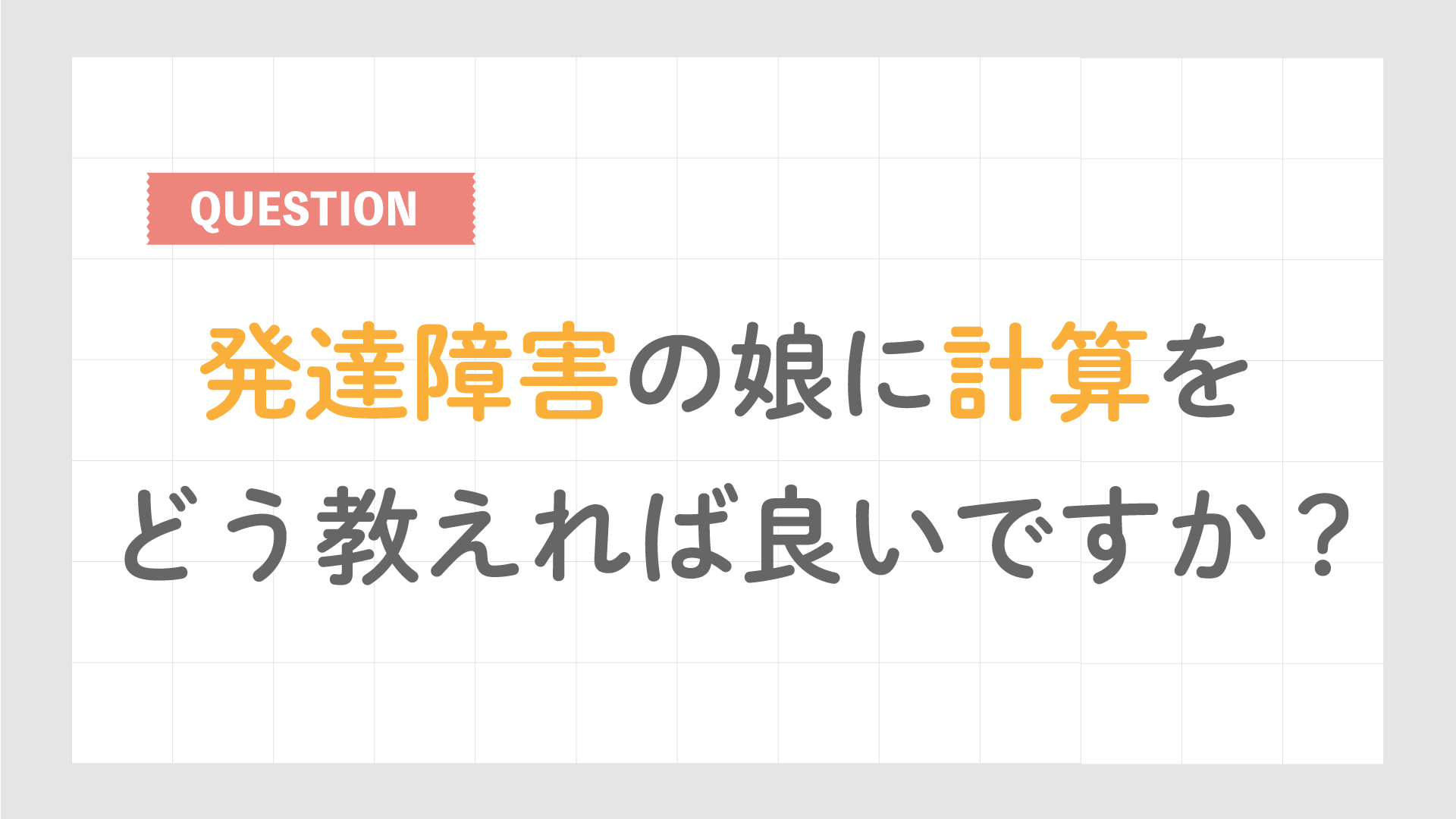ASDの子どもが安心できる世界とは?現役指導員が教える「構造化(環境調整)」の驚くべき効果15選
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんにとって、なぜ『日課・ルール・見通し』、つまり『構造化』が大切なのか」についてです。
「お子さんが急な予定変更でパニックになってしまう…」
「次に何をすればいいか分からず、不安そうにしていることが多い…」
「『ちゃんと片付けてね』と伝えても、どこから手をつけていいか分からず固まってしまう…」
そんなお悩みを抱えていませんか?その背景には、世界の「見え方」「感じ方」の違いがあるかもしれません。
今日は、その不安を安心に変えるための「構造化」という考え方について、その具体的な効果をたっぷり15個、ご紹介していきますね。
なぜ「構造化(環境調整)」が重要なのか?
今日のテーマである「構造化」ですが、一言でいうと「環境調整」のことです。
発達障害の療育において、この「環境調整」はすごく大事な部分なんですよね。
というのも、生まれ持ったその子の特性(遺伝的な要因)を僕らが変えることはできません。
でも、環境を調整することによって、その特性の「働き方」を変えたり、特性を「活かす」ことはできるんです。
例えば、「聴覚過敏」という特性は変えられなくても、うるさい教室では話が聞けなかった子が、静かな部屋でなら、むしろ人の話をよく理解できるかもしれません。
これは、環境を調整することで、その子の能力が活かされた例ですよね。
僕ら支援者や大人ができること、それがこの「構造化」です。これを分解したものが、「日課」「ルール」「見通し」といった言葉になります。
構造化の3つの基本的な側面
構造化は、大きく分けると3つの側面からアプローチします。
1. 時間・活動の構造化(視覚的スケジュール)
まず、ASDのお子さんの多くは、言葉で説明されるよりも「目で見て分かる情報」の方が理解しやすい、という特性があります。
ですから、「何時になったら何をする」「何曜日は何がある」といったことを、「視覚的なスケジュール」としてあらかじめ作っておくことがすごく大事です。
これによって、お子さん本人が見通しを持って行動できる確率が上がりますし、親御さんがいちいち声かけをしなくても、自分でスケジュールを見て行動できるようになっていきます。
結果として、家族全体がスムーズに行動しやすくなるんですよね。
2. 空間の構造化(刺激の整理)
次に、「どこで何をするか」という活動スペースを明確にすることです。
例えば、「ご飯を食べるのはリビング」「寝るのは寝室」「勉強するのは子供部屋」というように、場所と活動を一致させます。
「寝る部屋には寝るもの(布団など)以外は置かない」「勉強する部屋には集中できるもの以外は置かない」といった工夫をすることで、
お子さんは「この部屋ではこれをするんだ」というマインドセットになりやすく、余計な刺激に集中力を遮られることがなくなります。
「物の定位置化」も、この空間の構造化の一つですね。
3. 「伝え方」の構造化
時間や空間だけでなく、僕たちの「伝え方」そのものも構造化が大切です。
「ちゃんと片付けてね」といった抽象的な言葉ではなく、「具体的に」「視覚的に」「肯定的に」伝えることが重要です。
「おもちゃを、あの赤い箱にしまってね」
「本を、本棚に戻してね」
このように具体的な指示を出すこと。言葉だけで伝わらなければ、絵カードや写真を使って指差ししながら「これを、ここ」と視覚的に示すこと。
そして「走らないで!」(否定形)ではなく、「歩こうね」(肯定形)と、してほしい行動を伝えること。
言葉って、目に見えないですよね。ASDの子どもたちは、その「見えないもの」を理解しようと頑張って、頭の中がぐちゃぐちゃになってパニックになってしまうことがあります。
だからこそ、見える形で具体的に伝えることが、彼らの安心につながるんです。
必見!構造化がもたらす「15の効果」
さて、ここからが本題です。この「構造化」を実践すると、子どもたちにどんな良いことがあるのか?その効果を15個、一気にご紹介します。
見えない世界を「秩序ある世界」に変える
ASDの子どもたちにとって、世の中は「次に何が起こるか分からない、不安な場所(カオス)」に見えていることが多いんです。
闇の中を手探りで歩いているような状態、と言ってもいいかもしれません。
だからこそ、どうすればいいか分からず不安になり、自分のルール(こだわり)に頼ってしまう。僕はその気持ち、しょうがないなと思うんですよね。
【効果1】カオスを秩序へ変える
構造化(日課、ルーティン、手順書)は、その暗闇に差し込む光のようなものです。「こうすればいいんだ」という予測可能性が、不確実な世界を「安全で理解しやすい場所」に変えてくれます。
【効果2】「実行機能」の負担を軽減する
「次に何をしようか」と計画を立てたり、行動を切り替えたり、衝動を抑えたりする脳の力(実行機能)に困難さを抱えるお子さんは多いです。構造化によって「次にやること」が決まっていると、この実行機能へのエネルギー消費を節約できます。

ゆう先生の補足解説:実行機能(じっこうきのう)とは?
「実行機能」とは、目標に向かって行動を管理・調整する、脳の高次な機能のことです。
例えば、「計画を立てる」「作業を記憶する(ワーキングメモリ)」「注意を切り替える」「衝動をコントロールする」といった働きを含みます。
ASDのお子さんは、この機能の使い方が苦手な場合があり、物事を順序立てたり、柔軟に考え方を変えたりすることに困難を感じやすいと言われています。
構造化は、この実行機能が担う「計画」や「順序立て」の部分を外側からサポートしてあげる役割があるんです。
【効果3】曖昧な表現をなくし、文字通り解釈できる
「ちゃんと」「少し」といった曖昧な表現は、混乱と不安を招きます。「今から2つ話すよ」「このイラストの通りに手を出すよ」と具体的に示すことで、言葉の裏を読む負担がなくなり、スムーズに伝わります。
【効果4】流れの視覚化で「全体像」を把握しやすくする
ASDの特性として、物事を全体として捉えるより、細部に注目しやすい(木を見て森を見ず)という傾向があります。

ゆう先生の補足解説:中枢性統合(ちゅうすうせいとうごう)の弱さとは?
これは、バラバラの情報を集めて、全体として意味のあるまとまりとして理解する力のことです。
例えば、顔の「目」「鼻」「口」というパーツを見て、瞬時に「(怒っている)人の顔だ」と全体を把握するような働きです。
この機能が弱いと、情報が部分部分で処理されるため、「片付け」と言われても「何から手をつけて、どうなったら終わりなのか」という全体の流れ(文脈)を掴むのが難しくなります。
だからこそ、「片付けて」という森(全体)を見せるのではなく、「①本を戻す」「②おもちゃを箱に入れる」「③箱を棚に置く」という木(細部)を順番に示す視覚的スケジュールが有効なんです。
細部優位の強みを活かしつつ、結果として全体の流れを掴む手助けになります。
【効果5】「暗黙のルール」を言語化し、推測の負担を下げる
「廊下は走らない」といった、僕らが当たり前だと思っている「暗黙のルール」。これはASDの子どもには伝わりません。
ちゃんと「学校のルール」「お家のルール」として言語化・視覚化してあげることで、安心してみんなと同じ行動が取れるようになります。
コミュニケーションと感覚のミスマッチを防ぐ
【効果6】「言葉+視覚」でコミュニケーションミスを減らす
言葉だけでいくら伝えてもダメだったことが、絵カードを見せながら伝えた瞬間にスッと理解できる、ということは本当によくあります。
表情や声色といったリアルタイムで変化する情報を読むのは困難なので、「絵」という変わらない情報をプラスすることで、受信ミスが劇的に減ります。
【効果7】ルールの共有で「二重共感問題」のギャップを埋める
親子間や支援者との間でお互いの思っていることが分からない、というすれ違いが起こることがあります。
これを、二重共感問題(にじゅうきょうかんもんだい)と言います。
これは、「ASDの人は共感性が低い」という従来の考え方に対し、「ASDの人とそうでない人(定型発達者)との間で、お互いに考え方や感じ方が違うために、お互いに共感が難しくなっているだけだ」という新しい捉え方です。
ASD側だけの問題ではなく、定型側もASDの人の感じ方を理解しようとしていない、という双方向のギャップを指します。
このお互いのギャップを埋めるのが、「構造化されたルール」です。
暗黙の了解ではなく、「うちのルールはこうだよね」と誰にでも見える形にしておくことで、共通の土台ができ、すれ違いを減らすことができます。
【効果8】予期せぬ刺激を減らし、パニックを防ぐ(感覚過敏)
感覚過敏がある子にとって、予期せぬ刺激はパニックの引き金になります。「掃除機をかける時間(大きな音)は子どもがいない時にする」「服のタグは先に切っておく」など、環境を構造化して刺激をコントロールすることで、本人は落ち着いて生活できます。
【効果9】必要な刺激を意図的に取り入れ、安定させる(感覚探求)
過敏とは逆に、強い刺激を求める「感覚探求(感覚鈍麻)」がある子もいます。
これは、感覚が鈍感(鈍麻)なために、脳が適切な覚醒状態を保とうとして、より強い刺激を自ら求めてしまう行動のことです。
例えば、ぐるぐる回ったり(前庭覚)、人や物に強くぶつかったり(固有受容覚)することがあります。これは「わざと」やっているのではなく、脳が必要な刺激を求めているサインなんです。
こういう場合は、トランポリンやブランコなど、必要な刺激を得られる活動を「あらかじめ日課に組み込む」という構造化が有効です。
刺激が満たされることで、他の活動に落ち着いて取り組めるようになります。
「安心」が「自信」と「意欲」のサイクルを生む
【効果10】変わらない手順が「安心の種」になる
こだわりが強いのは、不安の裏返しでもあります。通学路や食事の手順など、慣れたやり方を維持する(構造化する)ことで、本人は安心して過ごせます。
その安心が土台にあるからこそ、「今日はこっちの道も試してみようか」と、新しい柔軟性を学ぶ余裕が生まれるんです。
【効果11】タスクの自動化で「脳のエネルギー」を節約する
Appleの創業者スティーブ・ジョブズは、毎日同じ服を着ることで「服を選ぶ」という意思決定のエネルギーを節約していたそうです。
これと同じで、歯磨きや荷造りなどをチェックリスト化・日課化(自動化)することで、子どもたちは脳のエネルギーを温存できます。その余力を、勉強や友達関係といった、もっと頭を使いたい部分に振り向けられるようになります。
【効果12】「何が起こるか分かる」世界が安全な場所になる
「いつ当てられるか分からない」授業中は緊張しますよね。ASDの子どもたちは、日常的にその緊張を抱えていることがあります。
スケジュールによって「次」や「終わり」が分かることは、「間違うかもしれない」という恐怖を減らし、穏やかな状態を保つことにつながります。
【効果13】予定の把握が「未来への安心感」を育てる
構造化によって「自分でスケジュールを確認して準備できる」仕組みができると、「やらされている感」が減り、「自分でできた!」という感覚が育ちます。
この「自分で管理できる」という感覚が、未来への安心感と意欲の循環を生んでいきます。
【効果14】小さな成功体験の連鎖が「自信」になる
構造化こそが、この成功体験のスタート地点です。ガチガチに環境を整えてでも、「朝の支度が一人でできた」という小さな勝利を積み重ねていく。
できたことを視覚的にチェックして褒めていく。この「できる」という体験が、「僕は(私は)できるかもしれない」という無意識の信念(自己肯定感)を強化し、学習や社会参加への前向きな挑戦につながっていきます。
【効果15】【総まとめ】好循環のサイクルが生まれる
構造化によって「不安」が減少します。
不安が減るから、パニックなどの「問題行動」が減少します。
問題行動が減るから、新しいことに挑戦する「意欲」が増加します。
この素晴らしいサイクルを生み出すために、構造化は本当に大事なんです。
ASDの子どもが安心できる構造化の「コツ」
最後に、構造化を始めるための簡単なコツをいくつか紹介します。
- 鍵となる時間帯から始めるいきなり全部やろうとせず、まずは「朝起きてから家を出るまで」や「夜寝る前」など、一番バタバタしがちな時間帯からルールや日課を決めてみてください。
- 否定形より「肯定形」で短く具体的に「走らないで!」は「走る」という言葉に意識が向いてしまうことも。「(お店の中は)歩こうね」と、してほしい行動を具体的に伝えましょう。
- 視覚支援ツールを活用する写真、絵カード、チェックリスト、色付きのタイマーなど、「見える」ツールはたくさんあります。お子さんに合ったものをぜひ活用してみてください。
- 予定変更は「視覚的に」事前告知する変化が苦手なのは当然です。変更がある場合は、できるだけ早く、言葉だけでなく視覚的にも(例:スケジュールのカードを入れ替えるのを一緒に見る)伝えることが大事です。
- 100%の完璧を目指さないこれが一番伝えたいことかもしれません。完璧な計画なんて立てられません。大枠は同じにしつつ、「例外もあるんだよ」ということを、お父さんお母さん自身が心に留めておいてください。そして、その「例外」に落ち着いて対応できた時は、ぜひお子さんを褒めてあげてください。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- ASDのお子さんにとって、世界は「次に何が起こるか分からない」カオスな場所に見えがちです。
- そこで「構造化」=「環境調整」が重要になります。「時間」「空間」「伝え方」を整え、世界を「予測可能で安全な場所」に変えてあげるアプローチです。
- 構造化によって脳の負担(実行機能)が減り、不安やパニックが軽減されます。
- 何より、「自分でできた」という小さな成功体験を積み重ねる土台となり、それがお子さんの「自信」と「意欲」を育てる好循環につながっていきます。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。