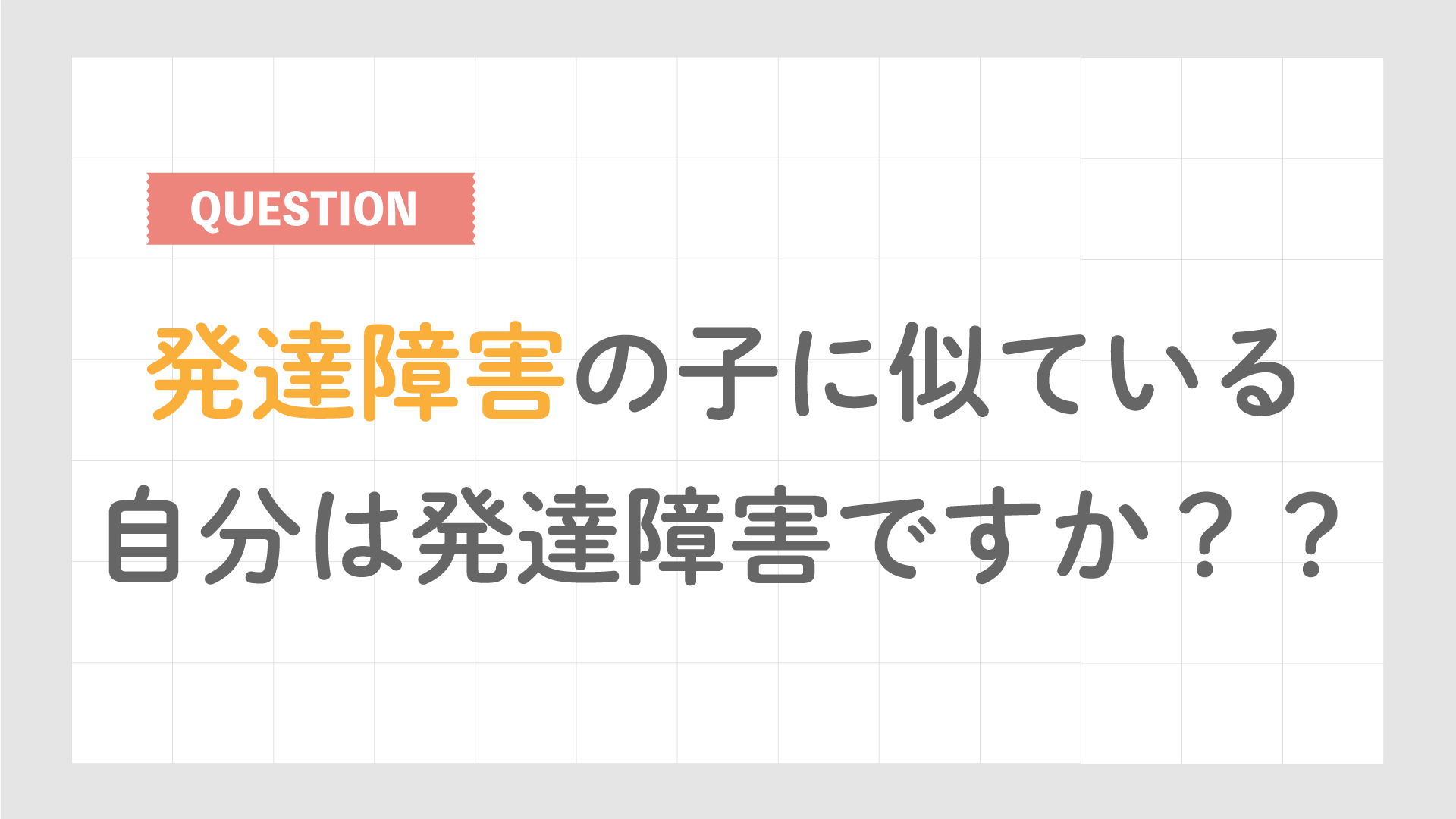発達障害の診断は終わりじゃない!「支援の始まり」として前向きに捉えるヒント|富山の現役指導員が解説
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場リアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「診断はゴールではなく、支援の始まり」についてです。
お子さんに発達障害の診断が下された時、「これからどうなってしまうんだろう…」という戸惑いや不安、悲しみ、怒りなど、様々な感情が湧き上がってくるかもしれません。ショックで、絶望的な気持ちになってしまう方もいらっしゃると思います。それは、とても自然な感情です。
診断直後の複雑な感情:それは自然な反応です
僕も療育の現場で、毎年多くのお父さんお母さんと出会います。診断を受けた直後の感情は、本当に人それぞれです。
戸惑い、不安、怒り、悲しみ…時には、「やっと原因が分かってホッとした」という安堵感と、「でもこれからどうしよう」という不安が入り混じることもあります。
どんな感情であっても、それは自然な反応だと僕は思います。
すぐには受け止めきれなくて当然ですし、気持ちが定まらず辛い時期が続くこともあります。何年経っても、その気持ちが完全に消えるわけではないかもしれません。
でも、今日お伝えしたいのは、診断は決して「ゴール(終わり)」ではないということです。
むしろ、診断を受けた「ここから」がお子さんの人生をより良くしていくためのスタートなんだ、という視点を持っていただけたら嬉しいです。
診断は「前向きな支援」への転換点
僕にとって、診断は「困り事の原因を明らかにし、前向きな支援への転換点になるもの」だと捉えています。
例えば、勉強がなかなかできなかったり、指示がうまく通らなかったりするお子さんがいたとします。
周りからは「やる気がないんじゃないか」「しつけの問題では?」と誤解されてしまうかもしれません。
でも、診断を通して「それは本人のやる気の問題ではなく、脳の特性(発達のデコボコ)によるものなんだ」と理解できればどうでしょうか。
「やる気がない」「しつけが悪い」という誤解が解け、脳の特性に基づいた困難だと分かれば、お子さんへの接し方や考え方が変わってきますよね。
この「周りの関わり方が変わる」ということが、お子さんの成長にとって非常に大きな意味を持ちます。
「発達障害です、おしまい」ではなく、「発達障害という特性があるから、こういう工夫をしてみよう」「この子に合ったやり方なら、うまくいくかもしれない」と考えられるようになる。そのための第一歩が「診断」なんです。
診断を受けることの具体的なメリット
診断を受けることには、具体的なメリットもたくさんあります。一言でいうと、利用できるサポートが増え、お子さんも周りも安心しやすくなるということです。
支援体制や制度が利用しやすくなる
- 学校での配慮(合理的配慮):診断があることで、学校に対して、お子さんの特性に合わせた配慮(例えば、テスト時間の延長、別室での受験、ICT機器の使用など)をお願いしやすくなります。

ゆう先生の補足解説:合理的配慮(ごうりてきはいりょ)とは?
「合理的配慮」とは、障害のある人がない人と同じように学んだり生活したりできるよう、学校や職場などが、負担になりすぎない範囲で必要な調整を行うことです。
これは、障害者差別解消法という法律で定められています。診断があることで、学校側も「なぜ配慮が必要なのか」を理解しやすくなり、具体的なサポートにつながりやすくなる、という側面があります。
- 福祉サービスの利用:児童発達支援や放課後等デイサービスといった療育(発達支援)サービスを利用できるようになります。(※利用には「通所受給者証」が必要な場合が多く、その申請に診断書や医師の意見書が必要になることが一般的です)。
- 医療・教育・福祉の連携:診断があることで、関係機関(病院、学校、療育施設、役所など)が情報を共有し、連携して一貫したサポートを提供しやすくなります。
- 本人の自己理解:お子さん自身が「なんで自分はこれが苦手なんだろう」と悩んでいる場合、診断名を知ることで「自分のせいじゃなかったんだ」「こういう特性があるからなんだ」と、自分自身を理解し、受け入れるきっかけになることもあります。
このように、診断を受けることは、決して悪いことではなく、むしろお子さんを取り巻くサポート体制を整え、将来の選択肢を広げるための「武器」を手に入れることだと、僕は考えています。
診断名は「ラベル」ではなく「ユーザーガイド」
「発達障害」「自閉スペクトラム症」といった診断名を聞くと、どうしてもネガティブな「ラベル」を貼られたように感じて、「この子はもうダメなんだ」と思い込んでしまう方も少なくありません。
でも、診断名は、お子さんを制限するための「レッテル」ではありません。
それは、お子さんの「取扱説明書(ユーザーガイド)」のようなものだと考えてみてください。
「この子には、こういう得意なところ(強み)と、こういう苦手なところ(弱み)があるんだな」「苦手な部分には、こういう配慮が必要だけど、得意な部分はどんどん伸ばしてあげよう」
そう理解するための「共通言語」であり、「支援の出発点」なんです。
支援によって広がる子供の可能性
診断を受け、適切な支援(療育)につながることで、お子さんの可能性は確実に広がっていきます。
「強み」を活かし、「自信」を育む
療育では、苦手なことの克服だけに焦点を当てるわけではありません。むしろ、本人の「強み」や「好きなこと」に着目し、それを伸ばしていくことを大切にします。
「できた!」という小さな成功体験を積み重ねることで、お子さんは自信を持ち、「もっとやってみたい!」という意欲が育まれます。この自信が、将来、困難に立ち向かうための大きな力になるんです。
日々の関わり方と環境の工夫
診断によって特性が明確になると、ご家庭での関わり方や環境設定の工夫もしやすくなります。
例えば、ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんであれば、
- 指示は一つずつ、具体的に伝える
- 絵や写真を使った視覚的な支援(スケジュール表など)を活用する
- 部屋の物を整理し、どこに何があるか分かりやすくする(空間の構造化)
- 毎日の決まった流れ(ルーティン)を大切にする
といった工夫を取り入れることで、お子さんは見通しを持って安心して過ごせるようになり、パニックや混乱を防ぐことができます。
安定した行動ができるようになると、新しいことを学んだり、できることが増えたりする良い循環が生まれてきます。
支援は「チーム」で!繋がりを広げよう
ここまで読んで、「診断後の支援が大事なのは分かったけど、家庭だけでできるか不安…」と感じた方もいるかもしれません。
その通りです。発達障害の育児や支援は、決して一人(一家族)だけで抱え込むものではありません。
医療・教育・福祉との連携
病院の先生、学校の先生、療育施設のスタッフ、役所の担当者…様々な専門家と「チーム」を組んで、お子さんを支えていくことが理想です。

ゆう先生の補足解説:多面的な支援の重要性
なぜ連携が重要かというと、それぞれの専門家が見ている側面が違うからです。
- 医療:医学的な診断、薬物療法、合併症の管理など
- 教育:学習面の支援、学校生活での合理的配慮など
- 福祉(療育):日常生活スキル、コミュニケーション、社会性のトレーニングなど
これらの情報がバラバラだと、支援がちぐはぐになってしまいます。関係機関が連携し、情報を共有することでお子さんにとって一貫性のある、最適なサポートを提供できるようになるんです。
一つの機関だけに頼るのではなく、複数の視点からお子さんを見てもらうことで、より柔軟で効果的な支援につながりやすくなります。
保護者自身のセルフケアを忘れずに
そして、これも非常に大切なことです。
発達障害の支援は、明日明後日で終わるものではありません。年単位、時には一生をかけて向き合っていく、長い長い長距離走(マラソン)です。
だからこそ、お父さんお母さん自身の心と体の健康が何よりも大切になります。
感情的になったり、心が辛くなったりするのは当然のことです。でも、その状態が長く続くと、保護者の方自身が疲弊し、二次障害(うつなど)につながってしまう可能性もあります。
意識的に休息の時間を取り、リフレッシュする方法(趣味、運動、好きな活動など)を見つけてください。
同じ立場の仲間との繋がり
「一人じゃない」と感じられることは、大きな支えになります。
同じ悩みを持つ親御さん(ママ友、パパ友)や、ピアサポートのグループなど、経験や気持ちを分かち合える仲間を見つけることも、とても大切です。

ゆう先生の補足解説:ピアサポートとペアレントトレーニング
ピアサポートとは、同じような立場や経験を持つ人同士が、互いに支え合う活動のことです。
保護者の会などがこれにあたります。専門家には話しにくい本音を共有できたり、「うちだけじゃないんだ」と孤独感を和らげたりする効果があります。
ペアレントトレーニングは、発達障害のあるお子さんの保護者が、子どもの行動理解や具体的な関わり方のスキルを学ぶプログラムです。
スキルを学ぶだけでなく、同じ悩みを持つ親同士が繋がる場としても機能しています。
悩みを共有できる場所があるだけで、安心感が生まれ、前向きな気持ちを支えてくれます。
【6】まとめ
今日の記事では、「診断はゴールではなく、支援の始まり」というテーマでお話ししました。
- 発達障害の診断は、絶望ではなく、困りごとの原因を理解し、お子さんに合った前向きな支援を始めるための「転換点」です。
- 診断名は「ラベル」ではなく、お子さんの特性を理解し、学校での配慮や福祉サービスといった具体的なサポートにつなげるための「ユーザーガイド(ツール)」として活用しましょう。
- 支援は長距離走です。医療・教育・福祉と連携し「チーム」で取り組み、保護者自身のセルフケアと、同じ立場の仲間との「繋がり」も大切にしてください。
結論:読者へのメッセージ
診断を受けた直後は、様々な感情に揺れ動くと思います。でも、それはお子さんと真剣に向き合っている証拠です。
診断は終わりではありません。お子さんと共に進む、新たな出発点です。
ここからが、お子さんの未来を作る大切な時間です。焦らず、できることから一緒に始めていきましょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの**「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」**ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。