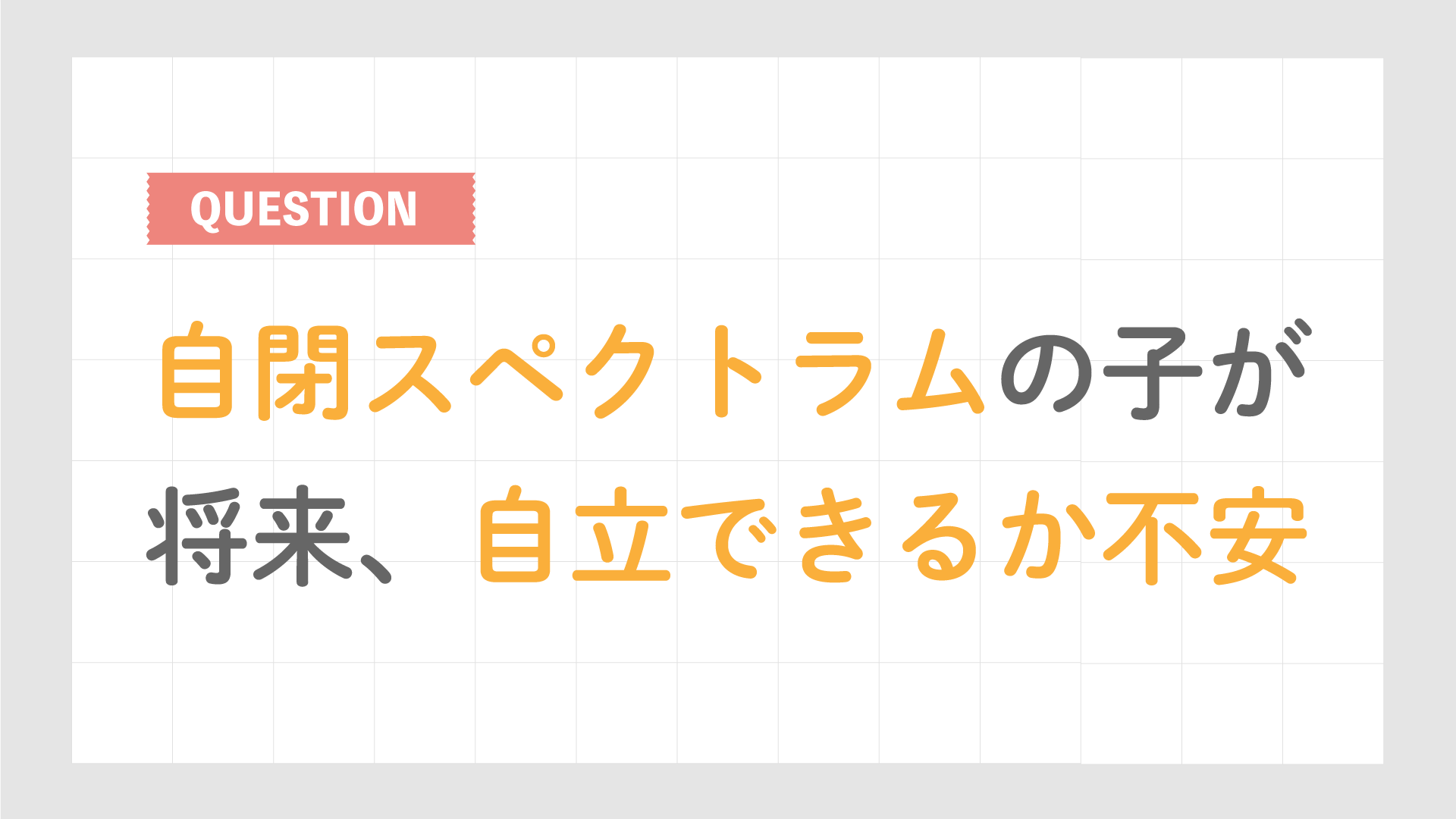「発達障害が瞬時に分かる」は本当?診断に必要な「持続性」と「多角的な視点」を現役指導員が解説
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「発達障害は一瞬で分かるのか?」についてです。
ネットや動画で「発達障害のサイン、瞬時に見抜く方法」
「これがあったらASD(ADHD)確定」
といった情報を見て、『うちの子もしかして?』と不安になったり、『あの人はきっとそうだ』と簡単に判断してしまいたくなったりした経験はありませんか?
本日はそれって本当なの?について深掘りしていきます!
なぜ「瞬時に分かる」系コンテンツが多いのか?
僕もYouTubeで発信している立場なので、障害福祉のトレンドや、皆さんがどんな情報に関心があるのかをよくチェックするんですよね。
その中で、「発達障害は一瞬で分かる」といったタイトルの動画が、すごく再生されているのをよく見かけます。
多くの方にとって、自分や他人が発達障害かどうかを「インスタント診断」のように一瞬で分かったら、面白いし、ある意味では楽なのかもしれません。
「あの人のあの行動は、発達障害だからなのかな?」と分かれば、対応しやすいと思う気持ちも理解できます。
ただ、エンターテイメントとして見るのは面白くても、結論から言うと、発達障害は「一瞬」では分かりません。
もし見た目や一瞬の行動で分かるなら、たぶん当事者の方も、周りの定型発達の方も、ここまで困っていないと思うんですよね。
どっちか分からないからこそ、コミュニケーションのすれ違いが起きて、みんなが困っているのが現状だと思います。
発達障害の「定義」と「診断の難しさ」
そもそも「発達障害」とは何なのか、その定義がすごく大事です。

ゆう先生の補足解説:発達障害とは?
発達障害は、単一の病気ではありません。生まれつきの脳機能の発達の「違い」によって、行動や情緒に特性が現れる状態の総称です。
例えば、インフルエンザのように「ウイルスに感染する」といった明確な原因がある病気とは異なり、「脳の発達の違い」に由来します。
代表的なものに、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)などがありますが、特性の現れ方は一人ひとり異なり、明確な境界線があるわけではなく、「スペクトラム(連続体)」として捉えられています。
発達障害の原因となる「脳」については、まだまだ未知の部分が多く、解明されていないことが多いんですよね。

ゆう先生の補足解説:脳科学と発達障害
脳科学はまだまだ発展途上の分野です。「なぜ、その行動特性が出るのか?」という根本的なメカニズムは、完全には分かっていません。
確かに、行動の特徴(アウトプット)はありますが、その原因が完全には分からないからこそ、「発達障害」という包括的な概念で呼ばれています。
そして一番大きな特徴は、特性の現れ方が「個人によって大きく異なる」という点です。「これに該当したら絶対に発達障害」とはっきり言えるような、単純なものではないんです。
また、インフルエンザが治るような「一過性」のものとは違い、障害は「生涯にわたる特性」として理解する必要があります。
だからこそ、「一瞬の判断」でその人の一生が決まってしまうような見方は、個人的にはすごく怖いな、と思います。
専門家はどう診断するのか?
DSM-5という「ものさし」
では、専門家(医師)はどうやって診断するのでしょうか。
その基準の一つに「DSM-5」という国際的なマニュアルがあります。
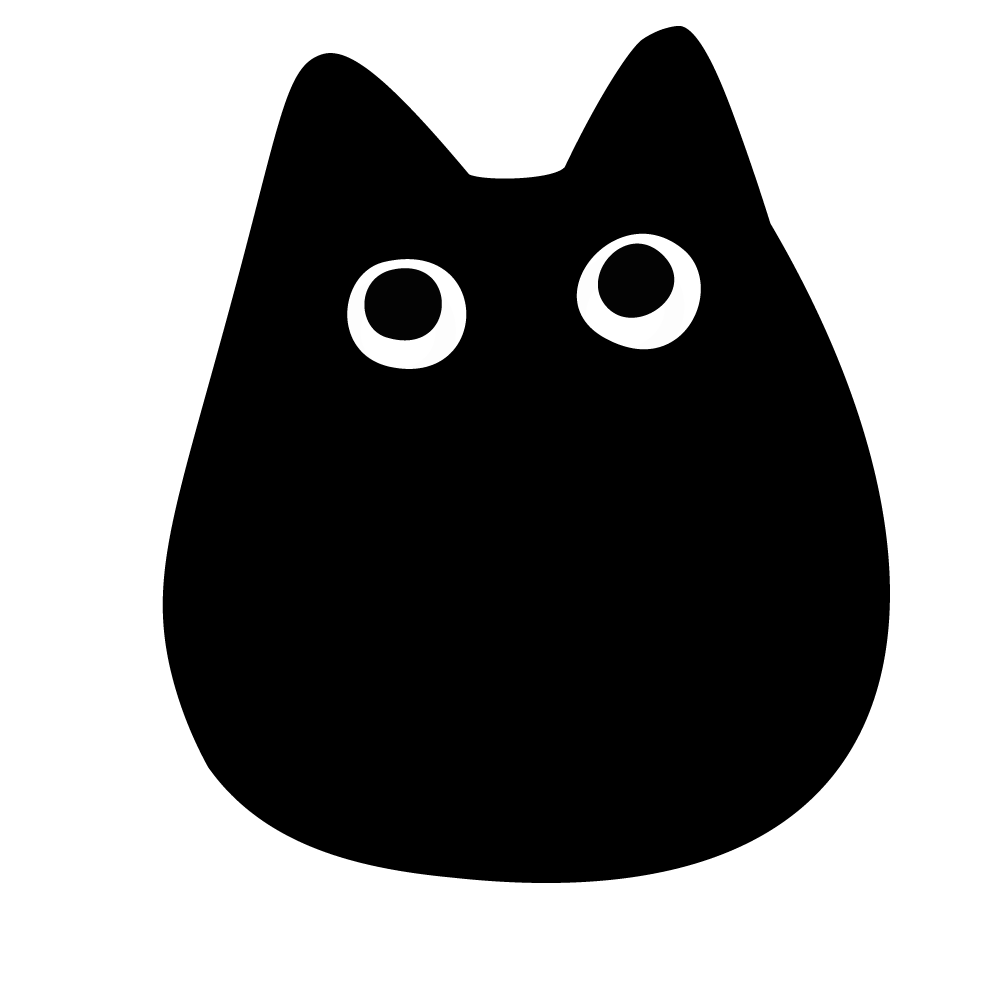
助手の補足解説:DSM-5とは?
「DSM-5(ディーエスエムファイブ)」とは、アメリカ精神医学会が作成している「精神障害の診断と統計マニュアル(第5版)」のことです。
これは、精神疾患の国際的な診断基準の一つとして広く使われています。
医師は、このDSM-5に記載されている診断基準(チェックリストのようなもの)に照らし合わせながら、本人の状態を判断していきます。
自己診断やチェックリストの危険性
大事なのは、医師はDSM-5だけを見て診断するわけではない、ということです。
- 本人やご家族からの詳細な聞き取り(生育歴)
- 幼少期から今に至るまでの様子
- 現在の困りごと
こうした様々な情報を「総合的」に判断して、初めて診断に至ります。
ですから、一般の人がネットの動画やチェックリストだけで「自分は発達障害だ」と自己診断してしまうのは、実は違う可能性も結構あるんですよね。
もちろん、それらが「気づきのきっかけ」になることは良いことですが、鵜呑みにしてはいけない、ということを覚えておくのが重要です。
具体例:ASDとADHDの診断基準
診断には「持続性」と「多角性」がいかに重要か、ASDとADHDの例で見てみましょう。
1. ASD(自閉スペクトラム症)の場合
ASDの診断基準には、大きく以下のような特徴があります。
- 社会的なコミュニケーションや対人関係の困難
- 限定された興味や、反復的な行動
- 感覚的な過敏さ、または鈍感さ
これらの特徴が「複数の領域」で「持続的」に現れている場合に、診断されます。
例えば、以下のような特徴が挙げられます。
- (コミュニケーション)目が合いにくい、相手の気持ちを想像するのが苦手、冗談が通じにくい。
- (反復的行動)特定の手順やモノへの強いこだわりがある、くるくる回るものを見続けるのが好き。
- (感覚)特定の音や光を極端に嫌がる(過敏)、逆に痛みや暑さ・寒さを感じにくい(鈍麻)。
現場で子どもたちを見ていても、「この子はもしかしたら」と感じることはありますが、それは体験療育などで一定期間の関わりや、保護者の方からのお話を聞いた上でのことです。外見だけ、一瞬の行動だけで判断することは不可能です。
2. ADHD(注意欠如・多動症)の場合
ADHDの診断基準は、大きく2つのタイプに分けられます。
- 不注意(忘れ物が多い、集中力が続かない、うっかりミスが多い)
- 多動・衝動性(じっとしていられない、喋りすぎる、順番を待てない)
これらの特徴が「少なくとも6ヶ月以上」続き、かつ「複数の場面(例:家と学校の両方)」で見られる場合に、ADHDと診断されます。
ADHDには、不注意の特徴が目立つ「不注意優勢型」、多動・衝動性の特徴が目立つ「多動・衝動性優勢型」、両方の特徴を併せ持つ「混合型」があります。
注目してほしいのは、「6ヶ月以上」という「持続性」と、「複数の場面」という「多角性」が診断基準に明確に含まれている点です。
昨日今日、忘れ物が続いたからといって、すぐにADHDと診断されるわけではないんですよね。
診断に本当に必要な「持続性」と「多角的な情報」
ここまでをまとめると、発達障害の診断で最も重要なのは、まさにこの2つです。
- 持続性:その行動が長期間(例えば6ヶ月以上)続いているか。
- 多角的な情報:家、学校、職場、幼稚園など、複数の場所で同じような行動が見られるか。
大人の発達障害の診断でも、必ず「生育歴(幼少期から現在までの生活の様子)」を聞かれます。それは、大人になってから急に特性が出るわけではなく、幼少期からの「持続性」を確認するためです。

ゆう先生の補足解説:二次障害とは?
動画の中で「二次障害」という言葉に触れました。これは、発達障害の特性(一次障害)そのものではなく、その特性による「生きづらさ」や、周囲からの不適切な関わり(叱責され続けるなど)が原因で、うつ病や不安障害、適応障害、自己肯定感の低下などを併発してしまう状態を指します。
大人になってから「うつ」や「適応障害」と診断されて病院に行ったら、実は背景に発達障害があった、というケースも少なくありません。
「特性」と「障害」は違う
「誰だってこだわりはあるし、忘れ物もするじゃないか」という意見があります。これは僕もその通りだと思います。
誰にでも「特性」はあります。
では、「特性」と「障害」は何が違うのか?
それは、その特性によって「日常生活や社会生活に、重大な影響(困りごと)が出ているかどうか」です。
例えば、すごくこだわりが強くても、それが仕事や生活に支障をきたしていなければ、それは「障害」ではなく「個性的な特性」です。
しかし、そのこだわりのせいで学校や職場に行けない、他の活動が一切できなくなってしまう場合は、「障害」としてサポートが必要になるかもしれません。
だからこそ、僕たち支援者は「環境設定(環境を調整すること)」が大事だと言い続けるんです。環境によっては、その特性が「障害」にならずに済むことも多いからです。
「瞬時に分かる」情報との向き合い方
「瞬時に分かる」という情報は、非常にキャッチーですが、同時に危険性もはらんでいます。
安易なラベリング(決めつけ)の危険性
人を一瞬で判断し、「あの人は発達障害だ」と簡単にラベルを貼ることは、いじめや差別の助長に繋がりかねません。
「あいつは変なところがある」「仕事ができない」といった分類は、人間関係に「分断」を生みます。
また、他者から「あなた、障害持ってるっぽいね」と言われたら、本人はどう思うでしょうか。すごく不安になったり、自己肯定感が下がったりして、「二次障害」を引き起こすきっかけにもなり得ます。
YouTubeなどは「気づきのきっかけ」
では、ネット上の情報をどう使えばいいのか。
僕は、YouTubeなどの情報は「ジャンクフード」みたいなものかな、と思っています。
ジャンクフードは手軽で美味しいし、食べたくなりますよね。でも、そればかり食べていたら健康にはなれません。
同じように、「瞬時に分かる」系の情報は、手軽な「気づきのきっかけ」や「ガソリン」として使うのが良いと思います。
「もしかしたら、自分(や家族)が困っているのは、これが原因かも?」と気づくためのエンジンとして活用し、そこで終わらせないこと。
情報を鵜呑みにせず、専門機関へ
大事なのは、情報を鵜呑みにしないことです。
発達障害は、専門家でさえ診断が難しい、目に見えないものです。
もしご自身やご家族のことで気になることがあれば、ネットの自己診断で完結せず、必ず専門機関(病院、発達支援センター、施設の職員など)に相談すること。
そこからスタートするのが、一番確実で、ご本人にとって一番良い道に繋がると思います。
まとめ
今日の記事の内容を、もう一度振り返ります。
- 発達障害は「一瞬」では分かりません。ネット上の「瞬時に分かる」情報は、エンタメや「気づきのきっかけ」程度に捉えるのが大切です。
- 診断には「持続性」と「多角的な情報」が不可欠です。専門家は、生育歴や複数の場面での様子を総合的に見て判断します。
- 安易なラベリングは避けましょう。「特性」は誰にでもあり、それが生活に支障をきたしているかが「障害」との分岐点です。むやみに決めつけることは、本人を傷つけ、分断を生む危険性があります。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。