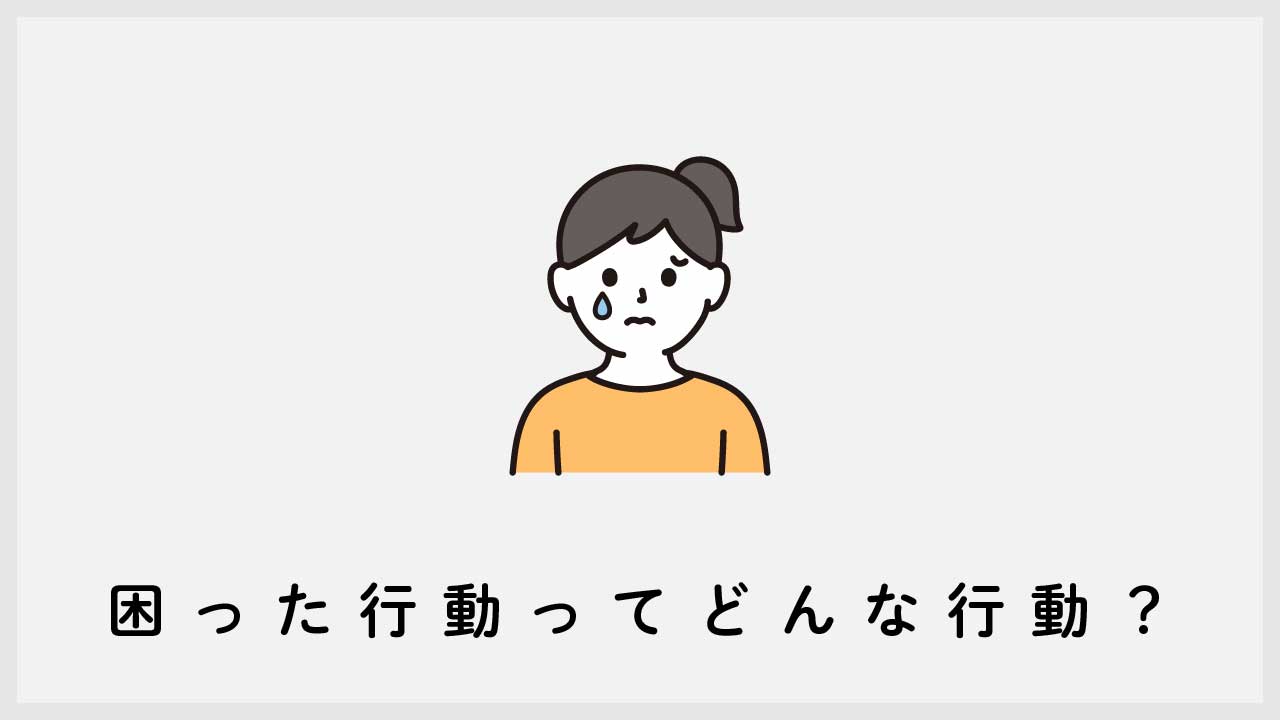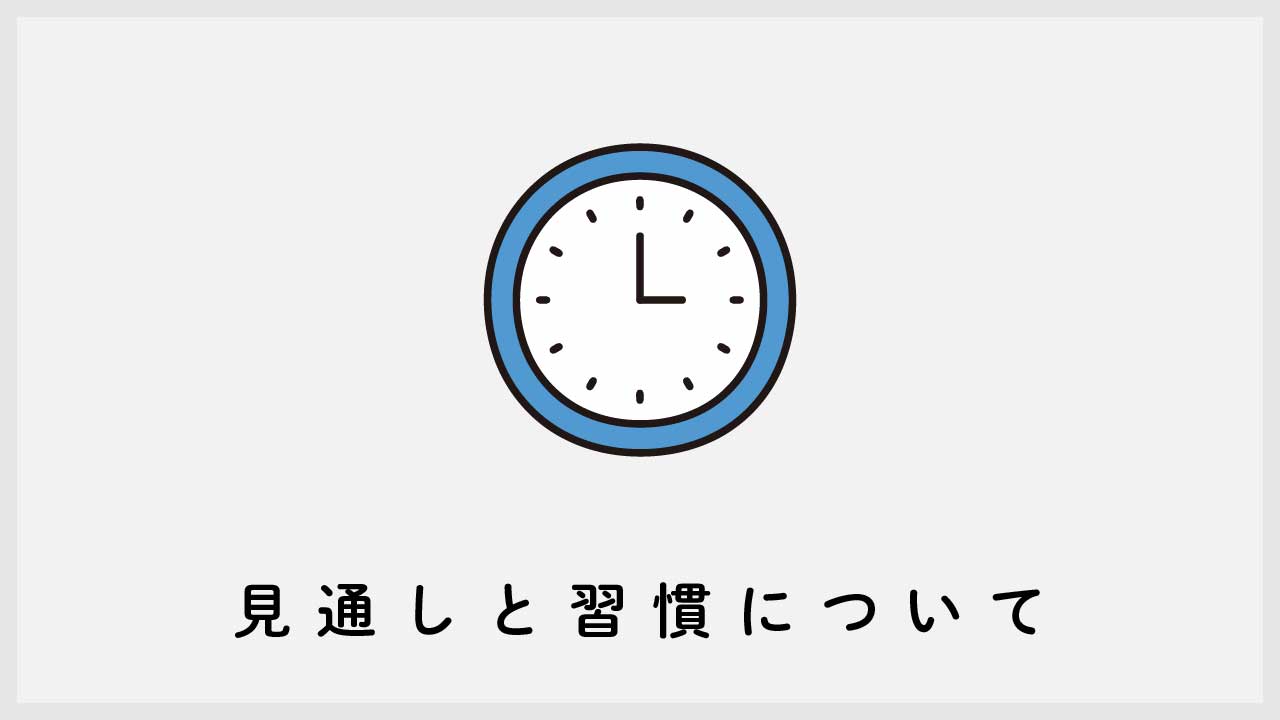上手な手助けの方法について|子どもの発達障害を解説

こんにちは!ゆう先生です!
子どもが新しいことに挑戦するとき、あなたはどんなふうにサポートしていますか?
「何でも手伝ってしまうと自立できなくなるのでは?」
と心配になる一方で、全く助けずに放っておくと子どもは「できない…」と自信を失ってしまうこともあります。
実は、適切な手助けをすることで、子どもは「やればできる」と実感し、自己肯定感を高めやすくなります。
今日は、子どもの自己肯定感を育てるための「上手な手助けの方法」について、より詳しくお話しします。
本日は、「プロンプト(手がかり)」という考え方を軸に、子どもが自信をもって行動できるようになるためのポイントを解説します。
なぜ手助けが大切なの?

子どもは、自分でできないことに挑戦するとき、不安や戸惑いを感じることがあります。
大人のほんの少しのサポートがあると、「あ、こうすればいいのか!」と気づいたり、「誰かが見守ってくれているから安心」と思えたりして、行動しやすくなります。
この「ちょうどいいサポート」を「プロンプト」といいます。
プロンプトを使うことで子どもは「できた!」という達成感を得やすくなり、結果として「自分にはできる力があるんだ」という自己肯定感を育てていくことができます。
プロンプトとは?
「プロンプト」とは、子どもが行動しやすくなるような手がかりやヒント、補助を指します。
プロンプトにはさまざまな種類があり、状況や子どもの特性に合わせて使い分けることが重要です。
主なプロンプトの例を見てみましょう。
音で伝えるプロンプト
- 「ピンポン」と音を鳴らして、行動開始の合図をする
- タイマーやアラーム音で「そろそろおしまいだよ」「次はこれをしよう」と知らせる
動きで伝えるプロンプト
- 子どもの手を軽く添えて「この向きに回すんだよ」など、動作の仕方を示す
- 一緒に体を動かして、正しい姿勢や動きを体感させる
見える物で伝えるプロンプト(視覚的なヒント)
- 絵カード、写真、イラストで「次はこれをやろうね」と示す
- スケジュール表やToDoリストを使って、行動の順番や目標を視覚化する
声かけによるプロンプト(言語的なヒント)
- 「次はここを持ってみようか」「ゆっくり数えてみよう」など、具体的な指示やアドバイスを言葉で伝える
これらを組み合わせることで、子どもは「どうすればいいのか」を理解しやすくなります。
適切なプロンプトの選び方と実践方法

プロンプトを使う際には、子どもの発達段階や個性に合わせることが大切です。
次のようなポイントを参考にしてみてください。
お手本を見せる(モデリング)
子どもが新しい動作や行動を習得するとき、言葉で説明するだけではわかりにくいことがあります。
例えば、紐靴の結び方を教えるとき、大人が実際に目の前でゆっくり見せると、子どもは「こうやるんだ」とイメージしやすくなります。
体を支える
実際の動作をサポートすることで、子どもは正しい体の使い方をつかみやすくなります。
例えば、はさみを使う練習をするとき、子どもの手に軽く手を添えて、開閉の動きを一緒にやってみると「この力加減で使うのか」と体感できます。
ヒントを与える
次の行動を予測できるような言葉がけやジェスチャーで、子どもがスムーズに取り組めるようになります。
例えば、「あと一回踏んでみよう」「もう少し左にずらしてみて」など、具体的な指示をする。
「ここをもう少し強く押してみようか」「この線に合わせてみて」と視覚的なヒントを加える。
基本的に、全部はやらないって感じで覚えておくと良いかもしれません。
ただ、全然サポートしないのも良くないです。
このちょうど良いサポートは、結構、熟練度や支援者の資質が見られるところです。
ただ長年、色々やってきて、簡単に言えば、
できないポイントを支援者が分かっている
ということが、プロンプトをする上で大事かと思います。
なので、まずは子供にやらせてみて、どこで失敗するのか?を見つけるところが一番大事かな?と感じます。
それ自体も、「分かる人は分かる」状態な時もあるので、ここは難しい部分でもあります。
ただ、なんだかんだ「一緒に何かをした」という経験が大事かもしれないので、怖がらずに、放置せずに、子供一緒に課題をクリアしていくのが大事かもしれません。
プロンプトフェードの大切さ
プロンプトは、最初から最後まで続けるものではありません。
子どもが慣れてきたら、徐々にプロンプトを減らしていく「プロンプトフェード」を行うことが重要です。
最初は手を添えていたのを、次第に言葉だけのアドバイスに切り替える
最初は「ここを持って」と細かく指示していたのを、「もう少し頑張ってみよう」と少し離れたところから声をかける程度にする
最終的には、子どもが自分で全てのステップを考え、行動できる状態を目指す
プロンプトフェードがスムーズにいくと、子どもは「もう自分でできる!」「一人でやった!」という達成感を味わえ、自信がついていきます。
この「達成感」が子供の成長にはとても大事だと日々感じます。
子どものペースを大切にする
手助けをする際には、子どもの反応をよく観察しましょう。
「まだ難しそうだな」と思ったら、プロンプトを少し増やして、「もう慣れてきたみたい」と感じたら少しずつ減らしていきます。
子どもが「できた!」と感じるまでには、それぞれにかかる時間や努力が異なります。
焦らず、子どものペースに合わせて進めることで、成功体験が増え、子どもはどんどん成長していくでしょう。
ただ、ここまで読んでみて、正直「どこまでサポートしていいのか、分からない〜」って方は、オンライン相談支援(初回無料)を行っておりますので、
そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。
まとめ
本日は、「プロンプト(手がかり)」という考え方を軸に、子どもが自信をもって行動できるようになるためのポイントを解説しました。
手助け(プロンプト)の使い方を少し工夫するだけで、子どもは「やればできる」という感覚を掴みやすくなります。
最初は、「どれくらい助けたらいいの?」と迷うかもしれませんが、試行錯誤しながら子どもの反応を見ていくうちに、ちょうどいいバランスが見えてきます。
子どもが一人でできるようになる喜びは、親や教育者にとっても大きな喜びです。
小さな成功体験を何度も重ねるうちに、子どもは自信をつけ、挑戦する意欲を高めます。
すると、子どもは自らの力で前に進み、自分の成長を楽しめるようになるでしょう。
「できた!」という達成感が、子どもの自己肯定感をグンと高め、次の目標へと向かうエネルギーになります。
どうぞ、今日から少しずつ「上手な手助け」を実践してみてくださいね。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
終わりに
意外と早いもので、これが最後の記事になります。
ここまでの学習お疲れ様です。
これで療育の基礎講習はおしまいになります。
意外と、難しいことは書いてないな〜と思われたかもしれません。
ただ実践は意外と難しいのですよね。
ただ、僕はこの7つのメソッドを十分に活用して、日々療育を行っております。
多くの保護者から「子供は先生のおかげで成長できました」と言われるので、大きくは間違っていないと感じます。
今まで通算、500人くらいお子さんを見ていますが、8割くらいは概ね満足してくれているようです。
本当に嬉しいことと同時に、「ただ、もっとできた」とも思ってしまう僕です。
つまり、終わりがないことなんだろうな〜とも思います。
ただ、だから面白く、難しいことだけど、やりがいがあります。
療育は難しいです。
育児は大変です。
でも、だからこそ価値が高いのだと僕は感じます。
この記事はあくまで基礎です。
皆様が、これから、自分自身の子供や、他の方の子供を支援する時の基礎となる考え方です。
この基礎の上に、もっと素晴らしい結果が出ることを陰ながら応援させていただきます。
一緒に頑張りましょう。今後ともよろしくお願いします。