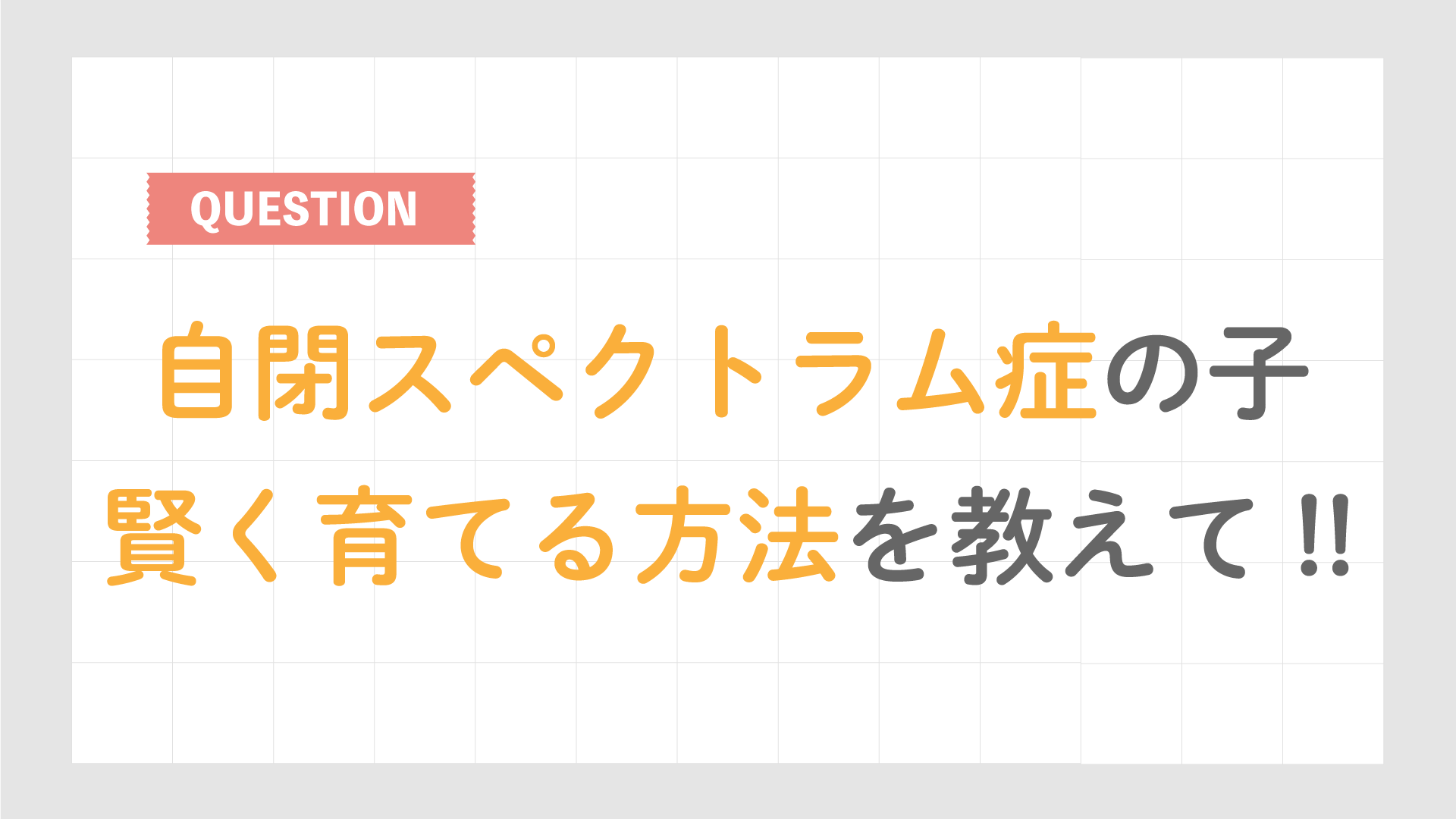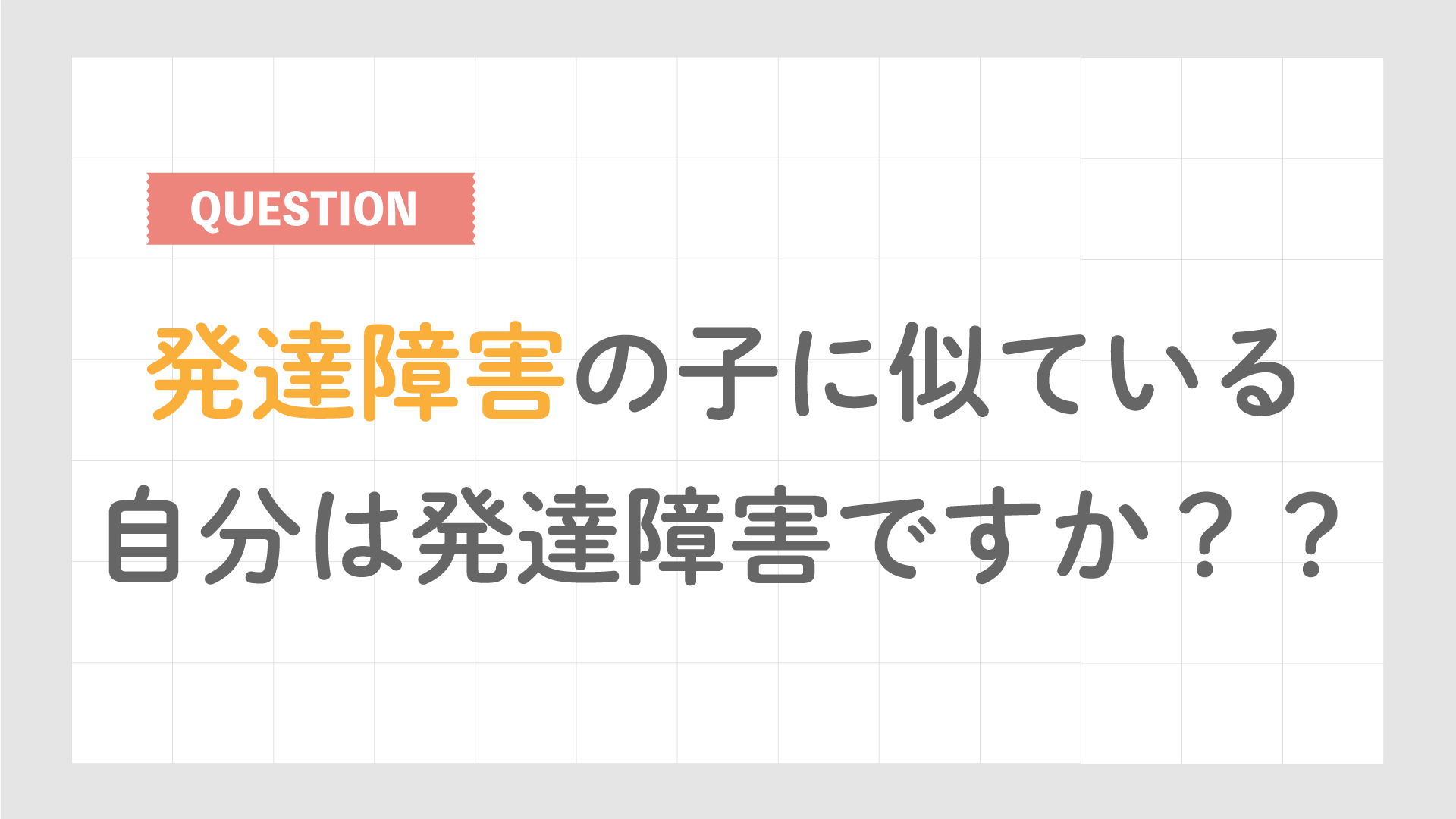算数障害(ディスカリキュリア)とは?努力不足ではない「数が苦手」な子の原因と安心できる支援法
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「算数障害(ディスカリキュリア)」についてです。
「うちの子、他の勉強はそうでもないのに、なぜか算数だけが極端にできない」「簡単な計算でも、いつまでも指を使っている」「文章問題になると、まったく式が立てられない」…
そんなお悩みはありませんか? それは本人のやる気や努力不足ではなく、脳の情報処理の特性が関係しているかもしれません。
算数障害(ディスカリキュリア)とは?
さて、今日お話しする「算数障害(ディスカリキュリア)」ですが、これは学習障害(限局性学習症:SLD)という大きなくくりの中の一つです。
学習障害には「読む(ディスレクシア)」「書く(ディスグラフィア)」そして今回お話しする「計算する・推論する(ディスカリキュリア)」の3つの領域があります。
算数障害とは、簡単に言うと数や計算に特有の困難さを示す発達特性のことです。大事なのは、知的発達に遅れがないにもかかわらず、数の理解や数学的な推論に著しい困難を示す、という点なんですよね。
これは本人の努力不足ではなくて、脳の情報処理の仕組みの違いによって生じます。
「苦手」と「障害」の違いは?
ここで、「算数が苦手」なのと「算数障害」って何が違うの?って疑問が湧くと思います。
日本人は「算数が苦手」って方が、僕の体感だと結構多いんですけど、その「なんとなく苦手」というのとは質的に異なるのが特徴です。
僕の考えでは、「苦手」というのは、努力をすれば解決する可能性があるもの。じゃあ「障害」は何かというと、努力だけでは克服できない可能性があるもの、と捉えています。
ちょっと例えが正しいか分かりませんが、手が無い人に物を持てと言っても難しいですし、目が見えない人に「これは何色?」って聞くのは失礼ですよね。
それと同じで、算数障害も、もともと脳の機能として持っている特性なので、「努力すればできる」とはちょっと違うわけです。
量の感覚(1, 2, 3個)と、数字の「3」という記号が結びつかなかったり、計算の手順を覚えられなかったり、そういった特有の問題があるのが算数障害です。
算数障害の主な困難の現れ方
では、具体的にどんな困難さとして現れるのか。算数の問題だけでなく、日常生活にも影響が出ることがあります。
- 数の大きさや順序が分からない(例:1と5、どっちが大きいか直感的に分からない)
- 筆算などで「位(くらい)」が揃わない、ずれてしまう
- 文章問題で、何を問われているのか分からず式が立てられない
- 時計がうまく読めない
- お金の管理(お釣りの計算など)がうまくできない
なぜ算数が苦手?考えられる4つの原因
算数障害の原因は、まだはっきりとは解明されていないんですが、脳を調べるとこんな傾向があるよ、ということが分かってきています。
① 数を感じる脳の領域(頭頂葉)の働き
一つは、脳の「頭頂葉(とうちょうよう)」という部分、だいたい頭のてっぺんあたりにある「数のセンサー」とも言える領域の働きが、少し弱いのではないかと言われています。
ここが弱いと、数の「大きい・小さい」を直感的に判断する力が育ちにくくなります。1, 2, 3, 4, 5…という言葉は言えても、それが「だんだん大きくなっている」という概念として掴みづらいんですね。
② ナンバーセンスの障害
二つ目は、「ナンバーセンス」の障害と言われています。
「ナンバーセンス」とは、その名の通り「数に対する感覚」のことです。
例えば、「5」という数が「4」より「1」大きいといった関係性や、たくさんのおはじきと少しのおはじきを見て「こっちが多い」と瞬時に感じ取るような、直感的な量感を指します。
これが弱いと、計算式自体は暗記できても、少し形が変わった「応用問題」になると、途端に分からなくなってしまうんです。
③ 「抽象化」の難しさ
三つ目は、これが結構根本的かもしれないんですが、「抽象化」の難しさです。
例えば、目の前に箱が7つあるのを見て「7個」と数えることはできても、それがスーパーで売っているみかん7個や、鉛筆7本と同じ、数字の「7」という記号とイコールだと結びつかないんです。
数字っていうのは「概念」なわけです。リンゴ3個を見ても「3」と結びつかないし、「3」という数字を見ても具体的な量が思い浮かびにくい。
算数や数学って、世の中の物事を「公式」や「数字」に置き換えて(抽象化して)分かりやすくする学問なので、ここができないと「算数って何をやっているのか分からない」となってしまうんですよね。
④ 認知機能(ワーキングメモリなど)の関連
あとは、発達障害全般にあるあるなんですが、記憶や空間認知の力も関係しています。
ワーキングメモリは、よく「脳のメモ帳」とか「作業台」に例えられます。情報を一時的に覚えておきながら、同時に別の作業をするための機能です。
算数で言えば、「繰り上がりの1を覚えておきながら、次の桁の計算をする」といった作業です。
発達障害の子はこのメモ帳が小さい傾向があり、算数障害の場合、計算の途中で「あれ、さっき何を覚えてたんだっけ?」と情報がこぼれ落ちてしまうんです。
遺伝的要因について
算数障害は、家族内で見られる傾向があるとも言われており、遺伝的な要因が強いと考えられています。
ここで大切なのは、親の関わり方や学習態度、教育環境が原因ではない、ということです。本人が努力していないわけでもありません。あくまで神経発達の特性として理解することが大切です。
【年代別】算数障害の特徴的なサイン
困難さの現れ方は、年齢によっても少しずつ変わってきます。
幼児期のサイン
- 数を順番に言えない(1, 2, 4, 5, 3…のようになってしまう)
- モノを数える時に、指差しと口で言う数がずれていってしまう
- 「どっちが多い?」と聞かれても、直感的に分からない
- 数字が出てくる遊び(トランプなど)を嫌がる
ただ、この時期はまだ数が苦手な子も多いので、「苦手なのかな?」くらいで、まずは見守るのが良いと思います。
小学校低学年の特徴
- 1桁の簡単な計算(例:1+1)でも、いつまでも指を使って数え続ける
- 繰り上がり、繰り下がりが理解できない
- 筆算で、位取りが曖昧になる
- 時計が読めない
高学年・中学生の特徴
この頃になると、算数が嫌いになっている子が多いです。分数、割合、図形など、より抽象的な概念がバンバン出てくるので、困難さが強まります。
こうなると、理科や社会で出てくる数字やグラフも嫌になってしまって、他の教科にも影響が出てくることがあるので、注意が必要ですよね。
成人期における影響
大人になっても特性は続くので、日常生活や仕事で影響が出ることがあります。
- お釣りの計算がとっさにできない
- 時間の計算(例:「あと何分で着く?」など)が難しい
- 家計の管理が苦手
ただ、ここら辺は自分が苦手だと分かっていれば、デジタル化(スマホアプリなど)で解決できる部分も多いのかなと思います。
算数障害の支援で最も大切なこと
ここから支援についてお話ししていきますが、まず一番大事なことをお伝えします。
① まずは「不安」を取り除くこと
算数障害の子は、「やればできそう」って周りから思われがちなんです。でも、やってもやってもできない。
そうすると、「算数が怖い」「算数が嫌だ」という気持ちがどんどん強くなってしまいます。
脳って面白くて、「不安」や「不快感」が湧き起こるだけで、脳の出力(ワーキングメモリなど)って落ちちゃうんですよ。ますます計算ができなくなる、という悪循環にはまってしまいます。
だから、まずは安心できる環境、落ち着いて計算できる静かな場所を整えてあげることが何よりも大事です。
② 自己肯定感を守る(結果より過程を褒める)
そして、学習障害全般に言えることですが、自己肯定感を守ってあげてください。
結果にフォーカスしすぎるんじゃなくて、「過程」を褒めてほしいんです。「ここ間違えた」よりも、「ここまで解けたから、すごいね」とか「昨日より1問多くできたね」って声をかける癖をつける。
算数は苦手でも、他の教科が得意なこともあると思います。その「得意」でバランスを取るのも大事な戦略ですよね。
学校でできる支援(合理的配慮)
もし学校に支援をお願いできるなら、次のような「合理的配慮」を相談してみるのが良いと思います。
① 「見える算数」で理解を助ける
算数障害の支援では、ちっちゃい頃から何回も何回もやるしかないんですけど、「モノ」と「数字」を関連付けることがすごく大事です。
おはじきやブロックを実際に操作しながら、「計算はクイズじゃなくて、実際のモノを置き換えただけなんだよ」ってことを理解させていく。「見える算数」を意識してもらうのが大事です。
数字だけのプリントが分からなくても、図や数直線を使ったり、具体的なモノを使ったりすることで、「こういうことか」と理解しやすくなることは多いです。
② ツール(電卓など)の活用をためらわない
合理的配慮として、電卓やタブレットの計算アプリを使うことを認めてもらうのも大事です。
筆算はうまくできなくても、タブレットならできる、という子もいます。
大事なのは、計算の「速さ」を競うのではなくて、「ちゃんと正しい答えを出す方法を育てる」こと。そのためのツールを使う力や、考える力に目を向けていくのが大事かなと思います。
ご家庭ですぐにできる支援
僕がご家庭で一番やってほしいと思うのは、買い物、料理、時間など、生活の中で数を体感させることです。
「みかん3つ取って」とか、「100円でこれ買えるかな?」とか。
「あと5分で出かけるよ」と時計を見せるとか。
こういう実物を通して「量」の感覚を育てていくことが、算数障害の緩和につながりますので、ぜひ日常から取り入れてほしいなと思います。
算数障害の子は、努力不足どころか、むしろ努力しすぎているくらいの子の方が多い印象があります。
まずはできることからやればいいし、できないところをどうやってサポートするかを周りが考えてあげる。最終的に正しい答えが出る手法を、書くことや暗算以外の方法で見つけられれば、それでいいんです。
まとめ
今日の記事をまとめます。
- 算数障害(ディスカリキュリア)は、知的発達に遅れがないにもかかわらず、数や計算の理解に特有の困難がある発達特性であり、本人の努力不足ではありません。
- 数の大小が直感的に分からない、位取りができない、文章問題が解けないといった困難は、「ナンバーセンス」の弱さや、「具体物」と「数字」を結びつける抽象化の苦手さが関係しています。
- 支援で最も重要なのは、本人の「不安」を取り除き、安心できる環境を整えることです。おはじきなどの具体物や、電卓などのツールを積極的に活用し、正しい答えを導き出す方法を育てていくことが大切です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。