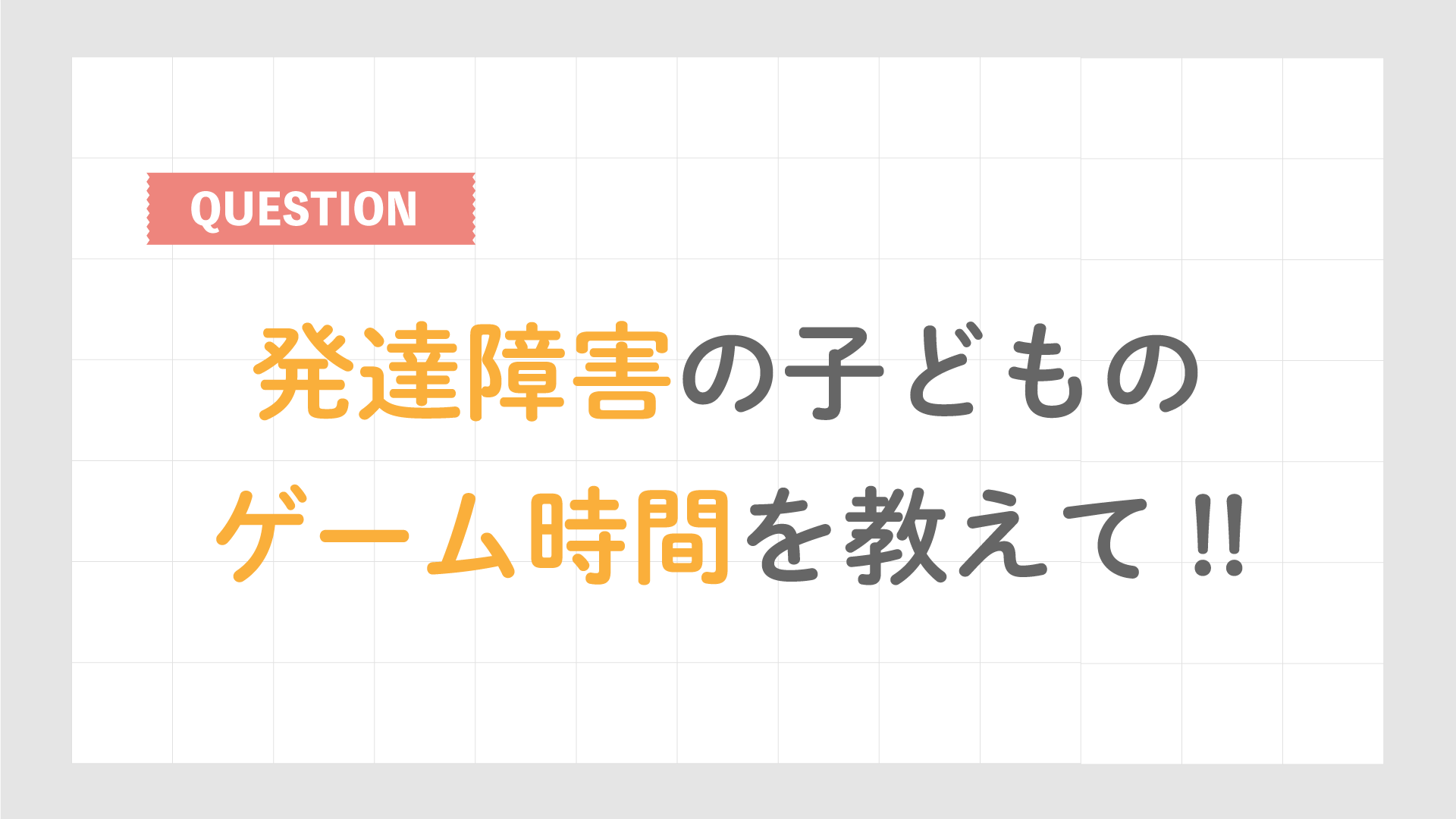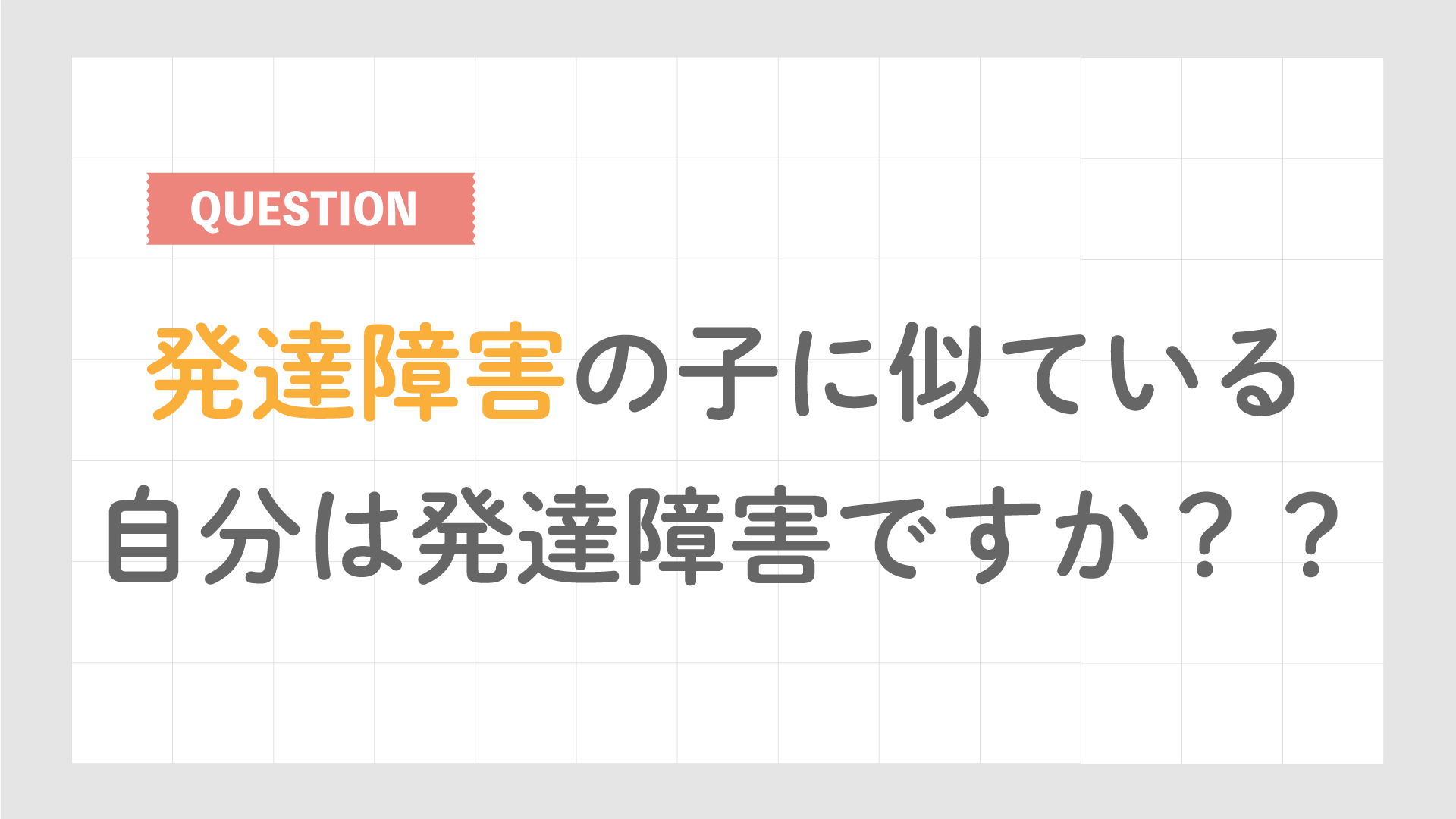軽度・中等度知的障害のある子の友達作りを応援!対人関係の壁と支援のコツ|富山の指導員が解説
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「軽度・中等度の知的障害があるお子さんの対人関係(人付き合い)」についてです。
「ウチの子、なんだか友達付き合いがうまくいかないみたい…」
「どうして周りの子とトラブルになりやすいんだろう?」
そんな風に悩んでいませんか? 人間関係は、子どもにとっても大人にとっても、心の安定にすごく重要ですよね。
今日は、なぜ対人関係に困難が生じるのか、その理由と具体的な支援策について、現場の視点からお話ししていきたいと思います。
人間関係は本当に必要か?
最近、「友達は必ずしもいなくてもいい」という風潮も少し広まっているな、とは感じています。確かにそれも一理あるなと思う部分はあります。
でも、僕は個人的に、人間はどこまでいっても「社会的な動物」なんだと思っています。
孤立や孤独が心に与えるダメージって、大人も子どもも関係なく、結構大きいんですよね。
自分の心の中をシェアできる相手がいるだけで、人間って安らげたり、頑張れたりすることが多いんじゃないのかなと思っています。
今回の記事では、主に軽度から中等度の知的障害があるお子さんの支援というテーマでお話しします。
中等度でも重度に近い場合や、重度・最重度の場合は、他者への依存度合いも大きく、ご家庭だけで支援するよりは、専門の支援施設に繋がることが最重要になってくると思います。
この記事では、ご家庭でも取り組めるレベルとして、軽度・中等度のお子さんをイメージしてお話ししていきますね。
なぜ対人関係に困難が出るのか?
人付き合いがうまくいかない原因は、本当に様々です。ですが、その根本には「コミュニケーション」の課題があることが多いです。
友人関係って、基本的にはお互いの意見交換ですよね。自分の気持ちを相手に話し、相手の気持ちも話してもらう。この「相互関係」が大事だと思うんです。
そして、その相互関係を築くために一番役立つのが、やっぱり「言語的なコミュニケーション」なんじゃないのかなと思っています。
理由①:言語理解の難しさ
まず、相手の言っていることを「理解する」部分の難しさです。
軽度・中等度の知的障害があるお子さんの場合、複雑な言語の理解が難しいことがあります。
例えば、
- 複雑な文章構造(シンプルに文が長い)
- 抽象的な概念
- 比喩表現(皮肉や冗談)
こういった、微妙なニュアンスを含む言葉の理解が難しいことがあります。動画で「布団が吹っ飛んだ」という冗談を例に出しましたが、これは極端な例だとしても、言葉を文字通りに解釈する傾向はあります。
また、全般的に情報を処理するスピードがゆっくりな方も多いです。早口で喋られたり、一度に大量の情報を渡されると処理しきれず、会話の早いテンポについていけなくなることもあります。
さらに、「あれ」「それ」といった指示代名詞や、「(暗黙の)あれやってほしいんだけどな」といった間接的な要求、曖昧な表現の理解も苦手な場合があります。

ゆう先生の補足解説:抽象的な概念と暗黙知
「抽象的な概念」というのは、例えば「友情」「ルール」「(人の)気持ち」といった、目に見えないけれど私たちが共有している考え方のことです。これらは具体的なモノではないため、理解するのが難しくなります。
また、日本語の会話は「暗黙知(あんもくち)」、つまり「言わなくても分かるよね」という前提で成り立つことが非常に多いです。
例えば「あれ取って」と言われても、定型発達の人は文脈や視線で「あれ=テーブルの上のリモコン」と推測できます。
しかし、この「推測する」作業には高度な情報処理が必要なため、知的障害があるお子さんにとっては非常に分かりにくく、「どれのこと?」となってしまうのです。
理由②:会話表現の苦手さ
次に、自分の気持ちを「表現する」部分の難しさです。
- 発音や流暢さの問題:滑舌が少し悪かったり、たどたどしくなってしまったり、逆に早口になったりして、相手にうまく言葉が伝わらないことがあります。
- 語彙の少なさ:自分の感情や考えを表現するための「良い言葉」を見つけるのに苦労することがあります。「悲しい」のか「悔しい」のか、その微妙な違いを言葉にするのが難しいんですね。
- 同じ質問の繰り返し:一度で覚えるのが難しく、何度も同じ質問をしてしまい、相手を困惑させてしまうこともあります。
- ヘルプサインが出せない:自分が混乱している時や困っている時に、「助けて」と自分から言うのが難しい。黙り込んでしまうことも多いです。
こういった「表現」の難しさがあると、周りの人たちもその子の状況が理解できないんですよね。本人は一生懸命伝えようとしているんだけど、言葉がずれていってしまう。
この「伝えたいのに伝わらない」という体験談は、当事者の方からよく聞かれます。
「自分の精神年齢が低く感じる」「友人関係に理想を求めすぎてしまう」といった悩みも、こういったコミュニケーションのズレから生じていることが多いように感じます。
理由③:会話の進行や「見えないルール」の壁
言葉そのものだけでなく、「会話のキャッチボール」を続けることにも難しさがあります。
- 順番を守れない:相手の話を遮って話し始めてしまう、など。
- 会話の主題から逸れやすい:あるテーマについて話していたのに、急に自分の興味がある話に移ってしまうことがあります。これは、言葉をうまく活用できない分、自分が話しやすい話題にピンポイントが合ってしまう、とも言えます。
- 非言語的サインの解読が難しい:表情、身振り手振り、声のトーンといった「言葉以外の情報」を読み取るのが苦手です。相手が怒っているのか、退屈しているのかが分からないまま、会話が一方的になってしまうことがあります。

ゆう先生の補足解説:非言語的サインと「空気を読む」こと
私たちは会話中、言葉の内容(言語情報)と同じくらい、表情や声色(非言語情報)を重視しています。
例えば「すごいね」という言葉も、笑顔なら称賛、無表情なら皮肉、と意味が変わりますよね。
この非言語情報をリアルタイムで読み取り、状況に合わせて自分の行動を調整することを、俗に「空気を読む(KY)」と言います。
これは、「相手の表情」「声のトーン」「その場の状況」「過去の経験」など、膨大な情報を瞬時に統合して判断する、非常に高度な脳の働きです。
ここに難しさがあると、「病院の待合室で大きな声で喋ってしまう」など、状況にそぐわない行動として現れることがあります。
これらの要因が複雑に絡み合い、結果として「友達作りの方法が分からない」「誤解や衝突が生まれやすい」という状況になり、孤立やトラブルに発展しやすくなってしまうのです。
一番大事なのは、これらは本人がわざとやっているわけではない、ということです。ですから、ご本人を責めないであげてほしいなと思います。
具体的な支援策:ソーシャルスキル・トレーニング(SST)
では、どうすればいいのか。今日一番お伝えしたいのが、療育施設などでよく行われる「SST(ソーシャルスキル・トレーニング)」です。
あ

ゆう先生の補足解説:ソーシャルスキル・トレーニング(SST)とは
SST(Social Skills Training)とは、日本語で「社会生活技能訓練」などと訳されます。難しく聞こえますが、要は「対人関係や社会生活に必要なスキル(挨拶、会話、感情コントロールなど)を、具体的に教えて練習する」ための、構造化された(やり方が決まった)アプローチです。
私たちが自転車の乗り方を練習するように、対人関係のスキルも「練習して身につける」という考え方に基づいています。
知的障害があるお子さんの場合、ただ「やりなさい」と言葉で言われるだけでは理解が難しいため、より構造化され、視覚的に分かりやすい支援を取り入れながらSSTを行うことが有効です。
SSTの具体的な進め方
SSTには大まかな流れがあります。
1. ターゲットスキルの特定
まずは、何に困っているのかを明確にします。例えば「挨拶がうまくできない」「会話の始め方が分からない」「他者の気持ちの理解ができない」など。
チェックリストなどを使っても良いですが、一度に全部やろうとせず、まずは1つに絞ることが大切です。
2. スキルの教示(モデリング)
次に、そのスキルをどうやればいいのか、「お手本(モデル)」を見せます。
「こんな風に言うんだよ」「こんな風にやるんだよ」と、お父さんお母さんが実際にやって見せます。紙芝居のように絵に描いて見せるのも良いですね。
3. リハーサル(ロールプレイ)
お手本を見たら、実際にその場を想定して練習(ロールプレイ)してみます。お父さんお母さんが相手役になって、お子さんにやってもらいます。
この時、可能であれば動画に撮って、後で本人に客観的に見せてあげるのもすごく効果が高いです。
4. フィードバック
練習したら、「フィードバック(評価)」をします。
ここで大事なのは、悪かったことを指摘するのではなく、良かったことを見つけて褒めることです。「今の言い方、すごく良かったよ!」「この部分、最高だった!」と伝えることで、その行動が定着しやすくなります。
5. 般化(はんか)
お家で練習してできるようになったら、最終ステップの「般化(はんか)」です。
般化とは、練習したスキルを、日常生活の様々な場面(学校やお店など)で実際に使えるようにしていくことです。例えば挨拶の練習をしたら、ご近所の方に協力してもらって実際に挨拶をしてみるなど、少しずつ使える場所を増やしていきます。
視覚支援の活用(ソーシャルストーリーとコミック会話)
SSTを進める上で、言葉だけの説明では理解が追いつかない場合があります。そこで「視覚支援」を活用します。
ソーシャルストーリー
これは、特定の社会的状況(例:友達の遊びに混ざりたい時、順番を待つ時)で、「どういう状況か」「相手がどう感じるか」「どう行動すればよいか」を、本人の視点で短く具体的に書いた「説明書」や「小さな絵本」のようなものです。困った時にそれを見返すことで、本人が自分で行動を思い出す手助けになります。
コミック会話
これは、キャロル・グレイ氏が開発した方法で、会話や社会的状況を「吹き出し」や「思考バブル(考えていること)」を使ってマンガのように書き出す手法です。特に、感情(嬉しい、悲しい、怒り)を「色分け」して表現するのが特徴です。例えば、怒っている言葉は赤色、悲しい気持ちは青色で書くことで、「言葉の裏にある感情」が視覚的に理解しやすくなります。
これらの視覚支援は、SSTの練習中にも使えますし、練習が終わった後の「お守り」として持たせてあげるのも非常に有効です。
良い人間関係の中で学ぶこと
いろいろな技術をお話ししましたが、可能であれば一番良いなと思うのは、「良い人間関係がある場所に行く」ことです。
やはり、周りに良い関係性のモデルがたくさんある環境にいることが、自然と良い関係を学ぶ一番の近道だと思います。同じ境遇の仲間がいる場所などで、一緒に課題を解決していくという視点も大事なんじゃないのかなと感じます。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- 軽度・中等度の知的障害があるお子さんは、言葉の理解(複雑な表現、抽象的な概念)や表現(語彙、自分の気持ちを伝える)に難しさを抱えやすいこと。
- また、会話の流れや表情・声色といった「目に見えないルール(非言語的サイン)」を読み取ることが苦手な場合があること。
- 支援策としては、スモールステップで具体的に教え、練習する「SST(ソーシャルスキル・トレーニング)」が有効であり、特に「ソーシャルストーリー」や「コミック会話」といった視覚的な支援が本人の理解を助けること。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
対人関係というのは、発達のでこぼこがあってもなくても、難しいものですよね。でも、難しさがあるからこそ、そこに感動や喜びも付随するものだと思います。
もしお子さんの対人関係で悩んでいたら、まずは何か一つ、小さなスキルからSST(練習)を始めてみることをお勧めします。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。