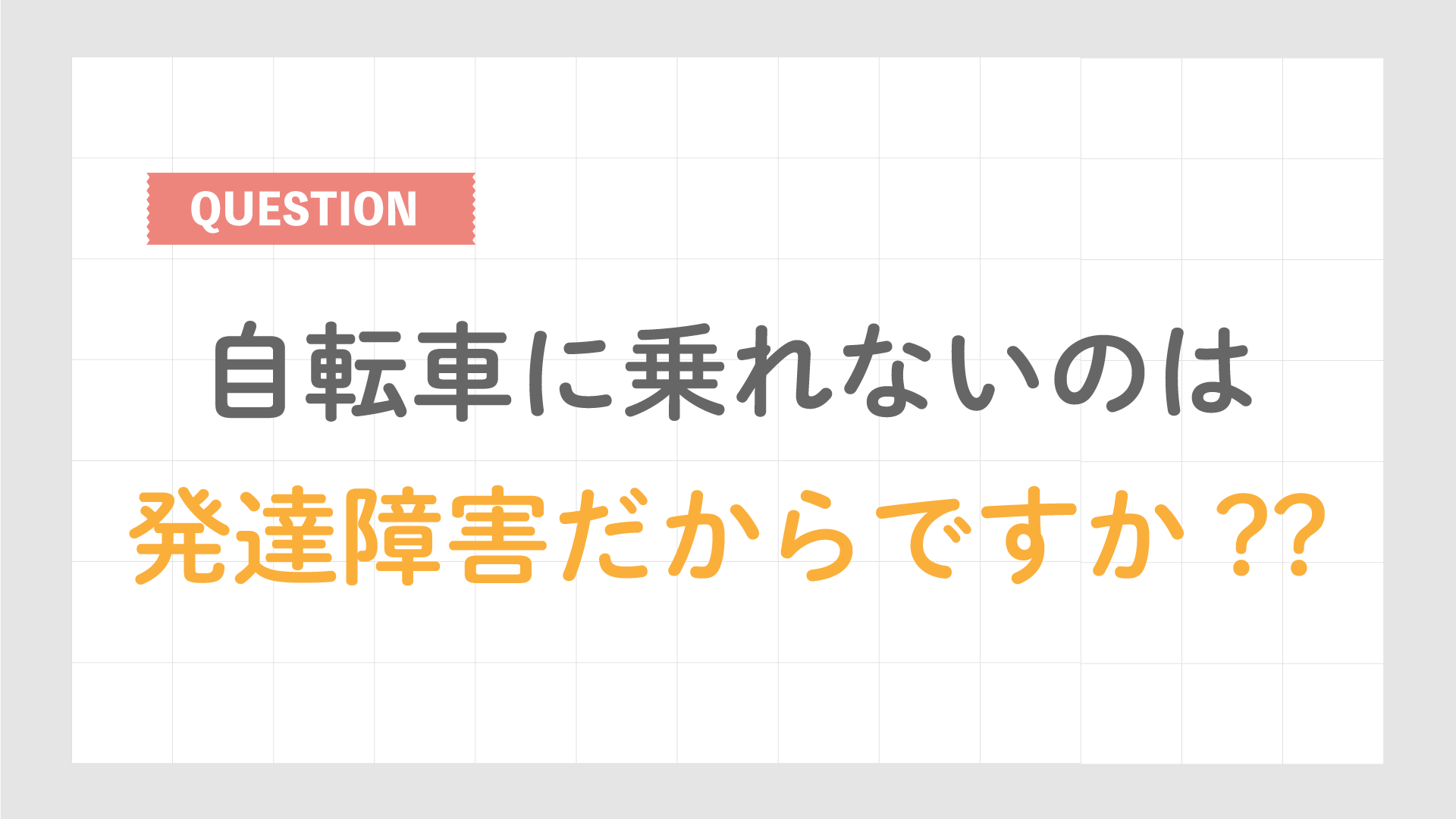軽度・中等度知的障害のある子への学習支援:カギは「具体化」と「繰り返し」|富山の指導員が解説
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「軽度から中等度の知的障害のあるお子さんへの学習支援」についてです。
知的障害支援の出発点:「適応機能」を理解する
前回の動画(記事)でもお話ししましたが、知的障害の支援を考える上で、IQの数値だけではなく**「適応機能」**を理解することがすごく大事なんですよね。

ゆう先生の補足解説:適応機能(適応行動)とは?
適応機能とは、簡単に言うと「生きる力」「生活力」のことです。その人が年齢や社会に合わせて、自立した責任ある生活を送るために必要なスキルのことです。
大きく分けて3つの領域があります。
- 概念的スキル:言葉の理解、読み書き、計算、時間やお金の管理など(今回のテーマである学習支援に大きく関わる部分です)。
- 社会的スキル:挨拶、順番を守る、友達作り、共感、ルール理解など(対人関係に関わる部分)。
- 実用的スキル:食事、着替え、トイレ、家事、健康管理など(生活スキルに関わる部分)。
知的障害の支援では、IQの数値と合わせて、この3つの領域のどこに、どのくらいのサポートが必要なのかを見極めることが、支援の出発点になります。
今日はこの3領域の中でも、特に保護者の方が悩まれることの多い「①概念的スキル=学習支援」に焦点を当てて、具体的なコツをお話ししていきます。
今回の対象:軽度〜中等度のお子さん
今回の学習支援のお話は、主に軽度から中等度の知的障害のあるお子さんを対象としています。
- 軽度知的障害:IQ目安 50〜70(75)程度
- 中等度知的障害:IQ目安 35〜50程度
この範囲のお子さんたちは、適切な支援があれば、自立してできることが増えたり、部分的に得意なことを伸ばしたりできる可能性が高いと僕は感じています。
(※重度・最重度のお子さんへの支援は、また違った視点が必要になるため、別の機会にお話しできればと思います。)
学習・対人・行動はつながっている
学習支援の話に入る前に、一つだけ知っておいてほしいことがあります。
それは、「学習」「対人関係」「行動」の困難さは、それぞれ独立しているわけではなく、互いに関連し合っているということです。
例えば、
- 勉強が分からなくて(学習の困難)→イライラして物を投げてしまう(行動の問題)
- 先生の指示が理解できなくて(コミュニケーションの問題)→課題に取り組めない(学習の困難)
というように、一つの困難が別の困難を引き起こしている場合があります。
ですから、今日お話しする学習支援だけでなく、次回以降にお話しする対人関係や行動面の支援も含めて、全体的に見ていくことが大切なんですよね。
早期発見・継続支援の大切さ
もし、「うちの子、もしかして…?」と思われる場合は、早めに専門家(病院の先生、地域の相談窓口、学校の先生など)に相談してみることをお勧めします。
療育施設などに通い始めると、「個別支援計画」というものを作成し、その子に合った具体的な目標や支援方法を計画的に進めていきます。
早期から継続的に支援を受けることで、お子さんの能力を高めたり、適切なサポートの仕方を学んだりすることができますよ。

ゆう先生の補足解説:個別支援計画とは?
児童発達支援や放課後等デイサービスなどの療育施設で、一人ひとりのお子さんの特性や発達段階、保護者の意向などを踏まえて作成される、個別の支援計画書のことです。
「〇ヶ月後にこういうことができるようになる」といった長期目標や、「そのために今週はこういう活動をする」といった短期目標、具体的な支援内容などが記載されます。
定期的に見直しを行いながら、お子さんの成長に合わせて計画を更新していきます。
学習支援の最大のコツ:「具体化」する!
さて、ここからが本題です。
知的障害のあるお子さんへの学習支援で、僕が一番大事だと考えていること。それは、学習内容をとことん「具体化」することです。
知的障害のあるお子さんは、抽象的な概念を理解するのが苦手な傾向があります。

ゆう先生の補足解説:抽象的な概念が苦手とは?
「抽象的」とは、目に見えない、形のない考えや概念のことです。例えば、「時間」「お金」「友情」「ルール」「面積」などですね。
知的障害のあるお子さんは、目に見える具体的な物(りんご、車など)は理解できても、こうした形のない概念を頭の中でイメージしたり、操作したりすることが難しい場合があります。
学校の先生の言葉だけの説明(聴覚情報)だけでは理解しにくいのも、言葉という抽象的な記号を処理するのが苦手なためと考えられます。
だから、言葉だけの説明ではなく、目で見て分かるように、実際に触って確かめられるように、具体的にしていくことが非常に重要なんです。
具体化の方法①:実物や模型を使う
特に算数や理科の学習では、実物や模型をどんどん活用しましょう。
- 算数:
- 足し算・引き算なら、おはじきやブロック、指を使う。
- 時計の学習なら、本物の時計の模型を操作する。
- お金の計算なら、おもちゃのお金を使ってみる。
- 理科:
- 植物や昆虫の観察なら、図鑑だけでなく、実際に外に出て本物を見てみる、触ってみる。
頭の中だけで考えるのではなく、目の前にある具体的なモノを通して理解を促していくことが大切です。
ただし、算数で扱う数が大きくなってくると(1000や1万など)、具体物で示すのが難しくなってきます。その場合は、数のまとまりを意識させるなど、別の工夫が必要になってきますね。
具体化の方法②:視覚教材を活用する
実物と並んで強力なのが、視覚教材(視覚支援)です。写真、絵カード、図、イラスト、グラフ、手順書など、目で見て分かるものは何でも活用しましょう。
知的障害や発達障害のあるお子さんの多くは、「耳で聞く情報」よりも**「目で見る情報」の方が理解しやすい**(視覚優位)という特性を持っていることが多いからです。
言葉で「片付けなさい」と言われるよりも、片付けの手順が写真で貼ってある方が、何をどうすればいいか分かりやすいんです。目で見えることで、安心感にもつながります。
最近は、ChatGPTのようなAIにお願いすれば、支援に使えそうなイラストを簡単に作ってくれたりもします。
そういったツールも活用しながら、お子さんが理解しやすい視覚的な手がかりを、生活のいろいろな場面に取り入れてみてください。
具体化の方法③:体験的な学習を取り入れる
頭で覚えるだけでなく、実際にやってみる体験を通して学ぶことも非常に有効です。
- 調理実習:料理の手順を体験する中で、計量(算数)、手順の理解(国語)、段取り(実行機能)などを学ぶ。
- 買い物学習:実際にお店に行って、お金を使う練習をする。
- 職場体験:(大きくなったら)働くことを体験してみる。
「言葉だけだと分からないけど、自分でやってみたことなら分かる」ということは、知的障害のあるお子さんにはとても多いです。

ゆう先生の補足解説:エピソード記憶との関連
体験的な学習が記憶に残りやすいのは、「エピソード記憶」と関連しているからかもしれません。
エピソード記憶とは、「いつ、どこで、何をした」といった、個人的な体験に基づいた記憶のことです。
例えば、「川について教科書で学ぶ」だけでなく、「実際に川に行って、水の冷たさや流れの速さを感じた」という体験(エピソード)があると、その時の感情や感覚と一緒に記憶に残りやすくなります。
机上の学習だけでなく、実生活と結びつけながら、体を通してスキルを習得していくことを意識してみてください。
学習支援の「原則」:スモールステップと反復練習
具体化の方法と合わせて、絶対に押さえておきたい支援の原則が2つあります。
原則①:スモールステップで課題を細分化する
どんな課題に取り組むときも、いきなりゴールを目指すのではなく、非常に小さなステップに分けて、一つひとつクリアしていくことが大切です。
スモールステップとは、目標達成までの道のりを、非常に小さく、簡単なステップに分解していく支援方法です。
例えば、「10までの足し算」を教える場合、
- まず「1+1」だけを練習する。
- できたら「1+2」を練習する。
- 次に「2+1」を…というように、少しずつ難易度を上げていきます。
小さな「できた!」を積み重ねることで、お子さんは達成感を得やすくなり、学習意欲や自信につながっていきます。
知的障害のあるお子さんは、一度にたくさんの情報を処理するのが苦手です。一つの課題を確実にクリアしてから、次のステップに進む。この丁寧な積み重ねが重要です。
原則②:反復練習で定着させる
そして、一度できたからといってすぐに次に進むのではなく、知識やスキルが確実に定着するまで、何度も何度も繰り返して練習することが非常に重要です。
知的障害のあるお子さんは、新しいことを覚えるのに時間がかかったり、覚えても忘れやすかったりすることがあります。
周りの子よりも時間はかかるかもしれません。でも、その子の一生を考えた時に、必要なスキルは根気強く、繰り返し練習して身につけていく必要があります。
ここで注意したいのが、「やり方」をコロコロ変えないことです。
いろんな方法を試したくなる気持ちも分かりますが、知的障害のあるお子さんの場合、やり方が変わると混乱してしまうことが多いです。
一度教えたやり方で、できる限り統一して練習を続ける方が、定着しやすいと僕は思います。
まとめ
今日の記事では、軽度から中等度の知的障害のあるお子さんへの学習支援のコツについてお話ししました。
- 支援の出発点は、「学習」「対人関係」「生活スキル」という3つの適応機能の領域で、どこにどの程度の支援が必要かを見極めることです。
- 学習支援の最大の鍵は、抽象的な概念を避け、実物・模型、視覚教材、体験学習などを通して、とことん「具体化」することです。
- どんな課題も「スモールステップ」で細かく分け、一つひとつ確実にクリアしていくこと。そして、定着するまで諦めずに「反復練習」を続けることが、成長への確実な道筋となります。
結論:読者へのメッセージ
学習支援は、根気のいる作業かもしれません。でも、お子さんに合った「具体化」の方法を見つけ、小さな「できた!」を一緒に喜びながら、焦らず一歩ずつ進んでいくこと。
それが、お子さんの持つ能力を最大限に引き出すことに繋がっていくはずです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。