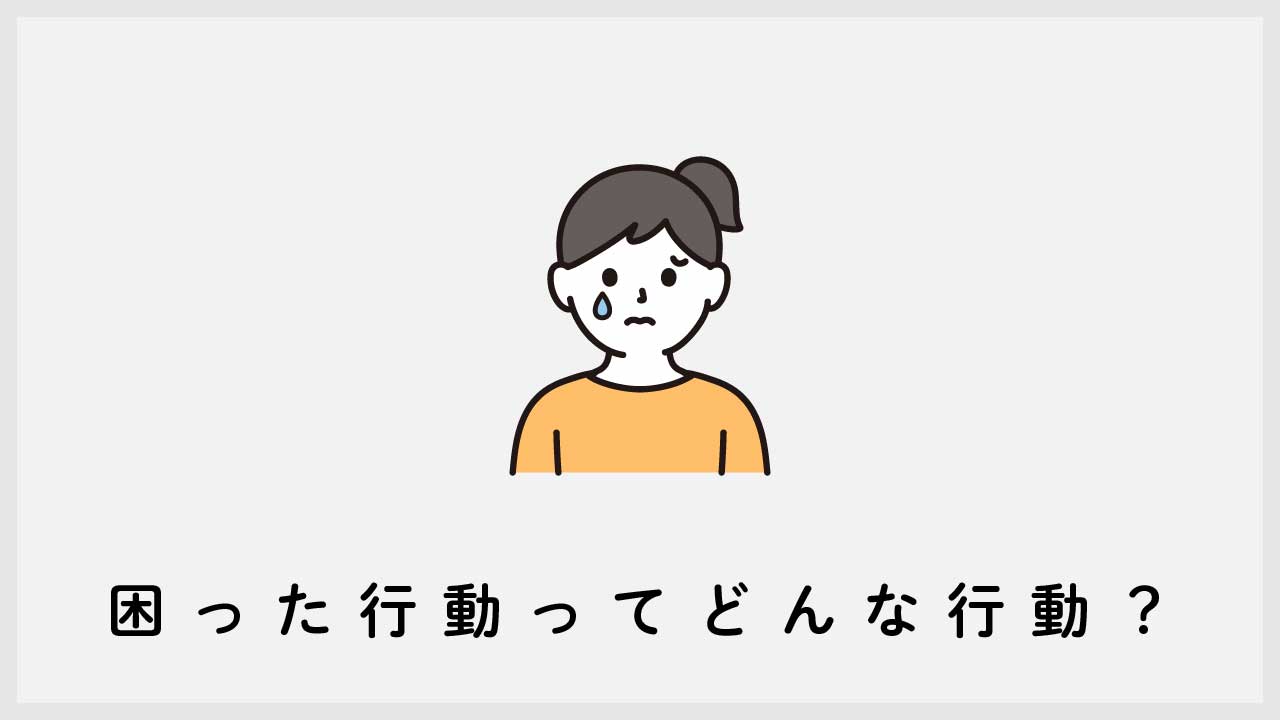上手な伝え方について|子どもの発達障害を解説

こんにちは!ゆう先生です!
「子どもがなかなか課題に取り組んでくれない」
「こちらの指示を聞いてくれない」
と感じたことはありませんか?
そんなとき、イライラして「ちゃんとやって!」と繰り返してしまうと、子どもも大人も疲れてしまいます。
実は、伝え方を少し工夫するだけで、子どもが「やってみよう!」と前向きになることが多いのです。
本日は、子どもが自発的に行動しやすくなる「上手な伝え方」のポイントについて、詳しくお話ししていきます。

伝わらない理由を理解する

子どもが指示に従わないとき、「この子は聞いていないんじゃないの?」と感じるかもしれません。
でも、実はただ聞いていないわけではなく、いくつかの理由が考えられます。
指示に気づいていない:
子どもは自分の好きな遊びや考え事に夢中になると、周りの声が耳に入らないことがあります。
指示が聞こえていない:
周りがざわざわしていたり、テレビの音が大きかったりして、そもそも指示が聞き取りにくい環境かもしれません。
指示の意味が分からない:
言葉が難しかったり、指示が抽象的すぎて「何をすればいいのか」わからない場合があります。
興味がない、やりたくない:
そもそも、その活動自体が子どもにとって楽しくなかったり、モチベーションがわかなかったりする場合があります。
やることが具体的に伝わっていない:
「片付けて」だけでは何をどこに片付ければいいのかわからず、行動に移せないことがあります。
子どもが指示に従わない背景には、こうしたさまざまな要因があるのです。
まずは、子どもの状態や環境を観察し、「なぜ伝わっていないのか」を考えてみましょう。その理解が、次のステップである「伝え方の工夫」につながります。
伝え方の工夫

子どもが指示を理解し、自発的に行動できるようにするためには、次のポイントを押さえてみてください。
1. 注意を引いてから指示を伝える
子どもが他のことに夢中になっているとき、いきなり指示を出しても気づかないことがあります。
その時には、以下のようにサインなどを送ることが重要です。
まず、子どもの名前を呼んだり、軽く肩に触れたり、目線を合わせたりして、まずは「今から話すよ」というサインを送ります。その上で

Aくん、ちょっといい?
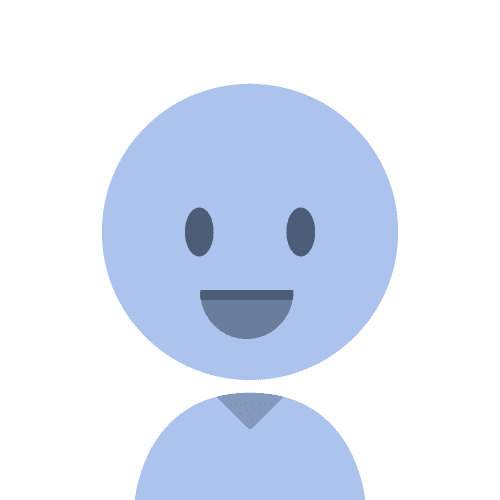
うん。

これから宿題を始めようね!
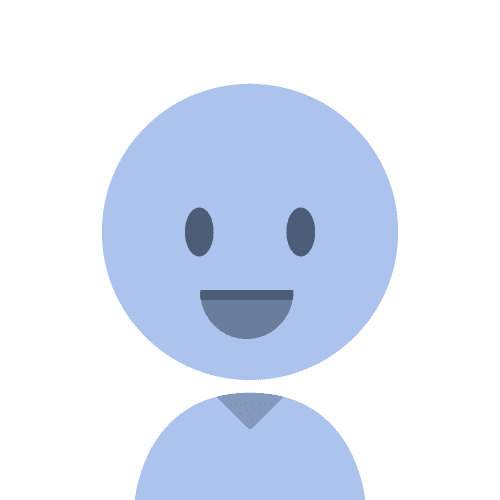
わかった!
このように、お話を聞ける状況を作ることで、子どもは指示に気づきやすくなります。
2. 短く具体的に伝える
あいまいな表現や長い説明は、子どもの理解を妨げます。
悪い例(BAD)
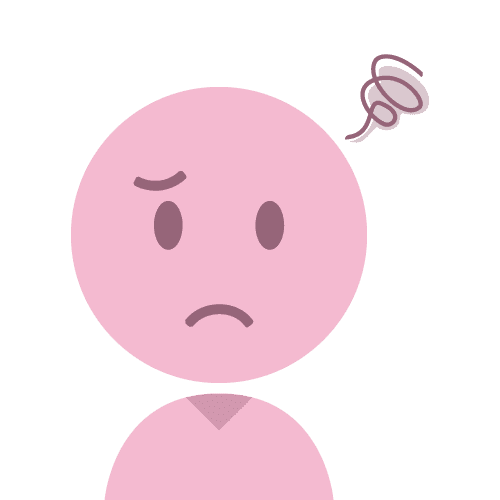
ちゃんとしなさい!
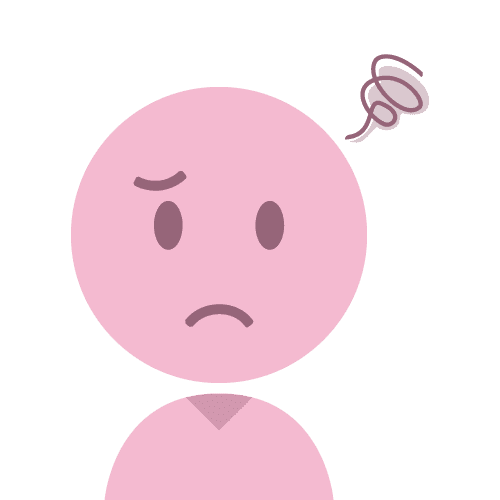
きちんと片付けて!
このように
「ちゃんとしなさい!」
「きちんと片付けて!」
のような抽象的な言葉だと、子どもは「何をどうすれば ‘ちゃんと’ なの?」と戸惑います。
良い例(GOOD)

青い本を机の右側に置いてね

おもちゃを箱に入れて、ふたをしてから棚に戻してね
こうした具体的な指示であれば、子どもは「なるほど、こうすればいいんだ」と理解しやすくなります。
3. 好きなもの・ことを取り入れる
子どもが好きなキャラクターや遊び、興味のあるものを使って指示を伝えると、意欲が高まります。
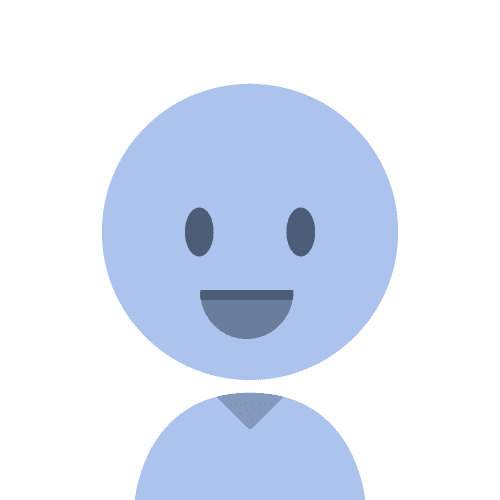
今からお片付けしたら、トミカで遊ぼう!

この問題が解けたら、大好きな昆虫図鑑を見せてあげるね
といった工夫で、子どもは「やってみようかな」と感じるでしょう。
ただ「これって幼児向け??」って思われた方もいるかもしれません。
事例は確かに幼児のものでしたが、基本的には、小学生も中学生も大人もこれでOKです。
なぜかというと、
人間は「知っているもの」「好きなもの」「メリットがあること」が聞き取りやすいという特徴があります。
なので、例えば、「勉強終わったら、一緒にゲームしよう!」みたいな言葉に変換して使って頂けたら幸いです。
良い伝え方を実践するために
上記のポイントを踏まえながら、さらに有効な方法を紹介します。
観察を大切にする
どんな言葉が分かりやすいか、どんなタイミングなら聞いてくれるか、子どもをよく観察しましょう。
子どもが集中しやすい時間帯や場所を探す
難しい言葉を使わず、子どもの理解力に合わせた表現を選ぶ
ポジティブな言葉を使う
「走らないで!」という否定的な表現よりも、「ゆっくり歩こうね」という肯定的な言葉のほうが、子どもは受け入れやすくなります。
「やめなさい!」よりも「こっちに注目!」「静かにできるかな?」
「ダメ!」よりも「こうしようね」
こうした言葉選びで、子どもは「命令されている」よりも「提案されている」と感じ、行動に移しやすくなります。
シンプルに伝える
一度に多くの指示を出すと子どもは混乱します。
悪い例(BAD)

まず、青い本を机の右側に置いて、次に赤いノートをしまって、それから色鉛筆をまとめて……
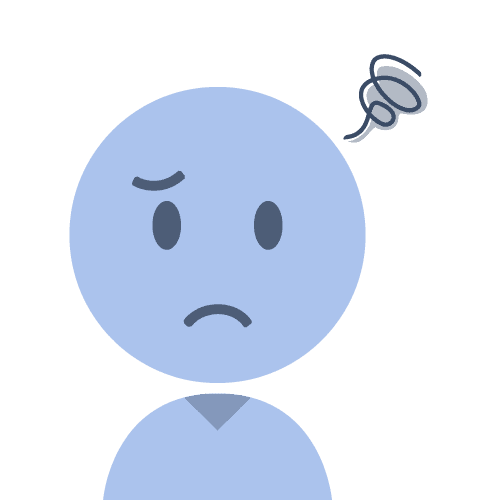
??????????
これでは子どもは途中で何をすればいいかわからなくなります。
代わりに、
良い例(GOOD)

まずは青い本を机の右側に置こうね!
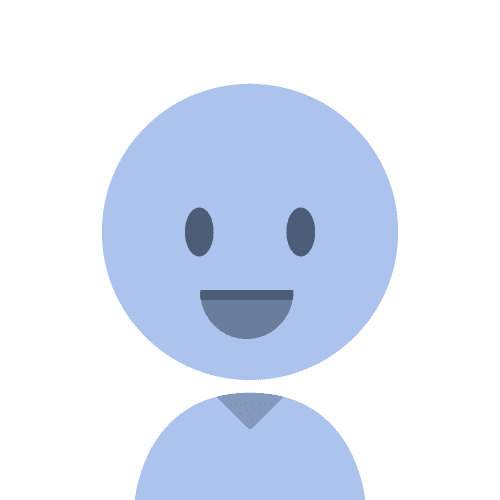
できた!!!!

じゃあ、次は赤いノートをしまってみよう!
とステップを分けると理解しやすくなります。
一回につき、一つの指示と覚えておくと良いかもしれません。
ただ、ここまで読んでみて、正直「どうすれば良いのか、分からない〜」って方は、オンライン相談支援(初回無料)を行っておりますので、
そちらも合わせてご確認いただければ幸いです。
まとめ
本日は、子どもが自発的に行動しやすくなる「上手な伝え方」のポイントについて、詳しくお話ししました。
子どもがなかなか指示に従わないと、つい苛立ちを感じたり、叱ってしまいがちです。
でも、ほんの少し伝え方を変えるだけで、子どもは驚くほど反応を変えます。
「子どもが気づいていないのかも」「言葉が難しいかも」「どんな表現がわかりやすいかな」と試行錯誤しながら、子どもに合った伝え方を探してみてください。
最初は思うようにいかなくても、少しずつ慣れてくれば「これでうまく伝わる!」という感覚がつかめてくるでしょう。
焦らず、やってみたことを振り返り、さらに改善していくことで、子どもとのやりとりがよりスムーズになり、楽しい時間が増えていきますよ。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!