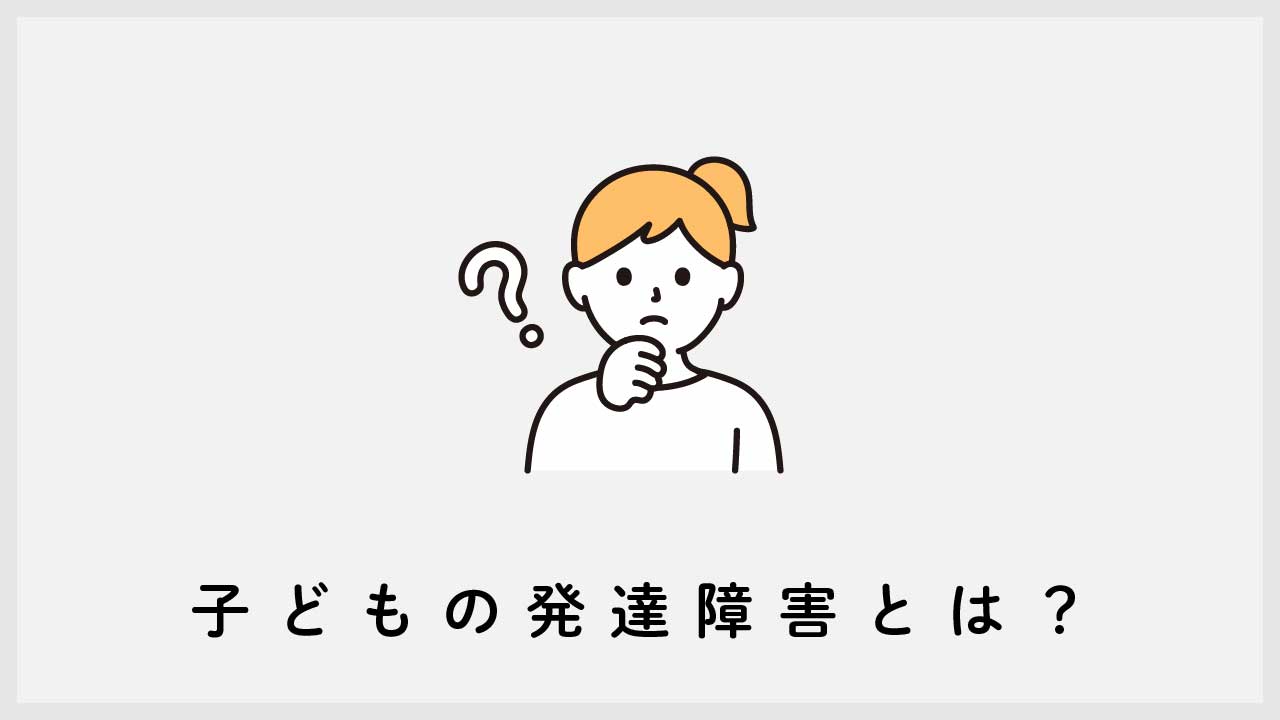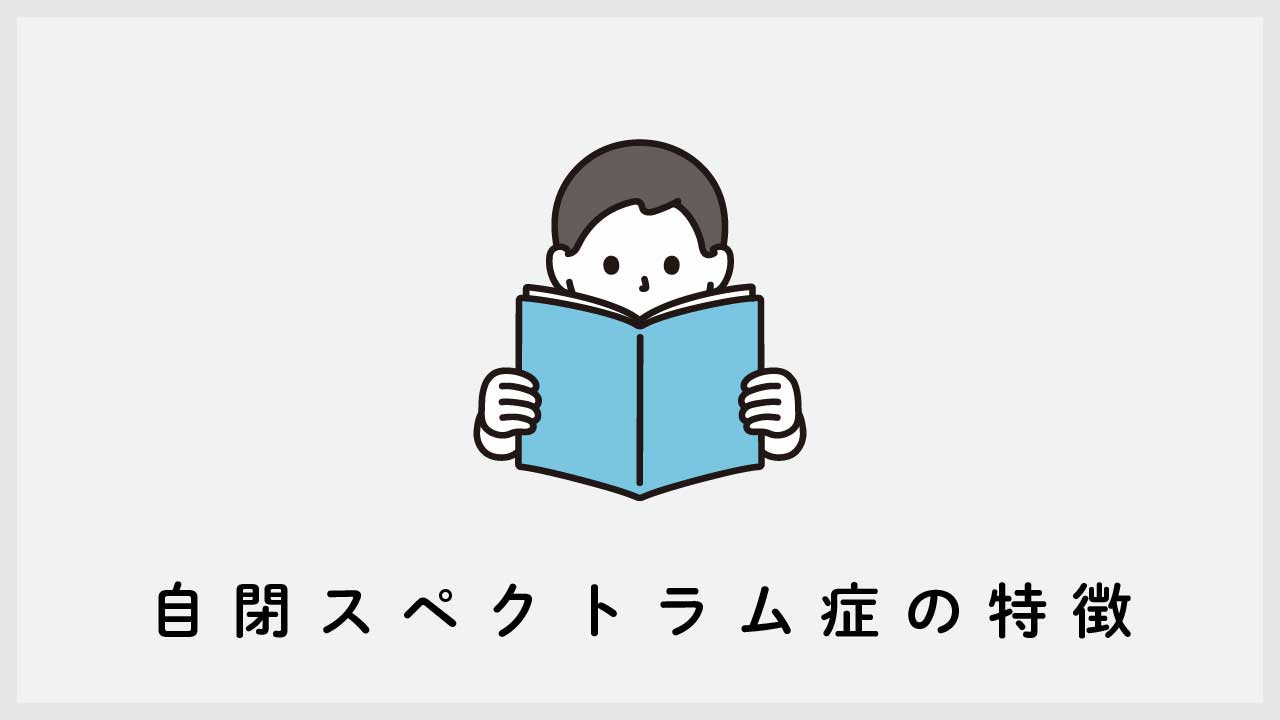ダウン症の子どもの特徴を解説|子どもの障害解説

こんにちは!ゆう先生です。
本日は「ダウン症」について解説していきます。
ダウン症のお子さんは、発達のペースがゆっくりだったり、運動や学習に時間がかかったりすることが多いですが、その分「できた!」という小さな成功を一緒に喜び合える瞬間もたくさんあります。
さらに、ダウン症のお子さんはとても穏やかで人懐っこく、周りを明るい気持ちにしてくれる不思議な魅力を持っていることも少なくありません。
ダウン症は、21番目の染色体が通常より1本多い「3本」ある状態で生まれる先天性の染色体異常です。
一人ひとり個性や得意なこと、苦手なことが違うように、ダウン症のお子さんにもさまざまな個性があります。
大切なのは「時間はかかっても、しっかりサポートすれば着実に成長していく」という前向きな視点を持つことです。

ダウン症の5つの主な特徴

(1)身体的な特徴
顔や体の特有の形
丸みのある顔つきや目尻がやや上向き、小さめの鼻や耳など、ダウン症のお子さんには共通して見られやすい身体的な特徴があります。
筋肉の緊張が弱い(低緊張)
赤ちゃんの頃は首がすわるのが遅かったり、寝返り・はいはい・歩行など運動面の発達がゆっくりになる場合が多いです。
このように運動面の発達がゆっくりなので、「首がすわったら次は座れるかな」といった小さなステップで成長を見守ってあげましょう。
作業療法士や理学療法士のサポートを取り入れると、体の使い方をサポートしてもらえます。
(2)知的発達の遅れ
学習や理解に時間がかかる
言葉や数字、色や形を覚えるのに時間がかかりやすく、一度にたくさんのことを理解するのは難しいことがあります。
視覚的な学習が得意
写真や絵カード、実物を見せて教えると理解しやすい子が多いです。
「具体物を見せてから名前を教える」「指差しをしながら短い言葉で伝える」など、一目でわかる工夫をすると、「なるほど、これが○○なんだ」とゆっくりでも確実に覚えていくことができます。
(3)言葉やコミュニケーションの遅れ
発音が不明瞭になりやすい
舌や口周りの筋肉の力が弱いため、音をうまく作りにくい子が多いです。
言葉の前にジェスチャーが出やすい
言葉でのやりとりより、指差しや身振り、表情などで気持ちを伝えることが先行することがあります。
お子さんが指差しや笑顔でアピールしているときは、「○○が欲しいんだね」「こっちを見てるんだね」と代わりに言葉にしてあげましょう。
無理に「しゃべって!」と求めるより、「伝わったね」「わかったよ」とポジティブに受け止めることで、少しずつ言葉への興味も引き出せます。
(4)社交的で人懐っこい性格
周りを笑顔にする力
穏やかで優しい雰囲気を持っていることが多く、家族や友だちともにこにこ関わろうとする姿がよく見られます。
他者と触れ合うことを楽しむ
「一緒に遊びたい」「抱っこしてほしい」という気持ちを素直に表すため、人とのつながりを育みやすいです。
この社交的な性格を伸ばすには、少人数での遊びや家族での交流を大切にしながら、「今日はみんなでおやつを作ってみよう」といった活動を通して、周りとのやりとりをたくさん経験させてあげるとよいでしょう。
(5)健康面での課題があることも
先天性心疾患や耳・鼻・喉のトラブル
ダウン症のお子さんには、心臓や呼吸器にトラブルを抱えやすい子もいるため、定期的な医療チェックが重要です。
感染症にかかりやすい
体調の変化にいち早く気づき、早めに病院を受診することで重症化を防ぐことができます。
健康面が落ち着いているときほど遊びや学習に取り組みやすいので、普段からかかりつけ医や専門医と連携しておくと安心です。
ダウン症のお子さんへのサポート3選
いきなり「服を全部着ようね」ではなく、「まずは靴下だけはいてみよう」というように、一つずつ具体的なステップを設定しましょう。
達成できたら大げさなくらいに「すごいね、できたね!」と褒めることで、お子さんの「もっとやってみたい!」という意欲が高まります。
口頭だけで伝えるより、写真や絵カード、動画など「目で見てわかるもの」を示すと、お子さんが理解しやすくなります。
たとえば「これがおもちゃの片付け方だよ」と写真を見せながら教えたり、「この色のブロックを箱に入れてね」と色カードを出してあげるのも良い方法です。
歌いながら言葉を覚えたり、音楽に合わせて体を動かしてみたり、楽しさを加えると集中力が続きやすくなります。
リズムに合わせて数を数える、掛け声を出すなど、「体を動かす・口を動かす」両方の練習を同時にできるので、運動面や言葉の面でのサポートにもつながります。
5. まとめ
本日は「ダウン症」について解説していきます。
ダウン症のお子さんは、ほかの子よりもゆっくりなペースで成長していくかもしれませんが、そのぶん一歩一歩の達成にたくさんの喜びがあります。
焦る必要はありません。「できないところ」にとらわれるより、「できるところ」「少しずつできるようになったところ」に目を向けて、毎日の積み重ねを楽しんでいきましょう。
また、健康面や発達面で不安があったら、遠慮なくかかりつけ医や専門家に相談してみてください。
適切な支援や療育プログラム、特別支援教育を活用しながら、「うちの子はここが得意だな」「こうすれば分かりやすいんだな」という方法を見つけていくことで、お子さんの世界はますます広がっていきます。
お子さんのペースを大切にしながら、一緒に一歩ずつ前へ進んでいきましょう。これからの成長を、心から応援しています!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。