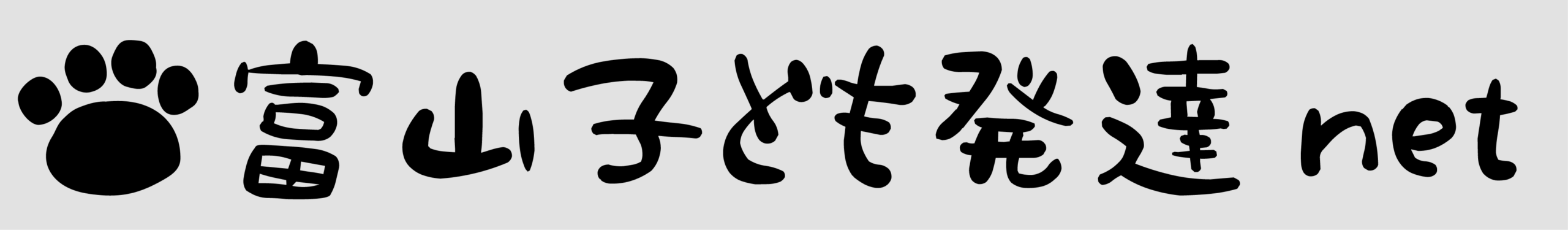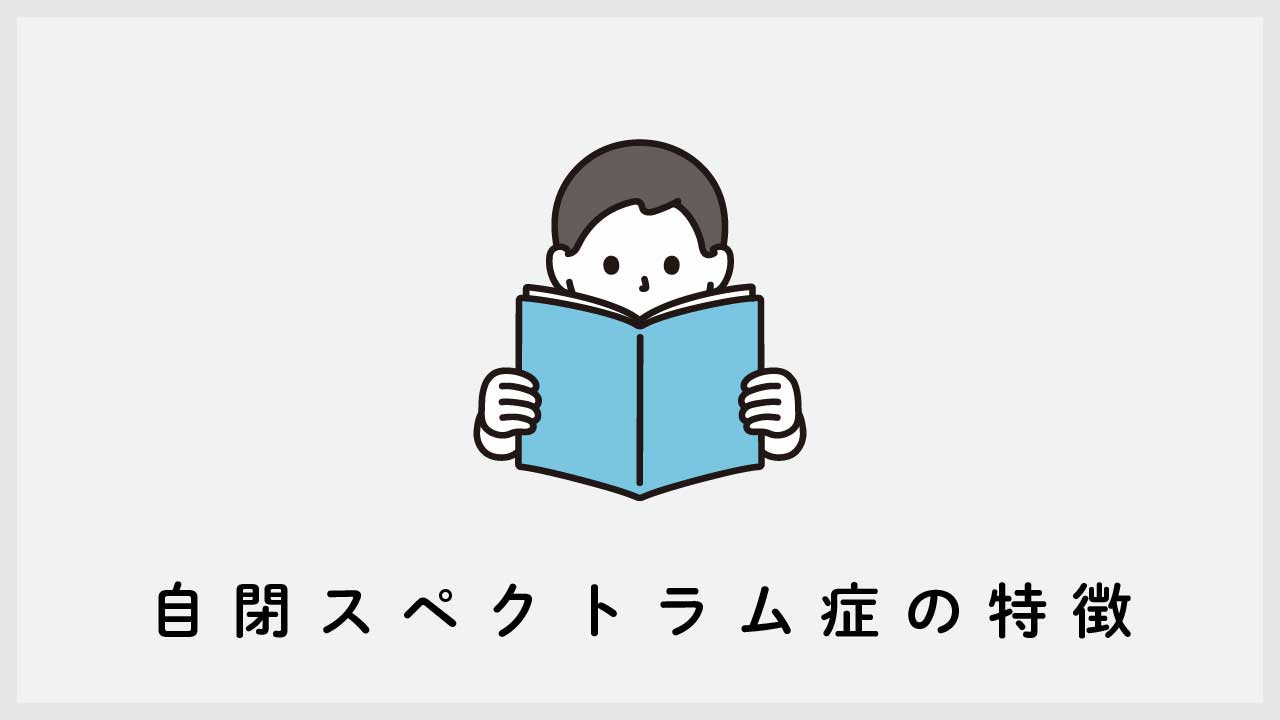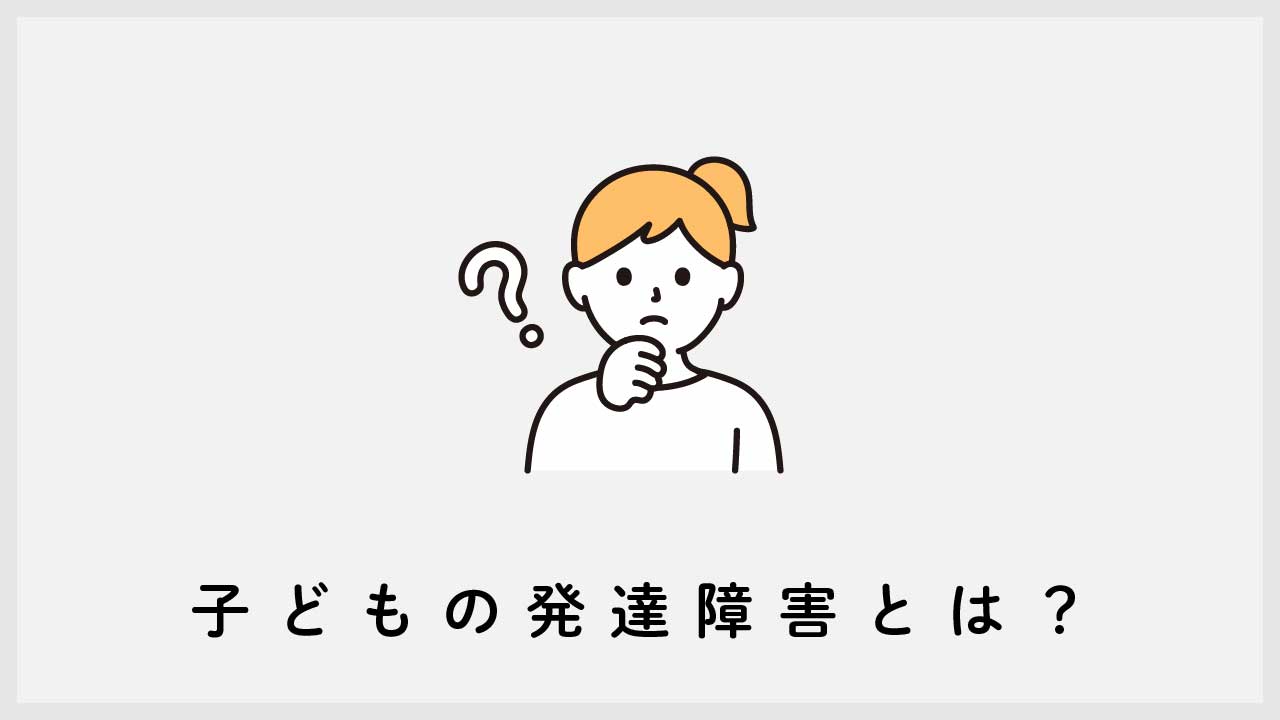ADHD注意欠如多動症の子どもの特徴を解説|子供の発達障害解説

こんにちは!ゆう先生です。
今回は「ADHD(注意欠如多動症)」のお子さんの特徴についてお話しします。
「うちの子がじっとしていられなくて…」
「集中がまったく続かない…」
と悩んでいる保護者の方もいらっしゃるかもしれませんが、ADHDは性格やしつけの問題ではなく、脳の働き方に特性がある状態です。
ADHDのお子さんは周りの刺激に反応しやすく、動き回るエネルギッシュさや、豊かな想像力・アイデアを持っていることが多いのが特徴です。
今回は、そんなADHDのお子さんが持ちやすい特性を理解し、少しの工夫でサポートする方法を一緒に考えていきましょう。

ADHDの3つの主な特徴

1)不注意 — 集中力の維持が苦手
落ち着いて作業が続かない
わずかな物音や視界に入るものが気になり、勉強や話し合いに集中できない場面があります。
忘れ物や紛失物が多い
朝持たせたはずのプリントがいつの間にか見当たらない、文房具を置いた場所をすぐ忘れてしまう、など。
このような特性があるため、作業を「10分区切り」など短いスパンで行い、適度に休憩や息抜きを挟むと集中力が続きやすくなります。
また、チェックリストや視覚的なスケジュールを活用して、やるべきことを一目でわかるようにすると見落としが減ることもあります。
さらに、忘れ物をしにくいように文房具やプリントを収納する定位置を作り、身の回りを整理しやすい環境を整えるのも有効な方法です。
(2)多動性 — じっとしているのが苦手
体を動かさずにはいられない
授業中やテレビを観るときでも、イスから立ち上がったり、つい落ち着きなく動いてしまうことが多いです。
周囲を巻き込むほど元気いっぱい
身振り手振りが大きく、声も思わず大きくなりがち。本人は悪気なくても、教室内で目立ってしまう場合があります。
こうしたエネルギッシュさは、生活の中に適度な運動の時間を取り入れることで上手に発散させることができます。
長時間の勉強や座り仕事は途中で区切りを入れ、「ここまで終わったらジャンプしていいよ」といった具体的な小休憩をはさむと、本人も我慢しやすくなります。
お子さんの「動きたい!」という気持ちを認めつつ、メリハリをつけながら集中すべきことと遊ぶ時間を上手に切り替える工夫をしてみましょう。
(3)衝動性 — 待つのが苦手
思いついたら即行動
相手が話し終わる前に口を挟んでしまったり、順番待ちができずに割り込んでしまうことがあります。
危険への配慮が抜けがち
道路に飛び出す、遊具から飛び降りるなど、先に行動してから「あっ、しまった!」と気づく場合も。
このように待ったり考えたりするのが難しい特性があるため、事前に「次は○○、その後××をしようね」と行動の順番を分かりやすく説明しておくと、衝動を抑えやすくなります。
「あと3回数えたら交代しようね」など、待ち時間をカウントダウンで見える化するのもおすすめです。
うまく待てたときにはしっかり褒め、自信と成功体験を積み重ねていくことで、少しずつ衝動性をコントロールできるようになります。
家庭でできるおすすめ支援3選
(1)刺激を減らす環境づくり
ADHDのお子さんは、どうしても周りの刺激が気になりやすいため、勉強机や遊ぶスペースをすっきり整えると集中力が高まりやすくなります。
例えば、机の上に必要なものだけを置く、壁に貼るポスターを最小限にする、音や光に敏感な場合は照明の強さを調整したりイヤーマフを準備したりしてあげるなど、小さな工夫を重ねてみてください。
(2)行動の手順を明確にする
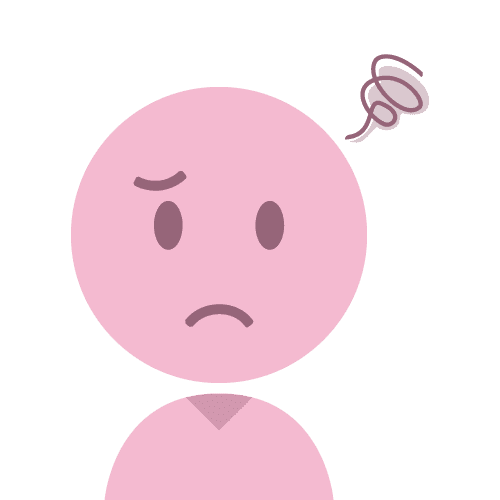
ちゃんとしなさい
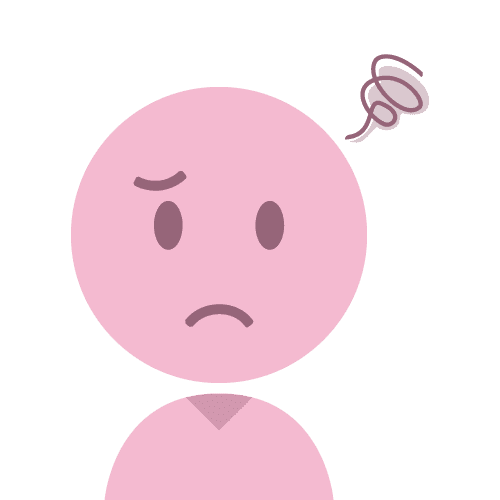
気をつけて
など抽象的な言葉では行動に移しにくいため、「廊下は走らないで」ではなく

廊下はゆっくり歩こうね!!
と伝えるように、望ましい行動を具体的に示すことがポイントです。
朝の準備やお出かけ前には、イラストや文字で作ったチェックリストを貼って、本人が見ながら確かめられるようにすると、自然と行動がスムーズになります。
(3)成功体験を積み重ねる
「また失敗しちゃったね」と注意ばかりしていると、お子さんの自己肯定感が下がってしまいます。
小さなことでもうまくいったら積極的に褒め、「今日は5分でも集中できたんだね!」といった具体的な成功を言葉にしてあげましょう。
ごほうびと言っても物だけではなく、一緒に好きな遊びをする時間を増やすなど、子どもが「やった!」と感じられる形を作ってあげるとより効果的です。
まとめ
ADHD(注意欠如・多動症)は、決して「わがまま」や「しつけ不足」ではなく、生まれ持った脳の特性です。
お子さんの特性を正しく理解し、適度に環境を整えたり、行動の手順をわかりやすく伝えたりするだけで、「困った…」と感じる場面をぐっと減らすことができます。
何より大切なのは、「この子はこういう特性があるんだ」と肯定的に受けとめる姿勢です。
ADHDのお子さんは、エネルギーや創造力に満ちあふれ、周りをパッと明るくするようなポジティブな力を持っています。
苦手なところを責めるのではなく、「好きなことや得意なことをどう伸ばせるかな?」と視点を変えてあげると、お子さんの笑顔も増えていくはずです。
もし悩みが大きくなったり、対応が難しいと感じた場合は、専門家や支援機関に相談してみるのもおすすめです。
一人で抱え込みすぎず、周囲と協力しながら少しずつ前に進んでいけば、きっと明るい未来が見えてきます。
焦らず、一歩ずつ、お子さんのペースに合わせて成長をサポートしていきましょう。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!