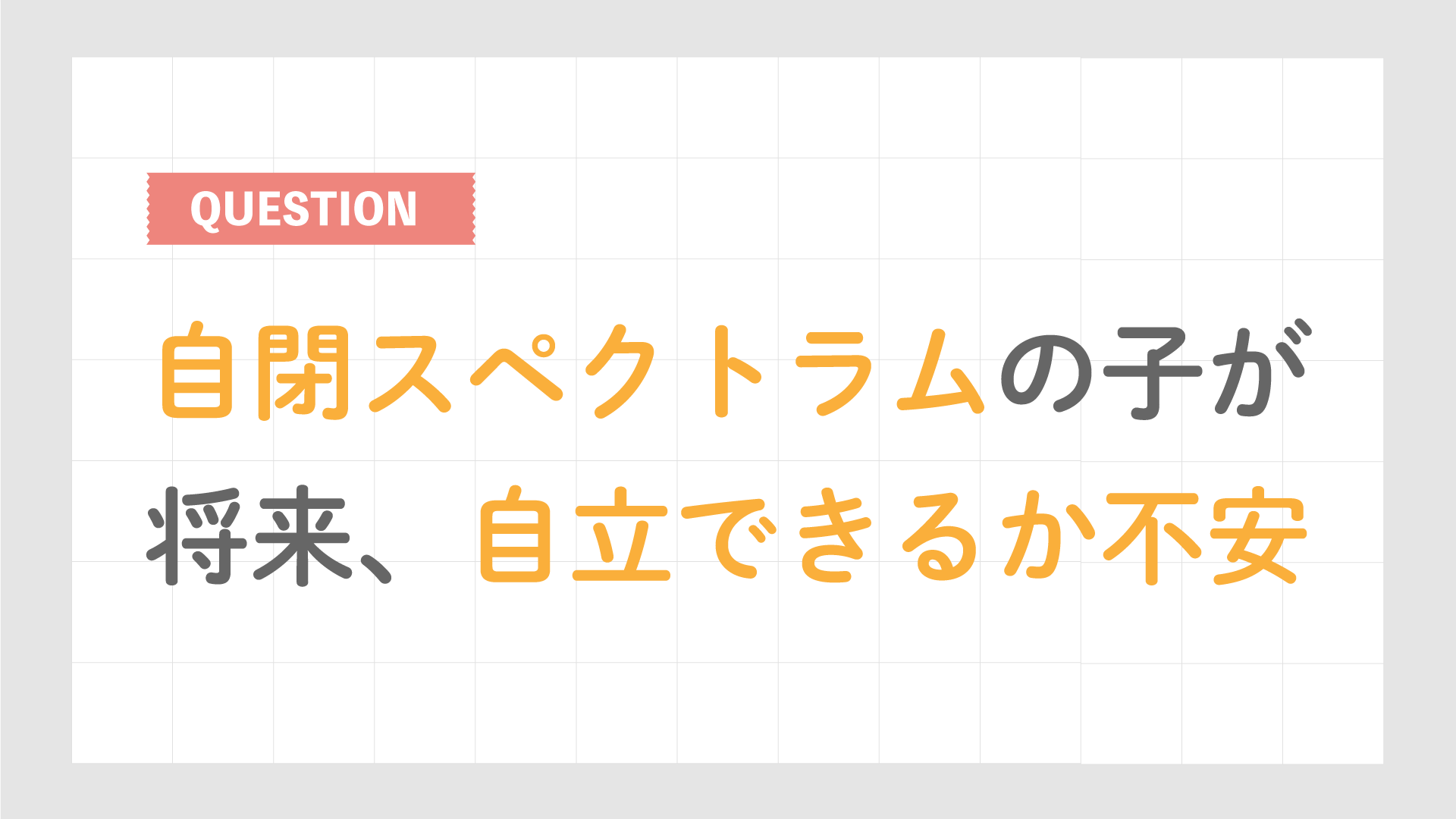診断がつかない「発達グレーゾーン」とは?富山の指導員が教える困難さの正体と“強みを伸ばす”支援のコツ
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「発達障害の“グレーゾーン”の理解と支援」についてです。
「うちの子、診断名はつかないけど、集団生活でなんだか苦しそう」「周りの子と比べて少しゆっくりで、本人が自信をなくしていないか心配」…そんな風に、“診断”と“定型発達”の狭間で悩んでいませんか?
「グレーゾーン」とは何か?(診断と“狭間”の正体)
皆さんは「グレーゾーン」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
これは、発達障害の正式な診断基準には満たないんだけれども、日常生活で「困難を抱えている状態」のことを指します。
発達障害の特性は「グラデーション」になっている、とよく言われます。
真っ白な「定型発達」の状態と、真っ黒な「発達障害の診断基準を満たす」状態があったとして、グレーゾーンはその「中間」に位置する存在です。

ゆう先生の補足解説:定型発達(ていけいはったつ)とは?
「定型発達」とは、発達障害の特性(ASDやADHDなど)とは対照的に、多くの人がたどる典型的な発達のパターンのことを指します。
先ほどのグラデーションの例でいうところの「白」の部分ですね。
「普通」や「異常」といった価値観を含む言葉ではなく、あくまで特性を分類する上での専門用語の一つです。
全く何もできないわけじゃない。でも、時々「あれ?」と思うことがある。
これがグレーゾーンの難しいところで、周りから見た時に、その「できなさ」が「まだ子供だからできていないのか」「発達のデコボコ(特性)だからできていないのか」の判断が非常に分かりづらいんですよね。
グレーゾーンが抱える「社会的な問題点」
この「分かりづらさ」が、グレーゾーンのお子さんたちを苦しめる社会的な問題につながっていきます。
診断名がないゆえに支援に結びつかない
グレーゾーンは、医学的な「診断名」ではありません。だからこそ、一番の問題は「診断名がないことで、適切なサポートを受けられない」という点にあります。
診断がつくお子さんより、特性としては軽いのかもしれません。
でも、不注意だったり、感覚過敏があったり、対人関係の難しさがあったり、本人の努力だけではどうにもならない困難を抱えている。
それにもかかわらず、「問題ない」「甘えているだけ」「もうちょっと頑張ればできるはず」と周りから誤解されてしまう。
特に親御さんや先生も、「もうちょっとやらせればできるんじゃないか」と期待をかけてしまいがちです。
本人は頑張っているのに結果が出ない。周りと自分を比べて、どんどん苦しくなってしまう…ということが起こりがちなんです。
公的支援(療育)が受けられない現実
そして、もう一つの大きな問題が、公的な支援を受けられないリスクです。
例えば、僕が働いているような「児童発達支援施設」や「放課後等デイサービス」といった療育(発達支援)のサービスは、多くの場合、自治体が発行する「通所受給者証」というものが必要になります。

ゆう先生の補足解説:通所受給者証(つうしょじゅきゅうしゃしょう)とは?
簡単に言うと、児童発達支援や放課後等デイサービスといった、児童福祉法に基づく福祉サービス(療育)を利用するために必要な「許可証」のようなものです。
これを取得するためには、基本的にはお医者さんによる「診断書」や「意見書」が必要になります。
つまり、「診断名がつかない」グレーゾーンのお子さんは、この公的な療育サービスを利用したくても、制度上利用できないという「壁」にぶつかってしまうことが多いんです。
その結果、本人に合った個別の支援を受けられないまま時間が過ぎてしまい、ストレスがどんどん溜まって、最終的に「うつ」や「不登校」といった二次障害につながってしまう可能性が、グレーゾーンのお子さんたちには潜んでいます。
グレーゾーンの子どもが抱える具体的な「困難さ」
グレーゾーンのお子さんが抱える困難さは、学業、仕事、対人関係、日常生活など、様々な場面で生じます。
例えば、学校生活。
- 集中力が続かないんだけど、授業中に立ち歩くなどの大きな問題は起こさないから、先生からは見過ごされてしまう。
- 読み書きが困難なんだけど、全くできないわけじゃないから、ギリギリのところで何とかついていけてしまう。
大人になってからも、
- タスク管理や「報・連・相」がなぜか毎回うまくできない。
- でも、挨拶はしっかりできるし、受け答えも一見普通にできるから、「仕事ができない人」と評価されてしまう。
対人関係でも、
- 発言がちょっとピントがずれている。
- でも、人柄は良いから、なんとなく許されてしまう。
こういう「ちょっとしたズレ」が、1回きりならいいんです。でも、何度も何度も続くと、周りからの誤解を招き、本人は孤立していってしまいます。
多くの困難の背景にある「実行機能」の弱さ
こうした困難さの背景には、発達障害の特性とも共通する「実行機能(じっこうきのう)の弱さ」があると言われています。

ゆう先生の補足解説:実行機能(じっこうきのう)とは?
「実行機能」とは、目標を達成するために自分自身を管理・調整する、脳の「司令塔」のような力です。
例えば、
- 計画を立てる(作業を順序立てる)
- スケジュールを管理する
- 優先順位をつける
- 衝動をコントロールする
といった、社会生活を送る上で非常に重要な能力を指します。発達に特性がある方は、この実行機能がアンバランスなことが多いと言われています。
この実行機能が弱いと、具体的には「遅刻が増える」「忘れ物が極端に多い」「イレギュラーな事態(環境の変化)にパニックになりやすい」といった形で現れます。
もちろん、誰にでもこういうことはありますよね。
でも、定型発達の場合、失敗から学んで「次からはこうしよう」と対策を立てて修正していくことができます。
一方で、発達障害の特性があると、どれだけ対策をしても、脳の特性として同じ失敗を繰り返してしまうことがあります。
グレーゾーンは、まさにこの「中間」です。できるようになったこともあるけど、どうしてもできないこともある。
解決までのスピードがすごくゆっくりだったりする。だからこそ、周りも本人も「頑張ればできるはず」と「できなくて辛い」の間で揺れ動いてしまうんですよね。
心理的影響:なぜ自己否定感がたまりやすいのか
グレーゾーンのお子さんたちは、「診断がつく子」よりも、もしかしたら心理的に不安定になりやすい側面があると僕は感じています。
診断がつけば、「これは自分の特性だから仕方ない」とある意味で区切りをつけられますが、グレーゾーンは「できるはずなのに、できない自分」と向き合い続けることになります。
どうしても周りと比べてしまい、「なんで自分はダメなんだろう」と自己否定感がどんどん溜まっていきやすい。
その結果、不安感が強くなったり、気分が落ち込んだり、不登校になったり…と、心が不安定になってしまうお子さんが本当に多いんです。
僕の考え:迷ったら「支援を受ける」勇気
「支援が必要」とも言えるし、「支援は不要」とも言える。それがグレーゾーンです。
じゃあ、どうすればいいのか。
僕個人の意見としては、「正直、迷ったら支援は受けた方がいいです」とお伝えしたいです。
なぜなら、療育施設で多くのお子さんを見てきた経験上、支援の開始時期が遅れれば遅れるほど、問題が「こじれちゃって」いるケースが本当に多いからです。
逆に、受けてみて「あ、もう必要ないね」となってやめていくのは、すごく良いことですよね。
特に幼少期は、脳が柔軟で、いろんなことを吸収しやすい時期です。この時期に適切な関わり方を学ぶことは、その後の人生にとって大きな財産になります。
支援を受けることの「壁」(スティグマ)
ただ、僕が「絶対に受けた方がいい」と強く押せない理由も、もちろんあります。
それは、支援を受けること(例えば、支援学級に行くこと)で、周りのお友達から「あいつはあっちのクラスだ」というような偏見(スティグマ)にさらされる可能性がゼロではないからです。
これは本当に難しい問題で、その地域の環境や人間関係にもよるので、一概には言えません。
でも、僕が思うのは、小中学校の環境は変えられなくても、高校、大学、社会人と、大人になれば自分で環境を選ぶことができます。
その時に大事になるのは、「自分の得意なことは何か」「苦手なことは何か」「苦手なことをどうサポートすればいいか」というスキルを、本人が身につけているかどうかです。
そのスキルを身につけるためにも、僕は可能な限り、早期に支援の視点を取り入れることをお勧めしたいと思っています。
家庭でできる支援の基本(心の持ち方)
では、ご家庭ではどのようなことを意識すればいいのでしょうか。具体的なテクニックというよりは、「心の持ち方」として大事なことをお伝えします。
1. 最重要:本人の「強み」に目を向ける
グレーゾーンであってもなくても、支援の基本はこれに尽きます。
「苦手な部分をどうにかしよう」とすること以上に、「本人の強い部分(強み)は何か」に目を向けて、そこを伸ばす関わり方をしてほしいんです。
- 人と関わるのは苦手かもしれない。でも、一人で絵を描かせたらすごく上手かもしれない。
- 話すのは苦手かもしれない。でも、文章で書くのは得意かもしれない。
もしそうなら、まずはその「得意なこと」を思いっきりやらせてあげて、自信をつけてあげること。それが本人の土台になります。
2. 弱い部分は「環境」でカバーする
じゃあ、弱い部分は放置するのかというと、そうではありません。
弱い部分は、本人に「頑張れ!」と押し付けるのではなく、「環境の工夫」でカバーしてあげるんです。
- 忘れ物が多いなら、視覚提示(見える化)でチェックリストを作る。
- スケジュールが分からないと不安になるなら、予定を事前に伝えておく。
- 集中できないなら、無駄なものが目に入らないように環境を整える。
こうして「スムーズに行動できる」という経験を積むと、本人も安心しますし、親御さんに褒められることで「自分は大丈夫なんだ」という自信がついてきます。
3. 自己肯定感を育む「褒め方」のコツ
グレーゾーンのお子さんは、自己肯定感が下がりやすい傾向があります。だからこそ、意識的に「褒める」ことが大切です。
ここでのコツは、「結果」ではなく「努力の過程」を褒めること。
「100点を取ったね、すごい!」(結果)ではなく、
「昨日もプリント頑張ってたけど、今日も机に向かってるね、すごい!」(過程)
という感じです。
「自分は進んでいるんだ」「頑張りを見てもらえているんだ」という**「進んでる感」**が、安心感や自己肯定感につながっていきます。
4. SOSを伝える力と、親の相談先
「困った時は助けてって言っていいんだよ」と、日頃から伝えてあげてください。そして、お子さんが勇気を出してSOSを出してきた時は、すぐに対応してあげる。この経験が「いざという時に頼れる」という安心感を育てます。
同時にお父さんお母さん自身も、一人で抱え込まないでください。支援センターに相談するだけでもいいですし、インターネット上の家族会などで仲間を見つけるのも、とても大事なことです。
5. 「頑張ればできる」を押し付けないで
最後に、お父さんお母さんに強くお伝えしたいことがあります。
発達障害やグレーゾーンは、脳機能の特性によるものです。努力や頑張りだけでは解決できない部分が、必ずあります。
親御さん自身の「昔は頑張ったらできた」という経験を押し付けてしまうと、それはお子さんへの「無理解」となり、お子さんを追い詰めて、二次障害を引き起こす原因になってしまいます。
まずは「この子には、頑張りだけではどうにもならない特性があるのかもしれない」と受け止めた上で、本人の状況を把握し、得意なこと、苦手なことを見極めて、この子に合った環境を整えてあげる。
その視点を持っていただくことが、まず何よりの支援になるんだと僕は思います。
まとめ
今日の記事では、「発達グレーゾーン」の理解と支援についてお話ししました。
- グレーゾーンとは、診断と定型発達の「狭間」であり、診断名がないゆえに「甘え」と誤解され、公的な支援を受けにくいという社会的な問題を抱えています。
- 学業や対人関係、実行機能の弱さといった困難が、本人の自己否定感につながり、二次障害(うつや不登校)を引き起こすリスクがあります。
- 支援の基本は、本人の「苦手」を無理に直そうとせず、「環境調整」でカバーすること。そして何よりも、本人の「強み」を見つけて伸ばし、小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を育むことです。
結論:読者へのメッセージ
焦らなくて大丈夫です。
障害があるとかないとか、そういうことではなく、まずはお子さん一人ひとりに合った支援方法を見つけてあげること。
「できること」を見つけて、そこをしっかり伸ばしてあげること。
そこから、できることを一歩ずつ進めていってほしいなと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの**「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」**ことに繋gれば、僕もとても嬉しいです。