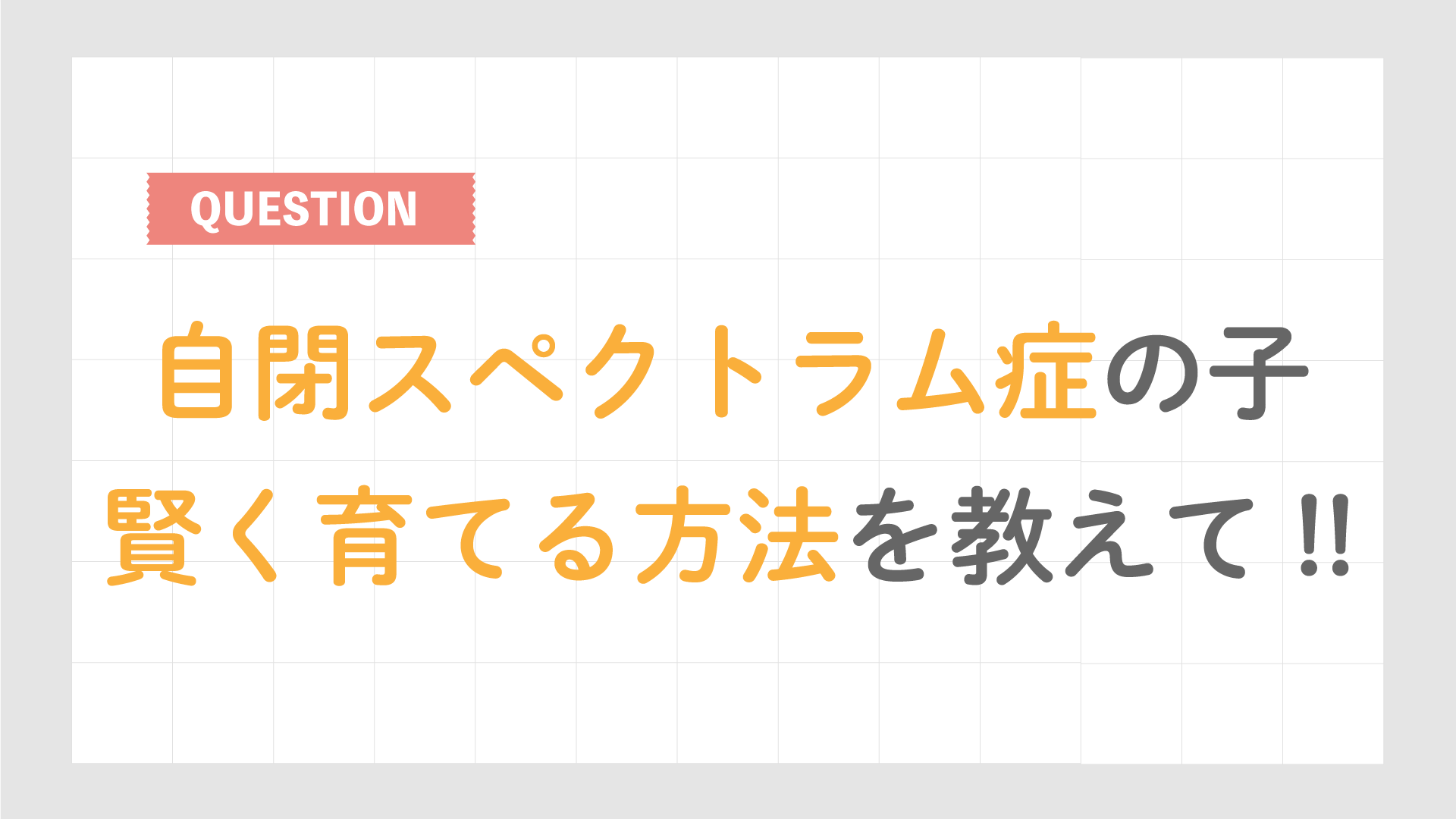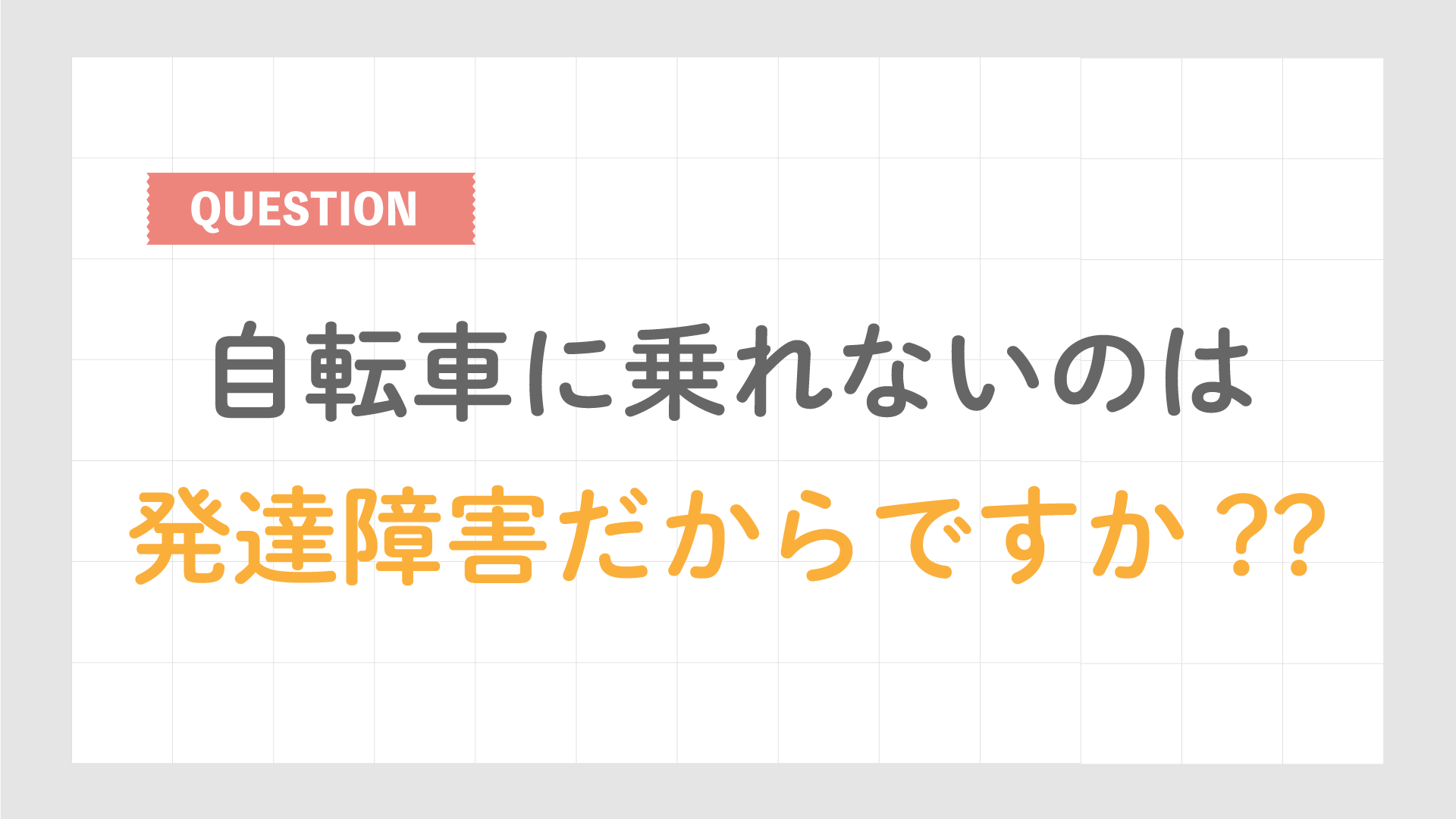発達障害の子育てが楽になる「ちょっとした工夫」|富山の指導員が教える日常生活5つの場面別支援
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「家庭でできる、発達障害のあるお子さんへの支援の“ちょっとした工夫”」についてです。
なぜ「小さな工夫」が大切なのか?
今回の記事は、僕がこれまで発信してきた発達障害に関する動画シリーズ(全10本)のまとめ的な内容にもなっています。
特別なことではなく、誰でも家庭でできる「小さな工夫」。これが意外と馬鹿にならなくて、生活全体を大きく変えるきっかけになることもあるんですよね。
小さな変化を積み重ねていくことで、いつか安定につながっていきます。
発達障害の診断があるお子さんだけでなく、グレーゾーンや「ちょっと気になるな」というお子さんにも当てはまる部分が多いと思いますので、ぜひ取り入れてみてください。
大原則:「見通し」が情緒の安定と自信を育む
僕がこのシリーズを通してずっとお伝えしてきたことですが、支援の大原則は「見通しのある生活環境が、情緒の安定と自信を育む」ということです。
「次に何をすればいいか分からない」という状態は、大人でも不安ですよね。発達にでこぼこがあるお子さんたちは、この不安を特に強く感じやすい場合があります。
だからこそ、「視覚提示(目で見て分かる手がかり)」を使ったり、「ルールをあらかじめ決めておいたり」、「環境を整えたり」することが、まず大前提としてすごく大事になってくるんです。

ゆう先生の補足解説:なぜ「見通し」がそんなに大事?
「見通しが立つ」とは、「これから何が起こるか」「自分は何をすればいいか」が予測できる状態のことです。
特に自閉スペクトラム症(ASD)の特性があるお子さんは、変化や予測できないことがとても苦手な場合があります。
見通しが立たないと強い不安を感じ、パニックになったり、逆にフリーズして動けなくなったりすることがあるんですよね。
逆に言えば、「次はこれ」「その次はこれ」と分かっているだけで、安心して行動に移しやすくなります。
この「自分で分かって行動できた!」という経験の積み重ねが、「自信」に直結していくんです。
場面別:家庭でできる「ちょっとした工夫」5選
では、具体的に日常生活の場面ごとに、どんな工夫ができるかを見ていきましょう。
1. 朝の支度をスムーズにする工夫
朝は時間との戦いですよね。「自分で着替えができない」「途中で遊びだす」「持ち物を忘れる」など、悩みは尽きないと思います。
工夫①:視覚的な手順書(お支度ボード)
特に小さいお子さんや、自閉傾向が強いお子さんには、視覚的な指示が有効です。
「朝にやること」を写真やイラストにして、順番に貼っておくだけでも違います。「1. トイレ」「2. 顔を洗う」「3. 服を着る」…といった感じです。
終わったらシールを貼ったり、カードを裏返したりするルールにすると、達成感にもつながります。
洋服の着替えも、お子さんの服を写真に撮って「①下着」「②ズボン」「③シャツ」のように順番に貼っておくと、一人で着替えやすくなるかもしれません。
工夫②:具体的で「短い」声かけ
朝は忙しくて、つい「あれやって、これやって、それも!」と一度にたくさんの指示(これを「多重指示」と言います)をしてしまいがちです。でも、お子さんは処理しきれずに混乱してしまいます。
声かけのコツは「1回につき1つの指示」です。
「まず、シャツに頭を通してね」…(できたら)…「次に、手を出そうね」という感じです。
動作を細分化(小さく分けること)して、一つずつ伝えていくんですよね。これを繰り返すうちに、一連の動作として覚えていきます。
工夫③:環境を整える
お子さんがやるべきことに集中できるよう、環境を整えることも大切です。
- 着替える場所を決める:テレビやおもちゃが目に入らない場所にする。
- 前日の夜に準備しておく:翌日着る服をセットしておく。
- 究極の工夫:どうしても着替えに時間がかかる場合、本人も嫌でなければ、次の日に着ていく服(肌触りの良いものなど)を着て寝る、というのもアリだと僕は思います。
その場所で何をすべきかが明確になっている環境が理想ですね。
工夫④:感覚への配慮
特定の服しか着たがらない場合、もしかしたら「感覚過敏」が影響しているかもしれません。
感覚過敏とは、五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)から入ってくる刺激を、他の人よりも非常に強く、時には苦痛に感じてしまう特性のことです。
服の例でいうと、「チクチクするタグが背中に当たるのが耐えられない」「特定の生地のごわごわした感じが気持ち悪い」といったことがあります。
これは「わがまま」ではなく、本人にとっては本当に不快な刺激なんです。
肌触りのいい素材を選んだり、服のタグは最初に全部切っておいたりするだけでも、着替えのハードルが下がることがあります。
工夫⑤:持ち物チェックリスト
忘れ物が多い場合は、玄関など目につく場所に「持ち物チェックリスト」を貼っておきましょう。
「リュック」「ぼうし」「すいとう」など、写真や絵と一緒にリスト化しておくと、お子さん自身でチェックする習慣がつきやすくなります。
2. 食事の場面を楽しくする工夫
「決まったものしか食べない(偏食)」「食事中に席を立ってしまう(多動)」といったご相談も非常に多いです。
工夫①:無理に食べさせない(食事は楽しく)
まず大前提として、食事は一生続くものです。ここで嫌な経験をして「食事=嫌悪感」となってしまうのが一番避けたいところです。
食べられなくても「それでいいんだよ」というメッセージを送りつつ、食事の時間は楽しいもの、という印象を持たせることが大事だと僕は思います。
ただ、一方で栄養バランスも気になりますよね。特に自閉症のお子さんは腸内環境が荒れていることが多い、という研究も(まだ途上ですが)言われています。
無理には食べさせませんが、例えば苦手な野菜は細かく刻んで好きなメニューに混ぜ込むなど、1週間単位でバランスが取れるような工夫は必要かもしれません。
工夫②:食べやすい工夫(見た目や形状)
偏食の背景には、味覚だけでなく、見た目や食感へのこだわり、感覚過敏が隠れていることも多いです。
- 苦手な食材は、細かく刻んでハンバーグやカレーに混ぜ込む。
- 好きなキャラクターの型抜きを使ったり、お皿を使ったりする。(これで食べられるようになる子、結構います!)
- 新しい食材は、まず「ほんのちょっと」から試してみる。
焦らず、できることからやっていきましょう。
工夫③:落ち着ける環境(食事に集中)
食事中に席を立ってしまう場合は、環境を見直してみましょう。
- 食事中はテレビを消す。
- おもちゃは片付ける。
「食事の時間は、食事に集中する」という環境を作ることが大切です。
また、「毎日だいたい同じ時間に食べる」「食べ終わらなくても〇時になったらおしまい」というように、生活リズムと終わり(見通し)を決めておくことも有効です。
3. 宿題への工夫
小学生になると「宿題」という新たなハードルが出てきます。「集中できない」「ケアレスミスが多い」「何から手をつけていいか分からず泣き出す」など、色々あると思います。
工夫①:環境設定(宿題スペースの確保)
まずは環境です。ゲーム、テレビ、漫画などが目に入るところでは、大人でも集中できませんよね。
- 宿題をする場所を決める。(リビングの一角でもOK)
- その場所からは、誘惑になるもの(好きなもの)が見えないようにする。
- 机の上は、今やるもの(鉛筆、消しゴム、ドリル)だけにする。
物がごちゃごちゃしていると、それだけで視覚的な情報が多くて疲れてしまう子もいます。
工夫②:スモールステップ(課題を小分けに)
宿題の量を見て「うわっ、無理…」とフリーズしてしまう子も多いです。

ゆう先生の補足解説:スモールステップ
「スモールステップ」とは、療育や教育の現場でよく使われる言葉で、目標を達成するために、課題を非常に小さく簡単なステップに分解していく手法です。
小さな「できた!」を積み重ねることで、達成感を得やすくなり、やる気や自己肯定感につながります。
いきなり「宿題全部やって!」ではなく、「まず計算ドリルだけやろう」「計算ドリルも、まず10問だけやってみよう」という風に、課題を小分けにしていくことが大事です。
工夫③:時間の管理(タイマーの活用)
発達にでこぼこがあるお子さんは、時間感覚が曖昧なことが多いんですよね。嫌なことはものすごく長く感じ、好きなことはあっという間に感じます。
そこで役立つのが「タイマー」です。
「15分だけ集中してやろう。ピピッと鳴ったら5分休憩ね」という風に、終わり(見通し)を明確にしてあげると、取り組みやすくなります。
この時、デジタル数字のタイマーよりも、残り時間が見て分かりやすい(アナログ時計のように、赤い部分が減っていくような)タイマーの方が、お子さんには分かりやすいのでおすすめです。
4. 片付け・整理整頓の工夫
「使ったものを元に戻せない」「部屋が散らかっている」というのも、よくある悩みです。
工夫①:低位置管理(すべての物に住所を決める)
これが一番大事です。「低位置管理」=すべての物に「住所」を決めることです。
「このおもちゃは、このカゴ」「絵本は、この棚」というように、どこに何を戻すのかを決めます。
そして、その場所に写真やイラスト、文字で「ラベル」を貼っておくんです。
「例外なく、必ずそこに戻す」というルールを徹底することで、少しずつ習慣になっていきます。
工夫②:視覚的な手がかり(色分けなど)
ラベルだけでなく、「おもちゃは赤いカゴ」「服は青いカゴ」のように、色で分けるのも分かりやすい方法です。
ただし、視覚過敏があるお子さんの場合、色が多すぎると逆に疲れてしまうこともあるので、その場合は印だけにするなど、お子さんの特性に合わせてみてください。
工夫③:手順の見える化
「片付けなさい!」と言われても、何からどうすればいいか分からない子もいます。
その場合は、「片付けの手順書」を作ってあげましょう。
- 床のおもちゃを拾う
- おもちゃ箱に入れる
- 本を本棚に戻す
というように、写真付きで貼っておくと、それを見ながら自分でできるようになるかもしれません。
5. 就寝準備をスムーズにする工夫
「寝つきが悪い」「寝る時間になっても遊びたがる」など、睡眠の問題も多いです。
僕は、食事と同じくらい、いやそれ以上に「睡眠」は大事だと思っています。睡眠不足は、多動傾向や不注意をより強くしてしまう可能性があるんですよね。
工夫①:寝室の環境(暗く・静かに・快適に)
まずは寝る環境です。
- 寝室は暗く、静かにする。(遮光カーテンがおすすめ)
- 快適な温度、湿度を保つ。(毎日同じ環境だと寝やすくなります)
また、寝る時間に向けて、徐々に部屋の明かりを暗くしていく(例:8時以降はダウンライトだけにする)など、日中の活動モードから睡眠モードへ切り替える工夫も有効です。
工夫②:リラックスできる時間(入眠儀式)
寝る1〜2時間前になったら、脳が興奮するような活動は避けたいところです。
- テレビ、ゲーム、スマホ、タブレットなどの強い光の刺激は避ける。
- 絵本を読んだり、静かな音楽を聴いたりする。
こうした「これをしたら寝る」という決まった流れ(入眠儀式)を作ることで、体が自然と睡眠モードに入りやすくなります。
多動傾向がある子に「寝なさい!」と強く言うと、その声かけ自体が刺激になってしまうこともあるので、徐々に静かな環境にしていくのがポイントです。
工夫③:安心できるアイテム
お気に入りのぬいぐるみやタオルケットなど、「これがあると安心する」というアイテムと一緒に寝るのも、安心して眠りにつく助けになることがあります。
【6】まとめ
今回の記事では、発達障害のあるお子さんの子育てについて、家庭でできる「ちょっとした工夫」を5つの場面に分けてご紹介しました。
- 全ての工夫の根底にあるのは、「見通しを立てる」ことです。これが不安を減らし、情緒の安定と自信につながります。
- 具体的な方法として、「視覚的な手がかり(写真やリスト)」を使い、「環境を整える」ことが非常に有効です。
- 「朝の支度」「食事」「宿題」「片付け」「就寝」という日常の場面こそ、小さな工夫を試すチャンスです。
- 大切なのは、できることから少しずつ試してみることです。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。