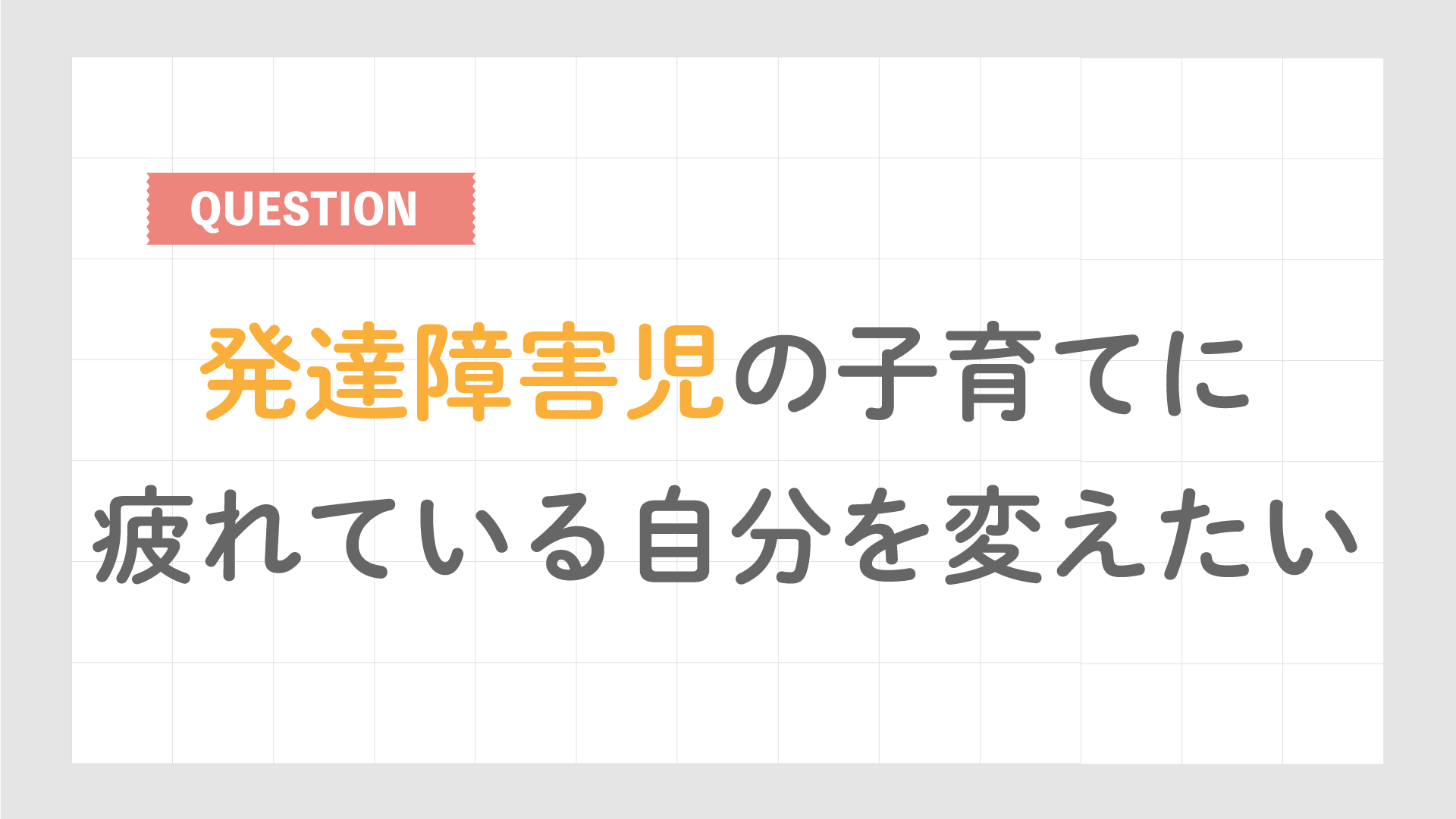ASDの子どもの「笑顔」を引き出す声かけ術|現役指導員が教える具体的な言葉選びのコツ
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの笑顔を引き出すための『声かけ』の完全ガイド」についてです。
「ちゃんとして!」「早くして!」とつい抽象的な言葉で叱ってしまい、後で自己嫌悪に陥っていませんか?
「どうしてこの子には、こちらの意図が伝わらないんだろう…」
「褒めているつもりなのに、なんだか響いていない気がする…」
そんな風に、お子さんとのコミュニケーションに悩んだことはありませんか?
ASDのお子さんとのコミュニケーションには、確かにちょっとした「コツ」があります。
今日は、僕が現場で大切にしている声かけの基礎を学び、お子さんの安心と笑顔につながるヒントを一緒に見つけていきましょう。
ASDの子どもとの声かけ:なぜ「コツ」が必要なのか?
まず大前提として、ASDと一口に言っても、特性の現れ方は本当に人それぞれです。
知的障害を伴うタイプのお子さんもいれば、言葉は流暢だけれど強いこだわりがあるアスペルガー症候群のタイプのお子さんもいます。
なので、今日の話がすべてのお子さんに当てはまるわけではないかもしれませんが、僕が日々の療育の中で「これは基礎として大切だな」と感じていることをお話ししますね。
曖昧な言葉が「不安」や「ストレス」の原因に
ASDのお子さんと接する上で一番大事なのは、「ふわっと言わない」ことです。
ASDのお子さんたちの特徴として、文脈や言葉の裏の意味、その場の雰囲気といった「暗黙の事柄」を推測するのが難しい、という点があります。
僕たちが日常で何気なく使っている「非言語的な合図」(表情や声色)や、「ちゃんとしてね」といった抽象的な声かけは、
彼らにとって「何をすればいいか分からない」という不安や混乱の原因になってしまうんです。
特に、「言葉を文字通りに受け取る」傾向が強いため、以下のような言葉は要注意です。
- 「ちょっと待ってて」→「『ちょっと』って、どれくらい?」と混乱してしまいます。具体的な行動の指針になりません。
- 「適当にやっといて」→「『適当』の意味が分からない…」となってしまいます。
どう行動していいか分からない状態は、大人でもストレスですよね。
だからこそ、「あと1回ね」「あと5分でおしまいだよ」というように、数字や時間、具体的な行動を伝えてあげる工夫が大切になってきます。
感情の理解と「二重共感の問題」
もう一つ、ASDのお子さんは「自分の気持ち」を理解するのにも時間がかかることがあります。
今、自分が感じているのが「悲しい」のか「怒っている」のか、その区別がつかず、心の中がごちゃごちゃになって無表情になったり、ちぐはぐな反応になったりすることがあります。
自分の心を正確に捉えられないからこそ、人の顔色や気持ちを読むことも苦手なんですよね。
ここで「二重共感の問題」という、とても大事な考え方が出てきます。

ゆう先生の補足解説:二重共感の問題(Double Empathy Problem)
これは、「ASDの人は共感性が低い」という一方的な見方ではなく、「ASDの人」と「定型発達の人」との間で、お互いの感じ方や表現方法が違うために、お互いに共感し合うのが難しくなっているという考え方です。
親御さんが「あの子の考えていることが分からない」と感じている時、実はASDのお子さんも「お父さん・お母さんが言っていること(暗黙のルール)が分からない」と感じています。
これは「認識のギャップ」であって、どちらかが一方的に悪いわけではないんです。
だからこそ、私たち(大人側)が、彼らに伝わりやすい「配慮のある声のかけ方」を学んで、そのギャップを埋めていく必要があるんですよね。
子どもの笑顔を引き出す「声かけ」7つの技術
では、ここからは具体的に「どんな声かけが良いのか」という技術的なお話をしていきます。
1. 基本のキ:「具体的」かつ「肯定的」な言葉選び
これが基本中の基本です。もちろん、本当に危ない時(災害時など)は「ダメ!」と強く言うことも必要です。
でも、日常生活の中では、極力「〇〇しないで」(否定形)よりも「〇〇しようね」(肯定形)という言葉を選ぶようにしてみてください。
つい「急いで!」と言ってしまう場面では、「あと5分で出かけるよ」と伝えたり、環境設定(タイマーを見せるなど)を工夫したりする方が、長期的には本人の自発的な行動につながります。
否定形で強く言わないと動かない、という状況になっている場合、それはお子さんが小さい頃だから通用していただけで、成長と共に反抗につながる可能性もあります。
さらに、具体性を高めるために「動作」と「目的語」を明確にすることをお勧めします。
(例)
- 「ご飯を食べ終わったら、食器を(目的語) 片付けてね(動作)」
- 「幼稚園に行くから、準備を(目的語) しようね(動作)」
このように具体的に伝えることが、混乱を防ぐ第一歩です。
2. 声のトーン:「穏やかな声」で安心感を届ける
「何を言うか」と同じくらい、「どう言うか」も大事です。
特にASDのお子さんに何かをしっかり伝えたい時は、「①静かな音量」「②ゆったりした速度」「③落ち着いた表情」の3つを意識してみてください。
ASDのお子さんの中には、「聴覚過敏」といって、特定の音(大きな声、甲高い音、機械音など)を非常に不快に感じたり、痛みとして感じたりする特性を持つ子がいます。
大人がイライラして大きな声で指示を出すと、その「音」自体が刺激になってしまい、伝えたい「言葉のメッセージ」が頭に入ってこなくなってしまいます。
穏やかで落ち着いたトーンで話すことは、こうした過敏な感覚系を刺激せず、お子さんが余裕を持って言葉を処理できる「安心」を届けることにつながるんです。
もちろん、楽しい時は一緒に楽しい声を出していいんですよ!この「コントラスト(使い分け)」を大人が見せることで、お子さんも感情表現を学んでいきます。
3. 視覚支援:言葉と「見る情報」をセットにする
言葉だけで伝えても、なかなか理解してもらえないな…と感じることはありませんか?
ASDのお子さんは、耳から入る情報(聴覚情報)を頭の中で処理するのが苦手な傾向がある、と僕は感じています。
そこで、言葉かけと同時に、絵カードやイラスト、写真といった「目に見える情報」を一緒に提示してあげてください。
「今言ってるのは、このことだよ」と視覚的に示すだけで、理解度が格段に上がることがよくあります。
4. 興味の活用:「好き」を会話の懸け橋にする
ASDのお子さんの素敵なところは、一度好きになったものを長く、深く好きでいてくれることです。
この「好き」という気持ちは、コミュニケーションの最強の武器になります。
電車、恐竜、アニメのキャラクター…なんでも構いません。会話の導入や、ちょっと頑張ってほしい作業の前に、本人の好きなテーマを少し入れてあげるんです。
「あ、この人は僕の好きなことを分かってくれてる」
この安心感が、話を聞くモチベーションや信頼関係の土台になります。
5. 褒め方①:「行動」を具体的に褒める
お子さんを褒める時、つい「すごいね!」「えらいね!」「かっこいい!」といった抽象的な言葉を使ってしまいがちです。
でも、これだと「何が」すごいのかが伝わりにくいんです。
褒める時こそ、具体的にいきましょう。
(NG例)「(ブロックを片付けた子に)えらいね!」
(OK例)「ブロックを全部、箱に入れられたね。えらいね!」
「どの行動が」良かったのかを具体的に言葉にすることで、お子さんは「この行動をすればいいんだ」と理解できます。
女性が褒められる時に「可愛いね」だけ言われるより、「そのショートカット、すごく似合ってますね」と具体的に言われた方が伝わりやすいのと似ていますね(笑)。
6. 褒め方②:「結果」よりも「プロセス(過程)」を褒める
これはものすごく大事なポイントです。
発達にでこぼこがあると、どうしても結果だけ見ると「失敗」になってしまうことも多いと思います。
でも、褒めるべきは結果(100点取れた、とか)だけじゃありません。そこに至る「家庭(プロセス)」や「努力」こそを褒めてあげてください。
「難しいパズル、最後まで諦めないで頑張ったね」
「宿題、毎日コツコツ続けててすごいね」
結果ではなく、その行動や「やろうとした心意気」を褒められる経験が、「次も頑張ろう」という挑戦意欲につながります。

ゆう先生の補足解説:自己効力感(じここうりょくかん)
「プロセスを褒める」ことは、「自己効力感」を育てることにつながります。
「自己効力感」とは、「自分ならできるかもしれない」「自分にはこの困難を乗り越える力がある」と自分を信じる力のことです。
「自己肯定感(ありのままの自分を認める力)」と少し似ていますが、こちらは「行動」に対する自信です。
結果がダメでも、プロセス(努力)を褒められることで、「頑張ること自体には価値があるんだ」と学びます。
これが、失敗を恐れずに挑戦できる「心のしなやかさ(レジリエンス)」を育てるんですよ。
7. 感情のラベリング:「悲しいね」と気持ちを代弁する
これが、すべての声かけのスタートラインかもしれません。
先ほどお話ししたように、ASDのお子さんは自分の感情をうまく言葉にできません。
だから、大人がそれを「代弁」してあげるんです。
- (転んで泣いている子に)「痛かったね、びっくりしたね」
- (おもちゃが取られて怒っている子に)「あれで遊びたかったんだよね。取られて悲しかったね」
- (ジャンプして喜んでいる子に)「わあ、楽しいね!嬉しいね!」
こうして感情に「ラベル」を貼ってあげることで、お子さんは初めて自分の心の中にあるモヤモヤした感覚と「言葉」を結びつけることができます。
この「共感」こそが、お子さんの心の扉を開く鍵です。心が安心している状態で、具体的な指示(技術①)や褒め言葉(技術⑤)を伝えるからこそ、言葉がスッと心に刺さるんですよね。
【実践ワーク】抽象的な言葉を「伝わる言葉」に言い換えよう
最後に、僕たちが日常でつい使ってしまいがちな「抽象的な声かけ」を、「伝わる具体的な声かけ」に言い換える練習をしてみましょう。
×「ちゃんと座って!」
○「椅子に座って、足は床につけようね」
(「ちゃんと」が何を指すのか、具体的な行動で示します)
×「早くして!」
○「(時計を見せながら)あと5分で(長い針が6になったら)おしまいだよ」
○「(写真カードを見せながら)次は、お着替えするよ」
(時間や次の行動を、視覚的に具体的に伝えます)
×「すごいね!」「えらいね!」
○「おもちゃを全部、箱に入れられたね。すごい!」
(まず具体的な行動を描写してから、褒め言葉を付け加えます)
×「(ぼーっとしている子に)話聞いてるの?」
○「〇〇くん(まず名前を呼ぶ)。(肩を優しく叩く)この絵を見て。今はおやつの時間だよ」
(まず注意を引くための声かけ(準備)をしてから、具体的な情報を伝えます)
×「(触ってほしくない物を触りそうな時に)触らないで!」
○「あ!(まず注意を引く)それは壊れやすいから、お目々で見ようね」
(否定せず、してほしい行動「目で見る」に置き換えます)
×「もういい加減にして!」
○「(まず共感から)イライラするね。一旦あっちで休もうか」
(お子さんもパニックになっている可能性が高いです。まず感情に共感し、クールダウンする場所へ誘導します)
×「なんでできないの!」
○「(まず共感から)難しいね。どこが分からないか、一緒に見てみようか」
(「なんで」という詰問は不安を強めます。共感し、問題点を具体的に探す姿勢を見せます)
×「(遊びを)やめなさい!」
○「あと10分で終わりだよ。その次は(大好きな)〇〇しようね」
(「やめなさい」は最終手段。まずは見通しと、次の楽しみを具体的に伝えます)
×「みんなやってるでしょ!」
○「〇〇ちゃんは、まずこれからやってみようか」
(「みんな」という抽象的な集団ではなく、「あなた」が「何を」すべきか、個別具体的に伝えます)
まとめ
今日の話を振り返ります。
- ASDのお子さんは言葉を文字通りに受け取るため、「ちゃんと」「早く」といった曖昧な言葉を避け、「足は床につけようね」「あと5分だよ」と具体的・肯定的に伝えることが重要です。
- 声かけの土台として、穏やかなトーン(聴覚過敏への配慮)や視覚支援(絵カードなど)を併用し、本人の「好き」な話題から入ることで、安心感と信頼関係を築きます。
- 「悲しいね」と感情を代弁(ラベリング)し、「〇〇できたね」とプロセス(過程)を具体的に褒めることで、子どもの自己効力感を育て、次の挑戦への意欲を引き出します。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。