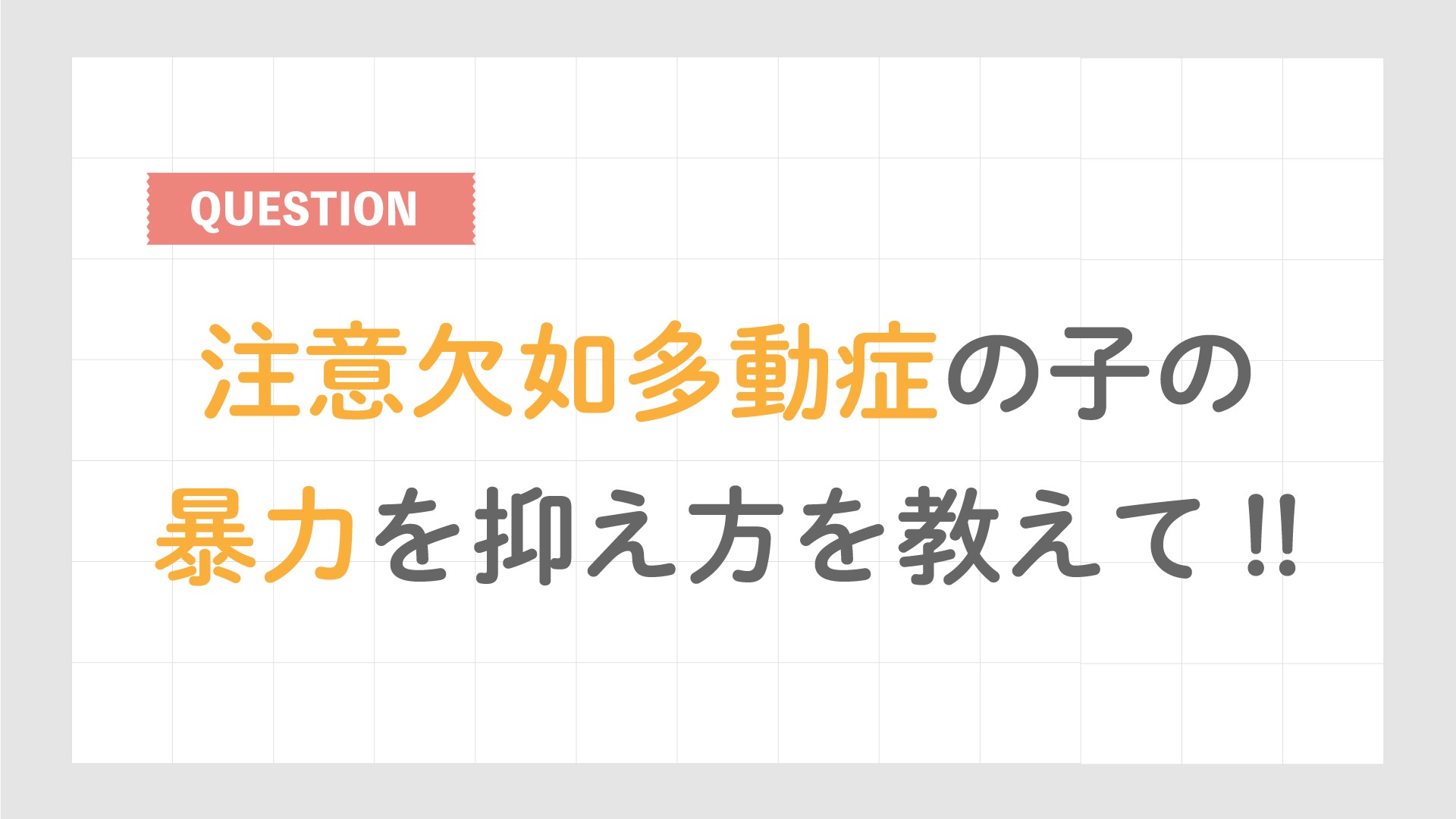ADHDの子がゲーム依存になりやすい理由とは?脳の「報酬系」の特性と家庭でできるルール作りのコツ
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ADHD(注意欠如多動症)とゲーム依存症」についてです。
ADHDと「依存症」の関係
さて、今日はADHDとゲーム依存症についてなんですけれども、ADHDのお子さんって、結構「依存症」になりやすいって言われているんですよね。
大人になってからだと、お酒だったり、ギャンブルだったり。幼少期でいうと、その入り口として一番身近なのが「ゲーム」なのかなと思います。
誤解のないように先に言っておくと、僕自身もゲームは嫌いじゃないんですよ。むしろ大好きでしたし、子供の頃はやりすぎだろってくらいやってました(笑)。今でもやります。
ただ、これがADHDの子供の場合、はまりすぎちゃって学校生活に支障が出ることがあります。そして、大人になった後にゲーム以外のものに依存が移っていく可能性もある。
なぜADHDが依存症になりやすいのか、特に「ゲーム」という側面から今日は深掘りしていきたいと思います。
「ゲーム障害」は病気として認定されています
皆さん、「ゲーム障害」という言葉を聞いたことはありますか?
実は2022年1月(※動画収録時点。正確にはWHOで2019年に採択され2022年1月に発効)に、WHO(世界保健機関)が「ゲーム障害」を国際疾病として正式に認定したんです。
「ゲーム=悪」と捉えてほしくないのですが、僕が療育の現場でテレビゲームを子どもたちとやると、すごく面白い傾向が見えることがあります。
特に自閉傾向(ASD)が強いお子さんだと、ゲームのプレイがうまくできないことがあるんです。例えば、目の前の画面(視覚情報)に目を取られていると手が動かなくなったり、逆に手を動かすのに必死だと画面を見ていなかったり。
「画面を見ながら、スムーズに手を動かして操作する」という動作は、実はすごく高度な「感覚統合(目と手の協応)」や「実行機能」のトレーニングになるんですよね。
学校の「黒板を見て、先生の話を聞きながら、ノートに書く」という動作とすごく似ています。だから僕は、学習塾の方で、勉強が苦手な子の感覚を鍛えるために、あえてゲームを取り入れたりもしています。
なので、ゲーム自体が悪いわけではなく、あくまで「過剰な利用」が問題なんだ、という視点で聞いていただけると嬉しいです。
WHOが言う「ゲーム障害」とは、ゲームの過剰な利用が、単なる遊びではなく、医学的に治療や予防が必要な状態であることを意味しています。
ゲーム障害の3つの診断基準
WHOの診断基準(ICD-11)によれば、ゲーム障害には大きく3つの特徴があるとされています。
- ゲームのコントロールができないことゲームをやる時間、頻度、いつやめるか、どの状況でやるか、などを自分で制御できなくなっている状態です。いわゆる「やめようと思ってもやめられない」状態ですね。
- 他のことよりもゲームを優先してしまうこと勉強、仕事、友人関係、趣味、睡眠、食事など、他の大切な生活上の活動よりもゲームを最優先してしまう状態です。
- 問題が起きているのに継続してしまうことゲームのせいで人間関係が悪くなったり、健康を損なったり、学業(成績低下)や仕事に明らかな悪影響が出ているにも関わらず、ゲームを続けてしまう、あるいはエスカレートしてしまう状態です。
これらが生活に大きな支障をきたしている場合に、ゲーム障害と診断される可能性があります。
これは単なる「ゲーム好き」や「習慣」ではなく、本人の意思だけではどうにもならない「病的な行動変容」が起きている、という認識が大事なんですよね。
なぜADHDの子はゲームに依存しやすいのか?
では、なぜ特にADHDの特性があると、ゲームに依存しやすいのでしょうか。
脳の「報酬系」とドーパミンの問題
ADHDの基本的な特性として「不注意」「多動性」「衝動性」がありますが、これらは脳内の神経伝達物質、特に「ドーパミン」系が関係していると言われています。
ADHDの人は、このドーパミンが不足気味だったり、「報酬系(ほうしゅうけい)」と呼ばれる部分の働きが弱かったりする傾向があります。
その結果、脳はより強い刺激を求め、「すぐに快感(報酬)を得られるもの」に依存しやすいんです。
勉強って、頑張ってもすぐに結果が出ませんよね。地道な努力が必要です。
でも、ゲームはどうでしょう? ボタンを押せば音が鳴る、敵を倒せばレベルが上がる、と、「即座に達成感と報酬」を与えてくれます。
これが、ドーパミンを補ってくれる手軽な手段として、脳に認識されやすいんです。
長期的な報酬(勉強)よりも、即時的な報酬(ゲーム)の方に、脳がはまりやすくなってしまうんですね。
「衝動性」と「待てない」心
ADHDの「衝動性」も、このゲーム依存と深く関連しています。
衝動性が強いと、長期的な影響(例えば、今ゲームをしたら明日のテストがボロボロになる、など)を考えるよりも、目の前の快楽(今ゲームをしたい)を優先して、のめり込んでしまう傾向があります。
例えば、目の前に「食べちゃダメだよ」と言われたケーキがあるとします。
衝動性が強いと、「ダメ」と分かっていても、「食べたら美味しい」という「今すぐの報酬」に我慢が効かず、食べてしまう。これと同じことがゲームでも起こります。
自己肯定感の低さと「現実からの逃避」
ADHDを持つ子どもは、現実世界で困難を抱えやすいです。学業での失敗、人間関係のトラブルなどを経験しやすく、どうしても自己肯定感が低くなりがちなんですよね。
でも、ゲームの世界ならどうでしょう。
ゲーム内では、ちょっとしたことで成功体験が積めます。レベルが上がり、周りから「すごいね」と言われることもある。
そうすると、ゲームの世界で一時的に「自分も価値があるんだ」と感じることができるんです。
これが「現実からの逃避先」となってしまい、現実が辛ければ辛いほど、ゲームに没頭し、依存が深まるという悪循環が生まれることがあります。
「過集中」による時間の消失
ADHDの特性に「過集中」があります。これは、興味関心のあることに対して、非常に高い集中力を発揮する特性です。
うまく使えば能力が伸びるきっかけにもなるんですが、ゲームと組み合わさってしまうと、疲労、空腹、睡眠不足といった身体的なサインに一切気づかず、長時間のめり込んでしまうことがあります。
僕自身もこの過集中傾向を持っていますが、動画作成などに集中し始めると、体感では15分くらいのつもりが、気づいたら3時間、4時間が過ぎている…なんてことが本当にあるんです。
子どもの場合、これが睡眠不足や健康問題に直結しやすいので注意が必要ですね。
コミュニティ(居場所)としてのゲーム
現実の学校生活などで、人間関係のトラブルや孤立感を抱えやすいADHDの子にとって、ゲーム内のコミュニティ(オンラインゲームの仲間など)が、唯一の「居場所」になっているケースもあります。
現実世界よりも、ゲームの世界の方が自分を認めてもらえる。だから、そっちの世界にどんどんのめり込んでしまう。
居場所があること自体は悪くないんですが、それによって現実の生活とのバランスが崩れてしまうのが問題なんですよね。
家庭でできるゲームとの向き合い方(対処法)
では、ご家庭でどのように対応していけばいいのでしょうか。
判断基準:生活に支障が出ているか
まず、今の状態が「問題のある利用」なのか「健全な利用」なのかを判断する基準が必要です。
- プレイ時間が徐々に増え続けていないか?
- 学校生活(宿題、睡眠、朝起きる)や家庭生活に支障をきたしていないか?
この2つが重要な判断基準になるかなと思います。「9時にはベッドに入る」というルールが守れず、寝坊して学校に行きたがらない、などが続く場合は、対策が必要です。
親の関わり方:一緒にルールを決め、一緒に関心を持つ
対策として一番大事なのは、「子どもと一緒にルールを決める」ことです。
親が一方的に「ゲームは1日30分!」と決めるのは、あまり良くありません。
例えば、
「いつも30分って決めてるけど、守れてないよね。大体1時間くらいやってるね?」
「じゃあ、1時間にしようか。その代わり、宿題はちゃんと終わらせてからにしようね」
というように、本人と話し合って、納得のいく約束事にすることが非常に大事です。
そして、可能であれば、親御さんもそのゲームに関心を持ってあげて、一緒にプレイしてみることをお勧めします。
一緒にやることでコミュニケーションが生まれますし、信頼関係を築きながら、健全な利用を促すことができるかなと思います。
具体的な管理戦略
ルールを決めたら、それを守るための「仕組み」も作りましょう。
- 時間管理:使用時間や終了時間を明確に決め、タイマーを活用する。
- 課金・ダウンロード:勝手にできないように制限をかける。やる場合は限度額を家族で決める。
- ペアレンタルコントロール:スマホやゲーム機には、使用時間やアクセスできるサイトを制限する機能があります。こういった技術的な対策も有効です。
そして、とても大事なことですが、保護者自身もルールを守る姿勢を見せてください。
「お父さんお母さんだって、ずっとスマホ見てるじゃん!」と子どもに言われてしまったら、ルールを守る説得力がなくなってしまいますよね。
専門家への相談と連携
もし、家庭内のルールだけではどうにもならないほど依存度が高まってしまっている場合、特にADHDの衝動性が強く出ている場合は、早めにお医者さんに相談することも大事です。
服薬によって衝動性がコントロールしやすくなり、結果としてゲームの時間を自分で制御できるようになるケースもあります。
依存症は一人で解決するのが難しい問題です。医療機関、学校、そして僕らのような福祉施設などと連携(多職種連携)して、チームでサポートしていく必要があるかなと思います。
まとめ
今日のポイントを振り返ります。
- ADHDの脳は、ドーパミン不足を補うために「即時報酬」を求める特性があり、すぐに達成感を得られるゲームに依存しやすい傾向があります。
- 自己肯定感の低さからの「現実逃避」や、「過集中」で時間を忘れてしまう特性も、ゲーム依存を深める要因となります。
- 対策としては、一方的に禁止するのではなく、まず環境を整え、本人と話し合って「守れるルール」を決めること。そして親も関心を持ち、必要な場合は服薬も含めて専門家と連携することが大切です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。