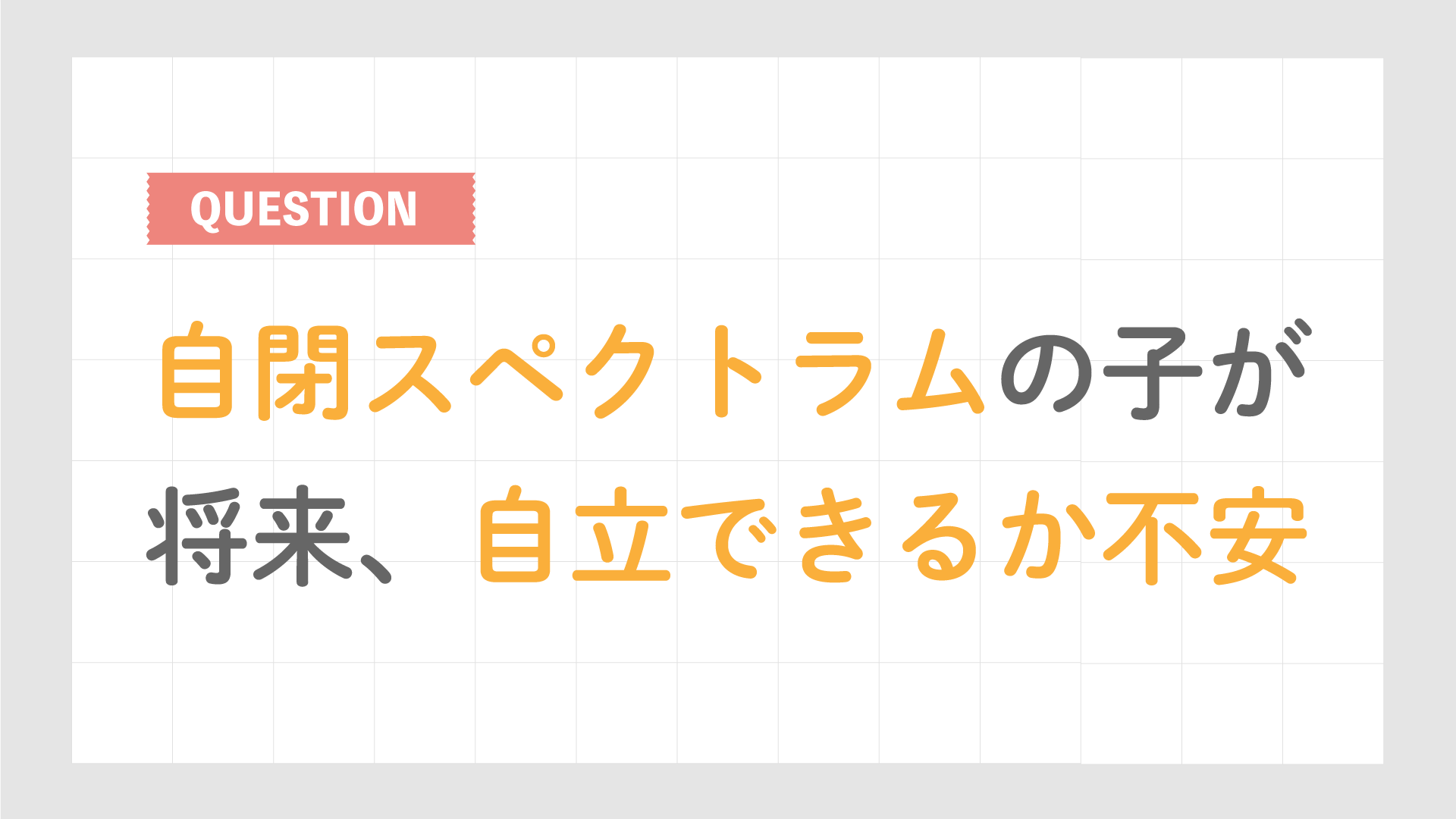ADHDの「不注意」は努力不足じゃない。忘れ物・片付け下手を克服する「環境整備」と「声かけ」の具体策
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ADHD(注意欠如多動症)のお子さんの『不注意』傾向に対する、ご家庭での具体的な支援方法」についてです。
「不注意」は努力不足ではなく、脳の特性
さて、今日の本題に入る前に、最初に一番伝えたいことがあります。
ADHDの「不注意」という現象は、本人の努力や育て方の問題じゃなくて、脳の情報処理の特性によって起こっている、ということをまず理解してほしいなと思います。
集中力が続かない、忘れ物が多い、ケアレスミスが多い…。周りから見ると「もうちょっと頑張ればできそうじゃん」とか「ちゃんとしろ」と思われがちなんですよね。
でも、本人も「頑張ってどうにかしたい」と思っていることがすごく多いんです。
子ども自身も「あ、失敗したな」と思っている。それなのに繰り返し注意されてしまうと、どんどん自信がなくなって自己肯定感が下がってしまいます。
これが続くと、大人になった後に二次障害(うつや適用障害など)につながる可能性も高くなるため、早期の理解と支援が大事になります。
なぜ起こる?不注意の具体的な困りごと
では、不注意傾向があると、具体的にどんな困りごとが現れるのでしょうか。
1. 忘れ物・なくし物が多い
持ち物の管理や記憶の維持に困難が見られます。教科書、文房具、水筒などを頻繁に忘れたり、置き場所を覚えられずになくしてしまったり。僕もこれはかなり該当しました(笑)。
これは、脳の「ワーキングメモリ」という機能の弱さと関連していると言われています。
ワーキングメモリは「脳のメモ帳」や「作業台」によく例えられます。私たちは話を聞きながら、その情報を一時的にこの作業台に乗せて物事を考えます。
ADHDの不注意傾向がある子の脳は、この「作業台が散らかっている」とか「作業台がすごく小さい」状態に近いです。
新しい情報が来ると、前に置いていた情報がポロっと落ちてしまう(忘れる)。だから、物をどこに置いたか、さっき何を言われたかを覚えておくのが難しいんです。
2. 整理整頓が苦手
机や部屋が散らかりやすく、片付けの途中で漫画を読み始めちゃう…なんてこともあります。
これは「実行機能」という、脳の司令塔のような機能の課題が関係しています。
「片付け」という行動は、実は「①不要なものを見分ける」「②どこにしまうか計画する」「③順番に実行する」という、非常に高度な実行機能を使っています。
ADHDの子は、この「計画」や「順序立て」が苦手で、「どこから手をつけていいか分からない」とフリーズしてしまうことが多いんです。
3. 指示が一度で聞き取れない
話しかけられても反応がなかったり、ぼーっとしていたり。話を聞いていないわけじゃなく、情報を頭の中に入れたんだけど、整理しきれない「情報渋滞」が起きているような状態です。
4. 集中力が続かない
窓の外の景色や周りの物音など、ちょっとした刺激にすぐに気を取られてしまいます。これは脳の「注意制御」や「抑制(関係ない刺激を無視する力)」の働きが関係していますね。
5. ケアレスミスが多い
計算ミスや文字の書き間違いなど、「注意していれば防げるミス」を繰り返してしまうのも、ワーキングメモリの課題(覚えておくのが難しい)が影響しています。
不注意支援の最重要ポイント:「環境」を徹底的に整える
では、これらの「不注意」にどう対応すればいいのか。
僕が療育する中で、もう「絶対だ」と言えることが一つだけあります。特に不注意傾向がある子に関して、一番大事なのは「環境」です。
正直、本人の「意思の力」とかを信じちゃダメで(笑)、環境を整えること以外にできるようになる方法ってあんまりないんです。
僕は「部屋と脳は関連してるな」と思っていて、脳が散らかってる時は、やっぱり部屋も散らかりがち。
だからこそ、脳を整理するために、まず「物理環境」をスッキリ整理整頓しておくことがすごく大事なんです。
1. 学習スペース(集中環境)の作り方
まず、集中すべき場所を明確にします。
- 机を壁向きに配置する
- パーテーションや棚で区切って「自分だけの空間」を作る
- 周囲にテレビ、漫画、おもちゃなど、注意がそれるものを置かない
そして、勉強中の机の上は、必要なものだけ(筆記用具とノートだけ)を置くことを徹底してください。
こうして「今やるべきこと」以外の情報(刺激)を物理的にシャットアウトするだけで、ワーキングメモリの負担が軽くなり、集中しやすくなります。
2. 視覚・聴覚(感覚)への配慮
刺激に敏感な子も多いので、感覚面にも配慮が必要です。
- 視覚:壁やカーテンの色は、白・茶色・グレーなど落ち着いた色にする。蛍光灯のピカピカした真っ白な光が強すぎる場合は、調光ライトなどで光の色や明るさを調整するのも手です。
- 聴覚:外の景色や音が気になる場合は、カーテンを閉めたり、ノイズキャンセリングイヤホンを活用したりするのも良いですね。
家族みんなで「集中タイム」としてテレビを消すなど、音を立てない時間を作るのも効果的です。
3. 収納と片付け(「定位置化」の徹底)
ここが、お父さんお母さんに特にやってほしいところです。
お家の片付けをするとき、場所は徹底的に「定位置化」してください。
1つ1つに必ず定位置を設け、「使ったら必ず戻す」という習慣を、不注意がある子には徹底してやっていった方がいいです。
- どこに何があるか分かるように、ラベルや写真を貼る
- 細かい仕切りはNG。箱の中に放り込むだけの「ワンアクション収納」にする
脳が整理しやすいように、まず物理環境を整理する。これは思ったよりも大きな結果を得られるので、ぜひ徹底してやってほしいですね。
(僕も昔は片付けられませんでしたが、ある時から「無駄なものを置かない」と決めて実行したら得意になりました。物を減らすのも一つの手ですよ)
声かけと習慣化の具体的なアプローチ
環境が整ったら、次に関わり方です。
1. 伝え方:「短く、具体的に、肯定的に」
不注意の子に「ちゃんと片付けといて」という曖昧な指示は伝わりません。
- NG例:「ちゃんとやっといて」
- OK例:「散らかってるおもちゃを、あの箱の中に入れておいて」
このように、何をどうするのか具体的に伝えます。
そして、「〜やりなさい!」という命令形は、反発を生みやすいので、「〜してね」とか「〜しようね」という肯定的な言葉を選ぶように意識してみてください。
2. 声かけの技術:CCQ(Calm, Close, Quiet)
何かを伝える時、遠くのキッチンから「宿題やりなさーい!」と叫んでも、まず伝わりません。

ゆう先生の補足解説:CCQ(Calm, Close, Quiet)とは?
これは療育の現場でも使う基本的な技術で、「Calm(落ち着いて)」「Close(近くで)」「Quiet(静かに)」の頭文字です。
- Calm:まず親が感情的にならず、落ち着く
- Close:子どものそばに近づく
- Quiet:相手の目を見て、静かな声で伝える感情的に怒鳴られると脳は防御的になり、指示が入らなくなります。遠くからの指示は他の刺激にかき消されます。「今から私はCCQモードだ」と、お父さんお母さん自身が意識を切り替えて伝えるのがコツですね。
3. 忘れ物対策:「前日の親子チェック」と「定位置管理」
忘れ物対策は、前日の準備が命です。そして、それを「親子で確認する習慣」がすごく大事。
1人でやらせると大概失敗するので、小学校中学年くらいまでは親子で一緒にチェックリストを見ながら確認する。
これが定着してきたら、徐々に親が確認する回数を減らしていきます。(ただし、確認ゼロが続くと元に戻りやすいので、週に1回は親がチェックするなど、定期的な関わりは続けた方がいいですね)
4. タスクの進め方:「スモールステップ」で小さく区切る
宿題やお手伝いを一気にやらせようとせず、細かく分解します。
- 「まずこの1ページだけやってみよう」→できたら褒める
- 「お皿を1枚運んでくれたら、ありがとう」→次を頼む
ADHDの子は、スモールステップでその都度褒められると「調子が出てくる」感じがすごくあります。「できた!」という小さな成功体験が意欲につながります。
5. 集中力の育て方:「タイマー」の活用
「勉強時間はどうすれば?」という質問をよくいただきますが、僕は「30分グダグダやるより、タイマーで10分だけ集中する」方がいいですよ、とよく言います。
視覚的に残り時間がわかるタイマーを使い、「この10分だけはやる」と決めて集中させる。
これができるようになったら、「10分集中→5分休憩→また10分集中」のように、休憩を挟みます。
これは「注意の切り替え訓練」にもなるんです。集中とリラックスを自分で切り替える練習ですね。
これができるようになると、いろんなことができるようになったな、と成長を感じることが多いですよ。
まとめ
今日のポイントを振り返ります。
- ADHDの「不注意」は、本人の怠慢ではなく、脳の「ワーキングメモリ」や「実行機能」の特性が原因であることを理解するのが第一歩です。
- 支援の土台は「環境整備」。勉強に集中できるスペース作り、そして何よりも物の「定位置化」を徹底し、脳の処理負担を減らすことが最も重要です。
- 具体的な関わりとしては、「短く、具体的に、肯定的に」伝える声かけ(CCQ)を意識し、「スモールステップ」や「タイマー」を活用して、短時間でも「できた!」という成功体験を積み重ねていくことが、本人の自信と習慣化に繋がります。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋gれば、僕もとても嬉しいです。