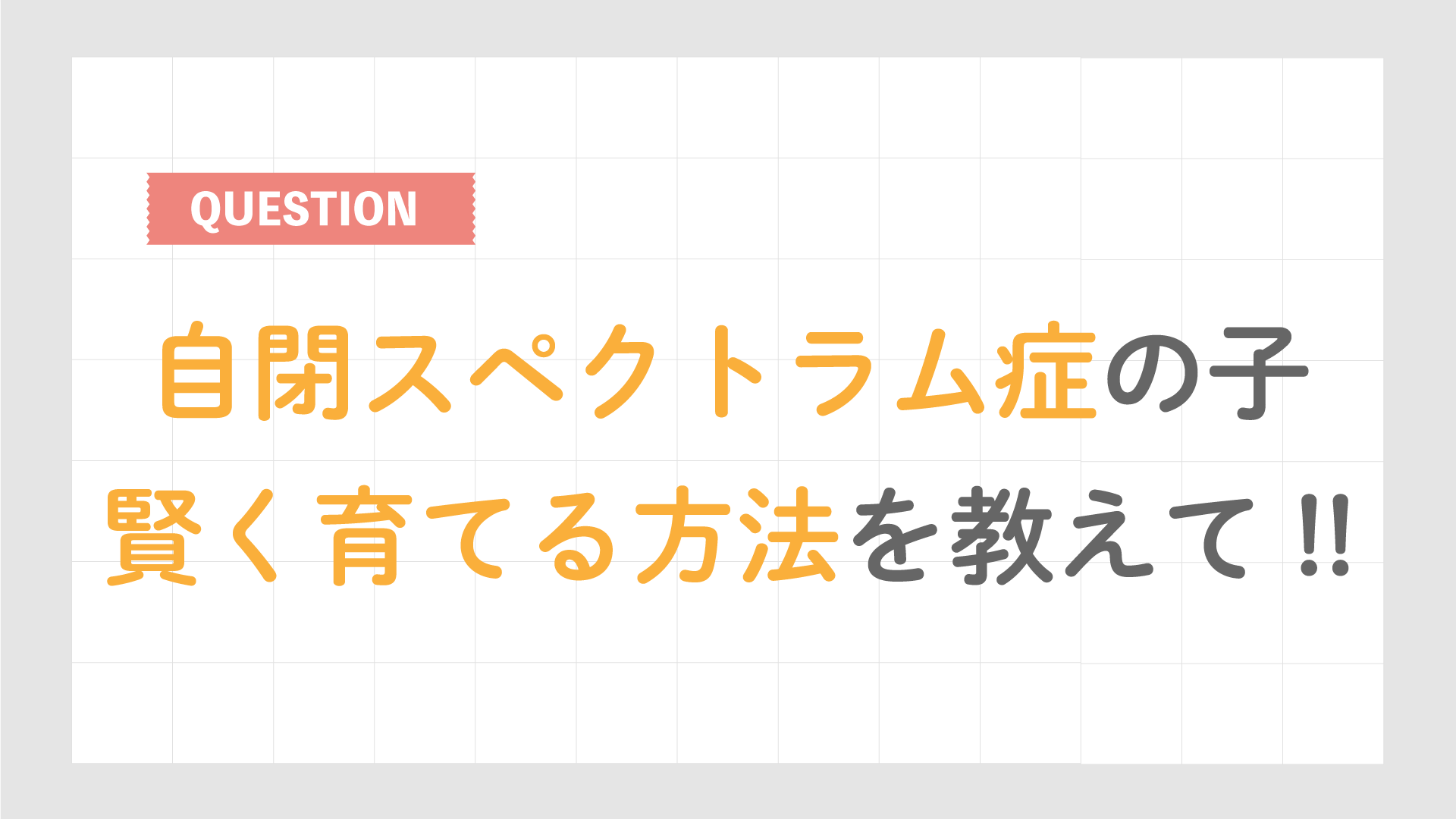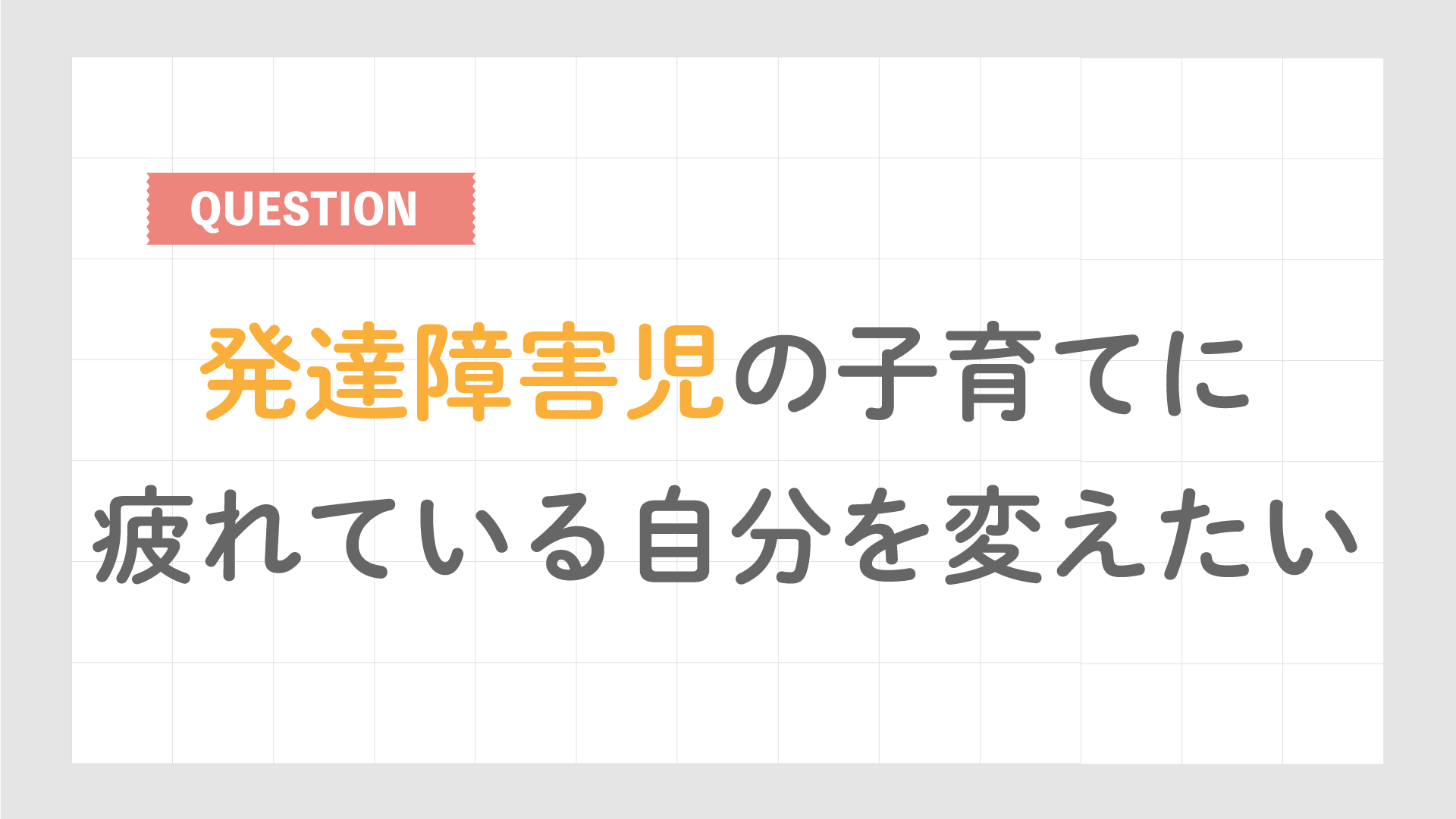ディスレクシア(読字障害)とは?年代別のサインとICT・AIを活用した「読める」支援法
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ディスレクシア(読字障害)」についてです。
お子さんが文字を読むのを極端に嫌がったり、教科書をスラスラ読めなかったりして、「なんでうちの子だけ?」「もしかして、努力が足りないのかな?」と悩んでいませんか?
その「読みにくさ」は、本人のやる気の問題ではなく、ディスレクシアという脳の特性が関係しているかもしれません。
ディスレクシア(読字障害)とは?
今日はディスレクシア、いわゆる「読字障害(どくじしょうがい)」について解説します。これは、以前の動画でも触れた学習障害(限局性学習症:SLD)の3つの分類のうちの一つですね。
簡単に言うと、「読むこと」に特有の困難を持つ特性のことです。「読むのが苦手」というお子さんや大人の方の障害特性になります。
なぜ「読む」のが苦手なの?ディスレクシアの原因
まず、ディスレクシアの原因はなんなのか。これはまだ完全に解明されたわけではないんですが、現状で分かっていることをお話しします。
原因①:脳の情報処理の違い(右脳と左脳)
一つは、脳の情報処理の違いがあるという論文があります。文字を読むときに使う神経回路が、一般的な方とちょっと異なっていると言われているんです。
具体的には、左脳の「言語を処理する部分」の連携が弱いのではないか、と。そのために、右脳などの別の領域を使って、いわば「遠回り」して読む傾向があるそうです。
読む力がないわけではなく、脳が違った方法で、遠回りして読んでいる。だから、読むのに時間がかかったり、パッと認識できなかったりする、と考えるのが良いのかなと思います。
原因②:音と文字を結びつけるのが苦手(音韻処理)
もう一つの原因として、「音」と「文字」を結びつけるのが苦手だという脳の特性があるそうです。

ゆう先生の補足解説:音韻処理(おんいんしょり)とは?
「音韻処理」とは、私たちが普段聞いている「言葉の音」を認識したり、操作したりする能力のことです。
例えば、「でんき」と「でんぱ」という言葉。私たちは「ん」の音が、後ろに来る「き」や「ぱ」によって、微妙に発音が違っていても、同じ「ん」の音として認識できますよね。
ディスレクシアの場合、この「音を認識し、同じものとしてまとめる」処理が少し苦手な傾向があると言われています。
そのため、文字一つひとつの音は分かっても、それを組み合わせて単語としてスムーズに認識するのが難しくなる、と考えられています。
また、研究では家族内での遺伝傾向も示唆されており、脳の機能的な問題によってディスレクシアが起こっている、ということをまず知っておいていただけると嬉しいです。
【年代別】ディスレクシアの気づきのサイン
ここからは、各年代ごとのサインを見ていこうと思います。
幼児期〜小学校低学年のサイン
まずは幼児期から小1・小2くらいまで。この時期は、音や文字への興味を示しにくい傾向があります。
例えば、
- 「しりとり」や「韻(いん)を踏む遊び」が苦手。
- 言葉の増え方(語彙)がゆっくりな感じがする。
- 絵本を見ていても、文字ではなく挿絵ばかり見ている。
- 「ぬ」と「め」など、形の似た文字の混同が続く。
- 文章をスラスラ読めず、「き・の・う・は…」のように1文字ずつしか読めない(逐字読み)。
- 「がっこう」の「っ」のような小さい「つ」(促音)を読み飛ばす。
ただ、正直この年代だと、これがディスレクシアの傾向なのか、それとも多動傾向(ADHD)があってじっくり見るのが苦手なのか、自閉傾向(ASD)があって興味が向かないのか、判断が難しい時期でもあります。
小学校高学年〜中学生のサイン
この年代になると、「読む速度の遅さ」が一番目立ってきます。
国語の教科書を読むのがたどたどしかったり、漢字の習得でつまずきが増えたりします。読めない漢字は、やっぱり書くのも難しいんですよね。
そして、読むのに時間がかかると、内容理解までに余力が回らなくなります。

ゆう先生の補足解説:ワーキングメモリと「読む」ことの関係
人の脳には「ワーキングメモリ」という、情報を一時的に記憶しながら作業する「脳の机の広さ」のような機能があります。
発達にでこぼこがある子はこの机が少し小さい傾向があると言われているんですが、ディスレクシアの子の場合、「読む」という作業自体に、この机の容量をたくさん使ってしまうんです。
結果、文章の内容を理解したり、前の内容を覚えておいたりするためのスペースが残っておらず、「読んではいるんだけど、内容は頭に入っていない」という状態が起こりやすくなります。
その結果、試験で問題文を読むだけで時間切れになったり、読書自体を避けるようになったりして、困難さが気づかれることがあります。
高校生〜成人期のサイン
大人になると、なんとなく読めるようにはなるけれど、「読むこと」にすごく強い負担・疲労を感じるようになります。
読む速度が遅いのは相変わらずで、集中力もすごく使うので維持しにくい。
だから、仕事で長い資料を読んだり、大学でレポートを書いたりする時に、ものすごいストレスや疲労を感じて、二次障害(うつや不安障害など)につながる方もいます。
「努力不足」という誤解と自己肯定感の重要性
年代を問わず言えるのは、ディスレクシアは「努力不足」と誤解されやすいということです。
特に、会話は普通にできるし、理解力もあるように見えるのに、勉強の「読む」ことだけができないと、「やる気がない」「努力が足りない」と周りから思われがちです。
これが、本人にとって「やってもできない」という失敗体験の積み重ねになってしまいます。「どうせ僕(私)は、やってもできないんだ」という自己否定につながってしまう。
だからこそ、学習支援と同時に、心理的な支援(自己肯定感を守る関わり)がものすごく大事になってきます。
家庭でできるディスレクシア支援の基本方針
では、ご家庭ではどんな支援ができるでしょうか。基本方針は「苦手(読む)を補って、得意(学ぶ)を伸ばす」ことです。
読めるように訓練することも大事ですが、「読む」ことの負担をいかに軽くして、「学び(内容を覚えること)」にアクセスできるようにしてあげられるか。そこを調整するのが支援者の役割だと思います。
方針①:苦手(読む)を補い、得意(学ぶ)を伸ばす
大事なのは「勉強の内容を覚えること」ですよね。だとしたら、家庭(プロセス)でつまずいているなら、そこを調整してあげればいいんです。
ICT機器、今だったら本当にAI。これらを活用して、例えば文章を「読んでもらう」(音声化する)。
耳から情報が入れば理解できる子は格段に増えます。分かれば、やりたくなりますよね。
方針②:環境調整(フォント、リーディングトラッカーなど)
勉強は、無駄な情報がない方が入りやすいです。静かで整理された場所で、短時間集中できるようにするのが基本です。
それに加えて、「読みやすさ」のための環境調整も大事です。

ゆう先生の補足解説:読みやすい「UDフォント」とは?
UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)は、「読みやすさ」を重視してデザインされた書体です。文字の形が分かりやすく、特に「ぬ」と「め」のように似た形の文字が見分けやすいように工夫されています。
もしWordなどで文書を作る際は、こうしたフォントに変えたり、文字の大きさや行間(文字と文字の間)を広く取ったりするだけで、読みやすさが大きく改善することがあります。

ゆう先生の補足解説:リーディングトラッカーとは?
イラストにあるような、真ん中だけが透明になっていて、読む行だけをハイライトできる補助具(文房具)です。
これを使うと、今読んでいる行に集中でき、別の行に目が移ってしまう「読み飛ばし」を防ぐ効果が期待できます。色がついていることで、白い紙のまぶしさを軽減する効果もあります。
方針③:多感覚学習の導入(見る・聞く・触れる)
特に幼少期には、「多感覚」を使った学習がおすすめです。
冒頭で、ディスレクシアは脳の連携がアンバランスかも、という話をしました。脳をうまく鍛える方法の一つは、脳のいろんな部位(見る、聞く、触るなど)を同時にたくさん使うことです。
例えば、「木」という字を覚えるとき。
- まず、指で「木」という字をなぞってみる(触覚)。
- 空中に「木」と指で書きながら、「もく」と声に出す(視覚+運動+聴覚)。
- その後に、鉛筆で書く。このように、いろんな感覚を組み合わせて情報を取り入れることで、脳が補い合い、定着しやすくなると言われています。
具体的な支援ツール(ICT・AIの活用)
これからの時代、テクノロジーの活用は必須です。
小学生向けの支援ツール(音声教材など)
小学生、特にディスレクシアに関しては、音声付きの教材が一番いいと思います。
教科書を読み上げてくれる「マルチメディアDAISY(デイジー)教科書」や、広島大学さんが作っている「UDブラウザ」など、音声と文字がカラオケの字幕のように同期して表示されるものがあります。
こういうものを活用したり、シンプルに大人が近くで読んであげるだけでも全然違います。
中高生向けの支援ツール(OCR、読み上げソフト)
中高生になると、勉強の量も増えます。ガリガリ書いて覚える従来の方法だと、設問を読むだけで疲れてしまいます。
- OCR (Optical Character Recognition):光学的文字認識。簡単に言うと、紙に印刷された文字や、黒板に書かれた文字をスマホのカメラなどで撮影して、テキストデータ(編集できる文字)に変換する技術です。
- TTS (Text-to-Speech):テキスト読み上げ。その名の通り、テキストデータを音声で読み上げてくれる機能です。
この2つを組み合わせると、例えば「配られたプリントをOCRアプリで読み取り、それをTTS機能で耳で聞く」という学習が可能になります。
大学生・社会人向けの支援(AIの活用)
そして、大学生や社会人になったら、テクノロジーは「補助」から「仕事の道具(仲間)」になります。
特に僕が推奨しているのはAI(ChatGPTやGeminiなど)です。
AIは完璧ではありませんが、こちらの苦手な部分をかなりサポートしてくれます。「読めない」「書けない」という部分に関しては、AIがものすごく助けてくれる世の中に間違いなく
なっていきます。
AIに文章を要約してもらったり、読み上げてもらったりすることで、読むのが苦手でも効率的に情報を得ることができます。
ディスレクシアの「強み」とは?
最後に、ディスレクシアは「弱み」だけではありません。「強み」に注目することもすごく大事です。
研究によっては、ディスレクシアの人は、文字ベースの処理は苦手な一方で、
- 視覚的・空間的な認識能力
- 創造的な発想力
- 全体を直感的に捉える能力に長けている可能性があると言われています。
文字のニュアンスは読み取りにくくても、その場の空気感や全体のニュアンスを読み取るのが得意だったり、クリエイティブな分野で力を発揮したりするかもしれません。
読めないことより「学べる方法」を選ぶ時代へ
これからの時代、「読めない」からおしまい、ではありません。
ディスレクシアは「できない」わけじゃなくて、「その方法だとできない」だけなんです。だったら、違う方法を見つければいい。
本人が「読めない」ことで苦しむのではなく、「どうやったら学べるかな?」とツールを掴み取り、選んでいく。学習障害があっても「学習が楽しい」と思える。そういう社会に移行していくことが、僕は何より大事だと思っています。
まとめ
今日の記事をまとめます。
- ディスレクシア(読字障害)は、本人の努力不足ではなく、脳の「音と文字を結びつける」処理などの機能的な違いが原因で起こる特性です。
- 幼児期の「しりとりが苦手」といった音への関心の薄さや、学齢期の「読む速度が極端に遅い」「読んでも内容が入らない」といった年代別のサインに気づくことが大切です。
- 支援で最も重要なのは自己肯定感を守ること。無理に読ませる訓練に偏るのではなく、音声教材や読み上げソフト、AIなどを活用し、耳から情報を得るなど「本人が一番学びやすい方法」を一緒に見つけてあげてください。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。