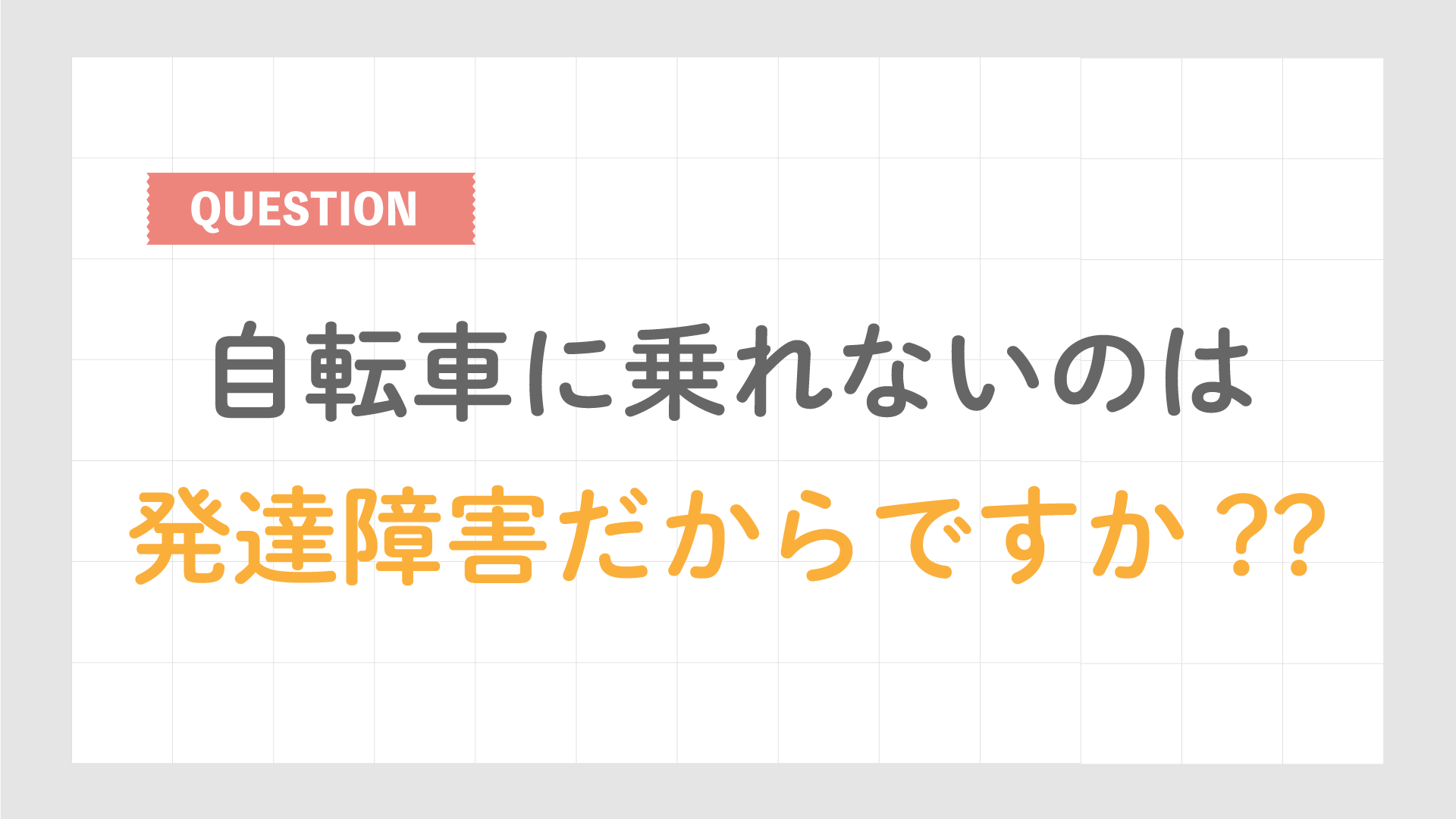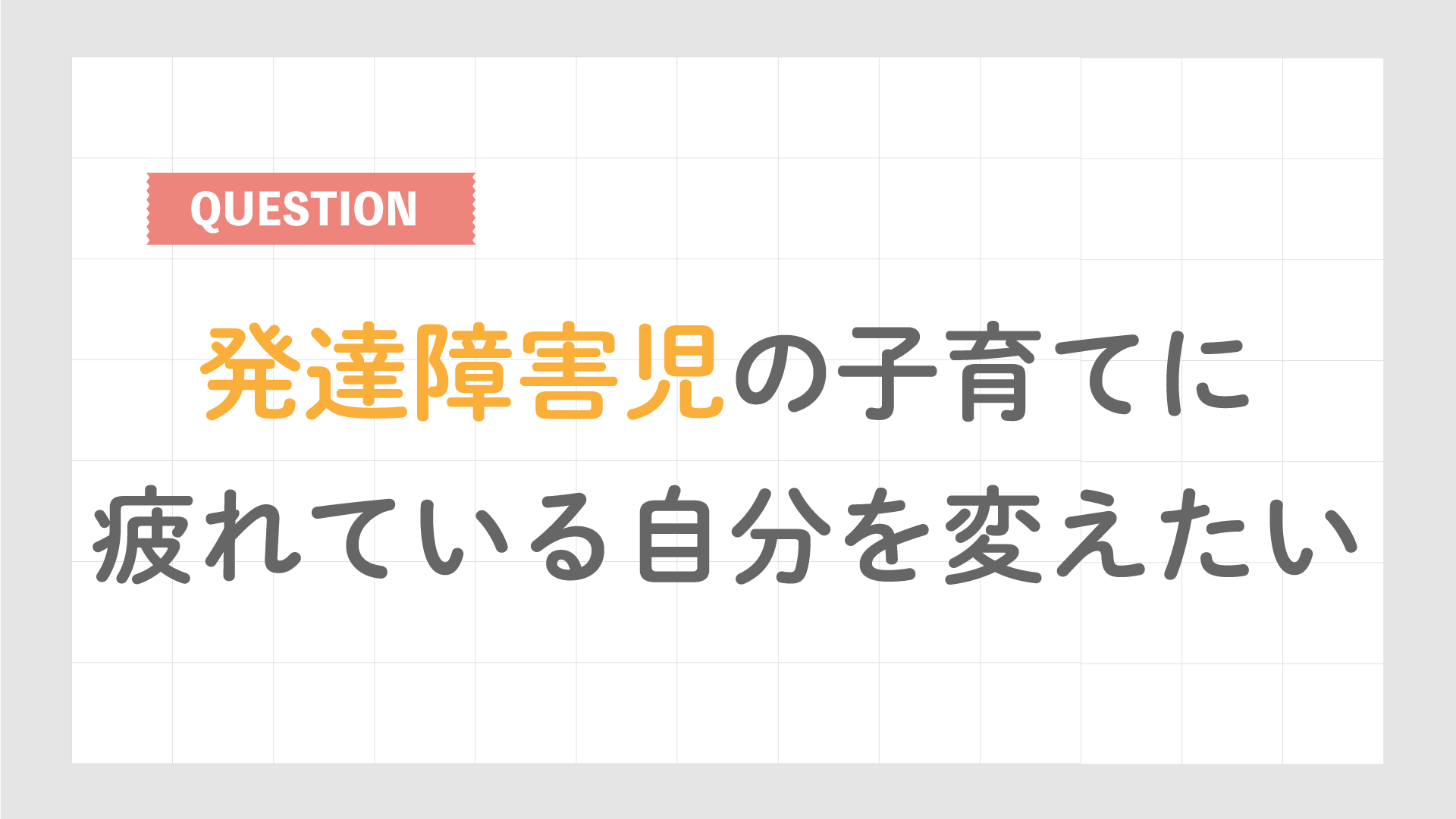ASD(自閉スペクトラム症)の感覚過敏・感覚鈍麻とは? 日常の「困りごと」の背景を理解する
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの感覚過敏(かびん)と感覚鈍麻(どんま)」についてです。
「特定の音をものすごく嫌がる」「服のタグを切らないと着てくれない」「怪我をしても平気な顔をしている」…
お子さんのそんな行動に、「どうしてなんだろう?」と不思議に思ったり、対応に困ったりしていませんか?
実は、それは単なるワガママや「しつけ」の問題ではなく、その子が感じている「世界」が、私たち多数派とは少し違うからかもしれません。
今日は、ASDのあるお子さんが抱えやすい感覚の違いについて、掘り下げていきたいと思います。
感覚の違いは「しつけ」ではなく「脳の特性」
まず大前提として、僕が皆さんに知っておいてほしいのは、感覚の問題は「しつけ」や「本人の努力」だけで変えられるものではない、ということです。
多少は「慣れる」部分もあるかもしれませんが、根本的な感じ方が大きく変わることは少ないです。
寒がりの人が、どれだけ頑張っても極端な暑がりにはなりませんよね。それと同じで、これは生まれ持った神経学的な違い、つまり脳の特性なんです。
脳の「フィルター」機能の違い
僕たちの周りには、目に見えるもの、聞こえる音、肌で感じるものなど、膨大な量の情報が溢れています。
でも、僕たちの脳は、そのすべての情報をそのまま受け取っているわけではありません。
無意識のうちに情報を「フィルタリング」して、不要な情報をカットし、必要な情報だけを選び取って処理しているんです。
だから、僕らは日常生活をスムーズに送ることができています。
しかし、ASDのある人の脳は、このフィルタリング機能の働き方が独特だったり、アンバランスだったりすることがあります。その結果、
- 感覚過敏(かびん):特定の刺激を過剰に強く感じてしまい、脳が処理しきれなくなる状態。
- 感覚鈍麻(どんま):特定の刺激を感じにくく、必要な情報を取りこぼしたり、刺激が足りなくなったりする状態。
ということが起こるわけです。
僕らが持つ「7つの感覚」
一般的に「五感」と言われますが、人間の感覚は大きく7つに分類されることがあります。ASDの感覚特性を理解する上で、この7つを知っておくと便利です。
- 視覚:見る感覚
- 聴覚:聞く感覚
- 触覚:触れる感覚
- 味覚:味わう感覚
- 嗅覚:匂いを嗅ぐ感覚
- 固有受容覚(こゆうじゅようかく):体の位置や動き、力の入れ具合を感じる感覚
- 前庭覚(ぜんていかく):体の傾きやスピード、重力を感じる感覚(バランス感覚)

ゆう先生の補足解説:固有受容覚と前庭覚
あまり聞き慣れないかもしれませんが、固有受容覚と前庭覚は、私たちが体をスムーズに動かすために非常に重要な感覚です。
- 固有受容覚は、筋肉や関節からの情報で、「今、自分の手がどこにあって、どれくらいの力で物を持っているか」などを無意識に把握する感覚です。この感覚が鈍いと、力の加減が分からず物を壊してしまったり、自分の体の大きさが掴めずによくぶつかったり、不器用さにつながることがあります。
- 前庭覚は、主に耳の奥(三半規管など)で感じる、体のバランスや動きに関する感覚です。この感覚が鈍いと、ぐるぐる回っても目が回らなかったり、逆に過敏だと、ちょっとした揺れでも気分が悪くなったりします。姿勢を保つことにも関わっています。
これらの7つの感覚それぞれに、「過敏さ」や「鈍麻さ」が現れる可能性があるんです。
ASDの「感覚過敏」の世界
感覚過敏は、特定の刺激が脳にとって「痛い」「うるさい」「まぶしい」と感じられ、処理しきれなくなる状態です。
視覚過敏
- 太陽光や蛍光灯の光がまぶしすぎて痛く感じる。
- チカチカする光や、ごちゃごちゃした色使いを見ると、めまいや頭痛がする。
- 教室やスーパーなど、視覚情報が多い場所に行くと、情報処理が追いつかず思考停止したり、パニック(メルトダウン)を起こしやすくなる。
聴覚過敏
- 時計の秒針の音や、人が食べ物を噛む音(咀嚼音)が大きく聞こえすぎて気になり、眠れなくなったり、強いストレスを感じる。
- 救急車のサイレン、掃除機の音、赤ちゃんの泣き声などが、まるで体への痛みのように感じられる。
- 多くの人がいる場所のざわざわした音(ガヤガヤ)が全て同じ大きさで聞こえてしまい、特定の人の声を聞き取ることが難しい。
聴覚過敏があると、学校などの集団生活が非常に苦痛になったり、外出自体が嫌になったりして、慢性的な疲労や社会的な孤立につながることも少なくありません。

ゆう先生の補足解説:メルトダウンとは?
メルトダウン(Meltdown)は、ASDのある人が、感覚的な過負荷や強いストレス、予期せぬ変化などによって、一時的に自己コントロールを失い、激しいパニック状態になることを指します。
大声で泣き叫んだり、攻撃的になったり、自傷行為に至ったりすることもあります。これは単なる「癇癪(かんしゃく)」や「わがまま」とは異なり、本人もコントロールできない、脳が限界を超えてしまった状態です。
感覚過敏は、このメルトダウンの大きな引き金の一つとなります。
触覚過敏
- 特定の素材の服(チクチクする、ゴワゴワするなど)や、服についているタグが痛くて着られない。(僕、個人的には服のタグってなんで付いてるんだろう?っていつも思っちゃうんですけど…笑)
- 人に軽く触れられることや、頭を撫でられることが苦痛。
- 満員電車など、人と体が触れ合う状況が耐えられない。
- 歯磨きや洗髪、散髪など、体に触れられるケアが苦痛でできない。
味覚・嗅覚過敏
- 特定の匂い(香水、芳香剤、食べ物の匂いなど)で吐き気をもよおす。
- 味付け(辛い、甘い、酸っぱいなど)を強く感じすぎてしまい、食べられないものが多い(極端な偏食)。
- 複数の味が混ざっている料理が苦手。
感覚過敏は、本人が「嫌だ」という表情や行動で示してくれることが多いので、比較的分かりやすいかもしれません。そのサインを見逃さず、「無理強いしない」ことが大切です。
ASDの「感覚鈍麻」の世界
感覚鈍麻は、過敏とは逆に、特定の刺激を感じにくい状態です。これが原因で、様々な困りごとにつながることがあります。
視覚・聴覚鈍麻
- 明るい光や大きな音がないと、覚醒レベル(意識のハッキリ度)が上がらない。
- ゲームなどに集中していると、名前を呼ばれても全く気づかない。(これは聴覚鈍麻だけでなく、注意の切り替えの問題も関わりますが)
重要な情報(危険を知らせる音など)を取りこぼしたり、周りから「無視している」「不注意だ」と誤解されやすいのが、このタイプの鈍麻さです。
触覚鈍麻
- 怪我をしても痛みをあまり感じない、または全く感じない。
- 暑さや寒さを感じにくく、季節に合わない服装をしてしまう。(冬でも半袖半ズボンで平気そうに見えるが、実は体は冷えていて体調を崩しやすい、など)
- 口の周りや手の汚れに気づきにくい。
- 力加減が分かりにくく、物をすぐに壊してしまったり、お箸や鉛筆をうまく使えなかったりする(不器用さ)。
特に痛みや温度を感じにくいことは、火傷や怪我などの危険に気づきにくく、安全面でのリスクが非常に高くなります。
固有受容覚・前庭覚の鈍麻
体の位置や動き、バランスに関する感覚が鈍いと、刺激を補おうとする行動が見られることがあります。
- 自分の姿勢や力加減を感じにくいため、わざと物に強くぶつかってみたり、椅子をガタガタ揺らしたり、変な姿勢を取ったりする(固有受容覚の鈍麻)。
- バランス感覚や動きの感覚が鈍いため、常に走り回ったり、その場でぐるぐる回ったり、高いところから飛び降りたりして、強い刺激を求める(前庭覚の鈍麻)。
また、力の加減が分からずに友達を強く叩いてしまったり、体の動かし方がぎこちなかったりして、「乱暴だ」「不器用だ」と誤解されたり、運動面での困難につながったりします。
刺激を求める「感覚探求行動」
感覚鈍麻がある場合、足りない刺激を自分で補おうとして、特定の行動を繰り返すことがあります。これを「感覚探求行動(かんかくたんきゅうこうどう)」と呼びます。
感覚探求行動は、感覚鈍麻によって不足している刺激を自分で補い、自分にとって「ちょうど良い」覚醒水準(意識のハッキリ度)に整えようとする、自然な自己調整行動です。
例えば、
- 前庭覚の鈍麻 → その場でぐるぐる回る、ブランコを激しくこぐ
- 触覚の鈍麻 → 物を強く噛む、壁に体を打ち付ける
- 聴覚の鈍麻 → 大音量で音楽を聴く、叫び声をあげる
周りから見ると「やりすぎ」「危ない」と感じる行動も、本人にとっては必要な刺激を得るための試みである場合があるんです。
感覚の違いがもたらす生活への影響
こうした感覚の違いは、日常生活の様々な場面に影響を及ぼします。
- 学習・集中:教室の光や音、服の不快感などが気になり、授業に集中できない。座っていること自体が苦痛になる。
- 対人関係:感覚の違いからくる誤解(無視している、乱暴だ、など)が生じやすい。他の子と同じ空間にいることが苦痛で、孤立してしまう。
- 食事・睡眠:味覚・嗅覚過敏による偏食。触覚・聴覚過敏による寝つきの悪さ、不眠。これらは本人の健康だけでなく、家族全体の疲労にもつながります。
- 感情の調整:感覚のコップが常に満杯に近い(過敏)ため、些細な刺激で感情が爆発(メルトダウン)しやすい。逆に刺激が足りない(鈍麻)と、イライラしたり、自己刺激行動(こだわり)を求めたりする。
- 日常生活動作:衣服の着脱、歯磨きや洗髪といった衛生行動、靴紐を結ぶなどの細かな動作(協調運動)が、感覚の問題で困難になる。セルフケアが難しく、常に手助けが必要になる。
- 心身のエネルギー消耗:常に不快な感覚に耐えたり、刺激を避けたりしているため、非常に疲れやすい。これが二次的な不安障害やうつ状態につながるリスクもある。
感覚は変動する:柔軟な対応の必要性
さらに難しいのは、この感覚の感じ方が常に一定ではないということです。
体調(疲労度)、ホルモンバランス、その時の周りの刺激量などによって、昨日までは大丈夫だったことが、今日はダメ、ということがよく起こります。
だからこそ、周りの大人は「昨日はできたでしょ!」と決めつけず、その時々の本人の状態を観察し、柔軟に対応を調整していくことが求められるんです。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- ASDのある人の感覚過敏・鈍麻は、しつけや努力の問題ではなく、生まれつきの脳の神経学的な特性です。
- 視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、固有受容覚、前庭覚の7つの感覚それぞれに、過敏さや鈍麻さが見られることがあります。
- 感覚過敏はメルトダウンの引き金に、感覚鈍麻は危険への気づきにくさや感覚探求行動につながりやすく、学習、対人関係、食事、睡眠など生活全般に大きな影響を与えます。
- 感覚の感じ方は日々変動するため、決めつけずに本人の状態を観察し、柔軟に対応を調整していくことが大切です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
感覚の違いというのは、目に見えないだけに、周りから理解されにくい苦しさがあります。
でも、その子が感じている世界を想像し、「しんどいんだな」と共感してあげることが、コミュニケーションの第一歩になるんじゃないかなと、僕は思います。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋గれば、僕もとても嬉しいです。