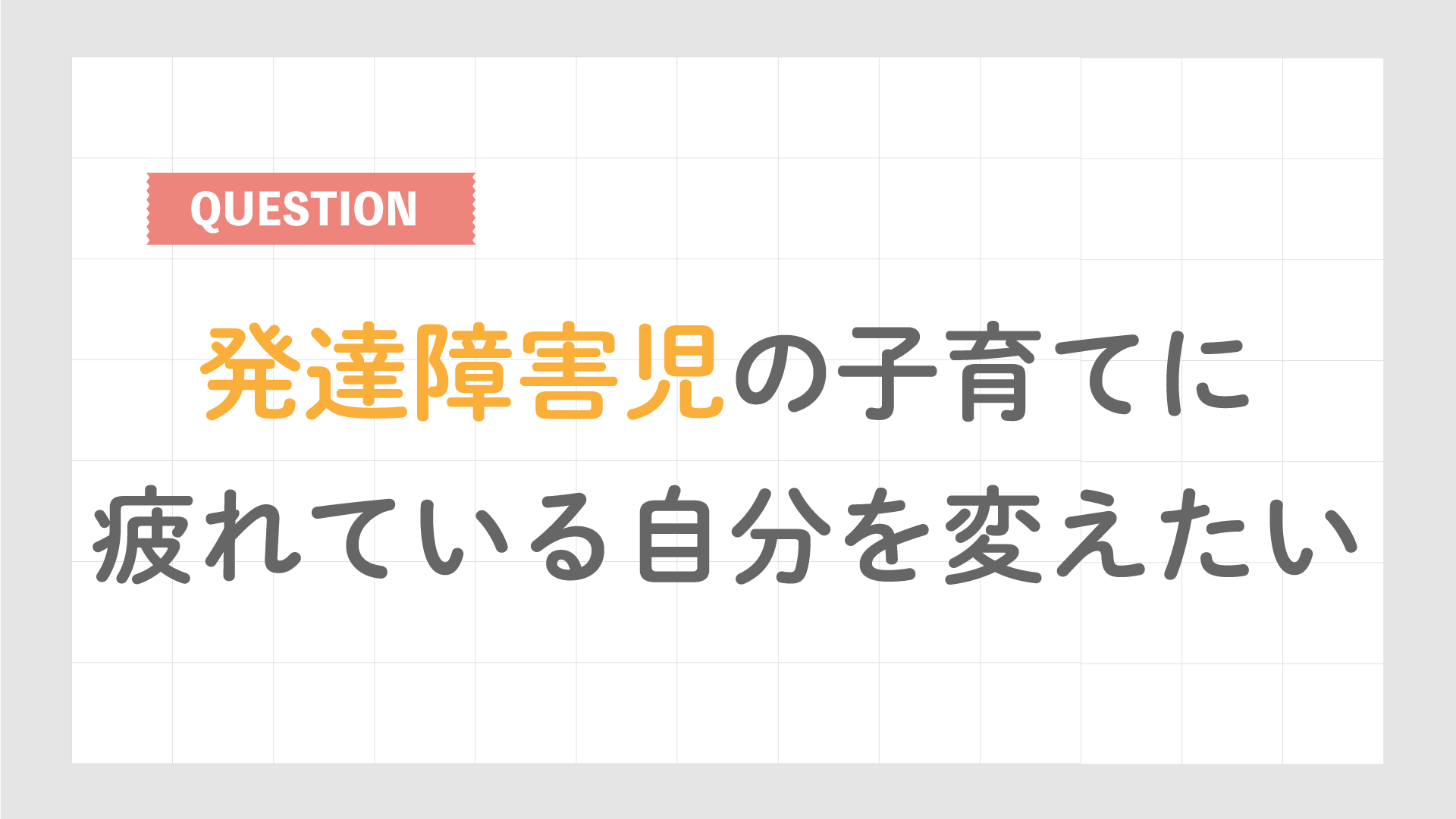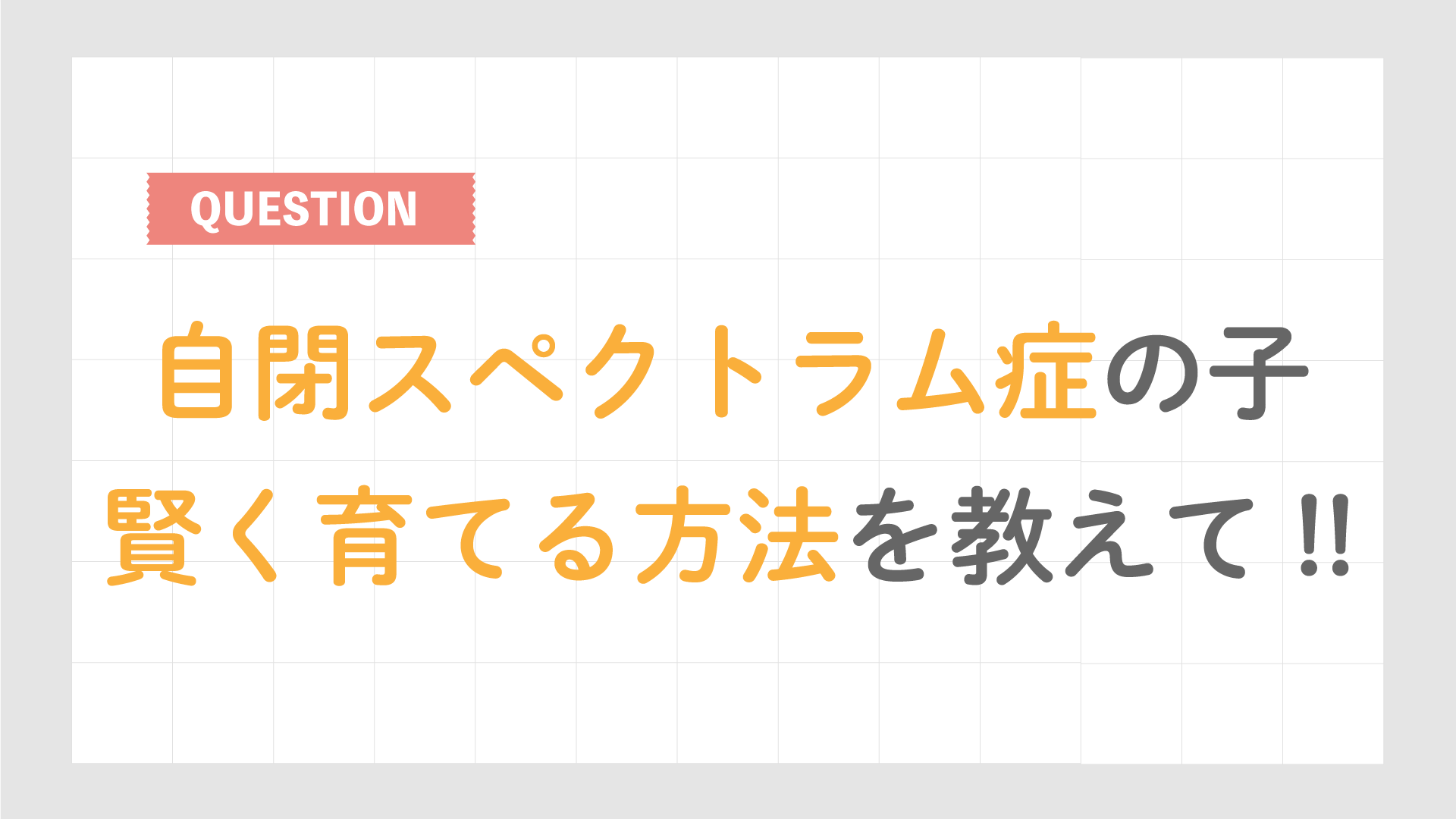境界知能とは? 7人に1人が抱える「支援をギリギリ受けられない」生きづらさと、年代別の困難を解説
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「境界知能(きょうかいちのう)」についてです。
境界知能とは? 7人に1人の「見過ごされた困難」
今日お話しする「境界知能」とは、知能指数(IQ)が70から84の範囲にある人のことを指します。
IQの平均は100とされていて、知的障害と診断される目安の一つが「IQ69以下」なんですね。境界知能は、その「知的障害」と「平均」の、まさに境界線上にいる方々のことなんです。
全人口の約14%、およそ7人に1人が該当すると言われています。これは、日本の人口に換算すると約1700万人。35人クラスなら、約5人が該当する計算になります。
支援をギリギリ受けられない、という問題
境界知能の何が一番問題なのかというと、一言でいえば「支援をギリギリ受けられない」ということです。
知的障害と診断されれば、「療育手帳」や「障害者手帳」の対象となり、幼少期の療育(発達支援)や、その後の就労支援など、様々な福祉サービスにつながることができます。
でも、境界知能の方々は、医学的な基準には満たないと判断されることが多いため、これらの支援制度から外れてしまうんです。
「IQ69」と「IQ70」で、知的能力にものすごく大きな差があるわけではないのに、制度の壁で支援が受けられず、結果として社会的に孤立したり、誤解されたりする大きな要因になっています。
教育や仕事、社会の仕組みの多くは、平均的な人を基準に設計されています。
そのため、クラスに5人いるかもしれない子どもたちは、その仕組みに合わずに苦しんでいる、というのが現状なのかなと感じます。
なぜ生きづらい? 境界知能の特性
境界知能の方々が抱える困難は、「努力が足りないから」では決してありません。その背景には、脳の情報処理に関する特性があります。
認知機能の特性(抽象的な思考・計画の苦手さ)
境界知能の方々は、抽象的な理解や計画に苦手さがあることが多いです。
「抽象的」というのは、目に見えない概念のことです。
例えば、言葉だけの指示や、複数の作業を同時に言われた時に混乱しやすかったりします。授業や仕事の作業スピードが、周りよりもゆっくりになる傾向もあります。

ゆう先生の補足解説:認知機能と「努力不足」ではない理由
「認知機能」とは、記憶、思考、理解、計算、学習、言語、判断といった、私たちが情報を取り入れて処理するための一連の脳の働きを指します。
境界知能の困難は、この認知機能の特性、つまり脳の情報処理の仕方が多数派と少し違うことに起因します。
本人は一生懸命頑張っているのに、情報処理が追いつかないのです。
これは「やる気の問題」や「努力不足」で解決できるものではなく、適切な環境調整や「構造化(分かりやすく手順を整えること)」が必要だ、という視点がとても大切です。
コミュニケーションの難しさ
人とのコミュニケーションにも難しさを抱えやすいです。
例えば、相手の表情や声のトーンから気持ちを読み取る、いわゆる「空気を読む」ことが難しかったり、逆に自分の気持ちを整理して言葉にするのが苦手だったりします。
質問された時にどう答えていいか分からず黙ってしまったり、間に合わない発言(TPOに合わない発言)をして誤解されてしまったり…。
その結果、友人関係ですれ違いが起きたり、孤立しやすくなったりすることもあります。
日常生活での課題(管理の難しさ)
日常生活でも、なんとなくは出来ているように見えても、ポカミスが多かったり、管理が難しかったりします。
- 金銭管理:支払いを忘れてしまう、計画的にお金を使えない。
- 時間管理:遅刻が続いてしまう。
- 健康管理:食事や体調の管理がうまくできない。
- 行政の手続き:複雑な書類の処理が一人でできない。
こういったことが苦手で、特に一人暮らしになると生活が破綻しやすい傾向があるとされています。

ゆう先生の補足解説:実行機能と抽象的思考
こうした日常生活の困難は、「実行機能」や「抽象的思考」の弱さが関係していると言われます。
- 抽象的思考:例えば「節約」や「健康」といった、目に見えない将来の目標を具体的にイメージする力です。
- 実行機能:これは「目的を達成する力」です。例えば「部屋を掃除する」という目的があった時、①まず本棚の漫画を片付けて、②次に掃除機をかけて…と計画を立て、それを実行に移す力です。
この機能が弱いと、掃除の途中で漫画を読み始めちゃって、気づいたら何時間も経っていた…ということが起こりやすくなります。
これは「だらしない」のではなく、「計画通りに実行するのが難しい」という特性なんです。
失敗体験による自己肯定感の低下
これらの特性によって、幼少期から失敗体験が多くなりがちです。
でも、周りからは「(障害がない)普通の子」として見られるため、「なんでこんなこともできないの?」と責められてしまうことも少なくありません。
失敗が続き、責められることで、ご本人も「どうせ自分はできないんだ」と自分を責めるようになり、プレッシャーに弱くなったり、新しいことへの挑戦を避けたりするようになりがちです。
【年代別】境界知能が直面する困難
この生きづらさは、ライフステージごとに形を変えて現れます。
幼児期・学童期(学習と人間関係のつまずき)
幼少期は、友達の気持ちがうまく読み取れず、いつも同じようなパターンで喧嘩になったり、トラブルになったりすることがあります。
そして、一番分かりやすくつまずきが出るのが、小学校中学年くらいからの勉強です。
足し算はできたけど、2桁の筆算や、掛け算・割り算が出てきて、勉強のレベルが上がった途端に対応できなくなる、文章読解が苦手…といった形で現れます。
ただ、これも「知的障害」の診断ラインまではいかないことが多いため、「勉強が苦手な子」「努力が足りない子」として見過ごされがちです。
思春期以降(進路の悩みと劣т感)
中学生、高校生になると、勉強はさらに難しくなります。
「自分は何が得意で、何が苦手なのか」を自分で把握することが難しく、進路選択の時期になっても、将来のイメージがぼんやりとして答えられない、ということもあります。
周りと自分を比較して強い劣等感を抱き、「学校に行きたくない」と感じることも増えてきます。この時期は、本人も誰に相談していいか分からず、親御さんに感情をぶつけることでしかSOSを出せない、という場合も多いですね。
成人期(仕事のトラブル)
成人してからの最大の困難は、仕事です。
まず、就職活動でつまずきます。書類作成や面接で、自分が何をしたいのか、何ができるのかをうまくアピールできません。
運良く就職できたとしても、今度は職場の「暗黙のルール」や、マニュアルにない人間関係でつまずきます。業務の習得が他の人よりゆっくりだったり、コミュニケーションで誤解を生んだりして、結果として短期離職を繰り返してしまう人も少なくないのが現状です。
中高年期(社会的孤立と生活管理)
成人後も親元を離れられず、親御さんと一緒に生活している方も多いです。親御さんが食事や金銭、健康の管理をしてくれている間は良いのですが、問題は親御さんが高齢になったり、亡くなられたりした後です。
急に一人で全てを管理しなければならなくなり、金銭管理や健康管理が破綻してしまったり、社会的に孤立してしまったりするリスクが高まります。
発達障害との併発(問題の複雑化)
さらに問題を複雑にするのが、発達障害(ASD:自閉スペクトラム症やADHD:注意欠如・多動症)との併発です。
境界知能であり、かつ「ASDやADHDの特性も『ギリギリ診断基準には満たない』レベルで持っている」というケースも非常に多いんです。
そうなると、困難はさらに複雑化するのに、知的障害の診断も、発達障害の診断もつかないため、さらに支援からこぼれ落ちやすくなってしまいます。
大切なのは「誤解」をなくし「相談」すること
境界知能も、発達障害もそうですが、外見では困難さが分かりにくいんですよね。だからこそ、「性格のせいだ」「やる気の問題だ」と誤解され、本人たちが傷ついています。
もし、お子さんやご自身のことで「努力しても、どうしても変わらない」「生きづらい」と感じることがあれば、それは決して本人のせいではありません。
「病院に行ったけど、様子を見ましょうと言われた」という方もいるかもしれません。確かに、今の制度では境界知能の方が公的な療育(支援)を受けるのは難しい場合もあります。
でも、昔と比べれば、今は様々なサポートが増えています。
公的支援でなくても、例えば学習支援をしてくれる場所や、ハローワークの職業訓練、同じ悩みを持つ親の会など、何かしらサポートしてくれる場所、話を聞いてくれる場所はあるはずです。
困っていたら、どうか一人で抱え込まず、誰かに「助けて」と声をかけてみてほしいなと思います。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- 境界知能(IQ 70-84)は、全人口の7人に1人と非常に多くの方が該当しますが、「知的障害」と診断されないため公的支援を受けにくいという課題があります。
- その困難は「努力不足」ではなく、抽象的な思考や計画、非言語的なサインの読み取りなどが苦手という「脳の情報処理特性」によるものです。
- 学習、就職、生活管理など、生涯にわたって困難が続きやすく、周りから誤解されて自己肯定感が下がりやすいため、一人で抱え込まず早期に誰かに「相談する」ことが非常に重要です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
境界知能やグレーゾーンの困難は、周りから「頑張ればできそう」に見えてしまうため、本人も周りも疲弊しやすい、という姿を現場でもよく見ます。
ご本人も、お父さんお母さんも、もう十分努力されていると思います。まずはその特性を理解し、ご自身ができること、ご自身に合う環境を見つけるという視点を持ってほしいなと思います。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。