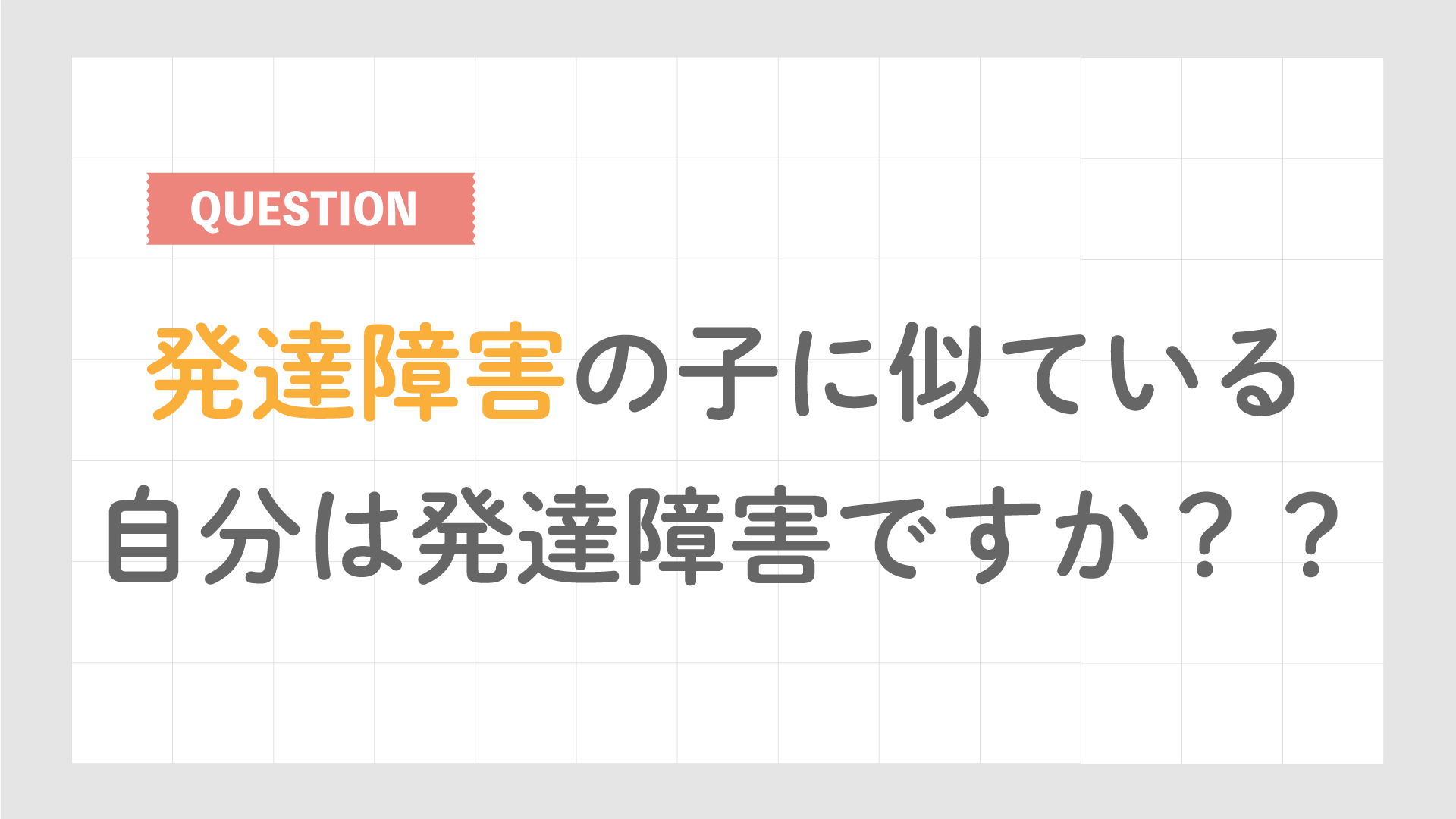知的障害児の「困った行動」には理由がある! ABC分析で読み解く4つの目的と、家庭でできる具体的な行動支援
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「軽度・中等度の知的障害があるお子さんの『困った行動』への支援」についてです。
お子さんの特定の行動に対して、「どうしてこんなことをするんだろう?」「何度注意してもやめてくれない…」と、対応に困ってしまうことはありませんか?
実は、それらの行動には、本人なりの切実な「目的」が隠されていることが多いんです。
「困った行動」は、本人なりのコミュニケーション
まず一番にお伝えしたいのは、僕らが「困った行動」や「問題行動」と呼んでいるものは、本人なりの目的を持ったコミュニケーションの手段である、ということです。
もちろん、やり方は間違っているかもしれません。でも、どうにかして自分の気持ちや思いを伝えようとした結果が、その行動として現れているんです。
特に知的障害があるお子さんの場合、自分でも「なんでこの行動をしちゃうのか」が分かっていないことも多いんですよね。
だからこそ、周りの大人がその行動の意味をよく理解して、サポートしてあげることがとても重要になります。
行動を理解するカギ「ABC分析」とは?
行動を理解するためには、その行動が起きた「瞬間」だけを見るのではなく、行動の「前後」に現れる流れを見ることがすごく大事です。
例えば、「人を叩いてしまった(行動)」という事実だけを見れば、それは悪いことです。
でも、その「前」に「お友達から悪口を言われた(直前の状況)」があったとしたら、叩いた理由は理解できますよね(もちろん叩くことはいけませんが)。
この行動の前後関係を整理し、支援に活かす方法が「ABC分析」です。

ゆう先生の補足解説:ABC分析とは?
「ABC分析」は、応用行動分析(ABA)という心理学の手法で使われる考え方です。
- A (Antecedent) = 先行事象(行動が起きる直前の状況・きっかけ)
- B (Behavior) = 行動(対象となる具体的な行動)
- C (Consequence) = 結果(行動の直後に起こったこと)
この3つの流れで行動を捉えることで、「なぜその行動(B)が起きたのか?」「その行動(B)によって、本人にとって
良い行動も悪い行動も、このパターンに当てはめることができます。
例えば、よくある「負けると癇癪を起す」パターンで見てみましょう。
- A(先行事象):じゃんけんで負けた
- B(行動):泣きながら怒る(癇癪)
- C(結果):(周りが困って)もう1回じゃんけんをさせてもらえた
この場合、お子さんにとっては「泣きながら怒る(B)」ことで、「もう1回やらせてもらえる(C)」という良い結果が得られたことになります。
すると、脳は「じゃんけんで負けたら、泣きながら怒ればいいんだ」と学習してしまい、同じ行動(B)が定着しやすくなってしまいます。
ABC分析でこうして整理することで、僕ら支援者は「じゃあ、Cの結果を変えよう(もう1回やらせない)」とか、「Aの段階で工夫しよう(負ける可能性を先に伝えておく)」といった、具体的な対策を立てやすくなるんです。
問題行動の「4つの機能(目的)」
多くの場合、問題行動(B)は、本人にとって何らかの目的(メリット)があるからこそ起きています。
その主な目的(機能)は、大きく分けて以下の4つに分類されることが多いです。
- 注目(Attention):大人や友達の注意を引きたい
- 要求(Tangible):欲しい物や、やりたい活動がある
- 回避(Escape):嫌な課題や場所、人から逃れたい
- 感覚刺激(Sensory):行動そのものから得られる感覚的な快感・不快感の低減
今日はこの4つの機能別に、どういう支援の工夫があるのかを解説していきます。
【具体策】4つの機能別・支援の工夫
①「注目」が目的の場合
親や先生が他の子や兄弟にかかりきりになっている時などに、わざと大きな声を出したり、悪ふざけをしたりして、自分に注意を向けさせようとする行動です。認めてほしい気持ちが強い子に多いですね。
【支援の工夫】刺激の強弱を使い分ける
基本は「良い行動を増やし、悪い行動を減らす」アプローチです。
- 悪い行動(注目を得るための行動)をした時:あえて反応しない、「能動的な無視」をします。「大きな声を出しても、誰も注目してくれない(メリットがない)」と学習してもらうためです。ここで声をかけたり叱ったりすると、たとえネガティブな反応でも本人にとっては「注目してもらえた」というメリットになってしまうので、グッとこらえます。
- 良い行動(静かに待てた、など)をした時:すかさず「強烈に褒め」ます。「静かに待っていたら、すごく褒めてもらえた!(メリットがあった)」と学習してもらうためです。
この差をはっきりさせることが大事です。また、日頃から信頼関係を築き、「悪いことをしなくても、あなたのことを見ているよ」という安心感を与えてあげることも重要ですね。
②「要求」が目的の場合
欲しいおもちゃがある、やりたいことがある、という時に、それが手に入るまで大泣きしたり、癇癪を起こしたり、物を壊したりする行動です。
知的障害があるお子さんの場合、見通しを持つことや「我慢する」ということが苦手な傾向があるため、この要求行動が激しく出てしまうことがあります。

ゆう先生の補足解説:要求(要求獲得)
これは「欲しい」という、ある意味で非常に原始的な欲求です。それ自体は悪いことではありません。
問題なのは、その「伝え方」です。癇癪や暴力で要求を通す体験を繰り返すと、それが一番簡単で確実な方法だと学習してしまいます。
特に体が大きくなってからこの行動パターンを変えるのは非常に困難です。
だからこそ、幼少期(特に脳が発達する6歳頃まで)に、「癇癪ではなく、言葉やジェスチャーで伝える」という“正しい伝え方”を根気強く教えていく訓練がとても大切になります。
【支援の工夫】正しい伝え方(モデル)を示し、できたら褒める
要求の癇癪が起きた時、僕はよくこうしています。
- ギャー!と叫んでいる間は、あえて無視(反応しない)をします。
- 一瞬でも静かになった瞬間に、すかさず「ギャーじゃなくて、『〇〇が欲しいです』って言うんだよ」と、**正しい伝え方(モデル)**を教えます。
- 最初はできませんが、何ヶ月も繰り返すうちに、少しずつ言えるようになってきます。
- 少しでも正しい方法で伝えられたら、ものすごく褒めてあげます(要求に応えるかどうかは別問題として、まず「伝え方」を褒めます)。
時間はかかりますが、これを繰り返すことで、正しい要求の仕方を定着させていきます。
③「回避・逃避」が目的の場合
僕の印象では、知的障害があるお子さんに一番多いかもしれないのが、この「回避」です。
嫌な課題(勉強など)、苦手な状況、特定の場所や人から逃れるために、その場からいなくなったり、分かりやすいウソをついたり、別の行動を起こしたりします。

ゆう先生の補足解説:回避(逃避)と環境調整
嫌なことから逃げたい、というのは当然の感情です。
特に知的障害があるお子さんは、過去の失敗体験(勉強でうまくできなかった、怒られた)が強い恐怖として残りやすく、似た状況になるだけで「もうやりたくない!」と強く回避しようとすることがあります。
この場合、「頑張れ!」と無理やり向き合わせるのは逆効果です。本人の恐怖に根付いていることが多いので、まずはその「恐怖」や「嫌だという気持ち」を取り除いてあげる「環境調整」が最優先となります。
【支援の工夫】環境調整と価値観の変化
まずは、なぜ逃げたくなったのか、ABC分析でその条件をしっかり記録・分析します。
その上で、環境調整を行います。例えば、勉強が嫌なのではなく、その場の「音」が嫌(感覚過敏)だったのかもしれません。
その場合は静かな場所を用意します。課題が難しすぎるなら、もっと簡単なステップ(スモールステップ)から始めます。
いきなり参加させるのではなく、まずはその活動の「価値観」を変えるアプローチも大事です。「勉強は楽しいものだ」「学校は安心できる場所だ」と思ってもらえるよう、視覚的な支援を使ったり、先生が一緒に手をつないで行ったりしながら、少しずつ成功体験を積ませていくことが大切です。
④「感覚刺激」が目的の場合
これは特に自閉スペクトラム症(ASD)を併発しているお子さんに多いですが、行動そのものから得られる感覚的な快感を得るため(または不快感を減らすため)の行動です。
例えば、その場でくるくる回る、手をヒラヒラさせる、椅子をガタガタさせる、などです。
一番気をつけなければいけないのが、「頭打ち(頭を壁などに打ち付ける)」などの自傷行為です。
これは、嫌なことや不快な感覚があった時に、別の強い痛み(頭を打つ痛み)でその不快感を忘れよう(上書きしよう)としている、本人なりの安定行動である場合があります。

ゆう先生の補足解説:感覚刺激(自己刺激)と自傷行為
これらは、本人が自分自身を落ち着かせたり、不安を解消したりするために行っている「自己刺激」の一種であることが多いです。
そのため、無理やり止めてしまうと、本人は安定を保つ手段を失い、かえってパニックになってしまうことがあります。
ただし、頭打ちなどの自傷行為は、当然ながら非常に危険です。エスカレートする前に、必ず専門家(医師や療育機関)に相談してください。
【支援の工夫】刺激をOKにする時間・場所・代替手段を作る
支援の基本は、「止める」のではなく「コントロールする」ことです。
- 刺激を入れてもOKな場所や時間をあらかじめ決めておき、リフレッシュできるようにする。
- 代替刺激を見つける。例えば、頭を打つ代わりに、クッションを叩く、ハンドスピナーを回す、特定のタオルを持つと落ち着くならそれを持たせる、など、より安全な方法で感覚欲求を満たせるように工夫します。
早期支援と保護者の心のケア
ここまで色々な支援方法をお話ししてきましたが、これをご家庭の中だけで行うのは本当に大変なことだと思います。
だからこそ、早期支援、つまり早めに療育などの専門機関に相談してほしいなと思います。
特に軽度知的障害の場合、適切な支援がないまま成長すると、本人の自己肯定感が下がり、うつや不安障害といった「二次障害」に繋がってしまうリスクもあります。
そうなる前に、専門家と一緒に支援方法を考えていくことが大切です。

ゆう先生の補足解説:二次障害とは?
「二次障害」とは、生まれ持った発達障害や知的障害(一次障害)そのものではなく、その特性を周囲に理解してもらえなかったり、
失敗体験を繰り返したりすることで、後天的に発症する心の問題(うつ、不安障害、不登校、非行、依存症など)を指します。
早期から適切な支援(療育)を受け、本人が「自分はダメじゃないんだ」と感じられる環境を整えることは、この二次障害を予防するために非常に重要です。
そして、保護者の方へ。障害があるお子さんを支援していると、心が辛くなる時が絶対にあると思います。
不安や混乱、孤独感を感じるのは、それだけお子さんのことに真剣に向き合っている証拠です。
でも、それをどうか一人で抱え込まないでください。話せる相手や専門家を頼って、ご自身の生活やリフレッシュする時間も大切にしてください。
保護者の方が心に余裕を持つことが、結果としてお子さんへの良い支援に繋がっていく部分も多いと僕は感じています。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- 知的障害があるお子さんの「困った行動」は、本人なりのコミュニケーション手段です。
- その行動を「A(直前)」「B(行動)」「C(直後)」で分析する「ABC分析」が、原因と目的を探るのに有効です。
- 行動の主な目的は「注目」「要求」「回避」「感覚刺激」の4つがあり、それぞれに適した支援(良い行動を褒めて強化する、環境を調整する、代替手段を用意するなど)を行うことが大切です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今回お話しした内容は、すぐに結果が出るものではなく、時間も根気も必要です。焦らず、できることから一歩ずつ始めてみてください。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。