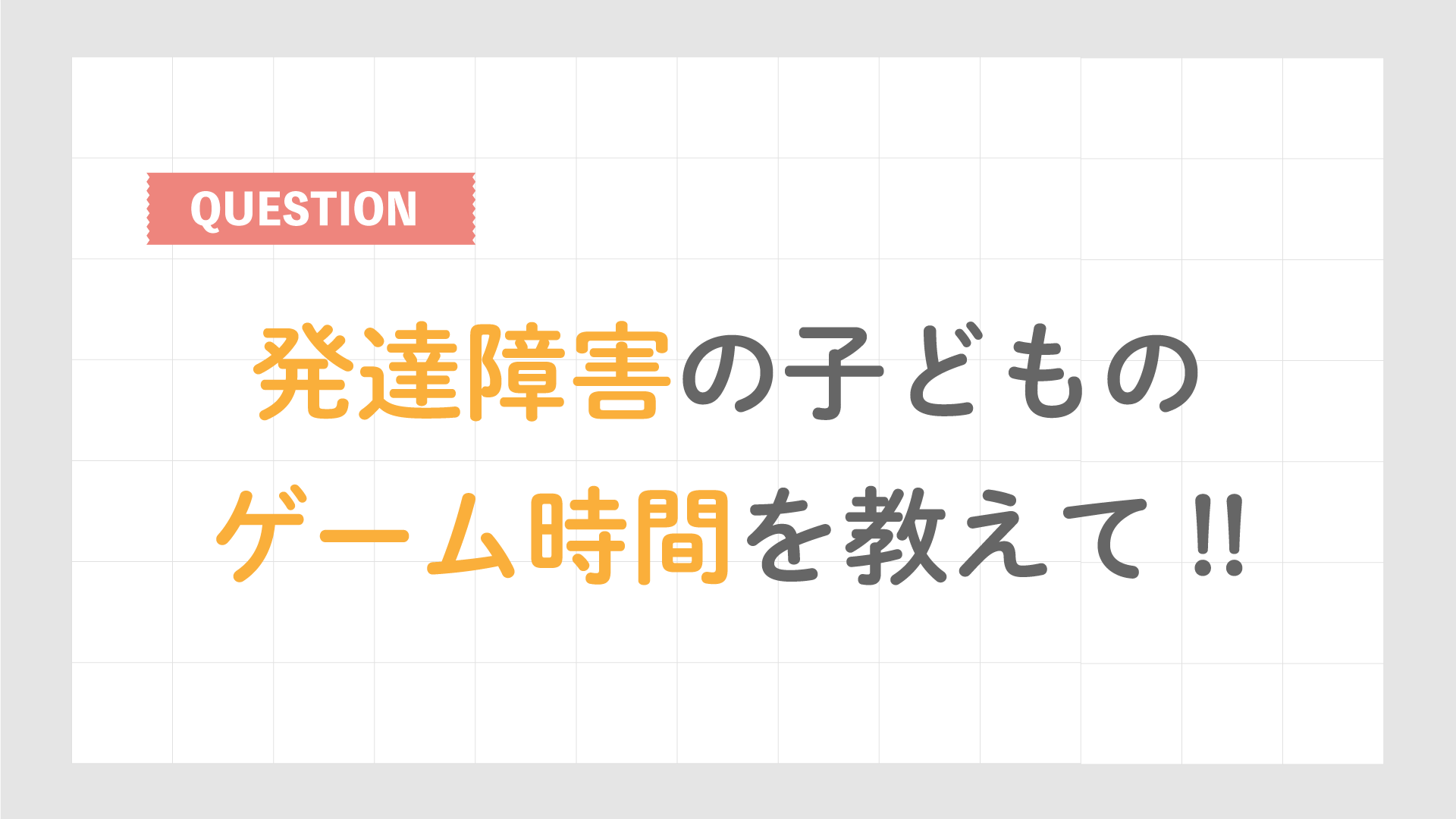軽度知的障害を見逃さないで!IQだけじゃない「適応機能」のサインと家庭でできること|富山の現役指導員が解説
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「軽度知的障害を見逃さないために知っておきたいこと」についてです。
軽度知的障害が見過ごされやすい「理由」
まず、皆さんに知っておいてほしいことがあります。それは、軽度知的障害は、知的障害の中で最も多いにも関わらず、見過ごされやすいという現実です。
統計のマジック?
厚生労働省の調査などを見ると、療育手帳を取得している方の割合としては、中度や重度の方が多く見えることがあります。メディアで取り上げられるのも、そういったケースが多いかもしれません。
でも、これはあくまで「手帳を取得した人」の統計なんです。
軽度知的障害の場合、日常生活がある程度送れているため、保護者の方も気づかなかったり、「手帳は必要ない」と判断したりするケースが多いんですよね。
世界的な基準(例えばDSM-5など)で見ると、知的障害と診断される人の約8割以上は軽度だと言われています。
つまり、実は最も身近な存在であるにも関わらず、その困難さが見えにくい、というのが軽度知的障害の特徴なんです。

ゆう先生の補足解説:DSM-5とは?
「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)」の略称です。
世界中の精神科医や心理専門職などが、共通の基準で精神疾患(発達障害や知的障害も含む)を診断するために広く用いられているマニュアルです。知的障害の診断基準もここに記載されています。
幼少期は「問題」が見えにくい
特に、未就学の時期(幼児期)は、軽度知的障害の特性が見えにくいことが多いです。
なぜなら、周りの定型発達のお子さんたちも、まだ成長途中で、できること・できないことの差がそれほど大きくないからです。
軽度知的障害のお子さんは、日常生活スキル(着替えや食事など)は比較的できることも多いので、パッと見ただけでは判断が難しいんですよね。
「周りに合わせる力」が発見を遅らせる?
軽度知的障害のある方は、経験を通して学んだり、周りの状況に合わせて行動したりする力(適応する力)を持っていることがあります。
例えば、先生の指示がよく分からなくても、周りのお友達の動きを見て真似することで、なんとなく集団に溶け込めてしまう。
小さい頃は、周りの大人が「しょうがないなあ」と手伝ってくれることも多いので、本人の困難さが表面化しにくいんです。
でも、学年が上がり、勉強が難しくなったり(抽象的な思考が求められたり)、人間関係が複雑になったりすると、これまで通用していた「周りに合わせる」だけでは乗り越えられない壁にぶつかります。
そこで初めて困難さが顕在化し、「もしかして…」と気づかれるケースが多いんです。
学校生活で見られるサイン
では、具体的に学校生活では、どのようなサインが見られるのでしょうか。
学習面でのサイン:抽象的なことが苦手
- 読み・書き・計算などの基礎学力の習得がゆっくり。特に、漢字を覚えるのが苦手(形をなんとなくで覚えてしまい、間違いが多いなど)。
- 抽象的な概念の理解が難しい。例えば、「時間」(時計を読む、時間の感覚)、「お金」の計算や価値、「面積」「体積」といった目に見えない概念。
- 複数指示の処理が苦手。「〇〇して、次に△△して、最後に□□して」といった複数のステップがある指示を一度に理解し、実行するのが難しい。
- 板書を書き写すのが遅い、または書き写せても内容を理解していない。
学習面での困難だけだと、発達障害のSLD(限局性学習障害)との区別がつきにくい場合もあります。
対人関係でのサイン:同年代とのズレ
- 同年代の子どもと遊ぶより、年上や年下の子と関わることを好む傾向がある。(同年代の会話のテンポや暗黙のルール、比喩表現などが理解しにくいため、より具体的で分かりやすい関わりができる年下の子や、合わせてくれる年上の子の方が安心できるのかもしれません)
- 場の空気を読むことや、冗談・皮肉の理解が難しいため、意図せず相手を怒らせたり、自分が傷ついたりすることがある。
- 他の子と違う言動から、敬遠されたり、からかわれたり、いじめの対象になってしまったりすることがある。
「ちょっと違う」という微妙なズレが、周りの子どもたちからの孤立を招いてしまうことがあるのが、とても悲しい現実です。
行動面でのサイン:計画性のなさや不器用さ
- 忘れ物や失くし物が極端に多い。
- 計画的に物事を進めるのが苦手(例:宿題を計画的にできない、時間割を揃えられない)。
- 運動面での不器用さが見られることがある(例:ボール運動、ハサミを使う、箸を使うなど)。
- 集中力が続かないように見える(授業中にぼーっとしているなど)。
これらの行動面の特徴は、ADHD(注意欠如・多動症)と併存している場合も多いので、一概に軽度知的障害だけのサインとは言えません。
家庭生活で見られるサイン
学校だけでなく、お家での生活の中にもサインは隠れています。
生活スキルでのサイン:自己管理の難しさ
- 金銭管理が苦手:お小遣いを計画的に使えず、すぐ使い切ってしまう(大人になると給料を使い果たしてしまうことも)。
- 時間管理が苦手:時計が読めても、時間の感覚が掴めず、遅刻が多い。予定を立てて行動するのが難しい。
- 家事の管理が苦手:決まった手順の簡単な家事(例:洗濯物をカゴに入れる)はできても、複数工程が必要な料理や、計画的な買い物、部屋全体の整理整頓などが難しい。指示は1つずつ具体的に出す必要があります。
- 身だしなみや衛生観念への意識が低いことがある(例:髪がボサボサ、同じ服ばかり着る、鼻をかんだティッシュをポケットに入れっぱなしなど)。
コミュニケーションでのサイン:一方的・言葉通り
- 会話が一方的になりやすい。一生懸命話してくれるけれど、話が噛み合わなかったり、聞きたいことと違うことを話し続けたりすることがある。(※ASDの特性と似ていますが、少しニュアンスが違うことが多いです)
- 言葉を文字通りに受け取ってしまう。比喩(例:「頭がおかしくなるくらい頑張った」→本当に頭がおかしくなった?)、皮肉、冗談、社交辞令などが理解できず、誤解やすれ違いが生じやすい。
- 人の話を鵜呑みにしやすい。状況判断や、相手の意図を推測するのが苦手なため、騙されやすかったり、利用されやすかったりするリスクがある。これは大人になってからの金銭トラブルなどにも繋がりかねない、心配な点です。
行動面でのサイン:ルーティンや疲れやすさ
- 物を元の場所に戻す、整理整頓された状態を維持するのが難しい。
- 日常生活のルーティンに従うのが苦手(例:帰宅後の手洗い・うがい・着替えなどの一連の流れが身につかない)。
- 疲れやすい。学校から帰ってくるといつもゴロゴロしている、集中力が短時間しかもたないなど。
ここでも大事なのは、「部分的」な苦手さではなく、生活全般の様々な場面で「全体的に」 어려움 (difficulties) が見られる場合、軽度知的障害の可能性を考えてみる、ということです。
困難さの背景にある「認知特性」
では、なぜこのような困難さが生じるのでしょうか。その背景には、いくつかの認知的な特性が関係していると考えられています。
1. ワーキングメモリの弱さ
情報を一時的に記憶(保持)しながら、同時に別の作業(処理)を行う脳の働きのことです。「脳のメモ帳」や「脳の作業台」に例えられます。
軽度知的障害の場合、この「メモ帳の容量が小さい」または「作業台が狭い」ような状態であると考えられます。
そのため、一度にたくさんの情報を処理したり、複数の指示を覚えたりするのが難しいんです。
長い説明を聞いている途中で最初の内容を忘れてしまったり、計算の途中で数字を覚えていられなかったりするのは、このワーキングメモリの弱さが影響している可能性があります。
2. 実行機能の問題
目標達成に向けて、計画を立て、行動を調整し、状況に合わせて柔軟に対応する、脳の「司令塔」のような機能です。
衝動を抑えたり、注意を切り替えたり、優先順位をつけたりする力も含まれます。
この実行機能が弱いと、計画的に物事を進めたり、段取り良く作業したり、状況に合わせて行動を変えたりすることが難しくなります。
忘れ物が多い、時間管理ができないといった問題にも繋がります。
3. 抽象的思考の困難さ
目に見えない概念(時間、お金、面積、友情、ルールなど)や、具体的な経験に基づかない事柄について考える力のことです。
軽度知的障害の場合、具体的なものや経験に基づいて考えることはできても、この目に見えない抽象的な概念を理解したり、イメージしたりすることが苦手な傾向があります。
算数で文章題が解けなかったり、国語で登場人物の気持ちを想像するのが難しかったり、社会のルールやマナーの意味が理解できなかったりするのは、この抽象的思考の困難さが関係している可能性があります。
「なんで勉強するの?」と聞かれても、将来の自分と結びつけて考えることが難しい、というのもこれにあたります。
特性は相互に関連している
これらの「ワーキングメモリ」「実行機能」「抽象的思考」は、それぞれ独立しているわけではなく、互いに関連し合っています。
例えば、計画を立てる(実行機能)ためには、目標や手順を覚えておく力(ワーキングメモリ)が必要です。
また、ルールを守る(実行機能)ためには、そのルールという抽象的な概念を理解し(抽象的思考)、覚えておく(ワーキングメモリ)必要があります。
これらの認知機能が全体的に少しずつ弱いことが組み合わさって、軽度知的障害の様々な困難さとして現れてくる、と考えることができます。
早期対応の重要性
軽度知的障害は、見過ごされやすいからこそ、早期に気づき、対応していくことがとても大切です。
「様子を見ましょう」と言われているうちに、本人は「自分はできない」という失敗体験を重ね、自己肯定感を失っていきます。
もし、「うちの子、もしかして…?」と感じることがあれば、どうか「軽度だから大丈夫」と思わずに、専門機関(病院、地域の相談窓口、学校など)に相談してみてください。
違ったらそれで良いんです。でも、もし支援が必要な状態であれば、早くから適切な関わり方を知ることで、本人の生きづらさを減らし、持っている力を伸ばしていくことができます。
まとめ
今日の記事では、見過ごされやすい「軽度知的障害」について、その理由や具体的なサイン、背景にある認知特性について解説しました。
- 軽度知的障害は、知的障害の中で最も多い(約8割)にも関わらず、幼少期には困難が見えにくく、周りの工夫や本人の頑張りで乗り越えられてしまうため、見過ごされやすいという特徴があります。
- 学校生活(学習、対人関係、行動)や家庭生活(生活スキル、コミュニケーション)の中に、IQだけでは分からない具体的なサインが現れます。「全体的に」困難さが見られるかがポイントです。
- その背景には、ワーキングメモリ、実行機能、抽象的思考といった認知機能の弱さがあり、これらが複合的に影響し合っています。
- 見過ごされやすいからこそ、早期にサインに気づき、専門機関に相談し、適切な支援につなげることが、本人の自己肯定感を守り、将来の可能性を広げるために非常に重要です。
結論:読者へのメッセージ
軽度知的障害は、「できないこと」ばかりではありません。「できること」「得意なこと」もたくさんあります。
大切なのは、その子の特性を正しく理解し、「できないこと」は環境調整や周りのサポートで補いながら、「できること」に目を向けて、自信を育ててあげることです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。