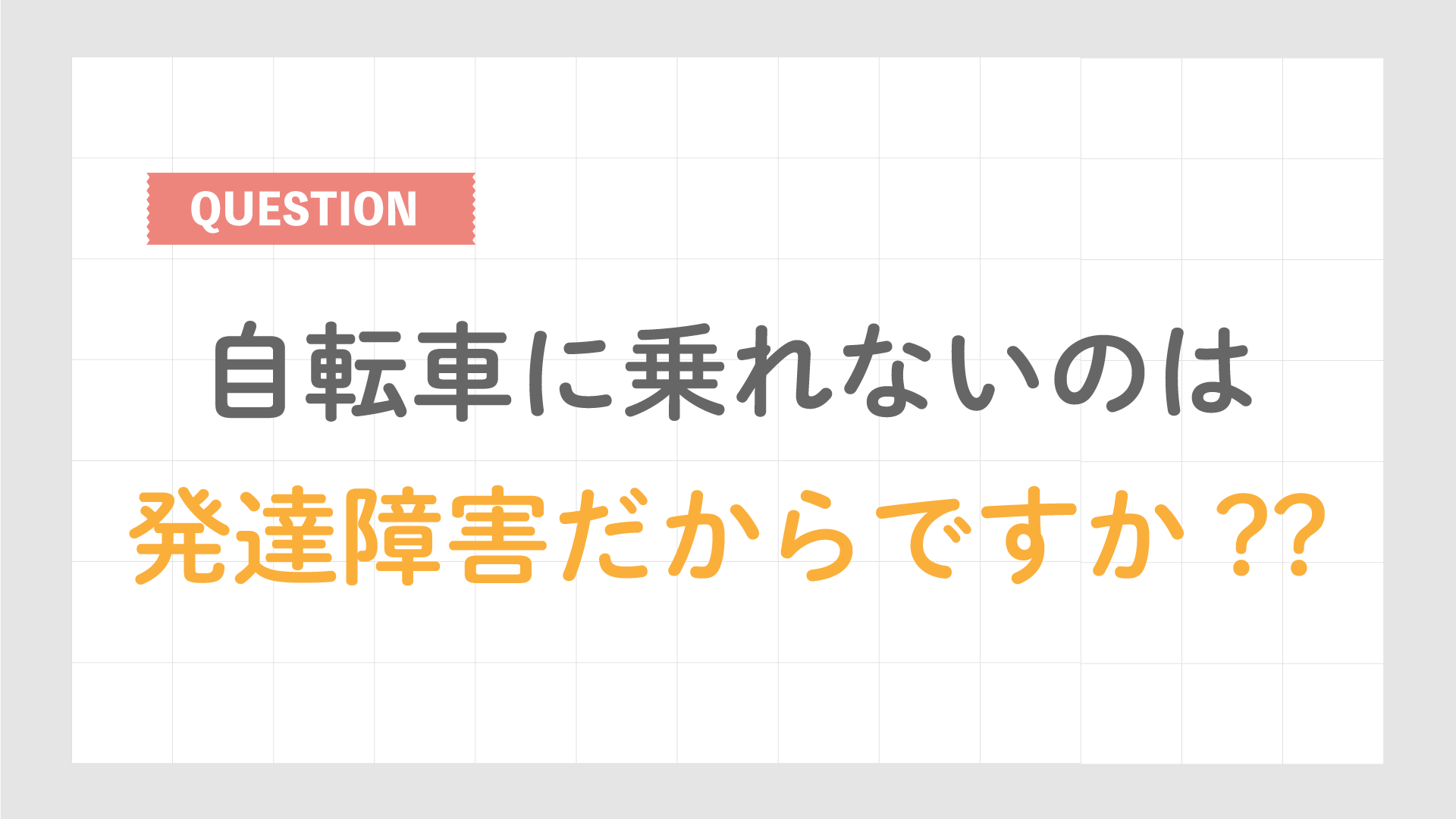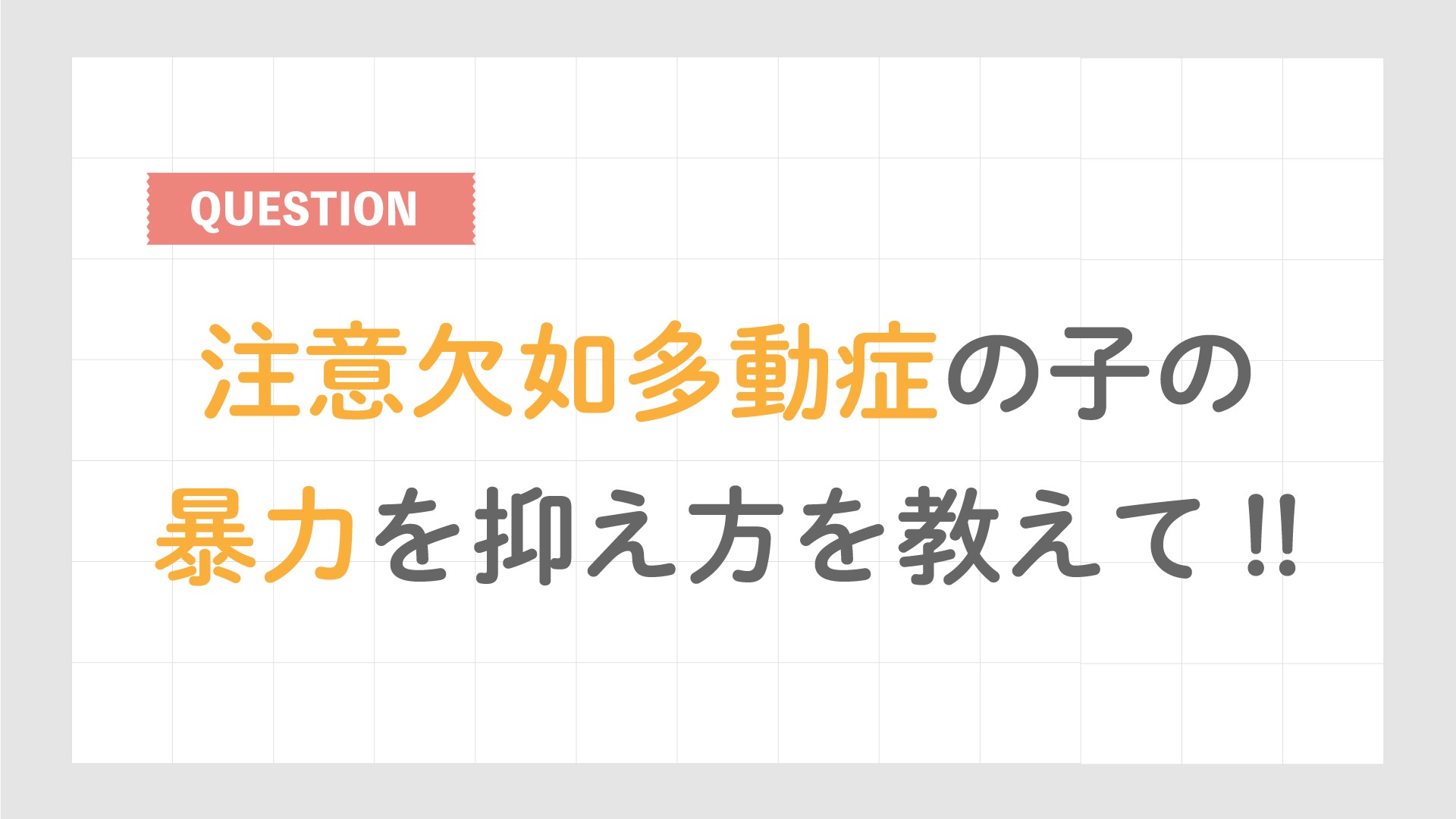IQだけじゃない!知的障害の理解を深める「適応行動(生きる力)」とは?|富山の現役指導員が解説
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、知的障害のシリーズ第1回目として、「IQだけでは測れない“適応行動”」についてです。
知的障害とは?~3つの指標で理解する~
今日は、まず「知的障害とは何か?」という基本的な部分と、特に誤解されやすいIQとの関係についてお話ししますね。
知的障害(ID: Intellectual Disability)とは、すごくシンプルに言うと、知的機能の制約と、それが日常生活へ影響していること、そしてそれが発達期(18歳未満)に現れる、という3つの基準を満たした場合に診断されるものです。
日本の公的な定義でも、
- 知的機能に制約があること
- 発症時期が18歳未満であること
- 適用機能(社会生活や日常生活への適応)に支障が出ているため、支援が必要な状態であることこの3つを総合して診断される、とされています。
大事な視点:「個人」だけでなく「環境との相互作用」
ここで、すごく大事なことをお伝えしたいんです。
この定義を見ると、「支援を要する状態」とありますよね。これはつまり、知的障害は単に個人の能力の問題だけではない、ということです。
本人の知的機能に課題があったとしても、それだけで知的障害と診断されるわけではありません。
その特性と、周りの環境(日常生活や社会生活)との相互作用によって困難が生じ、支援が必要になっている状態。これが、知的障害を捉える上でとても大切な視点なんです。
だから、「IQが低い=知的障害」と単純に捉えるのではなく、「その人が置かれている環境の中で、どういう困難が生じているか」を見ていく必要があるんですよね。
発達障害との併存も
また、知的障害は「神経発達症群(神経発達障害)」の一つであり、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)といった他の発達障害と併存(へいぞん:併せ持つこと)することも少なくありません。
そうなると、困難さの原因が知的障害によるものなのか、ASDやADHDの特性によるものなのか、見分けるのが難しくなり、支援がより複雑になることもあります。
だからこそ、ご家庭だけで抱え込まず、専門家(お医者さんや療育施設の先生など)と連携していくことが大切になってくるんですね。
IQ(知能指数)の役割と限界
知的障害の話をするとき、どうしても「IQ」の数値が注目されがちです。まず、このIQについて正しく理解しておきましょう。
IQ(知能指数)とは、推論力、学習能力、問題解決能力などを、標準化された検査(テスト)によって数値化したものです。同年齢の集団の中で、その子の知的な発達がどのくらいの位置にあるかを相対的に示します。平均は100です。
あ

ゆう先生の補足解説:IQ検査の種類
子どものIQを測る検査として代表的なものに、「WISC(ウィスク)検査」と「田中ビネー知能検査」があります。
- WISC検査:言語理解、知覚推理(目で見て考える力)、ワーキングメモリー(情報を一時的に記憶し処理する力)、処理速度(作業の速さ)など、複数の側面から認知特性の「デコボコ」を詳しく見ることができます。発達障害の特性理解にもよく用いられます。
- 田中ビネー知能検査:年齢に応じた課題をクリアしていくことで、全体的な知的発達の水準(精神年齢)を捉えやすい検査です。
これらの検査でIQがおおむね70以下の場合、知的障害の診断基準の一つを満たすことになります。重症度によって、さらに軽度・中度・重度・最重度に分類されます。
- 軽度:IQ 50〜70程度
- 中度:IQ 35〜50程度
- 重度:IQ 20〜35程度
- 最重度:IQ 20未満
ただし、これはあくまで目安です。特に中度〜最重度のお子さんの場合、検査自体を受けることが難しいケースも多く、正確な数値を測ること自体に限界があることも知っておく必要があります。
IQスコアの「限界」を知ることの重要性
ここで僕が一番伝えたいのは、IQスコアには限界があるということです。
僕も多くのお子さんを見てきましたが、IQの数値は低くても、すごく性格が良くて素直だったり、真面目にコツコツ努力できたりする子はたくさんいます。
IQテストでは、その子の想像力、芸術的な才能、運動能力、優しさ、粘り強さ、社会性、生活スキルといった、たくさんの側面を測ることはできません。
IQは、その子の能力のほんの一側面、「氷山の一角」でしかないんです。
水面下にある、数値では見えない部分、例えば日々の努力や小さな成長にも目を向けて、その子全体を理解しようとすることが、支援においては何よりも大切だと僕は思います。
また、同じIQの数値でも、併せ持つ発達障害の特性(ASDやADHDなど)によって、現れる困難さや必要な支援は全く違ってきます。
数字だけで判断してしまうと、その子に本当に必要なサポートを見誤ってしまう可能性もあるんです。
世界的な流れ:IQ偏重から「適応行動」重視へ
実は、世界的に見ても、知的障害の診断においてIQの数値だけを重視するのではなく、「適応行動」をより重視する流れになってきています。
アメリカ精神医学会の診断基準である「DSM-5」でも、IQスコアと合わせて、日常生活への適応度を評価することが明記されています。

ゆう先生の補足解説:DSM-5とは?
「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition)」の略称です。
世界中の精神科医や心理専門職が、共通の基準で精神疾患を診断するために広く用いられているマニュアルです。
知的障害(DSM-5では「知的能力障害(知的発達症)」という名称)の診断基準も、このDSM-5に記載されています。
つまり、「IQが低いから知的障害」なのではなく、「IQが低く、かつ、日常生活を送る上での困難さが大きいから、支援が必要な知的障害と診断される」という考え方が、今のスタンダードになってきているんですね。
IQだけでは測れない「適応行動(生きる力)」とは?
では、その重要視される「適応行動」とは、一体何なのでしょうか。
これは、簡単に言えば「生きる力」そのものです。
その人が属する年齢や文化、地域社会の中で、自立した責任ある生活を送るために必要とされる様々なスキルの総称を指します。
テストの点数のような知識(できること)だけでなく、それを実際に生活場面で使えるかどうか(していること)がポイントになります。
- お金の計算はドリルではできるけど、実際のお店で買い物はできない。
- 「ありがとう」という言葉は知っているけど、適切な場面で使えない。
- お箸の使い方は知っているけど、食事は手づかみになってしまう。
こういった、知識と実際の行動のギャップを見ていくのが、適応行動の評価なんです。
適応行動は、大きく3つのスキル領域に分けられます。
1. 概念的スキル
言葉、読み書き、計算、記憶、時間やお金の管理など、学習や問題解決の基礎となる力です。
学校の勉強だけでなく、日常生活で時計を読んだり、計画を立てたりするためにも必要なスキルですね。
2. 社会的スキル
挨拶、順番を守る、友達を作る、人の気持ちを理解する(共感)、状況判断するなど、他者と関わり、社会に適応していくための力です。
このスキルが弱いと、騙されやすかったり、人間関係で孤立してしまったりすることがあります。いわゆる「EQ(心の知能指数)」に近い部分かもしれません。
3. 実用的スキル
食事、着替え、トイレ、入浴といった身辺自立、家事、健康管理、安全確保、公共交通機関の利用など、日常生活を具体的に送るための力です。
この実用的スキルがどの程度自立しているかは、必要な支援の度合いを判断する上で非常に重要な指標となります。僕が療育の現場で、就学先(特別支援学校か支援学級かなど)を考える際に、特に重視するのもこの部分です。
これらの3つの領域のスキルが、年齢相応にどのくらい身についているか、実際の生活でどのくらい使えているか、という視点で見ていくことが、IQの数値だけでは分からない、その子の「生きる力」を理解することにつながるんです。
支援の焦点:IQよりも介入しやすい「適応行動」へ
僕たち支援者や大人が、お子さんの成長をサポートしていく上で、変化させやすいのはどちらでしょうか?
IQ、つまり元々の知的機能自体を大きく変えるのは、正直難しい部分があります。
でも、「適応行動」、つまり生活スキルや社会的な振る舞いは、**「習慣」と「環境」**へのアプローチによって、伸ばしていくことが可能です。
- 習慣:繰り返し練習することで、できることを増やしていく(例:歯磨きの練習、挨拶の練習)
- 環境:本人が行動しやすくなるように、周りの環境を整えてあげる(例:手順書を貼る、分かりやすい言葉で伝える)
これからの知的障害に関するシリーズでは、この「適応行動」をどう支援していくか、という視点を大切にしながら、具体的な関わり方などをお伝えしていきたいと思っています。
【6】まとめ
今日の記事では、知的障害の理解の第一歩として、「IQだけでは測れない“適応行動”」の重要性についてお話ししました。
- 知的障害の診断は、IQ(知的機能)だけでなく、日常生活を送る力である「適応機能」、そしてそれが18歳未満に現れているかという「発症時期」の3つを総合的に見て判断されます。
- IQテストの数値は一つの指標に過ぎず、それだけでは測れない「適応行動(概念的・社会的・実用的スキル)」、つまり「生きる力」全体を見ていくことが、より適切な支援につながります。
- 知的障害は、個人の能力だけの問題ではなく、その人が置かれている「環境との相互作用」の中で生じる困難さとして捉え、IQよりも介入しやすい「適応行動」への支援(習慣化や環境調整)に焦点を当てることが大切です。
結論:読者へのメッセージ
IQの数値に一喜一憂するのではなく、お子さんの日々の生活の中にある「できること」「頑張っていること」、そして「これから伸ばしていけること」に目を向けていくこと。それが、支援の第一歩なのかなと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。