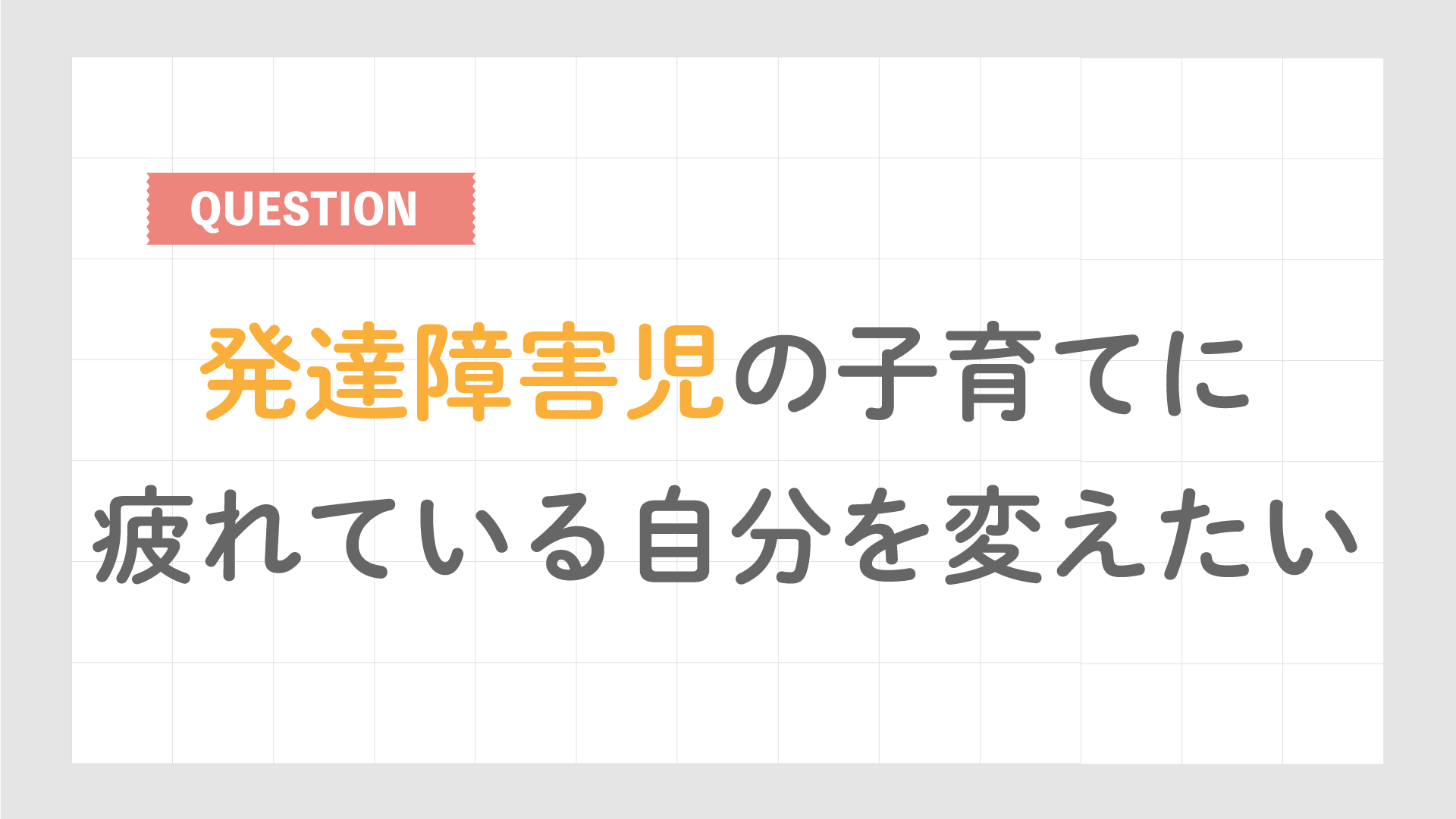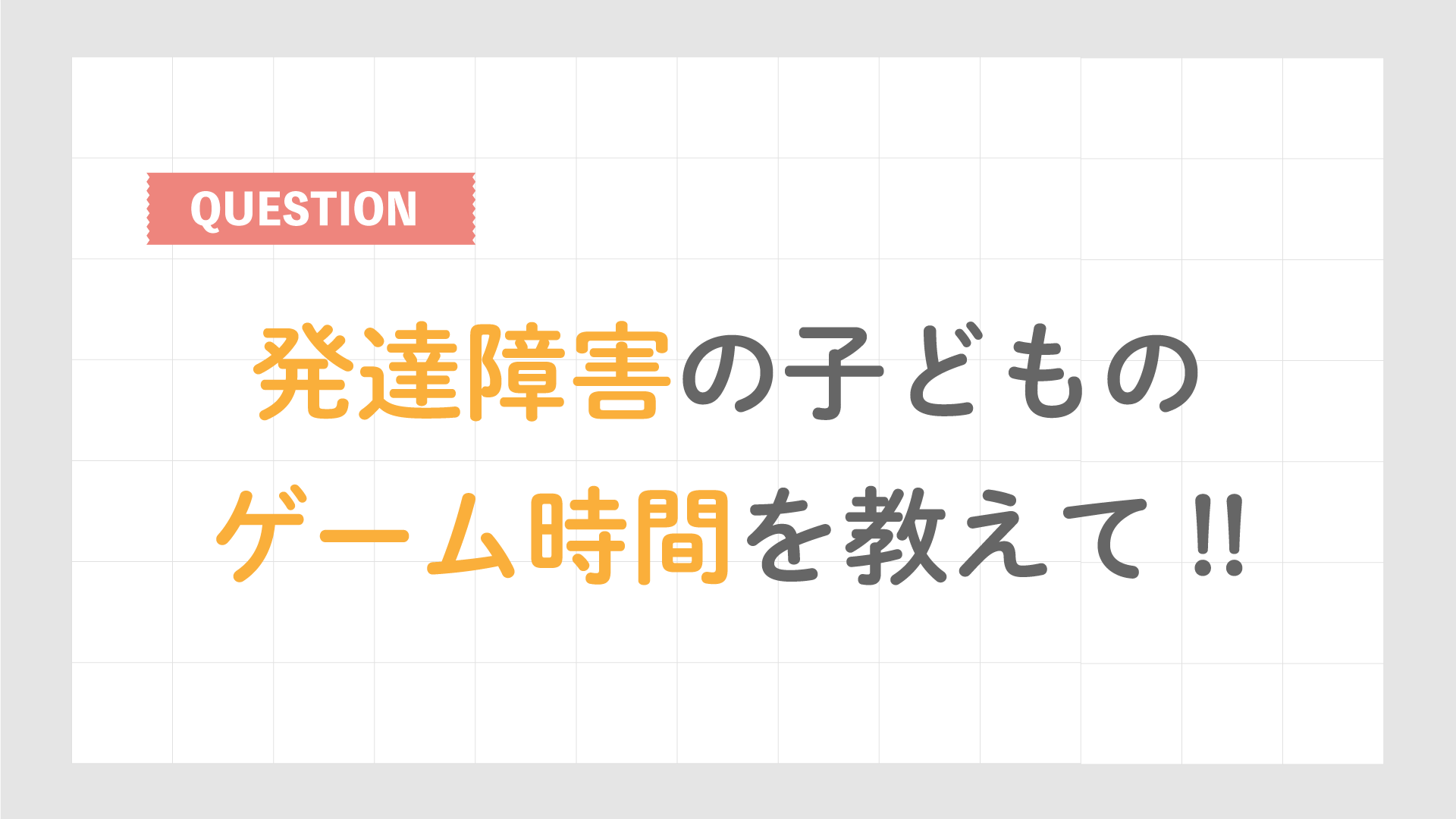発達グレーゾーンの各年代の特徴と支援について|富山の現役指導員が解説
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「発達グレーゾーン」についてです。
「発達グレーゾーン」とは何か?
最近、「発達グレーゾーン」とか「発達グレー」なんていう言葉をよく聞くようになりましたよね。
これはすごく簡単に言うと、「発達障害の傾向を持っているような、持っていないような…」という、まさに白と黒の中間に位置する状態のことを指します。
当事者の方からすると、「自分はどっちなんだろう?そうとも言えるし、そうじゃないかもしれない」と、かえって悩みを深くしてしまう言葉でもあるかなと思います。
発達は「スペクトラム(連続体)」で考える
最近の発達障害の考え方として、「スペクトラム」という考え方が主流になっています。スペクトラムというのは「連続体」という意味です。

ゆう先生の補足解説:スペクトラム(連続体)とは?
「スペクトラム」とは、物事の境界線がはっきりと分かれているのではなく、グラデーションのように連続している状態を指す言葉です。
発達障害でいうと、「発達障害(黒)」と「定型発達(白)」の間に、明確な一本の線が引けるわけではない、ということです。
発達障害の特性が非常に濃い「黒」に近い人もいれば、特性がほとんどない「白」に近い人もいる。
そして、その間には、薄いグレーから濃いグレーまで、無限の「グラデーション」が広がっています。
「発達グレーゾーン」とは、まさにこの白と黒の中間あたりに位置している状態、とイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
ASD(自閉スペクトラム症)の特性を持っている子が、ADHD(注意欠如・多動症)的な特性を併せ持っていることも多く、特性は単一ではありません。
だからこそ、はっきりと「障害」と「定型」に分けられるものではないんですよね。
なぜ「診断」がつかないのか?
「それなら、診断をつけてくれればスッキリするのに」と思われるかもしれません。
でも、これがなかなかセンシティブで難しい問題なんです。
診断基準には一部合っているんだけど、全ては満たしていない。
困難さが毎日見られるわけではなく、特定の場面に限られている。
大人になってから気づいた場合、診断に必要な幼少期の情報が不足している。
お医者さんの評価や状況によっても、判断が分かれることがある。
こういった理由で、診断がつかないケースが多いんです。
ここがグレーゾーンの本当に難しいところで、支援が必要とも言えるんだけど、不必要とも言える場面がある。
この対応の難しさに、ご本人やご家族が困ってしまうパターンがとても多いなと感じます。
【年代別】グレーゾーンの子どもが抱える困難
グレーゾーンのお子さんは、診断がつくお子さんほど特性が顕著ではないかもしれませんが、年代ごとに様々な「見えにくい困難」を抱えがちです。
幼児期(0歳〜6歳)の特徴
発達障害全般に言えることですが、言葉の遅れや「育てにくさ」として現れることが多いです。
- 3歳になってもなかなか意味のある言葉が出てこない
- お友達と遊ばず、一人遊びを好む(ように見える)
- 音や光、触覚などの感覚過敏が強い
- こだわりが強かったり、偏食がひどかったりする
- 指差し(共同注意)や、大人の呼びかけに対する反応が少ない
学童期(小学生)の特徴
集団生活や学習が本格化すると、困難が目立ちやすくなります。
- 授業中に座っていられない(逆に、座ってはいるけどずっとぼーっとしている)
- 忘れ物や失くし物が極端に多い
- ルールを守れなかったり、自分のルールを押し付けようとしたりする
- グループ活動や、友達同士の「冗談」の理解が難しい
- 特定の教科(読む・書く・計算など)だけ、ついていけない
- 感情のコントロールが難しく、癇癪(かんしゃく)が多かったり、物に当たったりする
思春期(中学生・高校生)の特徴
分かりやすい多動などは減ってくる反面、内面的な悩みや、より高度な社会性を求められることで困難が増えます。
- 周囲と合わせること、いわゆる「空気を読む」ことが苦手
- 雑談の輪に入れず、孤立しやすい
- 宿題の提出や時間管理など、計画的に物事を進める「自己管理」が極端に苦手
- 自己肯定感の低下(周りとの違いを強く意識し、「自分なんて…」と思い詰めてしまう)
成人期の特徴
就職や一人暮らしなど、環境が大きく変わり、自己管理のレベルが上がることで困難が表面化します。
- 職場での同じミスを繰り返してしまう
- 「適当にやっといて」といった曖昧な指示が理解できない
- 新しい人間関係が築けず、孤独感を強める
- 片付けや金銭管理(支払い忘れなど)がうまくできない
【特性別】グレーゾーンの傾向
グレーゾーンといっても、その特性の出方は人それぞれです。ASD的な傾向、ADHD的な傾向、SLD的な傾向に分けて見てみましょう。
ASD(自閉スペクトラム症)的な傾向
- 言葉を文字通りに解釈してしまう(冗談や皮肉が通じにくい)
- 興味のあることを一方的に話し続けてしまう
- 急な予定変更など、ささいな変化にも強い苦痛を感じる
- 感覚過敏(特定の服しか着ない、特定の音を嫌がるなど)がある
- 生活のルーティンを崩せない(決まった手順でないとパニックになる)
ADHD(注意欠如・多動症)的な傾向
- 忘れ物や、部屋の整理整頓が極端に苦手
- 衝動的な行動(思ったことをすぐ口にする、順番を待てない)
- 集中力の維持が難しい(特に興味のないことに対して)
- 段取りを立てて物事を進めるのが苦手
成人になると「多動(動き回る)」は目立たなくなるものの、「不注意(うっかりミス)」や「段取りの苦手さ」は残りやすい傾向があります。
僕が学習支援で出会うお子さんの中にも、診断はついていないけれど、ぼーっとしていたり、ケアレスミスが多かったりする子は多い印象ですね。
LD/SLD(学習障害)的な傾向
- 全体的な知能には問題がなく、会話も上手。
- でも、「読む」「書く」「計算する」といった特定の分野だけが極端に苦手。
このタイプは、知的な遅れがないため、小学校低学年くらいまでは本人の努力で何とかなってしまうことが多いんです。
でも、4年生くらいになって学習内容が急に難しくなると、途端についていけなくなる。
それまで「できる子」だったのに急にできなくなるので、本人も周りも混乱し、「努力不足だ」と誤解されて、本人の自己肯定感が大きく損なわれてしまうケースがよくあります。
グレーゾーン支援の「壁」と「リスク」
グレーゾーンのお子さんたちを支援する上で、大きな壁が2つあります。
1. 「見過ごされやすい」という壁
一番の問題は、「一見、普通に見える」ために困難が見過ごされやすいことです。
「努力不足だ」「性格の問題だ」と誤解され、周りから支援されないまま「頑張ってもできない」という経験だけが積み重なっていきます。
2. 「福祉サービスに繋がりにくい」という壁
はっきりと「発達障害」と診断されれば、療育(児童発達支援など)の福祉サービスにつながり、専門的な支援を受けることができます。
しかし、グレーゾーンは診断名ではないため、こうした公的な支援やサービスを受けられない(受給者証が下りない)ケースが多いんです。
この「見過ごされやすさ」と「支援の受けにくさ」が、最も恐ろしい「二次障害」のリスクを高めます。
二次障害とは、元々の発達特性(一次障害)が原因で、周囲からの無理解や不適切な対応(「怠けるな!」と叱られ続けるなど)によって、後から引き起こされる心の問題です。
例えば、うつ病、不安障害、不登校、引きこもり、自傷行為などがこれにあたります。
元々の特性よりも、この二次障害の方が、本人の人生をより深刻に、長期にわたって苦しめることになりかねません。だからこそ、早期の気づきと支援が重要なんです。
家庭でできる支援の基本
では、診断名がつかないグレーゾーンのお子さんに、家庭では何ができるでしょうか。
1. 「視覚提示」で具体的に伝える
僕が長く療育をやってきて、グレーゾーンであってもなくても、一番効果的だと感じるのは「視覚提示(しかくていじ)」です。

ゆう先生の補足解説:視覚提示(しかくていじ)とは?
「視覚提示」とは、言葉(聴覚情報)だけでなく、絵や写真、文字、スケジュール表など、「目で見て分かる」情報を使って伝える支援方法です。
発達に特性があるお子さんは、耳から入る情報(「片付けなさい」「勉強しなさい」)だけでは、何をどうすればいいか理解しにくいことが多いです。
「やることリスト」を貼っておいたり、タイマーで残り時間を「見える化」したりするだけで、安心して行動に移せるようになるケースは非常に多いです。
まずは、「あれ取って」のような抽象的な言葉をやめ、「醤油取って」と具体的に伝えること。
「勉強しなさい」ではなく、「今から15分、タイマーをセットしてドリルをやろう」と、具体的に分かりやすく伝えることが第一歩です。
2. 「強み」を活かす視点を持つ
これが一番大事かもしれません。
人間誰しも、弱い部分、うまくできない部分はあります。
その「苦手なこと」を無理やり直そうとするよりも、「この子の得意なこと、強みは何だろう?」という視点を持ってほしいんです。
特性の裏側には、才能が眠っている可能性があります。
- 「心配性」は、裏を返せば「物事を正確に、慎重に進められる」
- 「声が大きい」は、裏を返せば「元気で、周りを盛り上げられる」
ネガティブに見える部分も、見方を変えればポジティブな面があります。
その子の「弱み」ではなく「強み」を見て、その強みを活かせる場面(得意を発揮できる環境)を整えてあげることが、周りの大人の重要な役割だと僕は思います。
3. 自己肯定感を育てる関わり
グレーゾーンのお子さんは、心が傷つきやすい状態にあることが多いです。
「やりたくない」と言った時、その感情を否定せずに「そうか、やりたくないんだね」と一度受け止める。
そして、小さな成功や努力の「過程」を見逃さずに認めてあげる。
発達障害の支援は長丁場です。保護者の方も休息を大切にし、安心できる環境づくりを心がけてください。
診断がなくても支援は受けられる
最後に。
ここまで「診断がないと支援が受けにくい」と話してきましたが、診断名がなくても支援を受ける方法はあります。
例えば、お医者さんの「意見書」や、保健センターの保健師さんの意見書などがあれば、診断名がなくても療育施設(児童発達支援など)のサービスを利用できる場合があります。(※自治体によって基準が異なる場合があります)
「診断があるか、ないか」で悩むよりも、「今、本人が困っているかどうか」を基準に考えてほしいんです。
発達障害かどうかにこだわるのではなく、「困り事があるなら、それを解決するための道を探してみよう」という視点で、ぜひ支援機関のドアを叩いてみてほしいなと思います。
まとめ
今日の記事では、「発達グレーゾーン」について、その立場や困難さ、支援の考え方についてお話ししました。
- グレーゾーンとは、発達障害と定型発達の「狭間」であり、白黒はっきりしない状態を指します。
- 診断名がつかないことで「努力不足」と誤解されたり、公的な支援から漏れてしまったりすることで、二次障害を引き起こすリスクが高いという問題があります。
- ご家庭での支援は、診断の有無にこだわらず、「困り感」に寄り添うことが第一歩です。具体的には「視覚提示」を活用し、何よりも本人の「強み」を活かす視点を持つことが大切です。
結論:読者へのメッセージ
白黒つけられないと、すごく不安になる気持ちはよく分かります。
でも、白とか黒とか、障害があるとかないとか、そういう分類はいったん横に置いておいて。
「今、お子さんが困っていること」に目を向けて、それを解決するために、できることから一歩ずつ進んでみませんか。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことにつながれば、僕もとても嬉しいです。