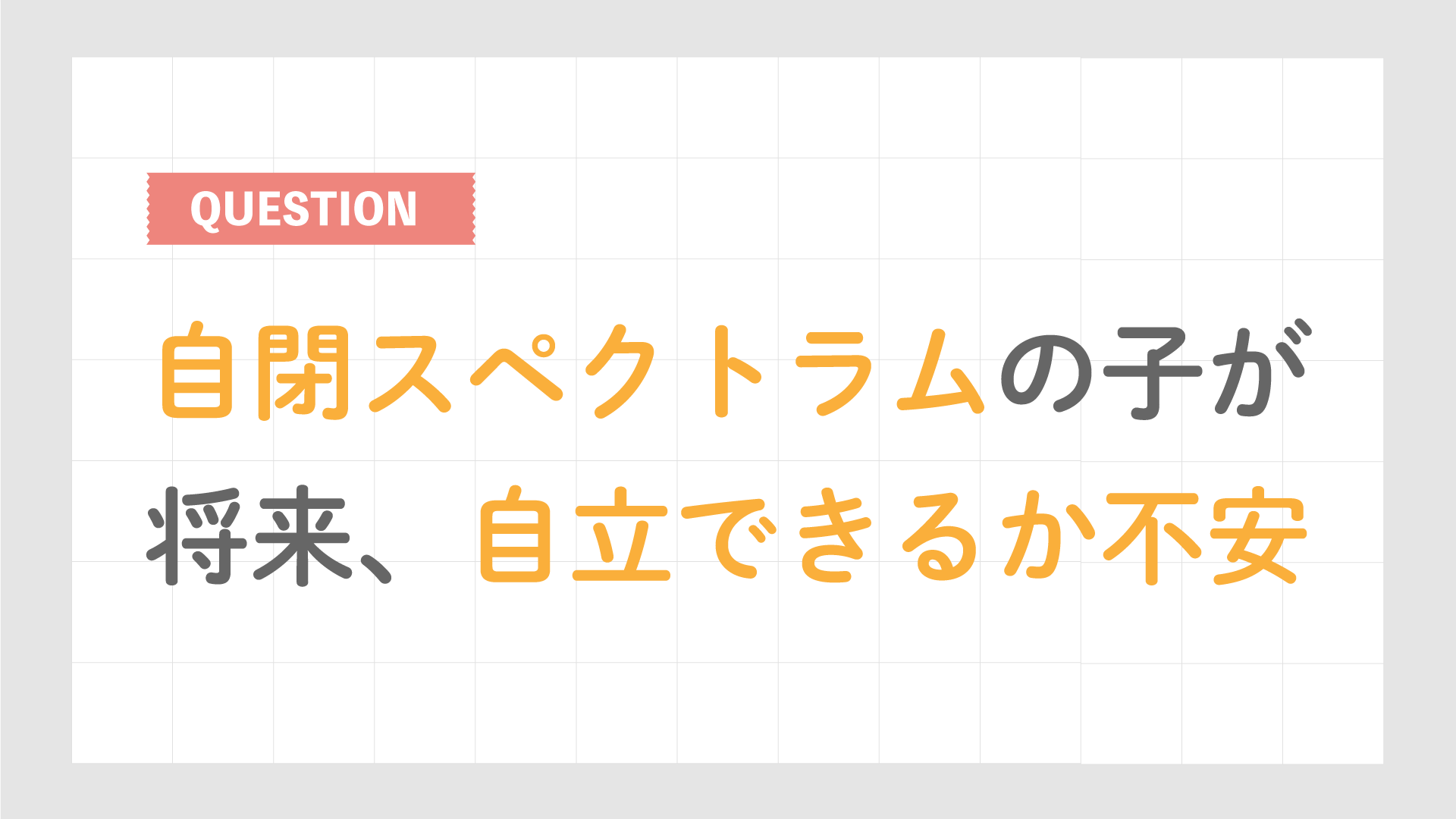子どもの発達障害かも?初めての相談先完全ガイド|富山の現役指導員が不安を解消します
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「発達障害かもしれないと感じた時の相談先ガイド」についてです。
まず知っておきたいこと:相談への「不安」を「勇気」に変えるために
「発達障害かもしれない」と感じた時、相談に行くのはとても勇気がいることだと思います。
診断を受けること自体に抵抗があったり、気持ちが重くなったりするお父さんお母さんも少なくないんですよね。
でも、僕がまずお伝えしたいのは、「相談することは決して悪いことではない」ということです。
早期の気づきとサポートが子どもの可能性を最大化する
早期からの気づきと適切なサポートは、お子さん本人の持つ可能性を最大限に引き出します。
特に幼児期は、いろんなことの変化をさせやすい時期であることは間違いありません。
例えば、18歳になって初めて発達障害だと分かるケースと、4歳で分かってサポートが始まるケースでは、できることの幅が大きく変わってくる可能性があると僕は思います。
勇気を出して相談窓口にアクセスすることは、お子さん本人にとっても、ご家族にとっても、本当に大事な「最初の一歩」になるんですよね。
相談は「悪いこと」ではなく「未来への一歩」
相談する目的は、お子さん本人が気持ちよく生活するため、そして引いてはお父さんお母さんが気持ちよく生活するためです。
だから、「相談=悪いこと」ではなく、むしろ「より良い未来のためのポジティブな行動」なんだって思っていただけると、僕もすごく嬉しいです。
相談前に準備しておくとスムーズなこと
いざ相談に行こうと決めた時、事前に準備しておくと、専門家の方にも状況が伝わりやすくなり、話がスムーズに進みます。
1. 「具体的な困りごと」をメモにまとめる
「何に困っていて、どんなことが起きていて、どういう状態なのか」。これを具体的にしておくことが大切です。
可能であれば、「いつ・どこで・誰と・どんな状況で・どんな頻度で」というように、気になっている行動を詳しく整理しておくと、専門家もすごく理解しやすくなります。
「お医者さんの前だとうまく話せないかも…」という不安も減らせますので、メモ書き程度でもいいので、ぜひまとめてみてください。
2. 関連資料(母子手帳、通知表など)を準備する
お子さんのこれまでの育ちが分かる資料は、できる限り持っていくのがおすすめです。
- 母子健康手帳
- 園や学校の資料(通知表、連絡帳など)
- 過去に受けた心理検査や発達検査の結果(もしあれば)
- 他の医療機関からの紹介状(もしあれば)
- 先ほどの「相談メモ」や育児日記など
これらの情報があることで、相談がスムーズに進みますし、その後の支援にも役立っていきます。
【重要】相談先を見つける前に知っておくべき心構え
さて、準備ができたら「どこに相談するか」ですが、その前に一つだけ知っておいてほしい心構えがあります。
診断や支援計画には時間がかかる
それは、「意外と時間がかかる」ということです。
特に病院での診断の場合、予約が数ヶ月待ちということも珍しくありません。僕の肌感覚でも、初診の予約が3ヶ月後、6ヶ月後というケースもあります。
相談したいと思ってから実際に支援が始まるまで、早くても1ヶ月、長いと半年以上かかることもあるんだ、ということを念頭に置いておくと、焦らなくて済むかもしれません。
複数の窓口に相談することを念頭に置く
だからこそ、早めに動くことが大事です。そして、「ひとつの窓口がダメでも、他の窓口を当たってみる」という、複数の視点を持つことがすごく大切になってきます。
例えば、病院の予約が6ヶ月待ちだったら、その間にまず行政の窓口に相談してみる、といった動き方ですね。
具体的な相談先ガイド:どこにアクセスすればいい?
相談先は、正直どこからアクセスしても大丈夫です。最終的には医療・行政・教育は連携していくことになりますので、ご自身が一番話しやすいところからスタートしてみてください。
主な相談先として、今回は3つのルートと、その他について解説します。
1. 医療機関(小児科・児童精神科)
迷ったら、まず病院に連絡してみるのが手っ取り早いかなと個人的には思います。特に乳幼児期から思春期のお子さんであれば、「小児科」や「児童精神科」が専門になります。
最終的に「診断」を下せるのはお医者さんだけですし、療育(発達支援)を受けるために診断書が必要になるケースが多いので、発達の専門家であるお医者さんに診てもらうのは重要です。
ただ、先ほどもお伝えした通り、専門の医療機関は予約制が多く、非常に時間がかかるという側面があります。

ゆう先生の補足解説:なぜ児童精神科は予約が取りにくい?
児童精神科は、なぜこんなに予約が取りにくいのかというと、いくつかの理由が考えられます。
- 専門医の絶対数が少ない:児童の精神科を専門とするお医者さんの数は、全体のニーズに対してまだ十分とは言えない状況です。
- 診察に時間がかかる:お子さんの発達に関する診察は、行動観察や詳しい聞き取り、心理検査などが必要になるため、一人ひとりに非常に時間がかかります。
- ニーズが急増している:発達障害に関する認知が広まり、「相談してみよう」と考える保護者の方が増えていることも、予約が混み合う一因だと考えられます。
だからこそ、「気になったらすぐ連絡してみる」ことが大切なんですよね。
病院では、問診(困りごとや経緯、生活状況の聞き取り)のほか、必要に応じて行動観察や心理検査などが行われ、それらの情報を総合して診断がなされます。
2. 行政機関(保健センター・発達障害者支援センターなど)
市役所などの役所も窓口になりますが、より専門的な場所として「保健センター」や「発達障害者支援センター」「児童発達支援センター」などがあります。
行政機関のメリットは、多くの場合、無料で相談できるという点です。
まずはこうした場所で気軽に相談してみて、必要に応じて病院を紹介してもらう、という流れも一般的です。

ゆう先生の補足解説:児童発達支援センターとは?
「児童発達支援センター」というのは、児童福祉法に基づいて設置されている、地域の中核的な支援機関です。
簡単に言うと、発達に心配のあるお子さん(主に未就学児)が通って、日常生活の基本的な動作や、集団生活への適応訓練など、専門的なサポート(これを療育といいます)を受ける場所です。
僕が働いているのも、こうした施設の一つですね。 地域の療育の拠点として、相談支援なども行っていることが多いです。
未就学児の場合は「保健センター」が身近な窓口
特に、まだ園や学校に通っていないお子さんの場合、「保健センター」や「子育て支援センター」が一番身近で声をかけやすい窓口かなと思います。
1歳半健診や3歳児健診のタイミングで「ちょっと気になるんですけど…」と相談してみるのが、早期につながる良いきっかけになります。
その時点では発達障害かどうか分からなくても、「言葉の教室」くらいの気持ちで療育に通ってみて、成長とともに気にならなくなれば、それはそれで良いんですよね。
お子さんにとってマイナスになることは少ないので、気軽に相談してみてほしいです。
児童相談所の役割
「児童相談所」も相談窓口の一つです。児童相談所は、虐待や養育困難、非行、不登校など、子どもに関するあらゆる相談(障害相談も含む)を受け付けています。
ただ、発達障害がメインの場合は、先ほどの発達障害者支援センターなどの方が、より専門的にスムーズに話が進むかもしれません。
3. 教育機関(学校・教育委員会)
お子さんがすでに就学している場合は、学校や教育委員会も重要な相談先です。
学校での相談先(担任・特別支援コーディネーター) まずは、一番身近な担任の先生に相談するのが第一歩です。
また、学校には「特別支援コーディネーター」という、学校内の特別支援教育を調整する役割の先生が配置されていることが多いです。
担任の先生に相談すれば、コーディネーターの先生につないでくれると思います。
学校に相談するメリットは、診断がなくても、学校生活での困りごとに対して具体的なサポート(合理的配慮)を受けやすくなる点です。

ゆう先生の補足解説:合理的配慮とは?
「合理的配慮」とは、障害者差別解消法という法律で定められているもので、障害のある人がない人と同じように学んだり生活したりできるよう、学校や職場が必要な調整を行うことです。
例えば、「書くのが極端に苦手な子に、タブレットPCの使用を許可する」「聴覚が過敏な子に、教室でイヤーマフ(防音用の耳当て)の使用を認める」「テストの時間を少し延長する」などが挙げられます。
ただし、その配慮が学校にとって負担になりすぎない範囲で、という条件があります。
また、お子さん一人だけ違う対応をすることで、かえって本人が不利益にならないか、といった調整も必要になるため、先生とよく相談することが大切です。
教育委員会の役割(就学相談・教育相談) 教育委員会も相談窓口を持っています。
- 就学相談:年長さんの時期に、「来年の小学校は、通常の学級がいいか、特別支援学級がいいか」などを相談できます。
- 教育相談:在学中に、学校の先生には直接言いにくいことや、学校と連携して進めたいことなどを相談できます。
4. その他の相談先
上記の3つ以外にも、相談できる場所はあります。
民間の療育施設(児童発達支援施設など) 僕が働いているような、民間の児童発達支援施設(療育施設)に直接連絡してみるのも、全然アリです。
施設に直接相談するメリットは、現場の肌感覚が分かったり、「この地域なら、この病院がいいですよ」「次は行政のここに連絡するといいですよ」といった、具体的な次のステップを教えてもらいやすい点です。
ただし、施設によって特色(運動がメイン、学習がメインなど)が全く違うので、見学などをしてみて、自分のお子さんに合った場所を選ぶことが大切です。
また、地方都市では特に、療育施設の空きがなくて「待機」になってしまうことも多発しています。この点でも、やはり早めの行動が鍵になります。
保護者のサークルやピアサポート 意外と馬鹿にできないのが、同じ悩みを持つ保護者の方のサークルや、ピアサポート(仲間同士の支え合い)の会です。
実際に経験しているお父さんお母さんに話を聞いてもらうだけで、不安がかなり軽減されます。そこで「あの病院が良かったよ」「あの施設はこんな感じだよ」といったリアルな情報を得ることもできます。
まとめ
今日の記事では、「発達障害かもしれない」と感じた時の相談先についてお話ししました。
- まず、早期の気づきと相談は、お子さんの可能性を広げるポジティブな一歩だということを忘れないでください。
- 相談に行く前には、「具体的な困りごとメモ」と「母子手帳などの関連資料」を準備しておくとスムーズです。
- 主な相談先には**「医療機関」「行政機関」「教育機関」**があり、それぞれに特徴があります。
- 診断や支援開始には時間がかかることが多いので、早めに、そして複数の窓口にアクセスすることを心がけてみてください。
結論:読者へのメッセージ
何よりも僕が現場で療育をしていて思うことは、お父さんお母さんが孤立しないことが、本当にすごく大事だということです。
ぜひ一人で抱え込まず、この記事で紹介したどこかの窓口に「繋がってみる」という行動を起こしていただければと思います。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。