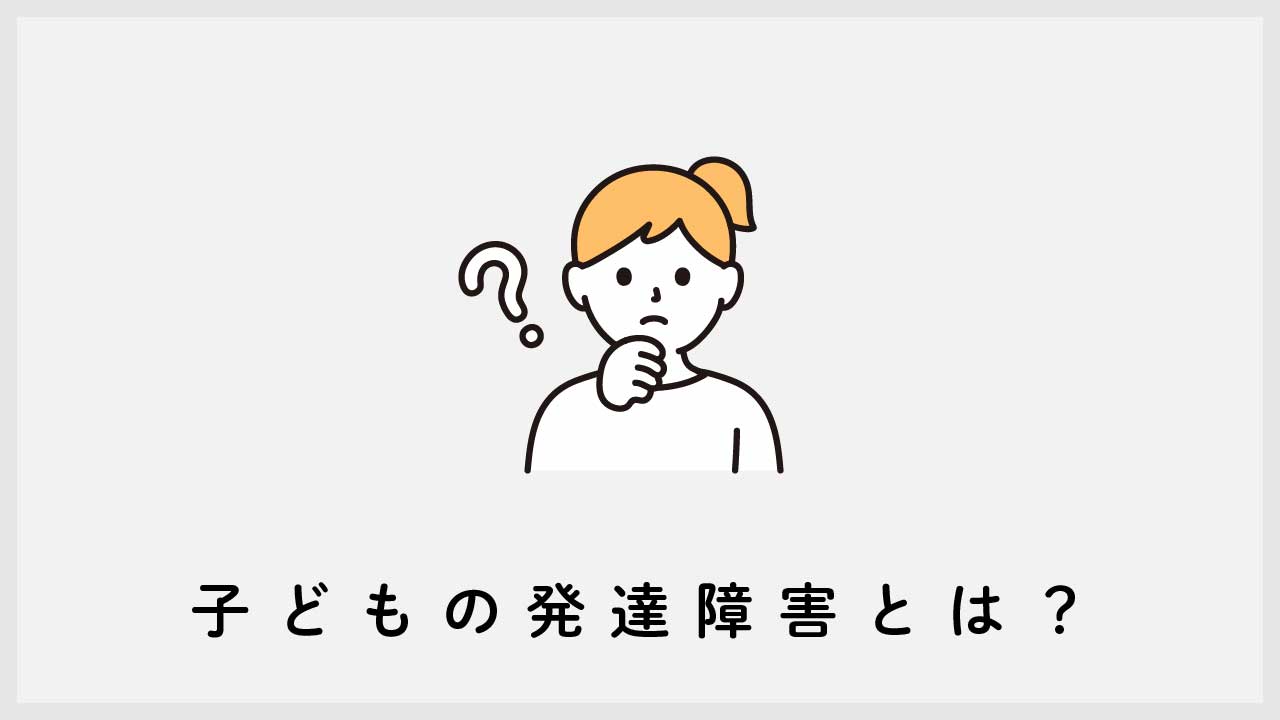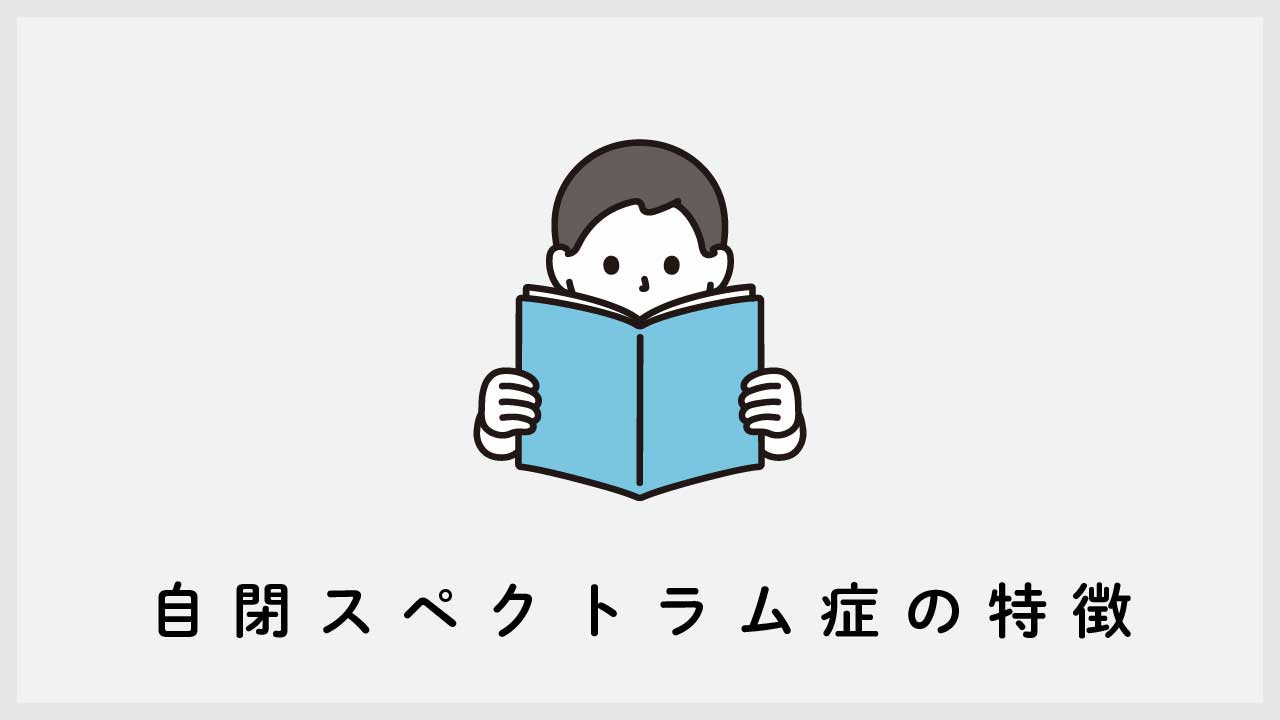SLD限局性学習症の子どもの特徴を解説|子供の発達障害解説

こんにちは!ゆう先生です。
本日は「SLD(限局性学習症)」についてのお話です。
「なぜうちの子だけ勉強がうまくいかないんだろう?」と悩んでいる保護者の方も少なくありませんが、SLDは特定の学習分野にのみ困難が生じる特性をもつ状態です。
たとえば、読むことだけが極端に苦手だったり、文字を書く作業がとても負担に感じたり、計算や数字の理解がどうしてもうまくいかなかったりすることが挙げられます。
一方で、それ以外の分野ではしっかり理解できたり、素晴らしい才能を発揮したりすることも多いのがSLDのお子さんの特徴です。
SLD(Specific Learning Disorder)は、知的発達に著しい遅れがないにもかかわらず、特定の学習領域だけで顕著な困難を抱える状態を指します。
これは決して「やる気がない」「努力不足」「しつけの問題」などではなく、脳の情報処理の得意・不得意によって起こるものです。
苦手な領域をどのようにサポートし、得意な分野をどう伸ばしていけるかが、子どもたちの自信や可能性を広げる大きなカギになります。
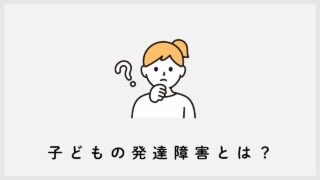
SLDの3つの主な特徴

(1)読むことの困難(ディスレクシア)
SLDの中には「ディスレクシア(読字障害)」と呼ばれる読みに特化した困難が見られるケースがあります。
たとえば、本や教科書を音読するときにつっかえたり、読み飛ばしがあったりするため、文章の内容を理解するまでに時間がかかり、本人にとって読書はとても疲れる作業になります。
こうしたお子さんには、無理に音読を続けさせるのではなく、オーディオブックや朗読アプリ、文字を大きくした教材、行をガイドする定規などの工夫が効果的です。
文章を「音声で聞く」スタイルに切り替えると理解がスムーズになり、「読めない」ストレスを軽減しながら読む内容をしっかり把握できるようになります。
(2)書くことの困難(ディスグラフィア)
「ディスグラフィア(書字表出障害)」をもつ子は、文字を書くこと自体に強い苦手意識や時間的負担を感じやすいのが特徴です。
文章を書くときに文字が乱れたり、漢字の練習を延々と嫌がったり、作文課題がなかなか進まなかったりします。
もし、紙に文字を書く作業があまりにも辛そうなら、パソコンやタブレットでの入力を試してみましょう。
キーボード入力や音声入力を使えば、手で書く苦痛が減り、学習内容や発想そのものに集中できます。
また、専門家の力を借りて「書字動作」を補うトレーニングをおこなうことで、少しずつ負担を軽くできる場合もあります。
(3)計算することの困難(ディスカリキュリア)
「ディスカリキュリア(算数障害)」では、数字や計算の概念をつかむのが難しかったり、九九や繰り上がり計算、時計の読み方などを覚えにくかったりします。
特に抽象的な数のやりとりが苦手なため、買い物で正しいお釣りを把握できなかったり、応用問題でつまずきやすいことが多いです。
このようなお子さんには、具体的なブロックや数直線、図やイラスト、計算アプリなどを活用して「見える形」で学ばせることがおすすめです。
抽象的な数字や記号だけで理解するのが難しい場合、計算機やステップをまとめたノートを使うなど、工夫を取り入れると格段に理解しやすくなります。
家庭でできるおすすめ支援3選
(1)得意な学び方を見つける
子どもによって、得意な学び方はさまざまです。
テキストよりも音声や映像からのインプットの方がわかりやすい子もいれば、図やイラストを多用すると理解しやすくなる子もいます。
苦手分野がテキスト中心であれば、動画教材やオーディオブックなどのマルチメディアを導入してみましょう。
イラストやグラフが豊富な資料を活用するのも効果的です。
(2)学習時間を区切り、ツールを活用する
SLDのお子さんは、苦手な学習を長時間続けると疲労感やストレスがたまりやすくなります。
10分~15分の短時間単位で区切りを入れ、少し休憩してから次の学習に移るなど、こまめにリフレッシュする時間を設けてあげてください。
また、パソコンやタブレット、音声読み上げソフト、計算支援アプリなどを使えば、苦手な部分をサポートしながら効率よく学習を進めることができます。
(3)成功体験を重ねる環境づくり
どうしても苦手な部分ばかりが目立ちがちですが、「できないところ」だけでなく「できるところ」「好きなこと」に注目してあげると、お子さんの自己肯定感が高まります。
たとえば、文章を読むのは苦手だけれど、絵を描くことは大好きなら、その得意分野をしっかり伸ばせるようなサポートをしてみましょう。
小さな成功でも褒め、成果を一緒に喜ぶことで、「自分にはこういう力があるんだ」と思えるきっかけが増えていきます。
まとめ
本日は「SLD(限局性学習症)」についての解説していきました。
SLD(限局性学習症)は、読む・書く・計算するなど、特定の学習領域にだけ大きな困難が生じる状態です。
しかし、裏を返せば、ほかの分野ではしっかり理解できていたり、ときには突出した才能を発揮したりする可能性が十分にあります。
保護者としては、「苦手な部分はどうフォローできるか」「得意な分野をどう伸ばせるか」に目を向けて、最適な学習環境やツールを探してあげることが大切です。
もし「うちの子は学習に偏りがあるかも」と思ったときは、一人で悩まずに学校の先生や専門家へ相談してみてください。
特別支援教室や通級指導教室の利用、療育プログラムやICT機器の活用など、多くの選択肢があります。
そして何より、お子さんの「ここは苦手だけど、ここなら輝ける」という一面を大事にしてほしいと思います。
子どもが自分らしく学び、成長していけるよう、家族や周りの大人が協力しながらサポートしていけば、きっとお子さんの未来はより明るく開けていくはずです。
ぜひ一緒に、あたたかく見守りながら前に進んでいきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。