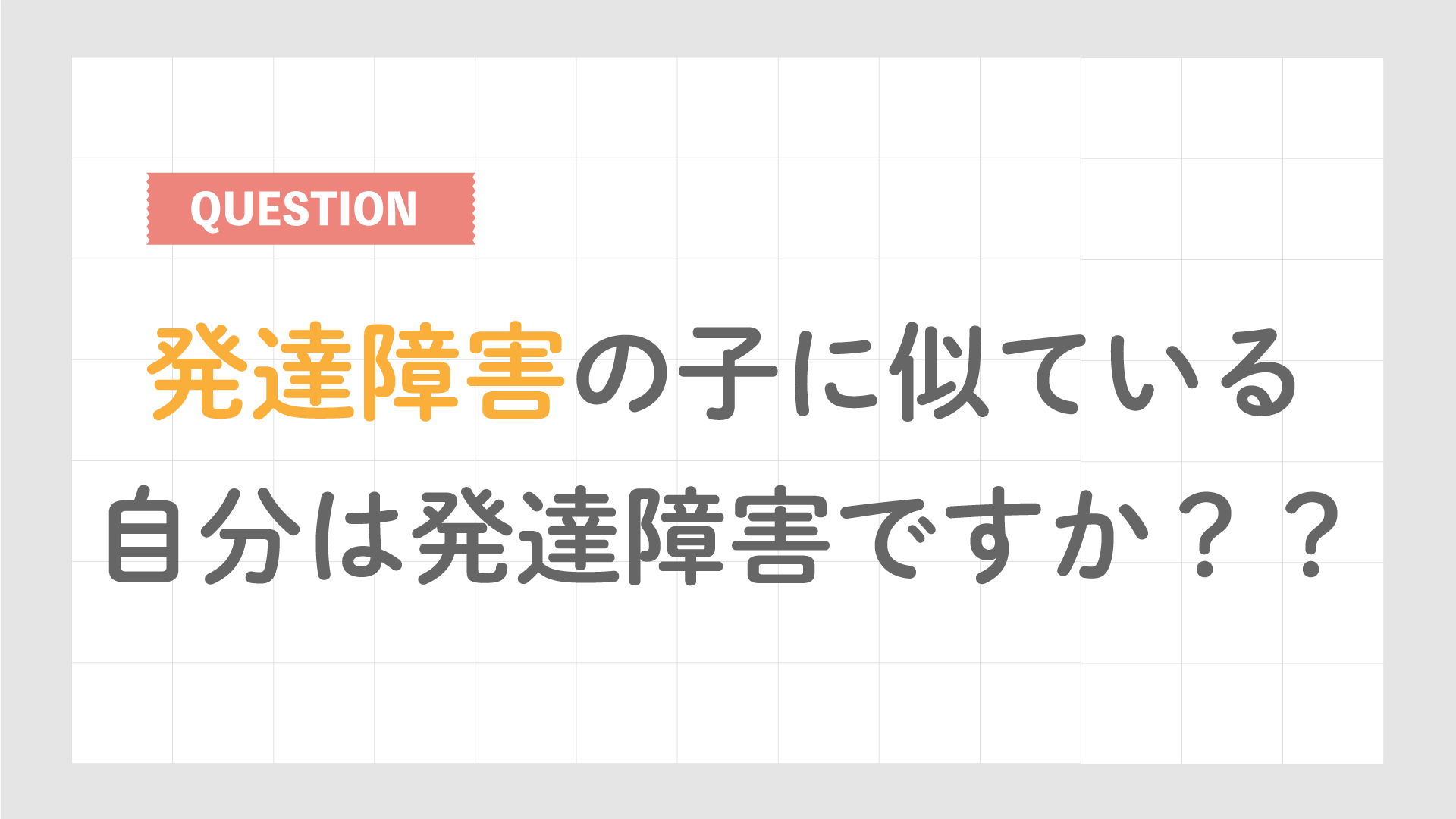ASD(自閉スペクトラム症)とは?自閉症やアスペルガー症候群との「違い」を現役指導員が解説します
はい、こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「ASD(自閉スペクトラム症)の今の定義と、昔の診断名(自閉症・アスペルガー症候群など)との違い」についてです。
「うちの子、ASDって診断されたけど、昔でいうアスペルガーとは何が違うの?」
「自閉症と高機能自閉症って、どういう分類だったんだろう?」
「診断名がいろいろあって、情報が混乱してしまう…」
そんな疑問やモヤモヤを感じたことはありませんか?今日はそのあたりをスッキリ整理していきたいと思います。
【3】記事のポイント(結論の先行提示)
現代のASD(自閉スペクトラム症)とは?
さて、今日は少し歴史のお話にもなるんですが、まず「今」のASD(自閉スペクトラム症)について整理します。
もともとASDというのは、昔あった「自閉症」「高機能自閉症」「アスペルガー症候群」といった、いくつかの障害が合体して、今の「自閉スペクトラム」という一つの診断名になっています。
じゃあ、そのASDの共通する特徴は何かというと、大きく2つあります。
ASDの2つの中核的な特徴
現在の診断基準(DSM-5)では、ASDと診断されるには、以下の2つの領域で特徴が見られることが基準となっています。
- 社会性コミュニケーションおよび相互関係における持続的な欠陥
- 限定された反復的な行動、興味、または活動
この2つがそろって、初めてASDという診断がされます。
「社会的コミュニケーションの欠陥」というのは、例えば、なかなか視線が合わなかったり、相手の感情を読み取ったり、自分の気持ちを適切に伝えたりすることが苦手な状態を指します。
僕らは会話の中で、言葉そのもの以外に「表情」「声のトーン」「身振り手振り」といった非言語的な情報も使ってやり取りをしていますが、ASDの方はそうした「言葉の裏にあるニュアンス」を汲み取ることが苦手で、言葉を額面通りに受け取ってしまう傾向があります。
もう一つの「限定的・反復的な行動」は、いわゆる「こだわり」や「常同行動」と呼ばれるものです。
例えば、手をヒラヒラさせたり、その場でくるくる回ったりする身体の動き(常同行動)。
おもちゃを一列にきれいに並べたり、車のタイヤだけをくるくる回して遊んだりする特定の方法。あるいは、オウム返し(エコラリア)や、大人びた独特な言い回しを繰り返すこと。
また、「同一性への強いこだわり」として、いつもと同じ服、いつもと同じ通学路、いつもと同じ手順(手の洗い方など)じゃないと嫌だ、といった柔軟性のなさとして現れることもありますね。

ゆう先生の補足解説:DSM-5とは?
動画の中で「現行基準」と話しているのは、主にアメリカ精神医学会が発行する『精神障害の診断と統計マニュアル 第5版』(DSM-5)のことを指しています。
これは世界中の医師や臨床家が使う診断基準の一つです。
2013年にこのDSM-5に改訂された際、それまで「広汎性発達障害」という大きなカテゴリの中にあった「自閉症」「アスペルガー症候群」「特定不能の広汎性発達障害」などが、「自閉スペクトラム症(ASD)」という一つの診断名に統合されました。これが、今日のテーマの核心部分なんですよね。
「スペクトラム」という考え方の重要性
ASDの「スペクトラム」というのは、「連続体」とか「切れ目がない」という意味です。
今の発達障害の理解では、この「スペクトラム」という概念がすごく大事です。ASD的(自閉症的)な特徴と、ADHD的(多動的)な特徴を両方持っているお子さんもたくさんいます。
ASDの土台となる「コミュニケーションの課題」と「こだわり」は共通しているんだけど、その上に生えてくる草、つまり特性の現れ方(言葉の発達、知的な能力、感覚過敏の強さなど)は、一人ひとり全く違うんです。
だから、ASDという診断名だけで「この子(人)はこうだ」と決めることはできなくて、その子の特性のデコボコを細かく見ていく必要があります。
なぜ診断名が変わったの?過去の分類との違い
「じゃあ、昔はどうしてわざわざ分けていたの?」と思いますよね。ここからは、その歴史的な分類について解説します。
① 古典的自閉症(カナー型)
1943年に、アメリカの児童精神科医レオ・カナーという人が初めて「自閉症」を報告しました。これが「古典的自閉症」や「カナー型自閉症」と呼ばれるものです。
特徴としては、「極度の社会的孤立」「同一性保持へのこだわり」そして「著しい言語(言葉)の遅れ」があるとされました。そして、報告された事例の多くが知的障害を伴っていたんですね。
このため、長い間「自閉症=知的障害がある」というイメージが強かったのは、このカナーの定義が最初だったから、という背景があります。
② 高機能自閉症(HFA)
次に「高機能自閉症」です。これは1990年頃から言われ始めた概念です。
カナー型自閉症と同じように「コミュニケーションの課題」や「こだわり」はあるんだけど、「知的な遅れはない」タイプです。ただし、幼児期に「言語の遅れはあった」というのがポイントです。
コミュニケーション、特に会話は苦手なんだけれども、記憶力がすごく良かったり、特定の分野(恐竜や虫など)にめちゃめちゃ詳しかったり、局所的に優秀さを発揮することがある、と報告されました。
③ アスペルガー症候群
最後に「アスペルガー症候群」です。
実はこれ、オーストリアの小児科医ハンス・アスペルガーによって、カナーが自閉症を報告した翌年(1944年)にはもう報告されていたんです。
特徴は、「知的障害がなく」「言語の遅れもない」ことです。むしろ言葉は流暢(りゅうちょう)で、大人びた丁寧すぎる話し方をすることがあります。
ただ、高機能自閉症と同じく、言葉の裏が読めなかったり、対人距離の調整が苦手だったり、強烈なこだわりを持っていたりします。
発見はカナーと同時期だったんですが、当時は戦争の影響などもあって、カナーの定義の方が強く広まりました。
アスペルガー症候群が広く知られるようになったのは、1980年代以降になってからなんですよね。

ゆう先生の補足解説:高機能自閉症とアスペルガーの違い
この2つの分類、とてもよく似ていますよね。一番の違いは「幼児期に言語の遅れがあったかどうか」でした。
- 高機能自閉症:知的な遅れはないが、言葉の遅れはあった。
- アスペルガー症候群:知的な遅れも、言葉の遅れもなかった。
ただ、現場の感覚としても、この線引きは非常に曖昧でした。
成長するにつれて言葉がすごく上手になってきた「高機能自閉症」の子と、「アスペルガー症候群」の子を、後から区別するのって難しいですよね。
診断名が「ASD」に統合された背景
まさに今お話ししたように、「高機能自閉症」と「アスペルガー症候群」の線引きが曖昧であること。
また、どちらにも当てはまらないけど発達に課題がある場合に「広汎性発達障害(特定不能型)」という、さらに曖昧な診断名が使われることも多かったんです。
こうした「診断の曖昧さ」を解消し、「支援の必要性」という観点から一貫して捉え直そう、という流れの中で、2013年のDSM-5改訂時に、これらの診断名は「自閉スペクトラム症(ASD)」という一つの大きな傘(カテゴリー)に統合されました。
【結論】診断名よりも「個々の特性」を見ることの大切さ
今日、僕が何よりお伝えしたいのはここです。
発達障害というのは、ASDであれADHDであれ、分類(診断名)よりも「特性の組み合わせ」で理解することが本当に大事です。
本やネットで「自閉症の支援はこうだ」と読んで、その通りにやってもうまくいかないケースがたくさんあるのは、まさに「スペクトラム」だからです。
根本は似ていても、特性の現れ方は一人ひとり全く違います。
だからこそ、僕たち支援者や保護者の方が大事にしたいのは、診断名に囚われるのではなく、目の前にいるお子さんの「強み」と「困難(困り感)」をちゃんと見ること。
その子の得意なこと(例えば、記憶力がいい、ルールをきっちり守れる)と、苦手なこと(例えば、急な変更がパニックになる、人の気持ちを想像するのが難しい)の組み合わせを理解して、その子に合った支援をしていくことが一番大切なんですよね。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- 現代のASD(自閉スペクトラム症)は、「社会性コミュニケーションの課題」と「限定的・反復的な行動(こだわり)」という2つの中核的な特徴を持つ状態を指します。
- かつては「言語の遅れ」と「知的な遅れ」の有無によって、「自閉症(両方あり)」「高機能自閉症(言語遅れあり、知的遅れなし)」「アスペルガー症候群(両方なし)」と細かく分類されていました。
- しかし、これらの境界は曖昧であり、連続的(スペクトラム)であるという理解から、2013年に「ASD」という診断名に統合されました。
- 最も重要なのは、診断名という「言葉」に振り回されず、目の前にいるお子さんの「強み」と「困り感」の具体的な組み合わせを理解し、支援することです。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。