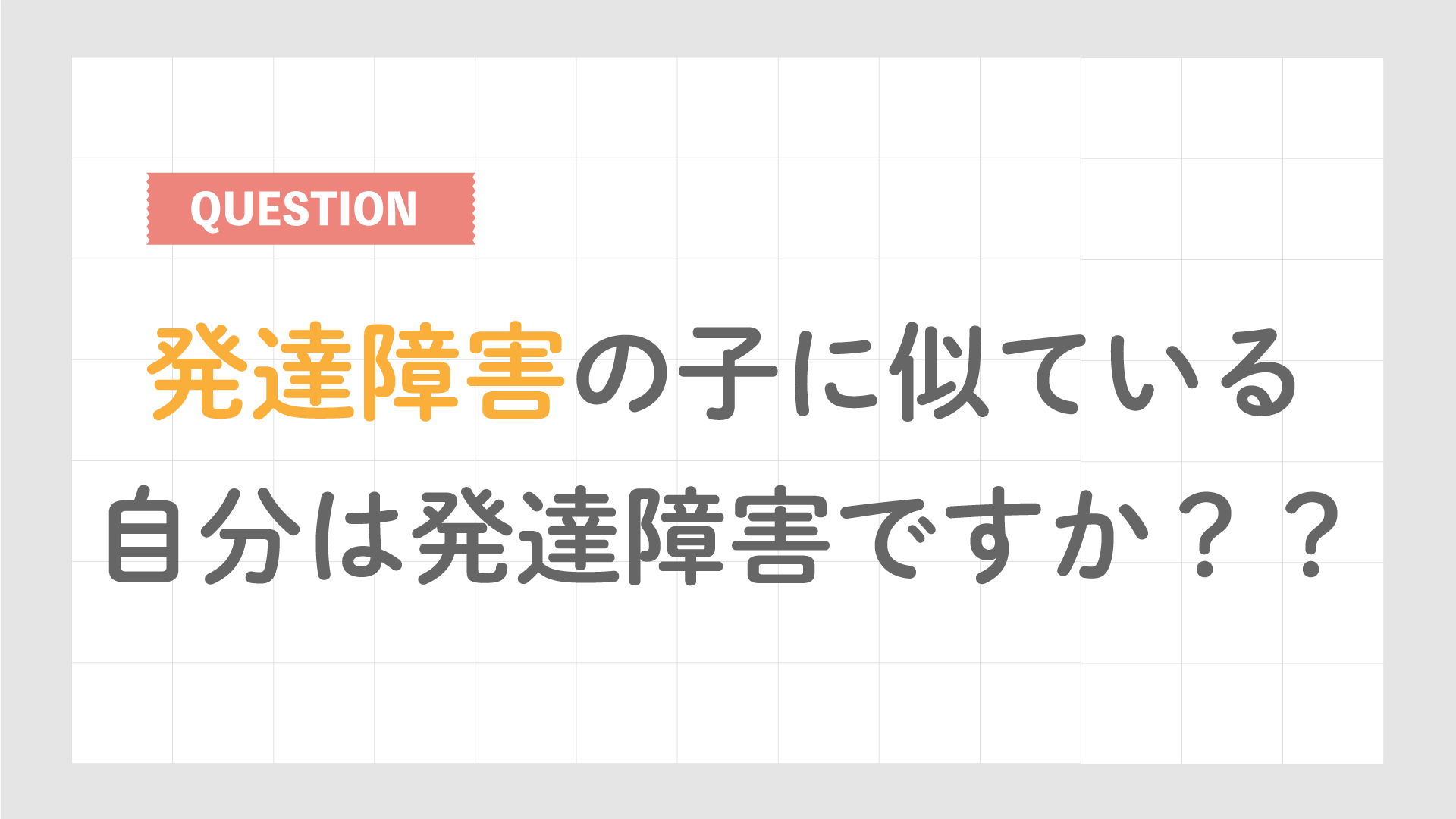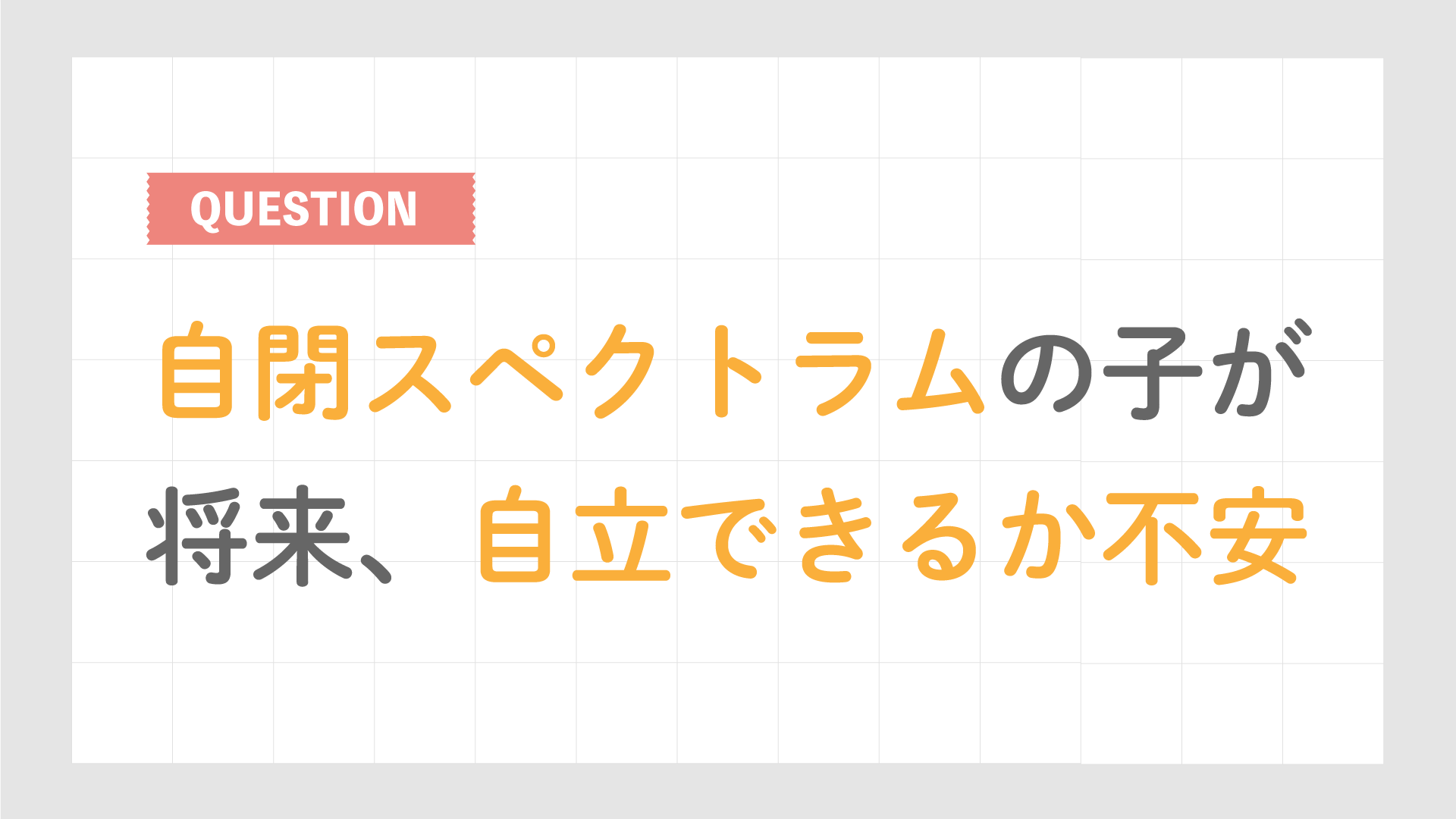「愛着障害」と「アダルトチルドレン(AC)」の違いとは? 似ている“生きづらさ”の根本原因を解説
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「愛着障害(あいちちゃくしょうがい)」と「アダルトチルドレン(AC)」の違いについてです。
「愛着障害とアダルトチルドレンって、結局同じことじゃないの?」「どちらも幼少期の家庭環境が原因で、大人になってからも生きづらさを抱えているイメージだけど…」そんな風に、この二つの言葉を混同してしまっていませんか?
どちらも現代社会の「生きづらさ」の背景として語られることが多く、症状も似ているため、混乱しやすいですよね。
ですが、この二つは「似て非なるもの」であり、その根本的な原因=スタート地点が異なります。今日はこの違いをしっかり解説していきます。
まずは「愛着障害」をおさらい
アダルトチルドレンとの違いを理解するために、まずは「愛着障害」がどういうものだったかを簡単におさらいします。(詳しくは前回の記事もご覧くださいね)
愛着障害は、「医学的な診断名」がつく精神疾患です。
これは、お子さんが養育者(お父さんお母さんなど)との間で築くべき情緒的な結びつき(=愛着、アタッチメント)に、異常が生じた状態を指します。
安全基地の「欠如」が根本原因
愛着障害の根本的な原因は、幼少期(DSM-5という診断基準では5歳までなどとされますが、おおむね未就学の時期)における深刻なネグレクト(育児放棄)や虐待、不適切な養育環境です。
こうした経験が、子どもが「安心できる」と感じる人間関係の基礎、つまり「安全基地」を築くことを妨げます。
その結果、感情が不安定になったり、人を試すような行動(試し行動)が増えたり、対人関係全般に困難を抱えてしまうのです。
愛着障害の2つのタイプ
愛着障害は、その現れ方によって大きく2つのタイプに分けられます。
- 反応性アタッチメント障害(RAD)養育者に対して安心や慰めを求める行動がほとんど見られず、笑顔が少なく無表情だったり、感情的に引きこもったりするタイプです。
- 脱抑制型対人交流障害(DSED)RADとは対照的に、見知らぬ大人にも過度に親しげに接したり、わざと相手が嫌がることをして愛情を試す「試し行動」が頻繁に見られたりするタイプです。誰にでもなれなれしい一方で、仲間との協調性は乏しい傾向があります。
では「アダルトチルドレン(AC)」とは何か?
一方、今日の本題である「アダルトチルドレン(AC)」とは何でしょうか。
決定的な違いとして、アダルトチルドレン(AC)は医学的な診断名ではありません。これは、「心理社会的な概念」として使われる言葉です。
ACとは、子どもの頃に家族から受けたトラウマや不適切な養育によって、成人後もその影響で生きづらさを抱えている状態を指します。
ACの歴史的背景と「機能不全家族」
この言葉は、1970年代のアメリカで、アルコール依存症の親を持つ家庭で育った成人を指す隠語として使われ始めたのが起源とされています。
その後、虐待やネグレクトだけでなく、家族間の不和、過度な期待など、家族が本来持つべき機能(安心感を与える、情緒的に支えるなど)がうまく働いていない「機能不全家族」で育ち、生きづらさを抱える人全般を指すようになりました。

ゆう先生の補足解説:機能不全家族とは?
「機能不全家族」と聞くと、虐待やネグレクトといった深刻な状況だけを思い浮かべるかもしれません。もちろんそれも含まれますが、ACの文脈ではもっと広い意味で使われます。
例えば、
- 親がアルコールやギャンブルなどの依存症である
- 親が過度に厳格で、子どもの感情を認めない
- 親が逆に子どもに依存し、愚痴の聞き役をさせる
- 夫婦喧嘩が絶えず、家庭が安心できる場所ではない
- 「良い子でいること」「勉強ができること」だけを過剰に期待する
このように、子どもが「子どもらしく」いられず、親の顔色をうかがったり、無理をして親の期待に応えたりしなければならなかった環境も、機能不全家族と捉えられます。
ACの特徴:家族の中の「役割」を演じる
ここがACを理解する上で最も重要なポイントです。
ACとされる人々は、この機能不全家族の中で、家族全体のバランスを保つために、無意識のうちに特定の「役割」を演じてきたと考えられています。
本当は親が果たすべき役割を、子どもが代わりに補おうとしてきた、とも言えます。代表的な役割には以下のようなものがあります。
- ヒーロー(英雄)家族の期待に応えようと、勉強やスポーツなどで必死に努力する「良い子」。家族の希望の星であろうとしますが、失敗を極度に恐れます。
- スケープゴート(生贄)家族の「問題児」として振る舞う「悪い子」。わざと非行に走ったりすることで、家族の負の部分や注目を自分一身に引き受けようとします。
- ロストワン(いない子)存在感を消し、手のかからない「静かな子」。家族にこれ以上迷惑をかけまいと、自分の欲求や感情を押し殺します。
- ケアテイカー(世話役)親の愚痴を聞いたり、幼いきょうだいの面倒を見たりする「小さな親」。いわゆる「ヤングケアラー」もこれに含まれます。家族の世話をすることで自分の価値を見出そうとします。
決定的な違い:「安全基地の欠如」と「役割の遂行」
愛着障害とアダルトチルドレン、どちらも幼少期の家庭環境が原因で、大人になってからも対人関係の困難や自己肯定感の低さ、感情調整の難しさといった、非常によく似た生きづらさを抱えます。
では、決定的な違いはどこにあるのでしょうか。
それは、その行動の背景にある「動機」=スタート地点です。
愛着障害は「安全基地の欠如」から来る行動
愛着障害の診断基準となるのは、「安全基地の欠如」です。
つまり、0歳から5歳といった非常に早い段階で、深刻なネグレクトや虐待により、「この世は安全だ」「この人は信頼できる」という人間関係の絶対的な土台そのものが築けなかった状態です。
そのため、愛着障害を抱える人の行動(例えば「試し行動」)は、「この人は本当に安全か?」「自分を見捨てないか?」という、関係性の「安全性」そのものを必死に確認しようとする動機から来ています。
ACは「身についた役割」から来る行動
一方、アダルトチルドレンは、診断名ではないため、もっと広い概念です。
もちろん、ACの方の中には愛着障害と診断されるレベルの虐待を受けていた方もいます。しかし、ACの概念はそれだけにとどまりません。
ACの生きづらさの根底にあるのは、機能不全家族の中で「演じざるを得なかった役割」と、それによって形成された「低い自己肯定感」です。
安全基地が「全くなかった」というよりは、「条件付き」だった、あるいは「歪んでいた」と言えるかもしれません。
例えば、
- 「良い子(ヒーロー)でいなければ、愛されない」
- 「世話役(ケアテイカー)をしなければ、自分の居場所がない」
- 「存在を消して(ロストワン)いなければ、怒られる」
このように学んできたため、大人になってもその「役割」を無意識に演じ続けてしまうのです。「ヒーロー」だった人は、大人になっても完璧主義で自分を追い詰め、「ケアテイカー」だった人は、他人の世話ばかり焼いて自分を後回しにしてしまいます。
行動の動機が、「安全性の確認(愛着障害)」というより、「自分の価値を証明するため」や「身についた役割パターンから抜け出せないため」にあるのが、ACの特徴と言えます。
土台がない(愛着障害)と、土台が歪んでいる(AC)。この違いを「家づくり」で例えてみます。
愛着障害は、そもそも家を建てるための「基礎(安全基地)」が作られなかった、あるいは破壊された状態です。
家(自分)は常に不安定で、いつ崩れるか分からない恐怖の中にいます。
だから、支援の第一歩は、安心できる関係性の中で、もう一度「基礎」を作り直す(安全基地の再構築)ことです。
アダルトチルドレンは、「歪んだ基礎」や「傾いた土地(機能不全家族)」の上に、なんとか家を建てようとした状態です。
家(自分)は、傾いた土地の上で倒れないよう、必死にバランスを取るために、歪んだ形(役割)で建ってしまいました。
支援は、まず「自分が歪んだ土地に立っていること」「歪んだ役割を演じてきたこと」に気づき、歪んだままでも倒れない方法や、新しい環境でまっすぐな部分を増築していく(自己の再構築)ことになります。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- 愛着障害は、幼少期の深刻な虐待・ネグレクトによる「安全基地の欠如」が原因で生じる「医学的な診断名」です。
- アダルトチルドレン(AC)は、機能不全家族の中で生き抜くために特定の「役割」を演じてきた結果、生きづらさを抱える状態を指す「心理社会的な概念」です。
- どちらも対人関係の困難や自己肯定感の低さといった症状は似通っていますが、行動の根本的な動機が「安全性の確認(愛着障害)」なのか、「身についた役割の遂行(AC)」なのか、というスタート地点に大きな違いがあります。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
愛着障害もアダルトチルドレンも、ご本人が幼少期に大変な思いをされてきたことには変わりありません。そして、どちらも「修復可能」なものです。
もしご自身の生きづらさの背景にこうしたことがあるかもしれないと感じたら、一人で抱え込まず、専門のカウンセリングなどを頼ってみることも大切です。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋గれば、僕もとても嬉しいです。