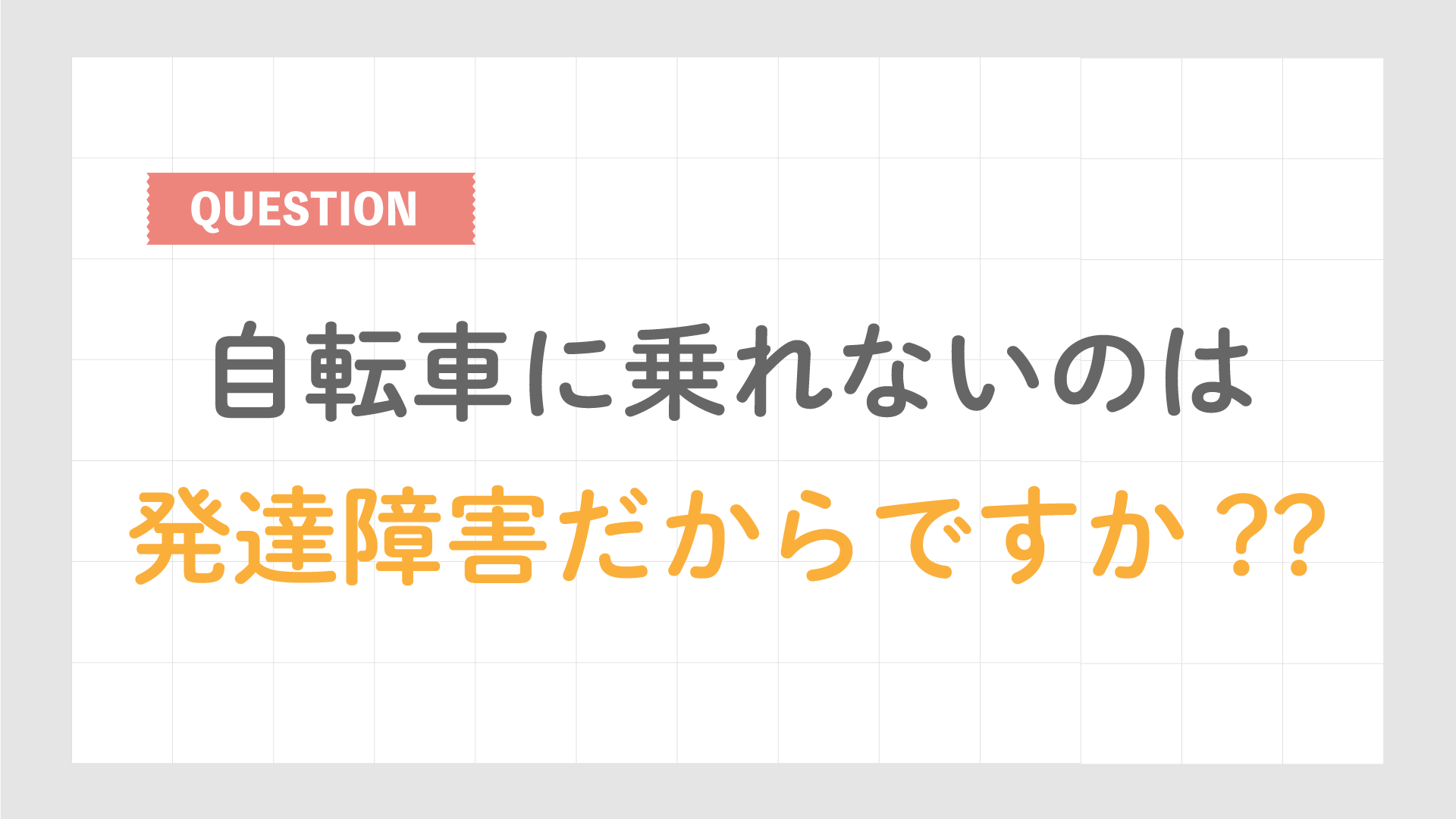愛着とは?子どもの「心の土台」を育むアタッチメントの基礎と、発達障害と混同しやすい愛着障害について解説
こんにちは。ゆうです。
僕は、富山県富山市で児童発達支援施設の指導員として活動している、現役の職員です。
このブログ(YouTube)では、発達障害や子育てに関する現場のリアルな情報や、保護者の方の気持ちが少しでも軽くなるような考え方を発信しています。
さて、本日の記事は、「愛着(アタッチメント)」についてです。
「愛着障害」という言葉は聞いたことがあるけれど、発達障害とは何が違うんだろう?」「子どもの健やかな心の土台を育むために、親として何が大切なの?」そんな風に考えたことはありませんか?
愛着は、特に幼児期(0歳から6歳頃)において、子どもの発達を支える非常に大事な概念です。
僕の現場感覚としても、療育(発達支援)がうまくいく背景には、この「愛着」がうまく形成されているケースがとても多いと感じています。
愛着(アタッチメント)とは何か?
まず、「愛着(アタッチメント)」とは何かについてお話しします。
これは、お子さんが特定の養育者(多くの場合はお父さんお母さん)に対して形成する、特別な情緒的な結びつきを指す心理学的な概念です。
これは単なる「依存」とは違います。お子さんが生き延びやすくするための、人間が本能として持っている「適用的な行動システム」だと理解されています。

ゆう先生の補足解説:ジョン・ボウルビィと愛着理論
愛着理論(Attachment Theory)は、イギリスの心理学者であるジョン・ボウルビィ(John Bowlby)によって提唱されました。
彼は、第二次世界大戦後の戦争孤児たちを観察し、親から引き離された子どもたちの精神発達に遅れが見られることに着目しました。
そこから、「子どもは危険や不安を感じた時、特定の養育者にくっつくことで安心を得ようとする、生まれ持った本能的な行動システムがある」と考えました。
ボウルビィは、この愛着こそが、他のどの要素よりも発達全般の「礎(いしずえ)」となると定義しています。
子どもが順調に成長していく背景には、この愛着という存在が欠かせないんですね。
なぜ愛着は「心の土台」なのか?
愛着というと、「愛情」や「感情的な結びつき」といった感性的なものだと捉えがちですが、その根源にはもっと生物学的な理由があります。
生き延びるための「生存戦略」
愛着が生まれるきっかけは、生物学的な「生存戦略」であった側面が強いと言われています。
生まれたばかりの赤ちゃんは、すごく無力ですよね。
もしこれが何千年も前の時代で、周りに狼などの外敵がいたら、赤ちゃんが一人で生き延びることはできません。
赤ちゃんは、お腹が空いた時、不安な時、危険を感じた時に「えーん!」と泣きます。そのシグナルに対して養育者がすぐに来てくれ、お世話をしたり守ったりする。このシステムがあったからこそ、人間はここまで繁栄できたとも言えます。
愛着とは、まず第一に、お子さんの生存に直結する根源的なシステムなんです。
内的作業モデル(心のテンプレート)
そして、愛着が「心の土台」と呼ばれる最大の理由が、この「内的作業モデル」の形成に関わるからです。
幼少期の愛着体験は、その後のすべての対人関係の基盤(テンプレート)となります。

ゆう先生の補足解説:内的作業モデル(Internal Working Model)
「内的作業モデル」とは、幼少期に養育者との間で築かれた愛着の体験を通して作られる、「心のテンプレート」のようなものです。
例えば、「自分が泣いたら、お母さんが来て優しくしてくれた」という体験を繰り返すと、「自分は助けを求める価値がある人間だ」「他人は信頼できる存在だ」というポジティブなテンプレートが形成されます。
逆に、「泣いても誰も来てくれない」という体験が続くと、「自分は愛される価値がない」「他人は信頼できない」というネガティブなテンプレートが形成されやすくなります。
このテンプレート(内的作業モデル)が、その後の友人関係、恋人、そして自分自身の子どもとの関係の築き方にまで、無意識のうちに影響を与えると言われています。
愛着が育つ4つのプロセス
愛着は、生まれた瞬間に特定の人に対して示されるわけではなく、一定の期間を経て、段階的に形成されていきます。
第1段階(出生〜12週頃):人なら誰でもOK
生まれたばかりの赤ちゃんは、まだ特定の養育者を選びません。「自分以外の人」という認識に近いです。
泣いたり、微笑んだりすることで、身近な大人からのお世話を誰からでも引き出そうとする時期です。
第2段階(12週〜6ヶ月頃):特定の大人への働きかけ
この時期になると、日常的によく関わっている人(多くの場合はお母さんやお父さん)に対する働きかけが顕著になってきます。
「自分が笑顔になると、周りの人も笑顔になる」といった経験を通し、自分の行動が周囲に影響を与えることを学び始めます。
第3段階(6ヶ月〜3歳頃):明確な愛着と「安全基地」
この段階で、いよいよ明確な愛着が形成されます。養育者を「安全基地」として認識し始め、他の人と区別できるようになります。

ゆう先生の補足解説:安全基地(あんぜんきち)」とは
「安全基地(Safe Base)」は、愛着理論の中心的な概念の一つです。
子どもは、お父さんやお母さんを「困ったり怖かったりした時に、必ず戻ってこられる安心できる場所(=安全基地)」として認識します。
この時期、急に人見知りが激しくなったり、お母さんの後追いがひどくなったりすることがあります。これは、特定の養育者を「安全基地」として正しく認識し始めた証拠であり、順調な発達のサインなんですよね。
この時期に子どもが甘えてくるのは、むしろ正常なことなので、できる限り受け止めてあげることが大切です。
第4段階(3歳頃〜):安全基地からの「探索」
安全基地がしっかりと確立されると、子どもはその基地を拠点として、外の世界へ「探索」を始めます。
興味のある場所へ行ってみて、不安になったり怖くなったりしたら、安全基地(お父さんお母さん)の元へ戻ってきて安心感を得る。
この「探索」と「避難(安全基地へ戻る)」の行き来を繰り返すことで、子どもの好奇心や積極性、ストレス耐性が育まれていきます。
愛着の4つのスタイル
愛着の形成は、養育者との関わり方によって、いくつかのスタイル(パターン)に分かれると言われています。

ゆう先生の補足解説:ストレンジ・シチュエーション法
これは、心理学者のメアリー・エインズワースが行った有名な実験観察法です。
見知らぬ場所(プレイルーム)で、①母親と子どもがいる状態から、②母親だけが退出(分離)し、③母親が戻ってくる(再会)という一連の場面で、子どもがどのような反応(不安の示し方、再会時の行動)をするかを観察しました。
この実験により、子どもの愛着のパターン(スタイル)は主に4つに分類されることが示されました
① 安定型(Secure)
最も望ましいとされるスタイルです。
母親が退出すると不安を示しますが、戻ってくるとすぐに安心を取り戻し、再び元気に遊び始めます。養育者を安全基地として信頼できている状態ですね。
成人してからも、バランスの取れた人間関係を築きやすいと言われます。
② 回避型(Avoidant)
母親が退出してもほとんど不安を示さず、無反応に見えます。そして、母親が戻ってきても、あまり反応しなかったり、無視したりする傾向が見られます。
成人すると、他人と親密な関係になるのを避けたり、感情をあまり表に出さなかったりする傾向があると言われます。
(発達支援をしていると、このタイプのお子さんはもしかしたらASD的な要素を持っていないかな?と気になる時もありますね)
③ 葛藤型(Ambivalent / Resistant)
母親と離れると激しい不安を示します。しかし、母親が戻ってくると、近づいて接触を求めようとしつつ、同時に「なんで行っちゃったの!」と怒ったり攻撃したりするような、矛盾した反応を示します。
成人すると、不安が強く、相手に過度に依存する傾向があると言われます。
(実は僕自身、子どもの頃これに近かったんじゃないかな…と思う節があります)
④ 無秩序型(Disorganized)
上記のどのパターンにも当てはまらない、一貫性のない矛盾した行動を示します。
養育者に近づこうとするのに目を合わせなかったり、急に呆然としたり、突然泣き出したりするなど、情緒が不安定な特徴があります。
成人すると、強い対人不安や情緒不安定さを抱えやすいとされます。
「愛着障害」と「発達障害」の決定的な違い
さて、ここまで愛着の基本をお話ししてきましたが、最後に「愛着障害」についてです。
愛着障害とは、主に乳幼児期に、養育者との間に愛着がうまく形成されないことによって起こる状態を指します。
ここで最も重要なのは、愛着障害は「後天的」なものであるという点です。
- 発達障害(ASD, ADHDなど):生まれつきの脳機能の特性による「先天的」なもの。
- 愛着障害:お子さんの育つ環境や養育者との関わり方に原因がある「後天的」なもの。
原因が全く違うんですね。
なぜ混同されやすいのか?
では、なぜ愛着障害と発達障害が混同されやすいのでしょうか。
それは、表面的な「症状」がとてもよく似ているからです。
例えば、「多動(じっとしていられない)」「衝動的」「ルールが守れない」といった行動は、ADHDのお子さんにも見られますが、愛着障害のお子さんにも見られることがあります。
ここが支援者にとっても一番難しいところです。例えば「多動(じっとしていられない)」という行動(B)が同じでも、その原因(A)が異なります。
- 発達障害(ADHDなど)の場合:脳機能の特性(衝動性)が原因で、じっとしていられない。
- 愛着障害の場合:養育者の気を引くため、または不安や混乱から、結果としてじっとしていられない。
表面的な行動は似ていても、原因が「脳機能(先天的)」なのか「養育環境(後天的)」なのかで、アプローチは全く変わってきます。だからこそ、愛着の理解が発達支援においても重要なんですよね。
もちろん、発達障害の特性(例:ASDで愛着を感じにくい)がベースにあって、その上で愛着の問題が併発し、より複雑になっているケースもあります。
愛着は「修復可能」です
愛着障害についてお話しすると、不安になるお父さんお母さんもいらっしゃるかもしれません。
でも、一番お伝えしたいのは、愛着は後天的なものだからこそ、どの年齢からでも「修復可能」だということです。
もし、お父さんお母さんご自身が、ご自身の親との関係(愛着スタイル)を振り返った時に、「自分は回避型だったかも…」と気づくことがあるかもしれません。子どもに甘えさせるのが苦手だな、と感じるかもしれません。
それでも大丈夫です。
今からでも、お子さんに対して、
- 抱っこや、応答的な関わり(子どもの発信に気づいて応える)
- 肯定的な声かけ
- 気持ちの代弁や共感
こういったことを意識的に増やしていくことで、愛着は再形成されていきます。
親子関係は、いつからでも修復できます。まずはご自身の心の安定を大切にしつつ、お子さんとの温かい関わりを育てていってほしいなと思います。
まとめ
今日の話を振り返ります。
- 愛着(アタッチメント)は、ジョン・ボウルビィが提唱した、子どもが養育者と築く情緒的な絆であり、生き延びるための本能であり、発達全体の「土台」です。
- 幼少期に形成される「安全基地」との関係が、その後の対人関係すべての雛形となる「内的作業モデル(心のテンプレート)」を形成します。
- 愛着障害は、養育環境に起因する「後天的」な状態であり、多動や衝動性など発達障害と似た症状を示すことがあるため混同されやすいですが、原因が異なります。そして何より、愛着は「修復可能」です。
結論:読者へのメッセージ
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
療育の現場で一番大事にしているのは、何よりもまず「愛」、つまり子どもと心を通わせることだと僕は思っています。
どんな子どもでも、心の通い(=愛着)が土台にあって初めて、療育の様々なアプローチが正しく伝わっていくんですよね。
今日の話が、この記事を読んでくださった保護者の方や当事者の方にとって、何かしらの「行動のきっかけ」になったり、見てくださった方の「気持ちが少しでも軽くなる」ことに繋がれば、僕もとても嬉しいです。